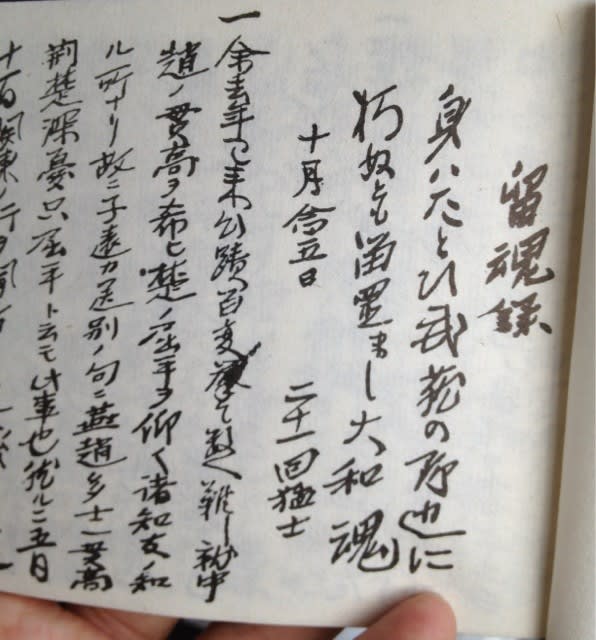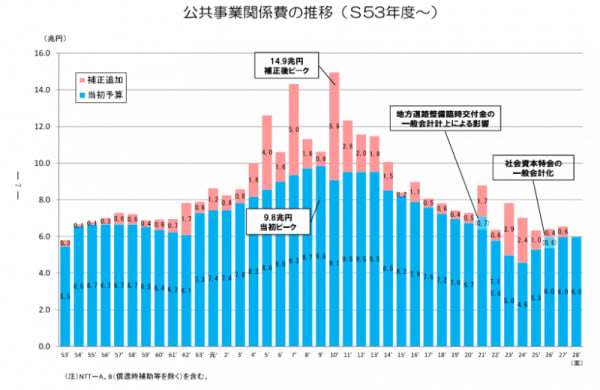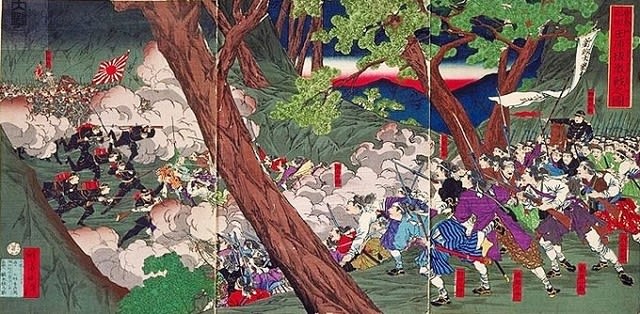このところ、平昌オリンピックの開会式に、
安倍首相が出席すべきか、すべきでないかの議論が、
一部で盛り上がっています。
筆者は、こんな議論自体がもはや空しいと思っています。
出席してもしなくても、事態は何も変わらないでしょう。
その理由を以下に述べます。
文在寅政権が親北べったり政権というか、
北のエージェント政権であることはもはや明らかです。
また、2015年12月の慰安婦問題をめぐる日韓合意を見直すというのが、
この政権の基本的な立場ですから、
たとえ首脳会談で「合意を守れ」と釘をさしても、
ただの物別れになることは目に見えています。
一方では、「平和の祭典」という建前が、
政治利用にまみれている実態もあります。
金正恩様はこれをチャンスと見て、
いろいろと工夫なさっているようですね。
だからこそ、行くなという議論も成り立ちますし、
だからこそ、行ったほうがいいという議論も成り立ちます。
アメリカからは出席を要請されているに違いないでしょうから、
それに適当につきあっておくという外交的意義が絶無とは言い切れません。
なにしろ、ペンス副大統領も行くのですから、
そこで米韓の水面下の交渉に加わっておくのも得策かもしれません。
筆者としては、
まあ、行かないよりは行ったほうがいいかな、
くらいの気持ちでおります。
しかしいずれにしても、
これは対韓外交としての意義というレベルでは、
興奮してその是非を論ずるに値しない議論です。
それよりも、これを機会に再確認しておくべきことがあります。
それは、
あの日韓合意がどういう性格のものであったか、
その結果国際社会で何が起きたか、
以上を国民がしっかり思い出すことです。
これに関して、次の二点を肝に銘じることが最も重要です。
①間違った中韓の「歴史認識」を誘発し助長させ、
さらに、それを承認してきたのが当の日本人であること。
②この「歴史認識」は中韓を利するのみならず、
第二次大戦の戦勝国である米英豪にとってもはなはだ都合がよいこと。
①の日本人の主役は、言うまでもなく朝日新聞などの反日メディアであり、
敗戦利得を手放したくない国内左翼勢力です。
しかし彼らの言動を無意識のうちに支持し、
暗黙の承認を与えているのは、
戦後教育を受けた一般の日本人です。
戦後教育は、
七年間にわたるGHQの占領統治期間に巧妙に準備されました。
これによって日本人は、魂を抜かれ、
主権回復後もその路線を歩み続けることになりました。
自虐史観に骨の髄まで侵されてしまったのです。
多くの戦後日本人は、周辺諸国に対して、
謝罪姿勢を自ら進んでとる習慣を身につけてきました。
さらに、そういう姿勢をとっておけば、
向うは許してくれて丸く収まるだろうという、
お人好し丸出しの習性まで身につけてしまったのです。
国際社会はそんなに甘くないのだというまともな感覚の喪失です。
②の、中韓の「歴史認識」が戦勝国にとって都合がいいという点。
このでっち上げられた「歴史認識」は、
戦勝国の「正義」を揺るぎないものにすることに貢献してきました。
また原爆投下など、民間人大量虐殺行為の「悪」を隠蔽する効果もあります。
中共は、そのことをよく知っていて、
欧米が抱いている「あの戦争では日本が一方的に悪い」という、
自分たちに都合のよいイメージを大いに活用し、
日米分断を図ろうとしているわけです。
そもそも「日韓合意」は安倍外交の致命的な失敗です。
この合意によって安倍政権の対韓外交は、
河野談話、村山談話と何ら変わらない醜態をさらしました。
当時の岸田外相発言、
「軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた。日本政府は責任を痛感している」
は、誰が読んでも軍の強制性を認めたとしか解釈できません。
また安倍首相は「心からのお詫びと反省」発言をしています。
さらに韓国新財団に10億円の出資。
これは名目上「賠償」ではないと謳ってはいますが、
国際社会はそう見ません。
以上の三点セットで、
「旧日本軍は20万人もの韓国女性をセックス・スレイヴとして扱い、虐殺した」
とのこれまでの戦勝国の定説を、
オウンゴールで追認したことになります。
その後、欧米メディアがこの「日韓合意」をどうとらえたかを見ると、
この認識が見事に裏付けられます。
山岡鉄秀氏が主宰するAJCNが、
合意直後の二〇一六年一月七日に出したレポートによると、
次のような記事が目白押しであることがわかります。
2015-12-28 The Guardian (Australia)
日本政府は、女性の性奴隷化に軍が関与していたことを認めた。
日本統治下の朝鮮半島で強制的に売春をさせられた女性の数には論争があるが、
活動家らは20万人と主張している。
2015-01-01 New York Times, To the editors (U.S.A)
生存者の証言によれば、この残酷なシステムの標的は生理もまだ始まっていない13,14歳の少女だった。
彼女たちは積み荷としてアジア各地の戦地へ送られ、日常的に強姦された。
これは戦争犯罪のみならず、幼女誘拐の犯罪でもある。
2016-01-03 Ottawa Citizen (Canada)
多くの被害者は14歳から18歳の少女で、軍の狙いは処女だった。
抵抗する家族は殺されるケースもあった。
41万人の少女や女性が誘拐され、生存者は46人のみ。
安倍の謝罪は誠意がなく、安部の妻は戦争犯罪者を奉る神社に参拝した写真を公開している。
10億円は生存者を黙らせるための安い賄賂だ。
ご覧の通りの集中砲火です。
これが戦勝国包囲網の常識なのです。
安易な「謝罪」や「責任表明」が何を呼び起こすか、
日本人は改めて肝に銘じるべきでしょう。
そもそも日本側には韓国の会談要求に応ずる必要などまったくなかったのです。
しかし応じてしまったからには、
最低限、次の三つを交渉の絶対条件として臨むべきでした。
①慰安婦問題に関してあらゆる意味で日本国には責任など存在しないことの確認
②大使館前の慰安婦像の撤去
③慰安婦問題に関するいかなる形での資金拠出も行わない。
あの反日メディア・朝日新聞が二〇一四年八月に、
はなはだ不十分ながらも慰安婦報道が誤報であったことを自ら認めました。
にもかかわらず、
安倍政権はこの合意によって、その事実をもひっくり返してしまいました。
安倍首相もまた、
占領統治時代の洗脳政策に始まる戦後教育の犠牲者です。
口では「戦後レジームからの脱却」などと言っていても、
その無意識レベルでは全然脱却などできていなかったわけです。
こういう状況ですから、
嫌韓感情から「安倍の平昌出席を認めるわけにはいかない」と言って、
毅然と拒否の姿勢を示したつもりになっても、
周辺の国際社会は「子どもの喧嘩だ」と受け取るだけでしょうし、
外交的配慮で出席して何か日本にとっての成果を期待しても、
アメリカ親分にくっついて日米同盟の堅固さを、
多少印象づけるくらいの効果しかないでしょう。
大切なことは、
短期間の時局に視野を限定して大騒ぎすることではなく、
私たち国民が日韓合意の大失敗を忘れず、
日本に対する国際社会の恐るべき名誉毀損を、
いかにして雪ぐかに知恵とエネルギーを集中させることなのです。
なお、以上の主張の基礎になる認識は、
拙著『デタラメが世界を動かしている』で展開しております。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%81%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B-%E5%B0%8F%E6%B5%9C-%E9%80%B8%E9%83%8E/dp/4569830404/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517381768&sr=8-1&keywords=%E5%B0%8F%E6%B5%9C%E9%80%B8%E9%83%8E
【小浜逸郎からのお知らせ】
●『福沢諭吉と明治維新』(仮)を脱稿しました。出版社の都合により、刊行は5月になります。中身については自信を持っていますので(笑)、どうぞご期待ください。
●月刊誌『正論』2月号「日本メーカー不祥事は企業だけが悪いか」
●月刊誌『Voice』3月号「西部邁氏追悼」(2月10日発売)