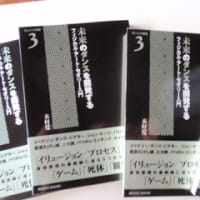それで、31日の夕方、熱海を出発すると、今度は帰宅ラッシュにもまれ、すっかりリゾート気分が揮発した後、代官山UNITにて行われた『Postmainstream Performing Arts Festival 2006』のエンディング企画を見たのだった。着くと山川冬樹のパフォーマンスが始まっていた。一年前に「アートノヴァ」で見たときには、心臓の鼓動にシンクロする電球の束は、四方に散らばって吊されていたのだけれど、先日の川口隆夫との公演の時と同様、電球はまとまってまるでそれは心臓のように舞台脇にある。基本的な音のパフォーマンスなのだけれど、それらの音に物理的なインパクト(別に爆音じゃないのだけれど、むしろディテールが感じられる、触覚的という意味)があって、また心臓を楽器のように扱う点で、きわめて身体的なインパクトがある。異常に不規則なリズムで鼓動が打たれると、危ない!と思いつつ、もっと変なことになってしまえ!と欲求がエスカレートしてしまう。心臓にエフェクター移植して欲しいなあ!とか、それをX線で撮ってプロジェクターで大写しするとか、見てみたいなあ!とか。その後、SIMが出て、恩田晃へと続き、OPTRUM、でドラびでおがトリ。
山川冬樹は例外として、こうした音響系のひとたちは、基本的に、楽器とか機械とかを用いることで、人間的身体の枠をどんどん超えて異常なレヴェルへとトリップ出来る。去年の夏頃か、ここでスクラッチは唯物論的だ、等と書いたけれど、「もの」のレヴェルへ観客の見る身体聞く身体を接触させる音響系の試みがぼくは純粋に好きだ。例えば、恩田晃は、カセットテレコを手で振り回しながら時々再生+早送りボタンを押すことで、「ギッギッギュー」という音を発生させたりする。そもそもかなりエフェクトがかかっているとはいえ、どこかで録音してきた音の再生というややセンチメンタルな行為を、そうしたノイズへとどんどん変換させることでクールにしている。そうして、唯物論的な要素とロマンチックな要素が奇妙に混在する音空間が生まれている。こういうの、リアルだなと思うのだ。で、恩田のパフォーマンスは陶酔(不思議に宗教的な感じさえある)させるだけではなく、例えばノイズの塊の連続はホラー(恐怖)でもある。「もの」の前で、身体は聞く「もの」見る「もの」へと変貌させられてしまう。もう意味とかメッセージとか、そうしたヒューマンな何かは発生する余地が消滅してしまっている。
この次元にダンスを引き込むこと、それは可能なのか。
例えば、先日の先にも触れたJADEで山川と共作した川口隆夫が、後半で、顔をぶるぶると横に振ると、頭の真上にある薄暗い光による残像の効果で、顔がゆがみ、ベイコンの絵のようにぐしゃぐしゃになったのはどうだろう。すごく小さなアイディアだけれど、あらわれるイメージはなかなか強かった。異形性は効果として上手く生じていた。
こういう、視覚の性格を用いた効果のレヴェルで、ダンスする身体にひずみを与える試みは、いろいろと出来そうだ。例えば、ビデオで撮影されながら踊り、その踊りの映像に瞬時にエフェクトをかけ、それを踊りの隣でプロジェクトするとか。写真は『呪怨』の映像の一部をデジカメで撮ったものですが、こういう歪みを与えることならば、もはやまったく容易いことだろう。
けれども、それはいわばビデオダンスなのであって、身体によるダンスのポテンシャルを引き出すことにはならず、やっても恐らく、ビデオはそこそこえぐい(すごい)けれど、その脇のダンスはそれ自体としてどうよ、と思われるに違いない。そうとう上手く、映像のエフェクト身体と実際の身体がコラボ出来ていなければ。
とはいえ、ダンスの一部は、こうした「もの」としての身体あるいは「ホラー」としての身体を舞台に上げる試みをしてきたのではないだろうか。しかも、照明などの装置に頼らず、素の身体によって。モダンダンスのなかには当時の表現主義芸術運動に影響を受けた、気味の悪い動きや表情が試みられていたし、暗黒舞踏というのはまさにこのホラーの身体を舞台に上げると言うことを実践してきた面があるのではないだろうか。超スローな動作というのは、観客の身体を脅かすひとつのアイディアだったろうし、立てない身体のもどかしい感じなども、身体についての標準的な観念を揺さぶる効果を持っていただろう。
ごく簡潔に言えば、ダンスは身体の怪物化によって、観客との新たな関係を引き出すことができるのではないか。そうして、ダンスという観念のレンジを拡張することが出来てはじめて、ダンスは、真の意味で他のアートや他のジャンルと交通するのに相応しい存在になりうるのではないか。
どうしたらダンスする怪物になれるのか、どうしたらダンスする改造人間になれるのか。
付記
こうしたことを最近考えるようになったきっかけは幾つかあるのだけれど、二月に横浜でHappy Side Showを見たのは案外に大きい。彼らのパフォーマンスは体を張った大道芸といったもので、なんらアート的な要素もないし彼らもそういったことを狙ってはいなかった。それはともかく、ぼくが驚きあきれたのは、ただひたすら身体に負荷をかけ、いじめ、ぐちゃぐちゃにする彼らの欲望というのはいったい何なのだ、ということ。例えば、のどに蛍光灯を飲み込んだら100万やるって言われているならば、やる理由にはなるけれども、多分、そんな高額のギャラじゃないだろう。金儲けじゃない、としたら動機は何なのだ?スリル?ぼくの心に残っているのは、スリルといった言葉よりは、ホラー的なものであり、また異常な身体に熱狂した感覚だ。だとすれば、「怪物ランド」にひとを引き込むことが彼らの欲望だったりして。あれが、近年見たパフォーマンスのなかでとびきりよかったと言ったら、笑われてしまうかも知れないけれど、、、そうだった。
山川冬樹は例外として、こうした音響系のひとたちは、基本的に、楽器とか機械とかを用いることで、人間的身体の枠をどんどん超えて異常なレヴェルへとトリップ出来る。去年の夏頃か、ここでスクラッチは唯物論的だ、等と書いたけれど、「もの」のレヴェルへ観客の見る身体聞く身体を接触させる音響系の試みがぼくは純粋に好きだ。例えば、恩田晃は、カセットテレコを手で振り回しながら時々再生+早送りボタンを押すことで、「ギッギッギュー」という音を発生させたりする。そもそもかなりエフェクトがかかっているとはいえ、どこかで録音してきた音の再生というややセンチメンタルな行為を、そうしたノイズへとどんどん変換させることでクールにしている。そうして、唯物論的な要素とロマンチックな要素が奇妙に混在する音空間が生まれている。こういうの、リアルだなと思うのだ。で、恩田のパフォーマンスは陶酔(不思議に宗教的な感じさえある)させるだけではなく、例えばノイズの塊の連続はホラー(恐怖)でもある。「もの」の前で、身体は聞く「もの」見る「もの」へと変貌させられてしまう。もう意味とかメッセージとか、そうしたヒューマンな何かは発生する余地が消滅してしまっている。
この次元にダンスを引き込むこと、それは可能なのか。
例えば、先日の先にも触れたJADEで山川と共作した川口隆夫が、後半で、顔をぶるぶると横に振ると、頭の真上にある薄暗い光による残像の効果で、顔がゆがみ、ベイコンの絵のようにぐしゃぐしゃになったのはどうだろう。すごく小さなアイディアだけれど、あらわれるイメージはなかなか強かった。異形性は効果として上手く生じていた。
こういう、視覚の性格を用いた効果のレヴェルで、ダンスする身体にひずみを与える試みは、いろいろと出来そうだ。例えば、ビデオで撮影されながら踊り、その踊りの映像に瞬時にエフェクトをかけ、それを踊りの隣でプロジェクトするとか。写真は『呪怨』の映像の一部をデジカメで撮ったものですが、こういう歪みを与えることならば、もはやまったく容易いことだろう。
けれども、それはいわばビデオダンスなのであって、身体によるダンスのポテンシャルを引き出すことにはならず、やっても恐らく、ビデオはそこそこえぐい(すごい)けれど、その脇のダンスはそれ自体としてどうよ、と思われるに違いない。そうとう上手く、映像のエフェクト身体と実際の身体がコラボ出来ていなければ。
とはいえ、ダンスの一部は、こうした「もの」としての身体あるいは「ホラー」としての身体を舞台に上げる試みをしてきたのではないだろうか。しかも、照明などの装置に頼らず、素の身体によって。モダンダンスのなかには当時の表現主義芸術運動に影響を受けた、気味の悪い動きや表情が試みられていたし、暗黒舞踏というのはまさにこのホラーの身体を舞台に上げると言うことを実践してきた面があるのではないだろうか。超スローな動作というのは、観客の身体を脅かすひとつのアイディアだったろうし、立てない身体のもどかしい感じなども、身体についての標準的な観念を揺さぶる効果を持っていただろう。
ごく簡潔に言えば、ダンスは身体の怪物化によって、観客との新たな関係を引き出すことができるのではないか。そうして、ダンスという観念のレンジを拡張することが出来てはじめて、ダンスは、真の意味で他のアートや他のジャンルと交通するのに相応しい存在になりうるのではないか。
どうしたらダンスする怪物になれるのか、どうしたらダンスする改造人間になれるのか。
付記
こうしたことを最近考えるようになったきっかけは幾つかあるのだけれど、二月に横浜でHappy Side Showを見たのは案外に大きい。彼らのパフォーマンスは体を張った大道芸といったもので、なんらアート的な要素もないし彼らもそういったことを狙ってはいなかった。それはともかく、ぼくが驚きあきれたのは、ただひたすら身体に負荷をかけ、いじめ、ぐちゃぐちゃにする彼らの欲望というのはいったい何なのだ、ということ。例えば、のどに蛍光灯を飲み込んだら100万やるって言われているならば、やる理由にはなるけれども、多分、そんな高額のギャラじゃないだろう。金儲けじゃない、としたら動機は何なのだ?スリル?ぼくの心に残っているのは、スリルといった言葉よりは、ホラー的なものであり、また異常な身体に熱狂した感覚だ。だとすれば、「怪物ランド」にひとを引き込むことが彼らの欲望だったりして。あれが、近年見たパフォーマンスのなかでとびきりよかったと言ったら、笑われてしまうかも知れないけれど、、、そうだった。