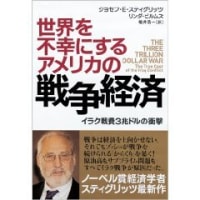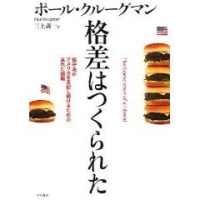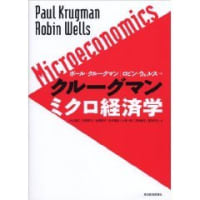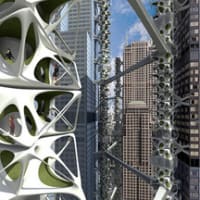まぁこの原油高と穀物の急騰を投機的、短期的、一時的な事象と見るかどうかって話はあるよね。でもそもそも何を短期として、何を長期とするかっていう話になるんだけど。
インフレターゲッティングの失敗 by Joseph E. Stiglitz 2008.5
世界の中央銀行関係者は閉鎖的なクラブを形成していて、流行りものやブームにはまりがちだ。1980年代の初頭には、ミルトン・フリードマンが推奨する単純な経済理論のマネタリズムのとりこになってたし、それを取り入れた国々があまりにコストがかかりすぎで頼れなくなったら、新しい真理を追い求める旅に出たわけだ。
その答えは、「インフレターゲット」という形でやってきた。物価が目標値を上回ったら、金利を上げるべきというものだ。この粗雑な対応策は、経済理論にもほとんど基づいてないし、実証的な証拠もない。インフレの原因を無視して、利子を上げるのがいちばんいいと考える理由はどこにもないのだ。ほとんどの国がインフレターゲットを導入しない良識をもっていることを望みたいものだ。私が同情するのは、導入された国々の不幸な国民たちのことだ(下記のリストには、どのような形にせよインフレターゲットを公式に導入した国々をあげている。イスラエル、チェコ共和国、ポーランド、ブラジル、チリ、コロンビア、南アフリカ、タイ、韓国、メキシコ、ハンガリー、ペルー、フィリピン、スロバキア、インドネシア、ルーマニア、ニュージーランド、カナダ、英国、スウェーデン、オーストラリア、アイスランド、ノルウェイ)
現在、インフレターゲットはテストされているわけだが、その結果はおおむね失敗だ。発展途上国が現在、高いインフレ率に直面しているのはマクロ経済政策がまずいからではなく、原油と食物の価格が高騰しているからだ。こうしたものが発展途上国の平均的な家計に占める割合は、先進国のそれよりはるかに大きい。たとえば中国では、インフレは8%以上になっている。ベトナムではもっと高くて、今年は18.2%になろうかという水準だ。インドでは、5.8%。一方、アメリカのインフレ率は3%。こうした発展途上国がアメリカより金利をはるかに高くにするべきだというのだろうか?
こうした国々のインフレは、だいたいが外から入ってくるものだ。金利は穀物や原油の国際価格にはほとんど影響を与えない。とくに、アメリカ経済の大きさを考えてみれば、発展途上国での景気後退よりもアメリカでの景気後退のほうが世界の物価にはるかに大きな影響をあたえることは分かるだろう。だから世界的な視点で見れば、発展途上国ではなく、アメリカの金利をあげるべきだということになる。
発展途上国が世界経済に統合されている間は、つまり国際的な物価が国内の物価に及ぼす影響を抑制するような手段をとらない間はということだが、国内の米やその他の穀物の価格は、国際的な価格があがっているときには急騰するものだ。多くの発展途上国では、原油や食物の価格が高いと三重苦におちいる。穀物を輸入する代金が増えるだけでなく、海外から運んでくるにもコスト増になるし、国内で港から消費者のもとへと届けるにもコストが増加する。
金利をあげることは、総需要を減少させて経済を減速し、ある種の財やサービス、とくに非貿易財やサービスの価格上昇を抑える。ただ我慢できないレベルにならなければ、こういった方法ではインフレを目標値までは下げられないだろう。たとえば、国際的なエネルギーと穀物の価格が今よりゆっくりと上がるとする。たとえば年に20%としよう、国内の価格にもそれが反映され、すべてのものにインフレが及ぶ。すると、金利を3%ぐらいあげないと物価を下げることにはならないだろう。これは必然的に著しい経済減速へとつながり、失業率も高くなる。治療のほうが病気より体に悪くなるよ。
じゃあどうすればいいのだろう? まず政治家や中央銀行の人々は、インフレが海外から入ってくるのに文句をつけるべきではない。それはちょうどわれわれが国際状況が良好だったときに、インフレ率が低かったのをそのおかげにしなかったのと同じことだ。前FRB理事長アラン・グリンスパークは、今ではみんな分かっているが、現在のアメリカ経済不況に大きな責任がある。在職期間中はアメリカを低いインフレ率にたもつ手腕を買われていたが、実際のところグリーンスパンが在職中のアメリカでは日用品の価格が下がっていること、つまり中国からのデフレで大いなる恩恵をうけていたわけだ。
つぎに、とくに所得が低い人にとっては、物価高は大きなストレスを生むということも認識しなければならない。いくつかの発展途上国での暴動や抗議行動は、インフレに対する抗議表明ともいえる。
自由貿易主義者はその利点は十分に売り込んでいるが、そのリスクを正直に話しているとは言いがたい。つまりマーケットはふつうは十分なセーフティネットを提供したりはしないのだ。4半世紀も前に、私はある十分に起こりうる状況下では、貿易自由化は全員にとって悪い結果になることを示している。保護主義を擁護しているわけではないが、経済の下降リスクに注意を払い、十分な備えをすることが必要だと注意をうながしたい。
農業に関して言えば、アメリカやEUのメンバのような先進国は、消費者も農業従事者もこのようなリスクから守ることができる。ただほとんどの発展途上国は、同じようなことをする制度的な仕組みもなければリソースもない。多くの国は輸出税とか輸出禁止といった緊急対応をとる。それは、自国の国民は守るが、他の全てを犠牲にしている。
もしグローバリゼーションに対するより強い反発をさけたいのなら、西欧諸国はより強く、迅速に対応しなければならない。バイオ燃料への補助金は、土地利用を食物生産からエネルギーへとシフトさせるので、撤回しなければならない。それに加えて、西欧諸国の農家に出されている何十億ドルは、貧しい発展途上国の基本的な食料やエネルギーのニーズを満たすのに使うべきだ。
もっとも大事なのは、先進国も発展途上国もインフレターゲットをやめる必要があるということだ。上昇し続ける食料価格とエネルギーの価格にあわせようとする努力は、つらすぎるものがある。インフレターゲットがもたらすのは、経済を弱体化し、失業率を上げることで、インフレには大した効果はない。インフレターゲットは、こうした状況を乗り切ることをより難しくするだけだろう。
先進国の農業への補助金を発展途上国に使うことに反対するまともな理由ってあるのかな? 食料自給率「だけ」見たってしょうがないんだって。だってあなた石油なしでは生きていけないでしょう? それに石油だけじゃなく、国民の多くは今の生活水準を切り下げることに同意しないんだから、自由貿易体制を率先して日本が守らなきゃいけないんじゃないの...バイオフューエルなんてもってのほかだよ。肉を食べない運動なんていいかもね。肉は穀物をえらく消費するからねぇ。
インフレターゲッティングの失敗 by Joseph E. Stiglitz 2008.5
世界の中央銀行関係者は閉鎖的なクラブを形成していて、流行りものやブームにはまりがちだ。1980年代の初頭には、ミルトン・フリードマンが推奨する単純な経済理論のマネタリズムのとりこになってたし、それを取り入れた国々があまりにコストがかかりすぎで頼れなくなったら、新しい真理を追い求める旅に出たわけだ。
その答えは、「インフレターゲット」という形でやってきた。物価が目標値を上回ったら、金利を上げるべきというものだ。この粗雑な対応策は、経済理論にもほとんど基づいてないし、実証的な証拠もない。インフレの原因を無視して、利子を上げるのがいちばんいいと考える理由はどこにもないのだ。ほとんどの国がインフレターゲットを導入しない良識をもっていることを望みたいものだ。私が同情するのは、導入された国々の不幸な国民たちのことだ(下記のリストには、どのような形にせよインフレターゲットを公式に導入した国々をあげている。イスラエル、チェコ共和国、ポーランド、ブラジル、チリ、コロンビア、南アフリカ、タイ、韓国、メキシコ、ハンガリー、ペルー、フィリピン、スロバキア、インドネシア、ルーマニア、ニュージーランド、カナダ、英国、スウェーデン、オーストラリア、アイスランド、ノルウェイ)
現在、インフレターゲットはテストされているわけだが、その結果はおおむね失敗だ。発展途上国が現在、高いインフレ率に直面しているのはマクロ経済政策がまずいからではなく、原油と食物の価格が高騰しているからだ。こうしたものが発展途上国の平均的な家計に占める割合は、先進国のそれよりはるかに大きい。たとえば中国では、インフレは8%以上になっている。ベトナムではもっと高くて、今年は18.2%になろうかという水準だ。インドでは、5.8%。一方、アメリカのインフレ率は3%。こうした発展途上国がアメリカより金利をはるかに高くにするべきだというのだろうか?
こうした国々のインフレは、だいたいが外から入ってくるものだ。金利は穀物や原油の国際価格にはほとんど影響を与えない。とくに、アメリカ経済の大きさを考えてみれば、発展途上国での景気後退よりもアメリカでの景気後退のほうが世界の物価にはるかに大きな影響をあたえることは分かるだろう。だから世界的な視点で見れば、発展途上国ではなく、アメリカの金利をあげるべきだということになる。
発展途上国が世界経済に統合されている間は、つまり国際的な物価が国内の物価に及ぼす影響を抑制するような手段をとらない間はということだが、国内の米やその他の穀物の価格は、国際的な価格があがっているときには急騰するものだ。多くの発展途上国では、原油や食物の価格が高いと三重苦におちいる。穀物を輸入する代金が増えるだけでなく、海外から運んでくるにもコスト増になるし、国内で港から消費者のもとへと届けるにもコストが増加する。
金利をあげることは、総需要を減少させて経済を減速し、ある種の財やサービス、とくに非貿易財やサービスの価格上昇を抑える。ただ我慢できないレベルにならなければ、こういった方法ではインフレを目標値までは下げられないだろう。たとえば、国際的なエネルギーと穀物の価格が今よりゆっくりと上がるとする。たとえば年に20%としよう、国内の価格にもそれが反映され、すべてのものにインフレが及ぶ。すると、金利を3%ぐらいあげないと物価を下げることにはならないだろう。これは必然的に著しい経済減速へとつながり、失業率も高くなる。治療のほうが病気より体に悪くなるよ。
じゃあどうすればいいのだろう? まず政治家や中央銀行の人々は、インフレが海外から入ってくるのに文句をつけるべきではない。それはちょうどわれわれが国際状況が良好だったときに、インフレ率が低かったのをそのおかげにしなかったのと同じことだ。前FRB理事長アラン・グリンスパークは、今ではみんな分かっているが、現在のアメリカ経済不況に大きな責任がある。在職期間中はアメリカを低いインフレ率にたもつ手腕を買われていたが、実際のところグリーンスパンが在職中のアメリカでは日用品の価格が下がっていること、つまり中国からのデフレで大いなる恩恵をうけていたわけだ。
つぎに、とくに所得が低い人にとっては、物価高は大きなストレスを生むということも認識しなければならない。いくつかの発展途上国での暴動や抗議行動は、インフレに対する抗議表明ともいえる。
自由貿易主義者はその利点は十分に売り込んでいるが、そのリスクを正直に話しているとは言いがたい。つまりマーケットはふつうは十分なセーフティネットを提供したりはしないのだ。4半世紀も前に、私はある十分に起こりうる状況下では、貿易自由化は全員にとって悪い結果になることを示している。保護主義を擁護しているわけではないが、経済の下降リスクに注意を払い、十分な備えをすることが必要だと注意をうながしたい。
農業に関して言えば、アメリカやEUのメンバのような先進国は、消費者も農業従事者もこのようなリスクから守ることができる。ただほとんどの発展途上国は、同じようなことをする制度的な仕組みもなければリソースもない。多くの国は輸出税とか輸出禁止といった緊急対応をとる。それは、自国の国民は守るが、他の全てを犠牲にしている。
もしグローバリゼーションに対するより強い反発をさけたいのなら、西欧諸国はより強く、迅速に対応しなければならない。バイオ燃料への補助金は、土地利用を食物生産からエネルギーへとシフトさせるので、撤回しなければならない。それに加えて、西欧諸国の農家に出されている何十億ドルは、貧しい発展途上国の基本的な食料やエネルギーのニーズを満たすのに使うべきだ。
もっとも大事なのは、先進国も発展途上国もインフレターゲットをやめる必要があるということだ。上昇し続ける食料価格とエネルギーの価格にあわせようとする努力は、つらすぎるものがある。インフレターゲットがもたらすのは、経済を弱体化し、失業率を上げることで、インフレには大した効果はない。インフレターゲットは、こうした状況を乗り切ることをより難しくするだけだろう。