解剖と変容 プルニー&ゼマーンコヴァー チェコ、アール・ブリュットの巨匠
会場:広島市現代美術館
会期:2012年5月26日~7月16日
今回の展覧会は、どちらかと言えばノーチェックだったし、ティザーを見てもよく分からない。だが、ちょうど開幕初日に近くまで出る用事があったので、現代美術館まで足を運んだ。
アール・ブリュットとは「生(き)の芸術、素材のままの芸術、という意味のフランス語です。 英語ではアウトサイダー・アートと訳されることもあります。専門的な美術教育を受けていない作り手が、芸術文化や社会から一定の距離を置きながら、自分自身の内なる欲求に従い制作した作品を指します。19世紀の後半に、精神科医が精神疾患のある人の創作物に関心を寄せたことがきっかけとなり、1920年代頃にはヨーロッパの前衛的な芸術家に注目されるようになりました。精神疾患のある人の作品の他に、霊能者、幻視家、ホームレス、知的な障がいのある人、独学で制作を始めた老人など、多様な作り手による作品が含まれ、近年では専門の美術館や画廊も各地にあって、前衛的な美術の一分野として確立しています。」(広島市現代美術館公式サイト)
その中からチェコのプルニーとゼマーンコヴァーの作品を中心に展示されている。
この二人、精神疾患を患っており、もちろん、作品にもそれが反映されている。語弊があるが、気色悪い作品なのだが、それがものすごい迫力で面白い。
万人受けするような作品ではなく、「好き・嫌い」「受け入れられる・受け入れられない」が明確に出るのだと思う。
ワタシが特に強く惹かれたのが、ルボシュ・ブルニーの作品。一見、落書きのようにも見えるのだが、ペンで細密に描き込まれ、根底には解剖学的な知識がある。1つ1つの作品にじっくりと見入っていると「この絵の中にはワタシたちには見えていない何かあるのかも知れない。」と思わせる。さらにチェコ語が理解できたら、そこに暗号めいたものを見い出せるかも知れない。
その感覚がすごく不安感と謎めいたワクワクドキドキ感を醸し出す。(両親の生まれた日からなくなった日まで、1からビッチリと数字を書き込んだ作品もすごい。)
この感覚に近いものがあるなら、ジョン・カーペンターの「マウス・オブ・マッドネス」とか「ビューティフル・マインド」で陰謀説に凝り固まるラッセル・クロウとか「ヘル・ボーイ」のオープニングかな。ラブクラフトのクトゥルフ神話も近いような。(←これらの例示でピンと来る人は本展はオススメだ。)
もう一人のゼマーンコヴァーの作品も脳内に潜む怪獣のよう。うねうねと動き出したら、かなりこわい。
会場で上映されているドキュメンタリー映画「天空の赤」では、アール・ブリュットについて「外国人は外見は似ていても話し方に訛りがあるので、それと分かる。アール・ブリュットも一目でそうと分かるものがある。」と語られるが、確かにそれは実感できる。
他にも「アール・ブリュットとアウトサイダー・アートは違う」とか「芸術とは狂気。」といった発言にも強烈な説得力がある。上映時間の途中から見たのだが、アート系の難解な作品という予想とは裏腹に、ドキュメンタリーとして分かりやすく構成されているので、ちゃんと頭から見直したい。
2人の他にも「天空の赤」に登場する作家の作品も展示されている。
「日曜日の墜落」
過去の飛行機事故を優れた記憶力で再構成し、一定の規則性から未来の事件も引きだそうと、紙ナプキンに書きつづった作品。ちょうど、ナンプレ(数独)を解いて、ル・カレの「ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ」を読んでいたワタシの精神状態にはピッタリフィット。
アレクサンドル・パブロヴィッチ・ロバノフ
ライフルとピストル大好きな病んだロシア人。建物の柱も馬車のスポークも全部ライフル。(笑)
無神論者の共産主義者のアカどものプロバガンダ作品に影響を受けているが、それらが好きなワタシはグッと惹かれる。
ヘンリー・ダーガー
まさか、ヘンリー・ダーガーの作品(実物)が広島でみることができるなんて思わなかったよ・・・。
ここ最近見た中では一番面白かった展覧会。もう一度行ってみるかな。
ただ、さすがに一般受けしない内容なのか、開幕初日の30分後くらいでワタシが3人目くらいの観客のよう。先日行った「ツタンカーメン展」と両極端。これはこれで現代美術館ぽくっていいね。
会場:広島市現代美術館
会期:2012年5月26日~7月16日
今回の展覧会は、どちらかと言えばノーチェックだったし、ティザーを見てもよく分からない。だが、ちょうど開幕初日に近くまで出る用事があったので、現代美術館まで足を運んだ。
アール・ブリュットとは「生(き)の芸術、素材のままの芸術、という意味のフランス語です。 英語ではアウトサイダー・アートと訳されることもあります。専門的な美術教育を受けていない作り手が、芸術文化や社会から一定の距離を置きながら、自分自身の内なる欲求に従い制作した作品を指します。19世紀の後半に、精神科医が精神疾患のある人の創作物に関心を寄せたことがきっかけとなり、1920年代頃にはヨーロッパの前衛的な芸術家に注目されるようになりました。精神疾患のある人の作品の他に、霊能者、幻視家、ホームレス、知的な障がいのある人、独学で制作を始めた老人など、多様な作り手による作品が含まれ、近年では専門の美術館や画廊も各地にあって、前衛的な美術の一分野として確立しています。」(広島市現代美術館公式サイト)
その中からチェコのプルニーとゼマーンコヴァーの作品を中心に展示されている。
この二人、精神疾患を患っており、もちろん、作品にもそれが反映されている。語弊があるが、気色悪い作品なのだが、それがものすごい迫力で面白い。
万人受けするような作品ではなく、「好き・嫌い」「受け入れられる・受け入れられない」が明確に出るのだと思う。
ワタシが特に強く惹かれたのが、ルボシュ・ブルニーの作品。一見、落書きのようにも見えるのだが、ペンで細密に描き込まれ、根底には解剖学的な知識がある。1つ1つの作品にじっくりと見入っていると「この絵の中にはワタシたちには見えていない何かあるのかも知れない。」と思わせる。さらにチェコ語が理解できたら、そこに暗号めいたものを見い出せるかも知れない。
その感覚がすごく不安感と謎めいたワクワクドキドキ感を醸し出す。(両親の生まれた日からなくなった日まで、1からビッチリと数字を書き込んだ作品もすごい。)
この感覚に近いものがあるなら、ジョン・カーペンターの「マウス・オブ・マッドネス」とか「ビューティフル・マインド」で陰謀説に凝り固まるラッセル・クロウとか「ヘル・ボーイ」のオープニングかな。ラブクラフトのクトゥルフ神話も近いような。(←これらの例示でピンと来る人は本展はオススメだ。)
もう一人のゼマーンコヴァーの作品も脳内に潜む怪獣のよう。うねうねと動き出したら、かなりこわい。
会場で上映されているドキュメンタリー映画「天空の赤」では、アール・ブリュットについて「外国人は外見は似ていても話し方に訛りがあるので、それと分かる。アール・ブリュットも一目でそうと分かるものがある。」と語られるが、確かにそれは実感できる。
他にも「アール・ブリュットとアウトサイダー・アートは違う」とか「芸術とは狂気。」といった発言にも強烈な説得力がある。上映時間の途中から見たのだが、アート系の難解な作品という予想とは裏腹に、ドキュメンタリーとして分かりやすく構成されているので、ちゃんと頭から見直したい。
2人の他にも「天空の赤」に登場する作家の作品も展示されている。
「日曜日の墜落」
過去の飛行機事故を優れた記憶力で再構成し、一定の規則性から未来の事件も引きだそうと、紙ナプキンに書きつづった作品。ちょうど、ナンプレ(数独)を解いて、ル・カレの「ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ」を読んでいたワタシの精神状態にはピッタリフィット。
アレクサンドル・パブロヴィッチ・ロバノフ
ライフルとピストル大好きな病んだロシア人。建物の柱も馬車のスポークも全部ライフル。(笑)
無神論者の共産主義者のアカどものプロバガンダ作品に影響を受けているが、それらが好きなワタシはグッと惹かれる。
ヘンリー・ダーガー
まさか、ヘンリー・ダーガーの作品(実物)が広島でみることができるなんて思わなかったよ・・・。
ここ最近見た中では一番面白かった展覧会。もう一度行ってみるかな。
ただ、さすがに一般受けしない内容なのか、開幕初日の30分後くらいでワタシが3人目くらいの観客のよう。先日行った「ツタンカーメン展」と両極端。これはこれで現代美術館ぽくっていいね。


















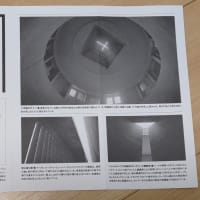







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます