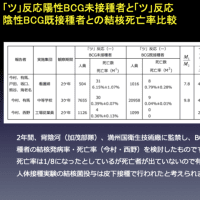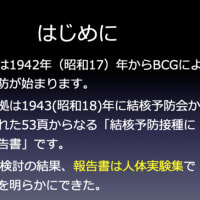天然痘(てんねんとう)は、天然痘ウイルスを病原体とする感染症の一つである。非常に強い感染力を持ち、全身に膿疱を生ずる。仮に治癒しても瘢痕(一般的にあばたと呼ぶ)を残すことから、世界中で不治の病、悪魔の病気と恐れられてきた代表的な感染症。世界で初めて撲滅に成功した感染症でもある(図1)。その大きな感染力、高い致死率(諸説あるが40%前後とみられる)のため、時に国や民族が滅ぶ遠因となったことすらある。疱瘡(ほうそう)、痘瘡(とうそう)ともいう。 医学界では一般に痘瘡の語が用いられた。18世紀半ば以降、ウシの病気である牛痘(人間も罹患するが、瘢痕も残らず軽度で済む)にかかった者は天然痘に罹患しないことがわかってきた。その事実に注目し、研究したエドワード・ジェンナー (Edward Jenner) が1798年、天然痘ワクチンを開発し、それ以降は急速に流行が消失していった。なお、ジェンナーが「我が子に接種」して効果を実証したとする逸話があるが、実際にはジェンナーの使用人の子に接種した。わが国でも種痘をすべくし、シーボルトなどの力を借り、オランダ領インド(インドネシア)から善感した子供の膿疱(図2)を入れようとしたが失敗した。しかし50年後の1849年には種痘後善感した子供の痂皮(かさぶた)を輸入し、佐賀藩の医師・楢林宗健と長崎のオランダ人医師オットー・モーニッケが種痘を実施し、ようやく日本全国に種痘が普及し始める。同年には日野鼎哉(ひの ていさい)が京都に、緒方洪庵が大坂に、「除痘館」という種痘所をそれぞれ開いている。江戸ではやや遅れた1858年に伊東玄朴・箕作阮甫・林洞海・戸塚静海・石井宗謙・大槻俊斎・杉田玄端(すぎた げんたん)・手塚良仙ら蘭方医83名の資金拠出により、神田松枝町(現・東京都千代田区神田岩本町2丁目)の川路聖謨の屋敷内に「お玉が池種痘所」が設立された。除痘館に集められた子供次々に種痘が行われ、腕から腕へと植え継がれたので膿疱をとして、B型肝炎ウイルスは広がった。しかしC型肝炎ウイルスを持つ子供たちは当時少なかったからC型肝炎ウイルスが感染したことは否定できないが、広がったとまでいえない。

↑↑↑
クリックお願いします