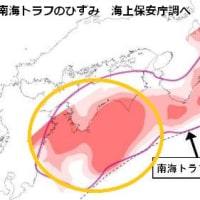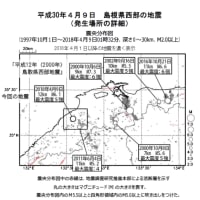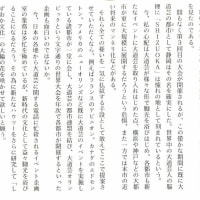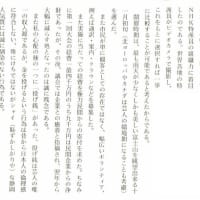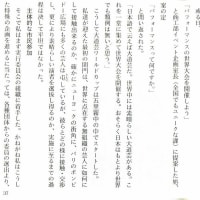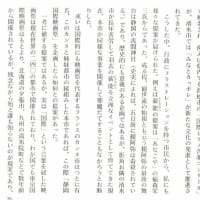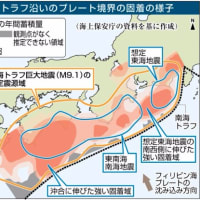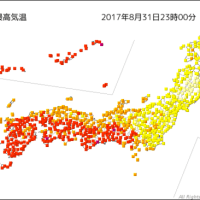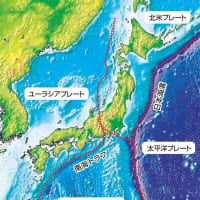鈴虫の音色が日に日に弱っている。
暗闇の中で、秋色を帯びた風に乗って聞こえてくる虫の声。
そのなかで、鈴虫のかごに近づいて来ている声があった。
カネタタキだ。その名のとおり、祭囃子に登場する小さな鉦を叩くかのように、
タッタッタッタッと、リズミカルな特有のなき方。
夕べは、どうやら部屋に入り込んだらしく、寝室に、鉦を叩く音がいつまでも響いた。
あ。。。。今も。。。。この部屋で、生きていけるのかな。
*鳴き声 http://www.nat-museum.sanda.hyogo.jp/wave/docs/kanetataki.html
*動画 http://www.nat-museum.sanda.hyogo.jp/musi/kanetataki.html
昔は蓑虫の鳴き声に間違えられたって、どういうことだろう。
蓑虫って、鳴くのか??
それとも、蓑虫の近くで鳴いていたのか。
鈴虫にもよってくるし、人の住まいに入り込むし、一人が嫌いな寂しがりの虫なのだろうか。
いやいや、一人がイヤでなくのだが、だからといって、他の虫が鳴いているとことに近寄ってくるのがユニーク。
ちなみに、かの清少納言が枕草子の一節で、ミノムシとカネタタキの過ちの記述を残している。
*http://homepage3.nifty.com/a-hiropy/kanetataki.htm

秋の虫、秋風、秋空の今日、そして秋の味覚の訪れ。
栗を頂いて、茹で栗にする。
隣には、大きく開いた黄色い華やかな花。
アオイ、ハイビスカス、その仲間の花だと一目で分かる。
花オクラ、またはトロロアオイ、そしてネリ、漢名は黄蜀葵(オウショクキ)、しかして通和散、
大抵こんな風に、いろんな呼び名を持つ植物は、なじみが深く、愛されていたり活用されてきたものに多い。
トロロアオイが示すように、花は葵で根はトロロ、
これを奈良時代に和紙の繋ぎに用いて日本の紙文化が向上、安定する。
*http://www.hm2.aitai.ne.jp/~row/aboutwashi/tokucho.html
ノリの粘りが身体にもよさそうだ、とご察しのとおり漢方に用いられて咳鎮め。
*http://www2.odn.ne.jp/~had26900/medplant/sonota/tororoaoi.htm
花を用いれば、フラノボイドを含む、腎良花。
*http://www.shizenkc.co.jp/jrk.htm
通和散は、色事に用いられてもいたようで。
ま、その、ぬめりは身体に良いようですな。。。。
花オクラというくらいで、オクラの花にも似ている。
違いはというと、花の大きさと、葉の様子。
「オクラよりも花が大きく、葉がオクラは3~5に浅く分かれるのに比べ、
トロロアオイは5~9に深裂することによって区別できる」
*http://had0.big.ous.ac.jp/~hada/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/choripetalae/malvaceae/hanaokura/hanaokura.htm
*花オクラとオクラとケナフと紅葉葵の違い(花、葉などの写真つき)
http://chimeian.hp.infoseek.co.jp/okura/okura_hanaokura.htm
似ている花は、多い。
*http://www.hana300.com/tororo.html
が、花オクラの名に恥じないオクラっぷりは、食べてみれば一目瞭然、
食べるのに一目って、変だが、一口瞭然、ってことで。
朝開いて、夕にはしぼむ花なのだから、早朝に摘んだのだろうか、たたまれた花びらのパックが売られていた。

パックから出した途端に、今や遅しと開ききって、見事なもの。
花びらを一枚ずつそっとちぎりとって、サラダに載せる。
トロロアオイは、エディブルフラワーでもあったのだ。
噛んでみると、癖がなく、しかも、ぬるりと粘りが。
花まで粘るのか。。。。
夏の疲れを癒してくれそうだ。
*オクラと花オクラ
http://member.cyberstation.ne.jp/mmb/MBWFREES/JR3191137045/IBCDATA0072.HTM
*花オクラの一生
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Kaede/1637/hanaokura.html
*オウショッキ(トロロアオイ)
http://www.hana300.com/tororo.html