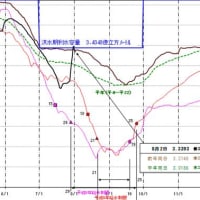本日の長野県県南の天候は快晴でした、かなり良い天気模様でした。
バイオ燃料先進国の米国で、遺伝子組み換えトウモロコシを原料にしたバイオエタノール生産が拡大中だ。穀物価格を高騰させたと批判もある中、生産過程で生じた残りかすを肉牛の飼料とし、牛のふんを肥料として再利用している企業が注目を集める。大量消費を謳歌(おうか)してきた国で循環型社会への転換に向けた新たな試みが始まっている。
◆バーボンの香り コーンベルト地帯に位置し、地平線までトウモロコシ畑が広がる米中西部ネブラスカ州。アドバンスト・バイオエネルギー社の工場から一直線に延びる専用の線路に、100両のタンク貨車が2キロの列をつくる。中身はすべてバイオエタノールだ。担当者は「10日で満杯になります」と語った。
工場の入り口には、原料のトウモロコシを満載した大型トラックが次々と到着。かつては主に飼料やコーンフレークに加工されていたが、ここで年間約3億8000万リットルのエタノールに姿を変える。工場に入ると、アルコールの甘いにおいが漂う。トウモロコシを粉砕して発酵、蒸留する過程はバーボンウイスキーと同じだ。エタノールになるのは3分の1で、3分の1の搾りかすが飼料としてトラックに積み込まれ、牛肥育農家に向かう。「かすは牛が食べてくれるし、排出した二酸化炭素も周辺のトウモロコシが吸収してくれる。無駄がないでしょう」と担当者は胸を張る。
◆エネ政策転換 近年、米国でバイオエタノール生産が盛んになった背景には、エネルギー政策の転換がある。米議会は2007年、原油の代替エネルギーとして、また地球温暖化対策の切り札にもなるとして、エタノールなどの使用を義務付けた新エネルギー法案を可決、生産を奨励した。
米国の化学・種子メーカーも、収量を上げるため作物の遺伝子を組み換え、農薬をまいても枯れない、害虫にも抵抗性を持つ品種の開発にしのぎを削ってきた。「収量を2倍にする」。大手メーカー、モンサント社の幹部の鼻息は荒い。08年現在、全米の作付面積の8割を遺伝子組み換えトウモロコシが占める。
多くのトウモロコシが原料に回り、シカゴのトウモロコシ相場は08年、例年の約3倍の1ブッシェル当たり7ドルを突破。世界的な穀物価格高騰を引き起こした一因となったと批判を受けた。三重県の四日市大学の河田昌東非常勤講師(69)は「バイオエタノール向けの生産により、穀物輸入国の食糧供給が不安定になる」と懸念。遺伝子組み換えトウモロコシが混入した飼料を食べた牛や牛肉の安全性について、長期的な検査はされていないとも指摘する。
◆日本向けの肉牛も ネブラスカ・トウモロコシ協会のランディ・クレイン市場開発部長は「農家はシカゴの穀物相場を見て、価格が高い時に売るだけだ」。「食料か燃料か」の穀物争奪戦は、生産者の関心外だと強調する。
バイオエネルギー社の工場から車で約3時間。約5万頭を育てる大規模な牛肥育場で、数え切れない頭数の牛が餌に群がっていた。支配人のジョン・シュローダーさんが両手ですくった餌に、エタノールを搾り終えたかすが交じる。「ふんは肥料としてトウモロコシ畑に返す。すべて、循環しているんです」
肥育場には耳に水色の標識を付けた日本向けの牛の姿も。消費者の「食の安全」に対する関心が高いことを反映し、「ほかの牛と違い、生年月日や餌など生産履歴を管理している」とシュローダーさんは説明する。バイオ燃料を起点とする新たなサイクルは、すでに日本も巻き込みながら回り始めている。
アメリカがその気になって実行を始めたとき、その実行力はやはり日本の比ではない、と言えましょうか。
栽培エネルギー、循環型社会と言った言葉が聞こえて来て、まだそれほどの年月は経過していないと思いますが、早くも栽培エネルギー、循環型社会へと移行を始めているようです。
やはり日本は、日本人は、社会の急速な変化を嫌う、そんな所があるように思います。
バイオエタノール燃料の開発、販売路の開発、バイオエタノール車の開発と言った事を、本来なら日本の自動車会社が先頭に立って走るべきなんですが、どうもそう言った気配が見えてきません。
相変わらず・・失敗を恐れる社会なんでしょう、この日本社会は。
バイオ燃料先進国の米国で、遺伝子組み換えトウモロコシを原料にしたバイオエタノール生産が拡大中だ。穀物価格を高騰させたと批判もある中、生産過程で生じた残りかすを肉牛の飼料とし、牛のふんを肥料として再利用している企業が注目を集める。大量消費を謳歌(おうか)してきた国で循環型社会への転換に向けた新たな試みが始まっている。
◆バーボンの香り コーンベルト地帯に位置し、地平線までトウモロコシ畑が広がる米中西部ネブラスカ州。アドバンスト・バイオエネルギー社の工場から一直線に延びる専用の線路に、100両のタンク貨車が2キロの列をつくる。中身はすべてバイオエタノールだ。担当者は「10日で満杯になります」と語った。
工場の入り口には、原料のトウモロコシを満載した大型トラックが次々と到着。かつては主に飼料やコーンフレークに加工されていたが、ここで年間約3億8000万リットルのエタノールに姿を変える。工場に入ると、アルコールの甘いにおいが漂う。トウモロコシを粉砕して発酵、蒸留する過程はバーボンウイスキーと同じだ。エタノールになるのは3分の1で、3分の1の搾りかすが飼料としてトラックに積み込まれ、牛肥育農家に向かう。「かすは牛が食べてくれるし、排出した二酸化炭素も周辺のトウモロコシが吸収してくれる。無駄がないでしょう」と担当者は胸を張る。
◆エネ政策転換 近年、米国でバイオエタノール生産が盛んになった背景には、エネルギー政策の転換がある。米議会は2007年、原油の代替エネルギーとして、また地球温暖化対策の切り札にもなるとして、エタノールなどの使用を義務付けた新エネルギー法案を可決、生産を奨励した。
米国の化学・種子メーカーも、収量を上げるため作物の遺伝子を組み換え、農薬をまいても枯れない、害虫にも抵抗性を持つ品種の開発にしのぎを削ってきた。「収量を2倍にする」。大手メーカー、モンサント社の幹部の鼻息は荒い。08年現在、全米の作付面積の8割を遺伝子組み換えトウモロコシが占める。
多くのトウモロコシが原料に回り、シカゴのトウモロコシ相場は08年、例年の約3倍の1ブッシェル当たり7ドルを突破。世界的な穀物価格高騰を引き起こした一因となったと批判を受けた。三重県の四日市大学の河田昌東非常勤講師(69)は「バイオエタノール向けの生産により、穀物輸入国の食糧供給が不安定になる」と懸念。遺伝子組み換えトウモロコシが混入した飼料を食べた牛や牛肉の安全性について、長期的な検査はされていないとも指摘する。
◆日本向けの肉牛も ネブラスカ・トウモロコシ協会のランディ・クレイン市場開発部長は「農家はシカゴの穀物相場を見て、価格が高い時に売るだけだ」。「食料か燃料か」の穀物争奪戦は、生産者の関心外だと強調する。
バイオエネルギー社の工場から車で約3時間。約5万頭を育てる大規模な牛肥育場で、数え切れない頭数の牛が餌に群がっていた。支配人のジョン・シュローダーさんが両手ですくった餌に、エタノールを搾り終えたかすが交じる。「ふんは肥料としてトウモロコシ畑に返す。すべて、循環しているんです」
肥育場には耳に水色の標識を付けた日本向けの牛の姿も。消費者の「食の安全」に対する関心が高いことを反映し、「ほかの牛と違い、生年月日や餌など生産履歴を管理している」とシュローダーさんは説明する。バイオ燃料を起点とする新たなサイクルは、すでに日本も巻き込みながら回り始めている。
アメリカがその気になって実行を始めたとき、その実行力はやはり日本の比ではない、と言えましょうか。
栽培エネルギー、循環型社会と言った言葉が聞こえて来て、まだそれほどの年月は経過していないと思いますが、早くも栽培エネルギー、循環型社会へと移行を始めているようです。
やはり日本は、日本人は、社会の急速な変化を嫌う、そんな所があるように思います。
バイオエタノール燃料の開発、販売路の開発、バイオエタノール車の開発と言った事を、本来なら日本の自動車会社が先頭に立って走るべきなんですが、どうもそう言った気配が見えてきません。
相変わらず・・失敗を恐れる社会なんでしょう、この日本社会は。