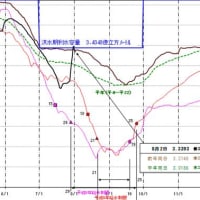【バンコク鵜塚健】タイの大洪水は5日、バンコク都心部から約5キロの地点まで迫り、デパートや企業の事務所が集中する首都中心部の被害は避けられないとの見方が強まっている。事務所ビルや商業施設は土のうを積み増して備えているが、本格的な冠水になれば交通網の寸断などで都市機能がマヒし、市民生活や企業活動に甚大な影響を与えそうだ。
この日、洪水は都心部を走る高架鉄道の終着駅付近に達した。高架鉄道は「水位が2メートル以下なら運行を続ける」としているが、終着駅で接続する地下鉄は浸水を防ぐため出入り口の一部を閉鎖しており、トンネルへの浸水の危険が高まれば運行を停止する見込みだ。
政府はバンコク北部で大型の土のうを使って仮設の堤防を築き、都心部方面へ流れ込む水を減らそうとしている。この数日、水の南下速度はやや緩やかになり、専門家は都心部の冠水は最悪でも50センチ程度にとどまると見ている。
在留日本人の自宅が集中する都心部東部スクンビット地区につながる運河の水位はまだ余裕がある状態だ。当局は北部や東部からの水を運河を通してチャオプラヤ川に排水する方針。今月10日ごろには再びタイ湾の潮位が高まり、川の流れが滞るため、運河増水にも警戒が必要となる。
バンコク都心部では昨年、タクシン元首相派市民団体による占拠で1カ月半にわたり都市機能がマヒしたばかり。占拠された交差点付近で花束を売るタニダンさん(46)は「ようやく観光客が戻り始めたのに洪水で完全に逆戻りだ。花の産地も被害を受け、仕入れの花代も値上がりして散々だ。一時的に浸水してもいいから、早く回復してほしい」と話した。
連日報道されているタイの洪水ですが、ますます冠水地域が増えているようです。50年に一度の洪水と、それほど多くの雨が降ったわけではなく、また洪水の多い地域である事も間違いなさそうです。
むろん、地球温暖化の影響もあって、降った雨の量も多かったに違いなく、しかしここまで被害が増加したのは、人災的な影響が強いようです。
では日本ではどうかと言えば、洪水の歴史は当然あります。
戦後に限って見ると、1000人規模の死者行方不明者を出した洪水は、ウィキペディアで紹介されている範囲では以下の通りです。
1945年(昭和20年)9月17日-9月18日 枕崎台風 死者2473名 行方不明1283名
1947年(昭和22年)9月14日-9月15日 カスリーン台風 死者1077名 行方不明853名
1953年(昭和28年)6月25日-6月29日 昭和28年西日本水害死者759名 行方不明242名
1953年(昭和28年)7月17日-7月18日 紀州大水害 死者615名 行方不明431名
1954年(昭和29年)9月24日-9月27日 洞爺丸台風 死者1361名 行方不明400名
1958年(昭和33年)9月26日-9月28日 狩野川台風 死者888名 行方不明381名
1959年(昭和34年)9月26日-9月27日 伊勢湾台風 死者4697名 行方不明401名
昭和20年代から30年代の半ばまでに集中している事が判ります。
日本国内で洪水が減った原因は、日本列島がやや乾燥化しつつあって、広範囲に大量に雨が降る事が少ない事もありますが、やはり最大の原因は治水ダムの整備と河川改修にあると思います。
ダムの話はいずれすることにしますが、国内にそれだけの資本を投下した日本国内は、比較的洪水に強いと言えます。
と言っても今年の台風で、紀伊半島中央部は大変な事になりました。タイの事は笑えない状況でもあります。
この日、洪水は都心部を走る高架鉄道の終着駅付近に達した。高架鉄道は「水位が2メートル以下なら運行を続ける」としているが、終着駅で接続する地下鉄は浸水を防ぐため出入り口の一部を閉鎖しており、トンネルへの浸水の危険が高まれば運行を停止する見込みだ。
政府はバンコク北部で大型の土のうを使って仮設の堤防を築き、都心部方面へ流れ込む水を減らそうとしている。この数日、水の南下速度はやや緩やかになり、専門家は都心部の冠水は最悪でも50センチ程度にとどまると見ている。
在留日本人の自宅が集中する都心部東部スクンビット地区につながる運河の水位はまだ余裕がある状態だ。当局は北部や東部からの水を運河を通してチャオプラヤ川に排水する方針。今月10日ごろには再びタイ湾の潮位が高まり、川の流れが滞るため、運河増水にも警戒が必要となる。
バンコク都心部では昨年、タクシン元首相派市民団体による占拠で1カ月半にわたり都市機能がマヒしたばかり。占拠された交差点付近で花束を売るタニダンさん(46)は「ようやく観光客が戻り始めたのに洪水で完全に逆戻りだ。花の産地も被害を受け、仕入れの花代も値上がりして散々だ。一時的に浸水してもいいから、早く回復してほしい」と話した。
連日報道されているタイの洪水ですが、ますます冠水地域が増えているようです。50年に一度の洪水と、それほど多くの雨が降ったわけではなく、また洪水の多い地域である事も間違いなさそうです。
むろん、地球温暖化の影響もあって、降った雨の量も多かったに違いなく、しかしここまで被害が増加したのは、人災的な影響が強いようです。
では日本ではどうかと言えば、洪水の歴史は当然あります。
戦後に限って見ると、1000人規模の死者行方不明者を出した洪水は、ウィキペディアで紹介されている範囲では以下の通りです。
1945年(昭和20年)9月17日-9月18日 枕崎台風 死者2473名 行方不明1283名
1947年(昭和22年)9月14日-9月15日 カスリーン台風 死者1077名 行方不明853名
1953年(昭和28年)6月25日-6月29日 昭和28年西日本水害死者759名 行方不明242名
1953年(昭和28年)7月17日-7月18日 紀州大水害 死者615名 行方不明431名
1954年(昭和29年)9月24日-9月27日 洞爺丸台風 死者1361名 行方不明400名
1958年(昭和33年)9月26日-9月28日 狩野川台風 死者888名 行方不明381名
1959年(昭和34年)9月26日-9月27日 伊勢湾台風 死者4697名 行方不明401名
昭和20年代から30年代の半ばまでに集中している事が判ります。
日本国内で洪水が減った原因は、日本列島がやや乾燥化しつつあって、広範囲に大量に雨が降る事が少ない事もありますが、やはり最大の原因は治水ダムの整備と河川改修にあると思います。
ダムの話はいずれすることにしますが、国内にそれだけの資本を投下した日本国内は、比較的洪水に強いと言えます。
と言っても今年の台風で、紀伊半島中央部は大変な事になりました。タイの事は笑えない状況でもあります。