9/8にFIT2010という会議で「仮想社会と電子書籍:紙の本はなくなるのか?」なる企画があった。長尾氏(国会図書館)、高野氏(NII)、佐藤氏(Google)、土屋氏(千葉大)がそれぞれTalkを行った。前者3人は実はあまり表題とは関係なく、図書と電子化に関わる話題提供だったが、土屋氏だけは正面から表題の問いに答えていた。
答え:YES。
理由は以下の通り。そもそも電子化云々の前に日本の出版業は衰退産業、右肩下がりになっている。それは負の連鎖ができてしまっているから。いま生き延びているのは再販制度のおかげでかろうじて出版し続けるとOKという仕組みに支えられているだけ。日本の電子書籍は紙の本の出版を前提に考えている。ならば、電子書籍も成立しないだろう。まあメディアの多様化でメディアの一つとして生き延びるだろけど。じゃあ何かできるか?ほとんどないが、情報鎖国でしないかぎりだめでしょうね。
そのとき僕からも一つ質問(コメント)をした。時間がなかったのであまり突っ込めなかった。それをここで書いておく。
出版業界が衰退するのはしょうがない。事実だし、もう実際救えないのだろう。確かにそれは我々の文化を担ってきた産業を消えるというのは困ったことだ。でもそれをもって書物を出版してそれを読むという文化活動が衰退することにはならない。出版業界=出版ではない。まさにインターネットを通じた電子書籍はいままでのような産業構造がなくても本が出版できる環境を用意している。つまり、いままでの著者-編集者-出版社-印刷業-取り次ぎ-書店というような産業構造はなくても、「出版」は成立するのである。
ただし、それには新しい担い手と新しい文化的仕組みが必要である。単に技術的に可能ではだめである。現にいままでもインターネットで書籍相当の情報を出すことができるが、それが「出版」となっていない。
これからの担い手と文化的仕組みはいわゆる同人型になると僕は思っている。ある種の先祖がえりかも知れない。同人誌では必ずしも経済的利益のために活動するのではない人たちが同士を募って出版する。経済的面でいえばかつての同人出版は借金を背負ってまでという悲壮なものだったけど、電子出版ならコストはほとんどかからないのでそうはならない。同人出版の重要な点は経済的な点だけではない。同人出版において出版の基準は自分たちの基準で決める。それなりに基準があるというところが重要である。いわゆる普通の出版に比べればその基準は低かったり特異だったりする。読者はその基準が気に入ればその同人を購読する。いやなら購読しなければよい。でも、そういった基準があるおかげで、作者と読者は安定したつながりをつくることができる。出版ではこれが重要である。
学術出版、ことに国内に限れば、学術出版は限りなく同人出版に近い。まず経済的に作者側の持ち出しが大きい。一般の方は知らないかも知れないが、日本の学会誌では論文を載せる方がお金を払うというところが沢山ある。また、基準だって身内の基準である。論文掲載基準は一般にピアレビューといって同分野の研究者が論文を読んで論文の価値を決めて掲載か否かを決める。両方とも同人誌と同じである。学術誌が同人誌だなんていうと顔をしかめる人もいるかも知れないが、僕はネガティブにいっているわけではない。むしろ逆で、学術出版は同人出版として成り立っていることに可能性を見いだしているである。
先も述べたようにこれまでの同人出版はお金のかかるものであったが、電子出版になれば劇的にコストが下がる。経済的利益を第一に考えるのではなければ同人出版はコスト的には十分な成り立つ訳である。もちろん、読者がいなければ出版にならない。学術といういささか特殊な分野では成り立っていることは先にも述べた。
ご承知のようにもっと広く社会で受け入れられている。同人といってふつう思い浮かべるのは漫画アニメ系の同人であろう。これはもはや社会現象、風物詩となっているコミケをみれば一目瞭然であろう。三日間で50万人を集めるイベントはそうない。
日本の社会は職業的クリエータと趣味的クリエータの境界が低く、同人的文化は受け入れやすいものになっていると思っている。これは職業的クリエータの存在を否定するわけではない。頂点に作品でもうけることができる職業的クリエータがいて、一方でアマチュアがいて、それがシームレスにつながっているということである。このような文化はそれこそ、平安時代の詩歌から、明治期の同人誌まで面々とつながっていて、その末端に漫画やアニメの同人誌があるだろう。
同人というまとまりはもっていないけど、クリエティブな活動の裾野が広いことは数々のネット上のサービスに現れている。ニコニコ動画やpixivの膨大な作品、多数の携帯小説サイトとその中の大量の作品。これをみれば日本人がいかにクリエイティブな活動に参加していることがわかるだろう。
いままで同人出版は出版において価値の低いもの、あるいは怪しいものとして、商業出版という”正しい”出版の範疇外に置かれていた。ここでいいたいのは、むしろ逆で,同人出版を基本として、その特殊事例として商業出版があるという仕組みなら、可能ではないかということである。コストを最小すること、自分たちで基準を作り編集すること、自らで読者を開拓すること、こういった同人出版の仕組みが持続可能であり、その中で大きな読者を得られるものはいわゆる”商業出版”的出版になるという訳である。まあ先祖返りというか出版の原点に戻るだけ、ということも知れないけど。
まあ、そのくらいドラスティックな変化がないと、日本語という限られた話者の言語の文化を維持できないのはないかというのが僕の危機感である。
もっとも同人出版の電子化には別の問題がある。それは長くなったので別稿で。
答え:YES。
理由は以下の通り。そもそも電子化云々の前に日本の出版業は衰退産業、右肩下がりになっている。それは負の連鎖ができてしまっているから。いま生き延びているのは再販制度のおかげでかろうじて出版し続けるとOKという仕組みに支えられているだけ。日本の電子書籍は紙の本の出版を前提に考えている。ならば、電子書籍も成立しないだろう。まあメディアの多様化でメディアの一つとして生き延びるだろけど。じゃあ何かできるか?ほとんどないが、情報鎖国でしないかぎりだめでしょうね。
そのとき僕からも一つ質問(コメント)をした。時間がなかったのであまり突っ込めなかった。それをここで書いておく。
出版業界が衰退するのはしょうがない。事実だし、もう実際救えないのだろう。確かにそれは我々の文化を担ってきた産業を消えるというのは困ったことだ。でもそれをもって書物を出版してそれを読むという文化活動が衰退することにはならない。出版業界=出版ではない。まさにインターネットを通じた電子書籍はいままでのような産業構造がなくても本が出版できる環境を用意している。つまり、いままでの著者-編集者-出版社-印刷業-取り次ぎ-書店というような産業構造はなくても、「出版」は成立するのである。
ただし、それには新しい担い手と新しい文化的仕組みが必要である。単に技術的に可能ではだめである。現にいままでもインターネットで書籍相当の情報を出すことができるが、それが「出版」となっていない。
これからの担い手と文化的仕組みはいわゆる同人型になると僕は思っている。ある種の先祖がえりかも知れない。同人誌では必ずしも経済的利益のために活動するのではない人たちが同士を募って出版する。経済的面でいえばかつての同人出版は借金を背負ってまでという悲壮なものだったけど、電子出版ならコストはほとんどかからないのでそうはならない。同人出版の重要な点は経済的な点だけではない。同人出版において出版の基準は自分たちの基準で決める。それなりに基準があるというところが重要である。いわゆる普通の出版に比べればその基準は低かったり特異だったりする。読者はその基準が気に入ればその同人を購読する。いやなら購読しなければよい。でも、そういった基準があるおかげで、作者と読者は安定したつながりをつくることができる。出版ではこれが重要である。
学術出版、ことに国内に限れば、学術出版は限りなく同人出版に近い。まず経済的に作者側の持ち出しが大きい。一般の方は知らないかも知れないが、日本の学会誌では論文を載せる方がお金を払うというところが沢山ある。また、基準だって身内の基準である。論文掲載基準は一般にピアレビューといって同分野の研究者が論文を読んで論文の価値を決めて掲載か否かを決める。両方とも同人誌と同じである。学術誌が同人誌だなんていうと顔をしかめる人もいるかも知れないが、僕はネガティブにいっているわけではない。むしろ逆で、学術出版は同人出版として成り立っていることに可能性を見いだしているである。
先も述べたようにこれまでの同人出版はお金のかかるものであったが、電子出版になれば劇的にコストが下がる。経済的利益を第一に考えるのではなければ同人出版はコスト的には十分な成り立つ訳である。もちろん、読者がいなければ出版にならない。学術といういささか特殊な分野では成り立っていることは先にも述べた。
ご承知のようにもっと広く社会で受け入れられている。同人といってふつう思い浮かべるのは漫画アニメ系の同人であろう。これはもはや社会現象、風物詩となっているコミケをみれば一目瞭然であろう。三日間で50万人を集めるイベントはそうない。
日本の社会は職業的クリエータと趣味的クリエータの境界が低く、同人的文化は受け入れやすいものになっていると思っている。これは職業的クリエータの存在を否定するわけではない。頂点に作品でもうけることができる職業的クリエータがいて、一方でアマチュアがいて、それがシームレスにつながっているということである。このような文化はそれこそ、平安時代の詩歌から、明治期の同人誌まで面々とつながっていて、その末端に漫画やアニメの同人誌があるだろう。
同人というまとまりはもっていないけど、クリエティブな活動の裾野が広いことは数々のネット上のサービスに現れている。ニコニコ動画やpixivの膨大な作品、多数の携帯小説サイトとその中の大量の作品。これをみれば日本人がいかにクリエイティブな活動に参加していることがわかるだろう。
いままで同人出版は出版において価値の低いもの、あるいは怪しいものとして、商業出版という”正しい”出版の範疇外に置かれていた。ここでいいたいのは、むしろ逆で,同人出版を基本として、その特殊事例として商業出版があるという仕組みなら、可能ではないかということである。コストを最小すること、自分たちで基準を作り編集すること、自らで読者を開拓すること、こういった同人出版の仕組みが持続可能であり、その中で大きな読者を得られるものはいわゆる”商業出版”的出版になるという訳である。まあ先祖返りというか出版の原点に戻るだけ、ということも知れないけど。
まあ、そのくらいドラスティックな変化がないと、日本語という限られた話者の言語の文化を維持できないのはないかというのが僕の危機感である。
もっとも同人出版の電子化には別の問題がある。それは長くなったので別稿で。










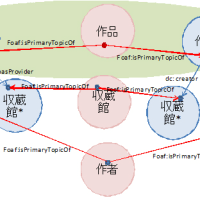
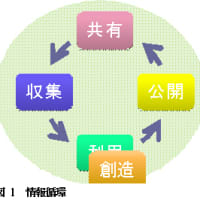


日本の出版産業が昨今の電子化時代以前から(1990年代から)長期低落であることは、数字が示しており、分析もいろいろあります(典型的には、講演でも引用した経産省2003年の“出版産業の現状と課題”です)。どの分析もなんとなく説得力がないような気もしますが、業界識者の共通認識として、「再販制」と「委託販売制」によって市場が硬直しているからであるということが(実際には因果関係の実証はないようのも思われるのですが)指摘されています。専門家ではないので、この共通認識を信じることにしたというのが、当該講演での前提です。ただし、武田さんは「再販制」だけ引用されていますが、「委託販売制」がそれに優るとも劣らず重要であろうと考えられていると思います(委託販売制の仕組みについては、上記経産省文書を参照してください)。個人的には、現状を理解するためにはこちらの要素を無視することはできないと思っています。
もうひとつ強調したつもりであるのは、雑誌を含めた出版産業においては、広告という要素を無視することができないということです。その広告の媒体別費用について、昨年インターネットへの出稿が新聞のそれを金額ベースで上回ったことは最近のひとつの話題でした。雑誌による広告費は2006年にすでにインターネットに抜かれています。しかし、新聞は別としても図書・雑誌の流通のシステムの規模が経済的に印刷媒体の流通を意味あるものとしてきたことは事実だと思います。つまり、日本の出版産業は、上述のような産業構造の問題もさることながら、そもそも流通を維持するだけの経済規模をもち得なくなってしまったのではないかということです。これは、インターネットの影響ではありそうです。
これらのことから、印刷媒体による情報流通というモデルはもはや不可能となりつつあり、かつ、大学関係でいわゆる「外国雑誌」の電子ジャーナル化によってすくなくとも国際的な科学技術医学医療関係のコミュニケーションに関して電子的流通のビジネスモデルが定着しつつある現在、印刷媒体による情報流通というモデルに代わる何かが、これからの情報流通のモデルとして必要なのではないかということであったわけです。
一応、スライドは、
http://cogsci.l.chiba-u.ac.jp/~tutiya/Talks
でご覧いただけます。
さて、武田さんの「同人誌」モデルですが、「別稿」で回答が用意されているかもしれませんが、ひとつ疑問点をあげておきます。
とりわけ雑誌については、これまでも実質的には「同人誌」のようなものだったわけです。たとえば10人の短歌同人が自分達の同人誌を作ることは、オンラインであれ、プリントであれワープロとゼロックスでそれほど大変ではないでしょう。昔であれば、それを書店に持っていったり、路上で販売したりして、対価徴収してみたり、自分達の考え方(歌風--短歌ではこうは言わないのかもしれませんが)を広く世に訴えたりしたわけです。今ならば、有料ウェブサイトやブログやGoogle Sitesなどでいくらでも人に知ってもらうことはできるわけです。
この10人が100人になると、質もさまざまになりすべてを掲載するわけにもいかないので、他人様に見せてよいものをそうでないものを同人が選択することになるわけです。こうなるとときとして意見の合わない人がでてきて、そういう人々は「独立」したりして、また10人規模から始めるということになります。これも上述のようなプロセスを経て、現代では楽なことです。
100人が1000人になると、どのようなものをブログサイトに載せるかが決まったあとは上述のようにすべてが用意ですが、そもそも会員管理がけっこく大変になります。いや、同人という理念共有型の集団では管理なんかいらないのだという理想はありますが、それはたんなる理想です。すると、そのような管理をするたとえば、事務局が必要になります。これをボランティア(余暇に無給)でやることも可能ですが、いずれにせよそろそろ経費が認識されるようになります。もちろん、すべてを郵送に頼った昔にくらべ、メーリングリストですべてがすみそうな現在では、そのような経費はおそらく非常安くなっています。
しかしさらにその同人がどんどん成長して、1000人が10000人になると、ボランティア的な貢献では同人を維持することができなるかもしれません。いや多分そのくらいの「同人」がいれば、商業的(つまり、儲けとまで言わなくても経費は出せる)出版が成り立ったかもしれないのです。
ここで注意するべきことは、経費の性質です、それはコンテンツ生産のための経費ではありません。なぜならば、コンテンツ生産は同人として自分の考え、思いを社会に伝えるものであり、そこに普通は対価請求はないからです。また、媒体制作費は印刷で実費相当だとしても、無料サイトでやればほぼゼロです。つまりそこで発生している経費は、同人を同人として維持するための「人」のための経費です。これは、発表媒体がプリントであれ、オンラインであれ、同人が一定規模を越えればほぼ必然的に発生するものです。この費用をどのようにして実現するべきでしょうか。
多分一番いいのは、会費を徴収してそれにあてることです。実際にそのようなことがさまざまな形で行なわれてきました。多くの場合には会費が媒体制作と会員あて頒布の経費をまかなっていたわけです。そのうえで、同人誌を市場に出すことによって、若干の収益を上げ、それらをあわせて「人」の経費としていたと考えらます。この仕組みのいいところは、会費を払うと同人誌を受け取ることができて、市場に出たぶんは同人の収入になっているようにみるところです。
ところが、これをウェブでやると、ものとしては何も受けとれませんし、会費を払っていない人も等しく同じ(知的、非知的)情報を受けとれます。情報を受けとるだけであれば、別に、会費を払って同人である必要はありません。10000人にもなると、当然集団としては、リーダーとかコアというような人々とフォロアーとかペリフェリというような人々が区別されてきますが、ここでフォロアーとかペリフェリというような人々が理念に共鳴して寄附する同人であり続けるほどの理念であれば、その同人はもつでしょうが、それほどの理念でなければ、10000人の同人は1000人に逆もどりです。しかし、その人数で同人誌が継続できるかは状況次第となってしまいます。
ということで、「同人誌」出版モデルってそもそも成り立つのでしょうか。