
21時からの「筆談ホステス」を見た。
これまでの聴覚障害者を扱ったドラマと違うことがあった。
それは会話の中に身振りやジェスチャーはあっても手話が一度も出なかったことだ。
聴覚障害者=手話の定式化があてはまらなかったドラマは聴覚障害者の多様性を示すものとして意義は大きい。
新聞の番組欄にも「耳の聞こえない」とあった。
もう一つは、聴覚障害者に重要なことはやはり自分に対する「自信」が持てるということが描かれていたことだ。
ドラマにも出ていたが里恵は洋服店でもクラブでも筆談でコミュニケーション出来たことが自信につながっていた。
聞こえる、聞こえないではなく、自分が認められるということが自分に対する自信であり、生きる原動力になる。
三つ目は、聴覚障害者は自分を理解し、支援出来る人が必要だということだ。
里恵には洋服店の店長、青森のクラブのママと弟とかがいて、「大丈夫」、「頑張って」と励ます人がいた。
聴覚障害者に必要なことは、聞こえる聞こえないではなく、自分が生きていることに意味があることを理解し(自尊心)、コミュニケーションの力を身につけ、価値観の多様性を身につけることだ。
そのためのプログラムとそれをきちんとリードできる専門家、ピアメンターが必要になる。
この番組は、聞こえない難聴者問題を解決するために何が必要かを考えさせてくれた。
聴覚障害は、少し難聴気味の高名な聴覚障害児教育の学者をして、難聴になって初めて難聴は説明するのが難しいと言わせるくらい、理解が難しい。
こうした理解のない社会と環境の中で、聞こえないことの意味と自分の生き方を考える機会を与えられる制度が必要だ。
それは、頑張った人だけとかたまたま機会が得られた人だけでなく、様々な聞こえない人がそれぞれにあった支援を受けられなくてはならないからだ。その機会を得ることは権利なのだ。
手話か筆談かでもなく、新聞の番組欄にある「愛と涙の感動秘話」という理解では聴覚障害者は救われない。
ラビット 記
これまでの聴覚障害者を扱ったドラマと違うことがあった。
それは会話の中に身振りやジェスチャーはあっても手話が一度も出なかったことだ。
聴覚障害者=手話の定式化があてはまらなかったドラマは聴覚障害者の多様性を示すものとして意義は大きい。
新聞の番組欄にも「耳の聞こえない」とあった。
もう一つは、聴覚障害者に重要なことはやはり自分に対する「自信」が持てるということが描かれていたことだ。
ドラマにも出ていたが里恵は洋服店でもクラブでも筆談でコミュニケーション出来たことが自信につながっていた。
聞こえる、聞こえないではなく、自分が認められるということが自分に対する自信であり、生きる原動力になる。
三つ目は、聴覚障害者は自分を理解し、支援出来る人が必要だということだ。
里恵には洋服店の店長、青森のクラブのママと弟とかがいて、「大丈夫」、「頑張って」と励ます人がいた。
聴覚障害者に必要なことは、聞こえる聞こえないではなく、自分が生きていることに意味があることを理解し(自尊心)、コミュニケーションの力を身につけ、価値観の多様性を身につけることだ。
そのためのプログラムとそれをきちんとリードできる専門家、ピアメンターが必要になる。
この番組は、聞こえない難聴者問題を解決するために何が必要かを考えさせてくれた。
聴覚障害は、少し難聴気味の高名な聴覚障害児教育の学者をして、難聴になって初めて難聴は説明するのが難しいと言わせるくらい、理解が難しい。
こうした理解のない社会と環境の中で、聞こえないことの意味と自分の生き方を考える機会を与えられる制度が必要だ。
それは、頑張った人だけとかたまたま機会が得られた人だけでなく、様々な聞こえない人がそれぞれにあった支援を受けられなくてはならないからだ。その機会を得ることは権利なのだ。
手話か筆談かでもなく、新聞の番組欄にある「愛と涙の感動秘話」という理解では聴覚障害者は救われない。
ラビット 記










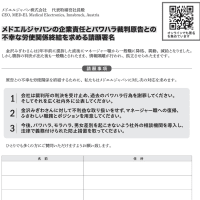

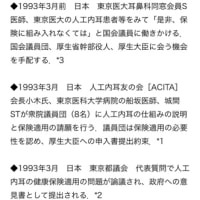






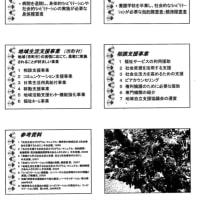

手話が登場しなかったことのほかに、もう一つ今までのドラマと違っているところがありました。
それは、主人公の里恵が声を出してしゃべることです。
「星の金貨」でも「愛していると言ってくれ」でも「オレンジデイズ」でも、絶対声を出さないか、あるいは勇気を出して声を出したことがお話の結末という作りでした。(それがいいか悪いかは別にして)
でもこの作品は、ろう者特有の低い声の不明瞭な話し方をそのまま演じていて、主人公の苦悩にリアリティが感じられました。
そうですね。ちょっと聞きにくかったですが、里恵さん、声で伝えようとしていましたね。
それで、苦悩にリアリティがありましたね。