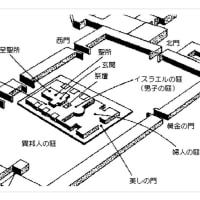30章は、マサの人ヤケの子、アグルのことばとされる。創世記にマサは、イシュマエルの子で、12氏族の長になった七番目の人物として出てくる(創世25:14)。彼の氏族は北アラビヤに住んだと考えられており、アッシリヤのティグラテ・ピレセル3世の碑文にその名が記録されていることが知られている。アグルはその子孫なのだろう。
彼がどんな人生を歩んだのか、知る術もないが、彼は自分が無知であり、悟りがないことを認めている(2節)。確かに、日々馬車馬のように働いているからこそ、今のペースが守られており、そうでなければ、いやそうであっても愚かさに陥ってしまうのが人間である。人間に確かであるということはなかなか言えたものではない。私は大丈夫、そんなことはない、とは言えたものではない、とあなたは思わないか。人間の愚かさというものは底知れず、人間は自分自身というものをわかっていない。人間をわかるとすれば、それは神様だけである。天地をお造りになり、私たちをお造りになった神様だけが、私たちを熟知しておられるのである。
だからこそ、私たちはいつも、神のことばに拠り頼んで、戒めと矯正を与えられ、訓戒と知恵をいただき、自分の歩みを真っ直ぐなものにしなくてはならないのだと思う。「神のことばは、すべて純粋。神は拠り頼む者の盾」(5節)。神は私たちにいつも、真実な私たちの姿を知らせてくれる。そして拠り頼むならば、神はその力をもって、私たちの歩みを守られるのである。アグルはそんな神に二つの願いをしている。一つは、決して嘘偽りを言わないようにということである(8節)。人間にとって不正直であることほど不幸なものはない。どんなに、楽しいことがあろうと、そこに嘘偽りがあるならば、決して心底楽しめないし、たとえその一瞬は忘れていても後に心身を蝕む害毒となってそれは跳ね返ってくる。人間にとって正直が一番、嘘偽りのないことが何よりもの平安であり、豊かさである。そして、アグルは願う。貧乏にも金持ちにもせず、ただ日々必要なものを与えてください、と。貧しさは嫌である、金持ちになりたいという思いはわかるものである。しかし金持ちにもなりたくはない、その気持ちもまた理解されるところがあるものだろう。ある金持ちが言っていた。金持ちというのは、ごまかしができると。自分のこころの苦しさ、平安のなさを物でごまかせる。だから物がなくなったら、耐えられないと。不幸な時に、幸せだった時を思い出すのは、苦しいことである。しかし、不幸な時に、あらゆるもので、これをごまかせるとしたら、苦しみと一瞬の楽しみが混じり合い、それも複雑な時になることだろう。ともあれ、貧しさの中で神を呪うことも、また金持ちになり神を忘れ、神に拠り頼むべき時に物に拠り頼むことも、これほど不幸なことはないのである。アグルの人生理解は、良く理解されるところではないだろうか。
10節以降は、断片的な格言集である。蛭のようにしつこく、いつまでも満足しないものがある(15節)。地獄と不妊の胎、水を溜めることのない乾ききった砂漠と消しがたい火(16節)。これは、堅く閉じられた門というべきか。当時のユダヤでは、不妊であるということがいかに不名誉であり、その汚名の消しがたいものであったことを物語っているように思われる。
どんなに考えても分からないことが四つ。いや五つというべきか(18-20節)。確かにおとめへの男の道。若い男女に恋心が芽生えるのか、それは不思議であるという。それは理由のつかないもの、プロセスのよく理解できないものである。それと同じくらいに不可解なのが、悪い事をしながら、それを認められない売春婦の存在というわけである。後ろめたさを感じているのが人間である。しかし、その後ろめたさが麻痺してしまうことがあるから人間はわからない。
ヘドがでるほどいやなことが四つ。男女から二つの例があげられる。奴隷が王となり、謀反人が権力を握り、憎まれ女が結婚をし、女中が女将になる。あって欲しくはないことということだろう。だがそれが起こるのが人間の人生であるから、人生というのはわからない。
感心させられるものが四つ。蟻と、岩だぬき、いなご、やもり。彼らは生きる術を知っている。人間は彼ら以上に知力がありながら、冬の食料を集めることもなく、自分の弱さを弁えず、指導者が無くては行動ができず、住み着くべきところを悟らない。勤勉であり、謙遜であり、真の指導者を弁え、安住すべきところに腰を落ち着けるべきことを、教えられるのではないか。
「乳をかき回すと凝乳ができる。鼻をねじると血が出る。怒りをかき回すと争いが起こる」(33節)。当然の結果というものがある。なるべくしてなったということがある。予測されること、特に悪い結果が予測されるのであれば、それは避けておくべきことが賢明であろう。悟りのある人生を歩ませていただこう。今日も主が、聡明さを得させてくださるように。人生の光の中を歩ませていただけるように祈ることとしよう。
彼がどんな人生を歩んだのか、知る術もないが、彼は自分が無知であり、悟りがないことを認めている(2節)。確かに、日々馬車馬のように働いているからこそ、今のペースが守られており、そうでなければ、いやそうであっても愚かさに陥ってしまうのが人間である。人間に確かであるということはなかなか言えたものではない。私は大丈夫、そんなことはない、とは言えたものではない、とあなたは思わないか。人間の愚かさというものは底知れず、人間は自分自身というものをわかっていない。人間をわかるとすれば、それは神様だけである。天地をお造りになり、私たちをお造りになった神様だけが、私たちを熟知しておられるのである。
だからこそ、私たちはいつも、神のことばに拠り頼んで、戒めと矯正を与えられ、訓戒と知恵をいただき、自分の歩みを真っ直ぐなものにしなくてはならないのだと思う。「神のことばは、すべて純粋。神は拠り頼む者の盾」(5節)。神は私たちにいつも、真実な私たちの姿を知らせてくれる。そして拠り頼むならば、神はその力をもって、私たちの歩みを守られるのである。アグルはそんな神に二つの願いをしている。一つは、決して嘘偽りを言わないようにということである(8節)。人間にとって不正直であることほど不幸なものはない。どんなに、楽しいことがあろうと、そこに嘘偽りがあるならば、決して心底楽しめないし、たとえその一瞬は忘れていても後に心身を蝕む害毒となってそれは跳ね返ってくる。人間にとって正直が一番、嘘偽りのないことが何よりもの平安であり、豊かさである。そして、アグルは願う。貧乏にも金持ちにもせず、ただ日々必要なものを与えてください、と。貧しさは嫌である、金持ちになりたいという思いはわかるものである。しかし金持ちにもなりたくはない、その気持ちもまた理解されるところがあるものだろう。ある金持ちが言っていた。金持ちというのは、ごまかしができると。自分のこころの苦しさ、平安のなさを物でごまかせる。だから物がなくなったら、耐えられないと。不幸な時に、幸せだった時を思い出すのは、苦しいことである。しかし、不幸な時に、あらゆるもので、これをごまかせるとしたら、苦しみと一瞬の楽しみが混じり合い、それも複雑な時になることだろう。ともあれ、貧しさの中で神を呪うことも、また金持ちになり神を忘れ、神に拠り頼むべき時に物に拠り頼むことも、これほど不幸なことはないのである。アグルの人生理解は、良く理解されるところではないだろうか。
10節以降は、断片的な格言集である。蛭のようにしつこく、いつまでも満足しないものがある(15節)。地獄と不妊の胎、水を溜めることのない乾ききった砂漠と消しがたい火(16節)。これは、堅く閉じられた門というべきか。当時のユダヤでは、不妊であるということがいかに不名誉であり、その汚名の消しがたいものであったことを物語っているように思われる。
どんなに考えても分からないことが四つ。いや五つというべきか(18-20節)。確かにおとめへの男の道。若い男女に恋心が芽生えるのか、それは不思議であるという。それは理由のつかないもの、プロセスのよく理解できないものである。それと同じくらいに不可解なのが、悪い事をしながら、それを認められない売春婦の存在というわけである。後ろめたさを感じているのが人間である。しかし、その後ろめたさが麻痺してしまうことがあるから人間はわからない。
ヘドがでるほどいやなことが四つ。男女から二つの例があげられる。奴隷が王となり、謀反人が権力を握り、憎まれ女が結婚をし、女中が女将になる。あって欲しくはないことということだろう。だがそれが起こるのが人間の人生であるから、人生というのはわからない。
感心させられるものが四つ。蟻と、岩だぬき、いなご、やもり。彼らは生きる術を知っている。人間は彼ら以上に知力がありながら、冬の食料を集めることもなく、自分の弱さを弁えず、指導者が無くては行動ができず、住み着くべきところを悟らない。勤勉であり、謙遜であり、真の指導者を弁え、安住すべきところに腰を落ち着けるべきことを、教えられるのではないか。
「乳をかき回すと凝乳ができる。鼻をねじると血が出る。怒りをかき回すと争いが起こる」(33節)。当然の結果というものがある。なるべくしてなったということがある。予測されること、特に悪い結果が予測されるのであれば、それは避けておくべきことが賢明であろう。悟りのある人生を歩ませていただこう。今日も主が、聡明さを得させてくださるように。人生の光の中を歩ませていただけるように祈ることとしよう。