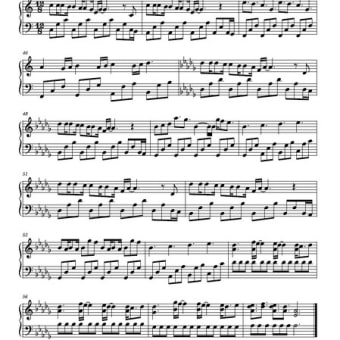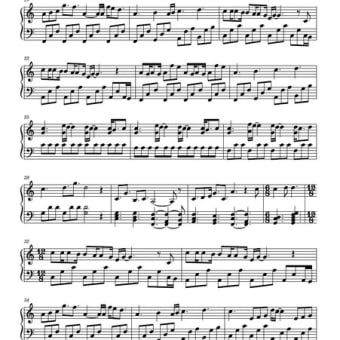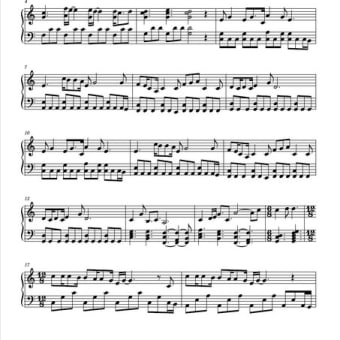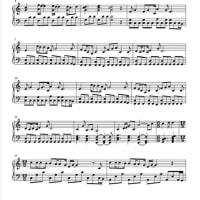「遠い山なみの光」を読み直して、
作品のラスト付近で、景子と万里子が
入れ替わっているということに気づいた、
ということを少し前に書いた。
その後も気になって、
ときどき検索していたら、
amazon のレビューに
驚愕の記述が・・・
<以下、ネタバレ>
原作(英語)で読むと、
他にも、
佐知子-悦子
万里子-景子
が混乱しているところが
あるらしい。
というわけで、早速、Kindle で
原作を買って確認してみた。
顕著なのは、
これもまた作品のラスト付近、
10章の終わり近くで、
悦子が、アメリカには行きたくない、
と言う万里子に語りかけているところ。
原文では、
"if you don't like it
over there, we can always
come back."
翻訳では、
「行ってみて嫌だったら、
帰ってくればいいでしょ」
となっている。
原文だと、"we" は明らかに、
悦子と万里子を指していて、
これは、悦子が万里子ではなく、
自分の娘である景子に対して過去に言った言葉
だと読める。
でも、翻訳だと、そういうふうに
読むことは難しい。
このすぐ後にも、念押しのような悦子の言葉があり、
このあたりで、作者には、
佐知子-悦子
万里子-景子
の二重写し、つまり、
悦子のそれまでの語りの中の
無意識の混乱を一気に明らかにする意図が
あったようだ。
インタビューの中でイシグロさんが答えているように、
佐知子や万里子が実在したのかどうか
(たぶん実在はしたのだろうと思うが)は、
どちらでも良いが、いずれにしても、悦子は、
そうした物語を自らの内に創り出すことによって、
自らのバランスを際どく保っている、
ということ、そして、それは、誰しもが普通にやっていることだ、
ということが、この小説の(そして、イシグロさんの
多くの作品の)大きな主題になっている。
* * *
この作品のこうした側面について詳しく述べた文献として、
山口大学の池園 宏さんが 2016年に書かれた
「喪失の諸変奏-A Pale View of Hills-」が見つかった。
ちなみに、この中で出てくる「インタビュー」というのは、
Gregory Mason という人の 1986年のインタビューで、
"Conversations with Kazuo Ishiguro" という
2008年のインタビュー集に収められている。
残念ながら、電子書籍版は無いようだが、
Google Book でほとんど読めるようだ。
また、JSTOR というサイトに登録すれば、
こちらから、オンラインで読むことができる。
池園さんの批評の最後は、
「イシグロは、そうした人間が陥りがちな人生の過ちを
丹念に描き出し、人間存在の在り方について真摯に問い続ける
作家なのである。」と結ばれている。
でも、それは「人生の過ち」なのだろうか?
イシグロさんの作品には、とりわけ優れた人も、駄目な人も、
殺人鬼も、正義の味方も、天使のような人間も、出てこない。
ごくごく普通の人間が、自分について語るものが多い。
そして、そうした、ごく普通の人のごく普通の人生の中にも、
たくさんの過ちがあり、成功があり、嘘があり、真実があり、
イシグロさんは、そうした山や谷を使いつつ、
私たち人間の意識、記憶、さらには私たちの世界の不思議さ、
怪しさ、そこに潜む闇の深さ、を描き出す。
それはもう、「怪談」の域にも
達しているようだ。
どなたかのレビューにも、
「純文学と思って読んだら、ホラーだった」
と書かれていたが、まさにそんな感じ。
「遠い山なみの光」にしても、
悦子は狂っている、と言えなくもない。
この小説を読んだ後に感じる、
何とも言えない、吐き気を催すような余韻。
今見ているこの世界が、
すべて崩れてゆくような感覚。
ノーベル賞の受賞理由となった
「大きな感情の力をもつ作品において、
我々の世界とつながっているという幻想の下にある
深淵を明らかにした」
も、こういうことを指しているのではないか、と思う。
* * *
ところで、インタビューをした Gregory Mason
という人は、どんな人なのだろう?
と思って検索したら、
こんなサイトが見つかった。
英国の画家なので、インタビューした人とは違うと思うが、
作品の感じはとても良い。
一枚欲しいなぁ・・・
さらに検索すると、インタビュアーは、
どうやら、この人のような感じだ。
最新の画像もっと見る
最近の「本」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事