前回VOL.9で、「情報流通」、つまり、「情報開示」のあり方について、国際海上輸送契約との関係、及び救助契約の性格との関係から、どうあるべきかに言及した。
つまり、契約である限り、契約の両当事者間に契約締結に伴う債権債務の関係が成立し、この契約に伴う債権債務の関係により、「情報開示のあり方」が規定される面があるということである。
今回の事件の場合、衝突事故であり、両船を分離する作業等を伴う大事故であったため、輸送契約に伴う債権債務に、救助行為に関する契約が複合することになり、事件に関する情報の流れが複雑になる側面はあった。
しかし、基本的には、ここの契約に伴う債権債務の関係を整理していくことにより、「情報のあるべき流れ」について、比較的シンプルに理解できたのではないかと考える。
今回VOL.10では、「衝突事件の展開」と「開示すべき情報」につき、その関連を整理していくこととする。
●両船の分離作業成功後の両船の状態
当時、下田海上保安部がこの両船の衝突事件について、事件速報をWEB SITEで公開していた。
下田海上保安部の事故情報は第一報が7月27日午前6時00分に発表され、両船の船体が成功裏に完了する7月29日午後5時00分頃までウォッチが続けられ、同日午後5時15分第三管区海上保安本部発表のニュースが公開されるまでの第八報まで、速報ベースで公開され、8月1日に最終報が公開された。
従って、海上保安部として、日々刻々と事件状況が変化するごとに、9回に渡り速報をニュースとして公表し、WEB SITE上で公開したことになる。
まず、下田海上保安部が撮影した写真を見て頂きたい。なお、この写真は、7月29日に両船の船体分離が成功裏に完了して以降、撮影された写真である。

("WAN HAI 307"号の船体分離後の被損状況)
"WAN HAI 307"号については、機関室が浸水している状況で、船体の機関を使って自力航行(自力航海)ができる状態ではなく、最低限浸水を防止できる応急的な処置を施して、タグボート(曳船)の助けを借りて、最寄の安全港(安全な場所)に非難させ、その後の事件処理の組み立てを行っていくことになる。

("ALPHA ACTION"号の船首部被損状況)
他方、"ALPHA ACTION"号も、船首部に破口が生じており、自力航行ができるとしても、破口部からの浸水による影響がどうか、ということを検討しなければならない状況であった。
自力航行するとしても、破口部に一定の処置を施して、修繕のために修繕ドックに向かうか否かを検討したものと考えられる。
いずれにしても、応急処置を施しても、船首部被損状況から、チリに向かうのは困難ではなかったかと推定され、修繕ドックに入渠し、修繕を施すことになったのではないかと考えられる。
●船会社及びNVOCCの情報公開は具体的にどこから始まるか?
たまたま、今年は7月28日、7月29日は休日であった。
仮にこれがウィークデーであっても、船社及びNVOCCが公表できる情報は限られていた。
理由は簡単。両船の船体が食い込んだ、あるいは、食い込まれた状況で、「海上を漂流している状況(=両船とも動きが取れない状況)」であり、公表できるのはこの情報のみである。
海上保安部による、船体分離成功のニュースは7月29日日曜日午後5時15分であった。
実際にはこれから後、船会社及びNVOCCによる情報公開が必要になってくる。
何故なら、両船の船体分離成功により、その後の事件処理の計画が立てられる段階に入ったからである。
従って、船会社及びNVOCCの具体的な情報公開作業がスタートするのは、今回のような衝突事件の場合、両船の船体分離が成功裏に完了した時点である、といっても過言ではない。
具体的に私の仕事が忙しくなったのも、週明けの7月30日からということになる。
もちろん、その前週シンガポールに出張しており、7月27日関西空港午前着便で帰国したということもあり、27日にこの衝突事件について事件処理をスタートしたが、その日の活動は限られていた。
27日当日は、「事件の一報」を各荷主顧客に知らせるのみで、それを営業ラインの担当者に通知し、営業ライン経由行なったくらいである。
しかし、週明けからは仕事が一変する。ニュースの収集、取りまとめ、荷主顧客に開示するべき情報をコンパクトにまとめ、書面情報として荷主顧客に開示する作業が、両船の船体分離成功により、スタートしたからである。
このVOL.10も、ボリューム的にそこそこの大きさになってきているため、ここで完了させ、VOL.11に移して続きを展開することとする。
Written by Tatsuro Satoh on 15th Sept., 2007
最新の画像[もっと見る]
-
 さらなる進化を遂げる、ロンドンのジャパニーズ・レストラン
16年前
さらなる進化を遂げる、ロンドンのジャパニーズ・レストラン
16年前
-
 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
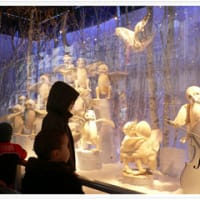 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
 パリのクリスマス
17年前
パリのクリスマス
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 “ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
“ネオ・クラシック”が象徴 2007年のNYトレンド
17年前
-
 神戸ルミナリエ開幕
17年前
神戸ルミナリエ開幕
17年前









