最高の芸術を語り、頽廃を生き、
ロウソクを吹き消すように消えた、
オスカー・ワイルドの貫いた美意識

Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde
1854〜1900
「芸術的な人生というのは、美しくも緩慢なる自殺であると、ぼくは時々考える。それを悲しいとは思わない」
世紀末、イギリスのヴィクトリア王朝の中流家庭に育った才人オスカー・ワイルド。自殺ではないが、死へ向かう道を自ら選び、死すべき時に静かに去った。
人生そのものを芸術に高めるため、自分と社会に挑む。
何を賭けたのか。
「見たこともない花々と精妙な香気に充ちた、いまだ知られざる世界がある。完璧にして有毒なものだけからなる世界が、この世にはあるのだ」
未踏の楽園に踏み入れたあとは、言葉はもういらなくなるようである。
彼は、そうして46歳の生涯を閉じた。
1. 学生時代まで
1854年、ダブリン生まれ。
父ウィリアムは眼科耳科の外科医で、王族の診療も行うことがあった。
母はアイルランドナショナリズムの詩人ジェイン・スペランザ・フランセスカ。
母親は語学力は高いが表現に誇張が多く、大層目立ちたがりで奇抜な格好を好んだ。
その性質は、次男オスカーが引き継いでいる。
オスカーには兄ウィリアムと妹アイソラの他に、父の前妻の子である、兄ヘンリー・ウィルソンとその下に双子の姉妹の姉達がいた。
9歳から16歳までポートラ王立学校で学ぶが、素晴らしい記憶力と速読で読書を極め、とくにラテン語やギリシャ語に優れた。
優秀な成績で、給費生としてダブリン大学トリニティカレッジに進学。古典学での目覚ましい成績によりゴールドメダルが贈られ、5年間の給費付きでオックスフォード大学モードリンカレッジに進学した。
唯美主義に染まり、派手な服装、さらに部屋には、「この世で最も美しく役に立たないもの」として百合をいつでも飾っていたそうだ。
成績は頗る優れていたが、努力している姿を見られるのを嫌い、真夜中に起きだして勉強していたらしい。
 オックスフォード大モードリンカレッジ
オックスフォード大モードリンカレッジエドワード8世(別記事あり)もこちらの卒業生
この頃から、ギリシャ文化に見られる、成人男性と少年の、戦闘に備える鍛錬の中での純粋な愛情の醸成に深く魅了されるとともに、ルネサンス期の人間解放から発展して生じる個人主義、利己残虐性、悪徳の解放にも啓発されていった。
こうした指向のベースには、恩師ウォルター・ペイターが著書『ルネサンス』で指摘する通り、
「経験の結果を求めるのではなく、経験そのものを求める」ところがあるのだが、堅実を良しとするイギリス社会では受け容れられない捉え方であった。
彼は、ギリシャ文学への傾倒のなかで、女性美より男性美(特に肉体美)を崇拝、軍人教育において育まれる同性愛と少年愛の世界にひきこまれていったが、一方で、現実生活では、フローレンス・バルコムという17歳の女性に恋し、失恋。
また、この頃父が亡くなったが、オスカーには不当に僅かな遺産しか遺されなかった。派手好きで金遣いの荒いオスカーには痛手であった。
学業においては、破格に優秀な生徒だった。
優秀な卒業生の王道である、フェローとして大学に残る道を志したが、不運にもポストがなく、諦めることとなった。
意に反して学校を去らねばならなくなったわけだが、
「とにかく有名になる、
たとえ悪名でも名を売る」
と豪語して、新しい世界の扉を開けたのだった。
彼はロンドンへ向かった。
2.ロンドン社交界からアメリカ、パリへ
ロンドンには詩人である母のサロンがあり、オスカーは奇抜な服装で注目を集め、巧みな会話術で魅了し、有名になっていった。
やがて、フランク・マイルズという画家と同居するが、肖像画を依頼してくる著名人らを端に交遊も広まり、“唯美主義者ワイルド”としてカリカチュアも描かれるほどに、ロンドン社交界の有名人になった。
しかし、有名なだけでは収入はなく、稼ぐために戯曲を書こうと思い立つ。
ロシアの女性革命家ヴェラ・ザスーリチをモデルに、空想のストーリーで描かれた戯曲『虚無主義者ヴェラ』は、上演に向けて準備が進められていたにもかかわらず、ロシア皇帝アレクサンドル2世暗殺事件への配慮のため、公演は中止を余儀なくされた。
続いて、詩集を出したが不評であった。
そこへ、アメリカ講演旅行の依頼がきた。
唯美主義者としてアメリカの地で、美についての講演をして廻るというもの。派手な格好でアメリカに降り立ち、早速耳目を集めた。
この講演旅行は評判が良く、オスカーの知名度を高めた。ニューヨークでは『ヴェラ』の戯曲の上演契約を結ぶこともできた。旅の途中で日本へも寄りたがったが、資金不足で果たせなかった。
 アメリカ滞在中に撮影された写真
アメリカ滞在中に撮影された写真その後、パリに出て、またしても今度はバルザック風の衣装に身を包み、芸術家と交流しようと試みたが、反応は冷ややかだった。
パリは世紀末芸術が爛熟を迎えていた。
退廃的な空気が漂い、同性愛が文学にも描かれる土壌は、オスカーには刺激的であったが、ヴェルレーヌと会うと、その文学には感動しても、その実在の醜さに失望を感じた。
3ヶ月ののち、ロンドンに戻った。
3. 結婚、幻滅、同性愛
浪費家で、常に金欠であることから、持参金付きの嫁をもらい、社会的信用も得るべきだと勧められ、中流階級で3歳下、祖父が著名な王撰弁護士であるコンスタンス・ロイド嬢と結婚した。裕福な祖父からの仕送りもあった。
おとなしく、知的で、スタイルも美しく、その美しさは審美性を求めるオスカーにも気に入っていた。静かに夫を支え、のちにどんなことがあっても夫を理解し、苦しみながらも支え続けようとした良妻である。
結婚後、立て続けに二人の息子に恵まれたのだが、出産後の妻は、ほっそりしていた体つきを失う。妻の体型の変化に幻滅したオスカーは、女性の肉体に嫌悪感を持つこととなった。
少年の華奢な肉体への渇望から、オスカーは若者の世界へと出かけていく。
 ワイルド夫妻
ワイルド夫妻あるとき、ハリー・マリリアという、幼い頃から見知っていた青年が、ケンブリッジ大に進学したのを機に再会したオスカーは、大学を訪ね、学生達に即興で物語を聞かせた。元々、オスカーの家系はケルトの口承詩人であったせいもあるからか、オスカーの物語はいつでも聴く人を魅了する大変素晴らしいものだった。このとき語って好評だったものが、のちに「幸福な王子」などの童話作品となっている。
さて、マリリアとはその後文通を続けつつ、次第にただならぬ関係になっていった。ほんのわずかな時間での濃密な逢瀬は、激しい思いが絡み合っていた。
当時のイギリスでは、1885年に刑法改正があり、それまでは口にするのもタブーだとして、同性愛は忌み嫌われるだけでなく、見て見ぬ振りもされていた。同性愛という名前すらなく、うやむやにされていた。つまり、そのような不謹慎なものは存在すらしないのだ、という拒絶的態度なのである。
ただし、法改正まえでも、ソドミーと呼ばれる男性間の肛門性交は、物理的証拠が認められれば死刑になった。罪は、肛門を侵された側がより重かった。ところが、法改正によって、ソドミーだけでなく、精神的な同性同士の恋愛的交わりも処罰の対象となる。手紙の往復すらも、内容によっては対象となった。
オスカーとマリリアの間に、ソドミーがあったとしても、なかったとしても、彼らの交遊は有罪であった。
オスカーには、ルネサンスへの傾倒が根底にあり、禁断を犯すことで、精神と芸術性を研ぎ澄ますことに身震いする陶酔感があったようだ。
それでも、芸術を高めるための原動力として、この頃のオスカーの同性愛は純愛で、コントロールもできていたかと思われる。
冒頭の「芸術的な人生‥」「見たこともない花々と精妙な‥」の言はこの頃の感情である。
秘密の花園に足を踏み入れ、誰にとっても未知の、自分にとっても新しい経験に、鼓動が高鳴る。
4. ロス、グレイ
自分を初めて押し倒したのはロスだ、とオスカーは周囲に言っていた。
ロバート・ロスは出会いの当時は17歳、1986年のこと。ケンブリッジ大学受験のための予備校に通う童顔の青年だが、すでにかなりの“経験者”だった。ロスはケンブリッジ大学キングズカレッジに合格したものの、言動をからかわれ、池に投げ込まれ肺炎を起こし、自分の性癖を暴露し、退学して記者の仕事をするようになった。
じきにロスとの関係は友情に変わり、オスカーを生涯、そしてその死後にも管財人となって支え続けた、かけがえのない親友になった。
その後、オスカーの性的嗜好は大胆になっていき、美青年を複数連れ歩くのが常となった。
 ロバート・ロス青年
ロバート・ロス青年この頃から、派手な生活で抱え込んでいた借金を返すために、減りつつあった講演の仕事から、小説・戯曲書きを始めた。オスカーの筆は、芸術によらず、常に金欠が動かしていた。
才能はこの頃、絶頂を迎えた。
『ドリアン・グレイの肖像』はこの時期の最高傑作だ。ジョン・グレイという美貌の青年が、創造のきっかけだった。
また、『嘘の衰退』では自然主義批判がなされている。
「どんなものでもその美しさを認めるまでは本当に見たことにはならない。そのものの美を認めたとき、初めてものは実在しはじめる」
経験することを通して実在させる、
「自然は芸術を模倣する」
これはオスカー・ワイルドの名言、
「人生は芸術を模倣する」
と同義である。
芸術は、内部に込められた意味を解釈するものでなく、
「この世の真の神秘は目に見えるものであって、目に見えないものではない」
ことを示した。これがオスカー・ワイルドの美学である。
5. 名付けられていない愛、ダグラス
秘密の花園のその先は、どうなっていたか。
暗澹たる沼、
その先は?
オスカーの取り巻きのある青年が、彼の知人で『ドリアン・グレイの肖像』に深く感動し、是非会いたいという貴族の青年がいると言い、伴って現れた。それがアルフレッド・ダグラス卿、当時21歳。スコットランド貴族クィーズベリー侯爵の三男でオックスフォードモードリンカレッジの学生、詩人、つまりオスカーの後輩にあたる。16歳歳下。
 アルフレッド・ダグラス
アルフレッド・ダグラス
 アルフレッド・ダグラスの幼少期
アルフレッド・ダグラスの幼少期母親譲りで美しい子だったので、母は「坊や」という意味のboysieからbodie(ボジー)と呼び、その呼び名は周囲の人からも生涯使用された

 オスカーとアルフレッド・ダグラス卿
オスカーとアルフレッド・ダグラス卿その青年は天使のよう、この世のものとは思えぬほど美しかった。金髪、スミレ色の瞳、小柄、貴族の出自。ダグラスは学生時代から、大胆な同性愛に耽り、ある時そのことで脅迫を受け、オスカーが救ってから、2人は深く関係するようになった。ダグラスは10代半ばほどの少年を好むため、オスカーと関係しつつ、美少年らを手元に置き、時折オスカーと相手を交換もし、男娼だろうと構わず肉体の享楽に耽ったのである。
オスカーはもはや家庭には帰らず、ホテルでダグラスや男娼らと、大っぴらに禁断の行為を楽しんだ。ダグラスはギャンブルも派手だった。当然、ホテル代などで金は底をつく。ダグラスは、自分の遊び代はオスカーの在不在にかかわらず全てオスカーが払うべきだ、と要請した。
我儘で、悪態をつき、どこででもわめき散らすダグラスにオスカーも手を焼き、何度も喧嘩別れと、ダグラスの泣き落としによる再燃を繰り返していた。

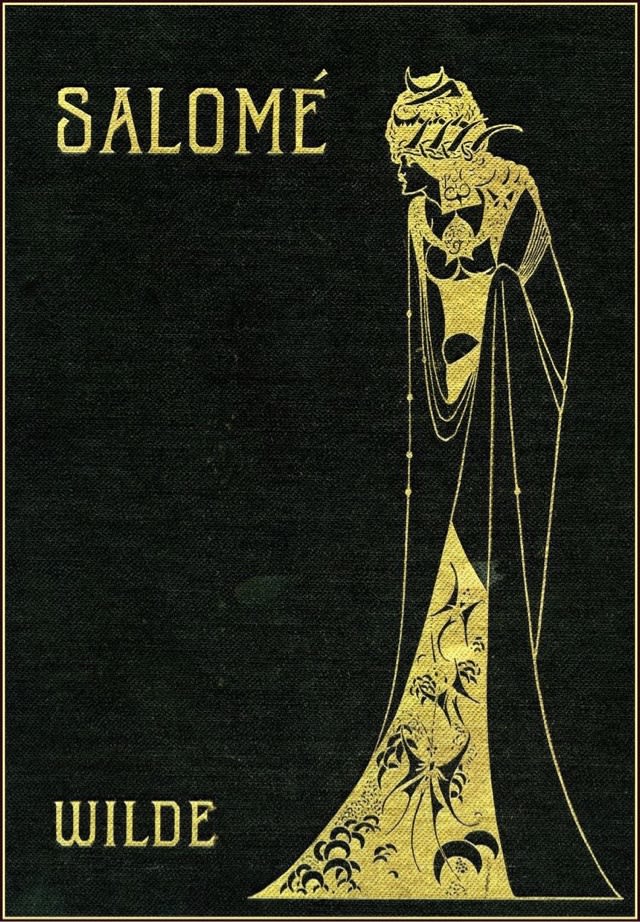
この頃のオスカーの代表作『サロメ』は、原版はフランス語で書かれたが、英訳版をダグラスに翻訳させたところ、オスカーの納得できるものではなかった。修正を依頼したところ、ダグラスは逆上。オスカーはこれを機に別れるつもりだったが、泣き落としに折れた。この英訳版はビアズレーの挿絵でも有名になったが、裏事情にそういう苦労もあったのだ。
私生活は波乱に流され続けたが、この間もお金のために、オスカーは作品を生み続ける。
6. 二つの裁判
快楽のあとにはどんな事態がくるか。
数々の物語の語り部であるオスカーならば、心中では理解していただろう。
放蕩息子ダグラスは、学業は放置、成績は酷いものだった。結局、最後のチャンスの試験も棒に振り、卒業できなかった。
ダグラスの父は激怒する。
ダグラスの父、クィーンズベリー侯爵は、大変な癇癪持ちで、些細なことで激昂しては誰彼となく鞭で打ちのめす性癖があった。4人の息子と、末に一人娘がいた。
長男のフランシス・ドラムランリグ卿はローズベリー首相の秘書を務めていたが、ローズベリーとの間に同性愛を疑われており、クイーンズベリー侯爵はローズベリーを打ちのめしてやろうと画策、鞭を持って、避暑中の二人の前に現れ、襲いかかったが、同席していた皇太子(エドワード7世)が仲裁し、事なきを得た。
 ジョン・ダグラス
ジョン・ダグラス 第9代クィーンズベリー侯爵
フランシスはその後、狩猟中の銃の事故で亡くなる。銃は顎を下から撃ち抜いており、明らかに自殺が疑われた。
この侯爵家には変死が多く、いずれも自殺と推測され得るものだった。
オスカーはこの頃、ダグラスに腹を立て、真剣に別れようとしていたが、フランシスの死を思うと、ダグラスも自殺するかもしれないと思い至り、やむなく復縁した。
オスカーがダグラスと別れようとした理由は2つ、すでにダグラスの父侯爵から、息子と交際するなと脅されていた事と、その頃、ダグラスがインフルエンザに罹った際、オスカーが丁重に看病したにもかかわらず、オスカーが今度インフルエンザに罹ると、ダグラスは看病どころか罵声を浴びせ、姿をくらましたという屈辱があったからだ。
長男を失ったクイーンズベリー侯爵の失意は、同じ同性愛に溺れるもう一人の息子アルフレッドに、復讐のように向けられた。息子を貶める同性愛の相手オスカー・ワイルドとともに、スキャンダルとして公にぶちまけよう、という計画だった。
探偵や男娼らの協力を取り付け、相当際どい証拠まで握った上、敢えてオスカーに侮辱を与え、名誉毀損で訴えさせ、裁判の中で赤裸々な証言を繰り広げることを目的とした。
そのきっかけ作りのカードには、
「男色家を気取るオスカー・ワイルドへ」
とだけ、書かれていた。
sodomiteは当時、口にするのもためらわれるほど、いかがわしい言葉であった。
父を憎むダグラスは、すぐに訴訟にかけようと言いだした。しかし、オスカーの友達も弁護士も、事態を無視することを勧めた。これは罠であると。オスカー自身も危険を感じていた。けれども、結局は、裁判費用は自分が持つからと言うダグラスに押し切られ、クイーンズベリー侯爵を名誉毀損で訴えることになった。
しかし、裁判では‥
数々の証言が正鵠に事実を暴いていき、オスカーは震撼した。その中で、ダグラスの不注意からゆすり屋に握られた手紙はセンセーショナルで、オスカーの最も痛いところを突いてきた。
「君のソネットはとてもすてきだ。
君のバラの花びらのように赤い唇が歌を奏でるためだけでなく狂おしいほど情熱的な接吻のためにあるとはなんとすばらしいことか」
これは芸術であって、個人への感情を述べる手紙なのではない、とオスカーは苦しい説明をしたが、場内は事実に騒然とした。圧倒的に不利になったオスカーは、弁護士と協議して名誉毀損の訴えを取り下げた。
しかし、これだけの証拠が明らかになった事で、ワイルドは猥褻罪で逮捕されるに至った。ダグラスの方は逮捕されなかったのは、彼が貴族階級だからだろう。オスカーは国外逃亡の機会を失った。
裁判では有罪になり、重労働と懲役2年の罰となった。さらに、多額の裁判費用(結局、ダグラスは支払わなかった)が支払えず、破産した。
7. 獄中記〜最期
オスカーには、天啓のように物語が降りてくるのかもしれない。残念ながら現代では、誰をもうっとりさせる彼の至上の語りを聞く事はできないが、語りよりはるかに質が落ちると当時は言われた小説や童話には、彼の辿る人生を予言で示すような展開がある。
自分の最期までの道のりを理解している、という点に限れば彼はイエスに似ているし、実際、自分で自分をイエスと重ねていた。キリストにしてはいかんせん不道徳である。
オスカーは、スキャンダルに巻き込まれる直前に、作家アンドレ・ジッドに語っている。
「ぼくは行ける限り遠いところへ行き着いてしまった。
今は何事か起きるよりほかに仕方ないのだ」
天使の容姿を持つダグラスは、破壊をもたらす天使だったようだ。あるいは、天上の花の姿をした毒。
それを知りながら、その魅力から離れられなくなったオスカー。ダグラスはそもそもコントロールできないし、オスカー自身、理性をどこかで置き捨ててきたようである。
実直なジッドに堕落を吹き込み、高笑するオスカー。
「私は人生の中にこそ精魂をつぎ込んだが、作品には才能しか注がなかった」
彼の作品は、天啓であり、才能である。
それを生むために、人生に破壊的なものを呼び込んだのか。
芸術の最終段階に必要なのは、悲哀だと、初期の作品から既に語られていた。
しかし、芸術の延長としてイメージしていた悲哀と異なり、実際の監獄で体験する悲哀は、過酷で惨めなばかりのものだった。オスカーのこころは枯れていく。
「小さな独房にいる私は、人の形をした影と番号にすぎなかった」
監獄では、ダグラスへの怒りがひたすらこみ上げるばかりだった。しかし、イエスがユダを許したように、自分もダグラスを許さねばならない。人生の物語の筋書き上、どうしてもそうしなければかたちをつけられないからである。
次第に、再びダグラスを心底から求める、そして生きがいになった。その過程は、ダグラスへの手紙の形で、のちに獄中記にまとめられる。
監獄よりも、世界に再び戻らなければならないことのほうが、次第に恐怖になっていった。
自分が存在しなくなった世界を見つめなければならないのだ。
「私を欲しない世界へ、歓迎されざる客として戻らなければならない」
案の定、芸術家たちはビアズレー始め、彼を無視した。現実を受け止めねばならなかったが、お金の心配もあった。ロスや友人達が苦労して集めてきたお金も、オスカーはたちまち浪費した。
そして、周囲の反対を押し切って、オスカーはダグラスと暮らし始めた。オスカーは芸術家として罪人であること、つまり、法には禁じられても、芸術家として罪人(同性愛者)であり続けることは変えられない、と考えてもいた。相変わらずダグラスとの諍いは絶えなかったが、ダグラスは母親から、オスカーは妻から、同棲するなら仕送りを打ち切ると告げられ、背に腹は変えられず二人は別れた。
ロスはときに八つ当たりもされながら、オスカーを距離を持って、支え続けた。
妻コンスタンスは重大な病で苦しいところ、金の無心ばかりしてくる夫に、怒りと憐れみの相反する感情に揺れ動きながら、かつ、二人の子供の将来の備えに腐心しながら、最期まで夫に心を砕いていた。最期、というのは、オスカーのでなく、彼女のである。不幸にも、軽微な手術後に容体がおかしくなり、亡くなってしまった。
オスカーは、自分の死すべき時を悟っていた。
パリで、落ちぶれた日々を過ごしていたオスカー。かつて母の知り合いであった夫人は、オスカーが近づいてきたのに気付きながら、周囲の手前、知らぬ顔をしてしまい、後悔していたが、翌朝、再びオスカーに会った。
(以下斜体字、『オスカー・ワイルド』宮崎かすみ著より引用)
‥夫人が、なぜもう書かないのかと尋ねると、こう答えた。
「書くべきものはすべて書いてしまったからです。
私は人生のなんたるかを知らないときに書きました。
人生の意味を知る今、私にはもう書くべきことがないのです。
それに私にはもう時間がありません。
私は仕事を終えました。
私の生が終わった時、私の作品は生きはじめるのです。
私は幸いにも、監獄で魂を見つけました。
魂について知らずに書いたものも、魂の導きによって書いたものも、いつか世の人々の目に触れるでしょう。
そのとき、私の魂から人類のすべての魂に向けて発したメッセージに人々は気づくのです」
船が河岸に着くと、目に涙をためた夫人に言った。
「私のために悲しまないでください。
どうか祈り、見守ってください。
そう長いことはかかりません」
これほどの覚悟ができているかと思いきや、患っていた耳の病気(この病が死因になる)の手術費用のことで友人に執拗に金の催促をした、というから、芸術家を標榜する人間にしては、相変わらず実生活と精神がかけ離れていると感じる。
天啓とも言える並外れた能力が備わりながら、肉体は欲望のままにさせる二重の影を持つ人物としては、オスカーはラスプーチンに似ていると、私は思う。ただ、オスカーの場合、ダグラスの存在がなければ、事はここに至らなかっただろうか。ダグラスと出会い、破滅し、早世することが、必要な運命だったのだろうか。
もし、オスカーがあと30年生きたとして、世紀末芸術家の旗手が、刻々と変わる時代に合わせて混乱なく作品を残せただろうか。
オスカーは、元から患っていた耳の病が悪化し、脳髄膜炎を引き起こして亡くなった。
1900年11月30日、46歳。
その年の1月、あのクィーンズベリー侯爵も既に亡くなっていた。
新しい20世紀が明けて、1901年1月22日ヴィクトリア女王薨去。ヴィクトリア時代は終わった。
8. 再び、脚光

オスカーを最後に看取ったのは、ロスだった。
ダグラスは死の二日後に駆けつけた。
オスカーの葬儀は友人数人しか参列しなかったが、たくさんの花輪が届けられていた。息子達の名前のものもあった。喪主はダグラスが務めた。
存命中、あれほど本人に冷たかった世間は、オスカー作品の再生には、国内外から次々に手が上がった。
戯曲は上演され、著作はロスによって全集にまとめられ、獲得した印税で、オスカーの負債は返済された。ロスは、出来る限り調べ上げ、生前オスカーにお金を貸した人に利子も添えて返した。また、その後の印税を遺児達が受け取れるように法的手続きをしたのもロスだった。オスカーの次男ヴィヴィアンは、長じてロスを信頼し、慕っていたそうだ。父の代わりのように思っていたのだろう。
ダグラスはどうしていたか。
すでに男性に関心をなくし、同性愛を嫌悪するようになったダグラスは、オスカーの死から2年後、女性詩人と結婚し、息子が1人。放蕩生活から足を洗い、ごく普通の貴族の家庭生活を送るようになった。
また、生涯で何度も、あらゆる名誉毀損裁判で訴えたり訴えられたりを繰り返した。チャーチルに訴えられたこともあり、敗訴している。
ダグラスはロスへの嫉妬から、雪辱に燃えていた。もっとも、オスカーの生前はおそらくロスがダグラスに苛立ちを感じていただろうとは思うが。
ダグラスは父侯爵がオスカーにしたのと同様の手法で、ロスを裁判に引っ張り込んだ。
ロスはオスカーと同様に、取り下げ、敗訴になってしまったが、世論はロスに同情した。ロスはその心労がたたったせいか49歳でなくなった。
ダグラスは、名誉毀損裁判の中で、オスカーについて、「過去350年間にヨーロッパに出現した中で最も邪悪な魔力」と言い、『サロメ』を「最も有害で嫌悪すべき作品」と述べている。
また、ダグラスが一時獄中にあったとき、そこで著した本のタイトルは『高みにて』。
オスカーの獄中記『深き淵より』との対比だけならよいのだが、上段から見下す高慢さが感じられ、不快な印象を与える。
しかしダグラスは、獄中であるときふと、父やオスカーが、かつてあの裁判で賭けたものは何であったか、
自分への愛ではなかったかと考える。
自分は愛されていないと思っていたのか。
破壊するほどかつて愛を渇望したダグラスの気づきには、父もオスカーも失い、尚しばらくの時間を要した。
ダグラスは72歳で亡くなった。
 アルフレッド・ダグラス
アルフレッド・ダグラス ロバート・ロス
ロバート・ロス今、ロスは遺言によりオスカーの隣に、ダグラスは母の隣に埋葬されているという。
9. 名言
目から鱗、言い得て妙な、オスカーの珠玉名言を、私個人の好みでいくつか。
ほとんどの人々は他の人々である。
彼らの思考は誰かの意見、彼らの人生は模倣、
そして彼らの情熱は引用である。
生きるとは、この世でいちばん稀なことだ。
たいていの人は、ただ存在しているだけである。
善人はこの世で多くの害をなす。
彼らがなす最大の害は、人々を善人と悪人に分けてしまうことだ。
戦争が邪悪だと認められている限り、戦争は常にその魅力を持つだろう。これが卑俗なものだと考えられるときは、戦争は一時的なものに終わるだろう。
戦争では強者が弱者という奴隷を、平和では富者が貧者という奴隷をつくる。
文学とジャーナリズムの違いは何だろうか。
ジャーナリズムは読むに耐えない。文学は読む人がいない。
他人に何を読むべきかを教えることは、たいてい無用であるか有害かのどちらかだ。
なぜなら、文学の理解は気質の問題であって、教える問題ではないのである。
付記
10. Stephen Tennant
1906〜1987
19世紀末、保守的なイギリスの同性愛問題は、オスカー・ワイルドが波紋を拡げ、その後はどうなっただろうか。
ダグラスの従姉妹(社交界で話題のウィンダム美人三姉妹の一人パメラ)の子息にあたる、同じスコットランド貴族のステファン・テナントは、男性との恋愛を謳歌し、奔放な人生を送った。20歳年上の詩人ジークフリート・サスーンとの同棲。サスーンはのちに女性と家庭を持ち、テナントはひとり、城館を散らかし放題に、いよいよ晩年の17年間はずっとベッド上で過ごす。奇矯で謎めいた生涯。
愛人?の写真家セシル・ビートンが彼をモデルにたくさんの写真を残している。








彼の日記には、迸る愛の感情がストレートな表現で綴られている。これほど露骨な描写は、裁判にかけられたオスカーのダグラスへの手紙の、秘められた表現と比較するなら、やはり隔世を感じる。
裁判から34年が経っている。
“He put his mouth over mine
crushing it–some kisses seem to
draw the very soul
out of one’s body–his do mine.
I feel all my heart swooning
at the touch of his mouth–
my soul dies a hundred million deaths
when his breath is on my face and neck.”
Stephen Tennant’s diary, 8 September 1929, Sassoon’s 43rd birthday
king's collage of Cambridge choir
the shepherd carol









