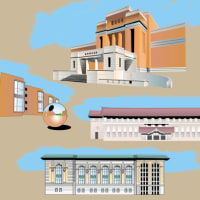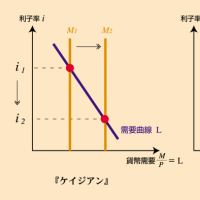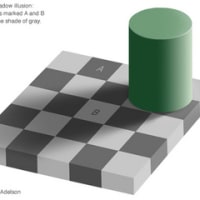小説はノンフィクションや取材記録、論文ではない。
だから小説の中に事実でないこと、嘘や矛盾があったとしても、それだけでその小説を批判する理由にはならない。
大事なのは物語内における整合性やテーマ。そして娯楽性である。
そのためなら事実は優先的に犠牲にすべきことである。
「童貞」は古代支那、女が権力をにぎり神聖な存在として扱われる一方で、男は卑しい生物として下賤な仕事や生け贄(にえ)に使われる世界での物語だ。
その世界では、女と男は別れて暮らしている。女はいい場所に住み、男は洞窟などで暮らす。
子作りは本来は男がいなくても成立するものなのだが、なぜか男と関係した後でないと子どもが生まれない。
だから女は仕方なく男を適当に選んで関係を強要する。
つまり「乱婚制」でる。
生まれた子どもは女たちのものであり、男とは関係がない。この世界に父はなく、母は全ての女性である。
男の子は成人するまで女たちの家で暮らし、そこで女たちへの畏怖の念を叩き込まれる。
男は畑仕事や河への生け贄に使われる。女は陶器を作り、祭司をつとめる。
つまり「母権制」である。
それは古代法学者バッハオーフェンが1861年に書いた「母権論」、もしくはモルガンの「古代社会学」のような世界である。
モルガンの「古代社会学」は歴史は全て同じ道筋に沿って進化するという考え方のもとに書かれている。
彼によると歴史は6段階のステップをふんで進化する。
はじめは「原始乱婚制」という家族の概念のない、「男女が勝手に子作りをし、その子どもを全体で育てる社会」ができる。この社会は家族も私有財産もない共産制である。
やがてこの社会は「血縁家族制(氏(うじ)族制度)」を通して、最終的には「一夫一妻制」という家族の集まりである国家へと変化するのだ。
ちなみに、この「古代社会学」に感動したエンゲルスにより書かれたのが、マルクス主義者の聖典である「家族、私有財産および国家の起源」である。
エンゲルスはこの原始的な共同体「氏族制度」の中に理想的な共産制度を見たのである。彼は言う。
この氏族制度こそ、その一切の天真さと純粋さにおいて驚くべき制度だ!
兵士も憲兵も警官もなく。貴族も国王も総督も、知事または裁判官もなく、牢獄も訴訟もなくて、一切が正しく進行する。
また社会は「母系」から「父系」へと移りかわるものとされている。
「乱婚制」「血縁家族制」という共同体では女性が重要な役割を果たす母系社会で、やがて「一夫一妻制」になり国家が作られるにつれて、男性が権力者となり父系社会になる。
どうであろう。モルガンの言う原始社会と酒見氏の書いた世界はとても似ているのである。
しかし現在の研究ではモルガンの説には多くの批判が寄せられている。
まず原始的な社会は「乱婚制」であるというのは嘘である。
調査によると、どんな非文明的な部族でも、一夫一妻や一夫多妻という形で、夫婦の関係は固定している。
「乱婚制」を採用している社会は存在しないことが分かっている。
共産制についても、私有財産がなく統治者のいない社会も存在しないことが分かっている。
また「母権」と「母系」の混同も指摘されている。
母系社会とは財産相続や地位の継承が母から子へなされる社会である。
しかしそれは必ずしも女が権力者になることを意味しない。
なぜか政治というものは、男ばかりがやりたがるものなのである。だから権力者になるのも男ばかりだ。
卑弥呼のように巫女である女王が女から女へと継承されることもあるが、その世界でも権力を使うのは男である。
北米インディアンのイロクォイ族は代議員を女だけで選ぶが、そこで選ばれて実際の政治活動をするのは男だけである。
社会進化学では、男性が政治権力や社会的地位を好む傾向を
「男性が女性よりも個人の権力や地位に興味があるのは、それらを獲得することが、人間の進化の歴史を通じて、女性よりも男性において、繁殖成功度に大きな影響を与えてきたからだ」
と説明している。
また現在では単純な進化文化説も否定されており、最近は多様な進化経路と文化の伝播が文明を進歩させたと考えられている。
たとえば「母系」から「父系」になるのは、男と女のどちらに経済力があるか、男女比の数、結婚してから夫が妻の家に住むか、妻が夫の家に住むか、などで変化する。
一方的な進化があるわけではない。
狩猟民族では男性の労働力の方が貴重で、最初から父系社会になる。
一方、石川県能登半島では海女(あま)が多く、彼女たちに経済力があり、発言権が強い。
その地方では夫が二、三年間、夜だけ妻のもとへ通い、その後夫婦で夫の家に行く。
これは母系社会に近い。
このように事実か否かで判断すれば、酒見氏の世界設定「乱婚制」「母権社会」には嘘がある。
しかし小説はもとから事実ではないのである。
最初に言ったように大事なのは整合性であり、テーマである。
事実ではないが真実には近いこともある。
「童貞」の物語は次のようなものだ。
シャ地方シィの村のグンは度重なる川の氾濫を治水工事で治めようとするが失敗し、そして神聖なる川を汚した罪で女たちに殺される。
彼の意志を継いだシャのシィのユウはそんな母権社会に激しい嫌悪感を抱き、最後には生け贄に選ばれたところで逆襲を始め、村人たちを虐殺し、深手を負いながら村から逃げ出す。
そして彼は旅に出て妻を持ち、女に支配されない父権社会を作り、その社会の下で治水事業を始めるための構想をねる。
この本のテーマは「母権社会から父権社会への移行」ではない。
テーマは「なぜ、世界は父権社会を選択したのか?」「父権社会であるということが世界にどのような影響を与えたのか」である。
更に言うならば、世界史は何故に「女の歴史」ではなく「男の歴史」になったのかという問いかけである。
酒見氏の問題意識を共有していると思われる文章を最近見つけたので、まずはそれを紹介したいと思う。
橋本治氏の「ぼくたちの近代史」からの一節である。
今までの歴史って“男の歴史”なんだよね。男の歴史だけで、女の歴史っていうのがないの。
女の歴史が何故ないのかっていうと、“変わった女の歴史”っていうのはあるんだよね。
だから女性の歴史っていうのは、その“変わった女の歴史”ばっかりで、そのエピソードの集成になっちゃうのね。
神武天皇だとか楠正成だとか、そういう偉人伝を女でやってるだけじゃないかって。
普通の歴史って人間の流れじゃない?女の歴史はなんで流れないの?
いつも変わった女がポンと出てきて、男と変わらないような権力を、男と変わらないような表現力を発揮したって、なんでそうなの?ったら、あることって、なんか七千年くらい変わっていないらしいのね。
つまり、人間であることの基準は男の観念世界から出てるものだからさ。
“女である”ってことは、そこには入らないんだよね。
人間として女は入らない。入らないから、流れないんだよね。
だから七千年くらいの間、女は進化してなかったと思うんだ。
女の歴史は日本の縄文式土器とか弥生式土器の時代のもんだよ。
時間がすっごく長いんだけど、書くべきエピソードがないもんだから「どこそこでなんとか土器発見される」とかさ、「どこそこでなんとか銅鐸(どうたく)発見される」っていう、それだと思うんだ。
だから女の歴史ってまだ始まってないんだと思うのね。
なんか、そのことを認めちゃえばいいんだけど、それ認めると女の今までがなんか劣ってるみたいな気がして、いやだって言うの。
劣ってるんじゃなくて、それは歴史の捉え方が変わっちゃって、今までが間違ってたんだから、やっとそのことが明らかになったんだから、もう認めちゃった方がいいじゃんて。
この先があんだし。
では「女の歴史」、「女の世界」とは一体どのようなものなのだろうか?
なぜ世界は母権ではなく父権でなくてはいけなかったのか?
酒見氏は後書きでこう述べている。
「それは月に行くためだ」
女の世界、女の歴史では人類は科学を進歩させ、ロケットを作り、月に行くことなどはできなかったと酒見氏は言うのだ。
この発言を念頭に置けば、シャのシィのグンが母権社会の中で治水工事を行い、それに失敗して八つ裂きにされたことも、シャのシィのユウが母権社会から逃げ出して父権社会の下で治水工事を行おうとしたことも、そのテーマがよく分かる。
確かに母権社会などというものは実際に存在しないので、この小説は事実ではない。
しかしもし母権社会が存在したらどうなるのか。その母権社会の下でも、私たちは現在のような文明を作ることが可能なのかどうか?
というifの世界、思考実験、センス・オブ・ワンダーとして、「童貞」は非常に魅力的な話なのである。
酒見氏は更に神話のようなSFのような話として「男と女のこれから」について述べているが、それは実際に読んで楽しんでいただきたい。
またこの小説の一番楽しい部分、小説のタイトル「童貞」に関わる部分については、わざと紹介しなかったので興味を持たれた方は実際に読んで確かめていただきたい。
(参考文献)
祖父江孝男 「文化人類学入門」
石田英一郎 「文化人類学入門」
ジョン・オルコック 「社会生物学の勝利」
だから小説の中に事実でないこと、嘘や矛盾があったとしても、それだけでその小説を批判する理由にはならない。
大事なのは物語内における整合性やテーマ。そして娯楽性である。
そのためなら事実は優先的に犠牲にすべきことである。
「童貞」は古代支那、女が権力をにぎり神聖な存在として扱われる一方で、男は卑しい生物として下賤な仕事や生け贄(にえ)に使われる世界での物語だ。
その世界では、女と男は別れて暮らしている。女はいい場所に住み、男は洞窟などで暮らす。
子作りは本来は男がいなくても成立するものなのだが、なぜか男と関係した後でないと子どもが生まれない。
だから女は仕方なく男を適当に選んで関係を強要する。
つまり「乱婚制」でる。
生まれた子どもは女たちのものであり、男とは関係がない。この世界に父はなく、母は全ての女性である。
男の子は成人するまで女たちの家で暮らし、そこで女たちへの畏怖の念を叩き込まれる。
男は畑仕事や河への生け贄に使われる。女は陶器を作り、祭司をつとめる。
つまり「母権制」である。
それは古代法学者バッハオーフェンが1861年に書いた「母権論」、もしくはモルガンの「古代社会学」のような世界である。
モルガンの「古代社会学」は歴史は全て同じ道筋に沿って進化するという考え方のもとに書かれている。
彼によると歴史は6段階のステップをふんで進化する。
はじめは「原始乱婚制」という家族の概念のない、「男女が勝手に子作りをし、その子どもを全体で育てる社会」ができる。この社会は家族も私有財産もない共産制である。
やがてこの社会は「血縁家族制(氏(うじ)族制度)」を通して、最終的には「一夫一妻制」という家族の集まりである国家へと変化するのだ。
ちなみに、この「古代社会学」に感動したエンゲルスにより書かれたのが、マルクス主義者の聖典である「家族、私有財産および国家の起源」である。
エンゲルスはこの原始的な共同体「氏族制度」の中に理想的な共産制度を見たのである。彼は言う。
この氏族制度こそ、その一切の天真さと純粋さにおいて驚くべき制度だ!
兵士も憲兵も警官もなく。貴族も国王も総督も、知事または裁判官もなく、牢獄も訴訟もなくて、一切が正しく進行する。
また社会は「母系」から「父系」へと移りかわるものとされている。
「乱婚制」「血縁家族制」という共同体では女性が重要な役割を果たす母系社会で、やがて「一夫一妻制」になり国家が作られるにつれて、男性が権力者となり父系社会になる。
どうであろう。モルガンの言う原始社会と酒見氏の書いた世界はとても似ているのである。
しかし現在の研究ではモルガンの説には多くの批判が寄せられている。
まず原始的な社会は「乱婚制」であるというのは嘘である。
調査によると、どんな非文明的な部族でも、一夫一妻や一夫多妻という形で、夫婦の関係は固定している。
「乱婚制」を採用している社会は存在しないことが分かっている。
共産制についても、私有財産がなく統治者のいない社会も存在しないことが分かっている。
また「母権」と「母系」の混同も指摘されている。
母系社会とは財産相続や地位の継承が母から子へなされる社会である。
しかしそれは必ずしも女が権力者になることを意味しない。
なぜか政治というものは、男ばかりがやりたがるものなのである。だから権力者になるのも男ばかりだ。
卑弥呼のように巫女である女王が女から女へと継承されることもあるが、その世界でも権力を使うのは男である。
北米インディアンのイロクォイ族は代議員を女だけで選ぶが、そこで選ばれて実際の政治活動をするのは男だけである。
社会進化学では、男性が政治権力や社会的地位を好む傾向を
「男性が女性よりも個人の権力や地位に興味があるのは、それらを獲得することが、人間の進化の歴史を通じて、女性よりも男性において、繁殖成功度に大きな影響を与えてきたからだ」
と説明している。
また現在では単純な進化文化説も否定されており、最近は多様な進化経路と文化の伝播が文明を進歩させたと考えられている。
たとえば「母系」から「父系」になるのは、男と女のどちらに経済力があるか、男女比の数、結婚してから夫が妻の家に住むか、妻が夫の家に住むか、などで変化する。
一方的な進化があるわけではない。
狩猟民族では男性の労働力の方が貴重で、最初から父系社会になる。
一方、石川県能登半島では海女(あま)が多く、彼女たちに経済力があり、発言権が強い。
その地方では夫が二、三年間、夜だけ妻のもとへ通い、その後夫婦で夫の家に行く。
これは母系社会に近い。
このように事実か否かで判断すれば、酒見氏の世界設定「乱婚制」「母権社会」には嘘がある。
しかし小説はもとから事実ではないのである。
最初に言ったように大事なのは整合性であり、テーマである。
事実ではないが真実には近いこともある。
「童貞」の物語は次のようなものだ。
シャ地方シィの村のグンは度重なる川の氾濫を治水工事で治めようとするが失敗し、そして神聖なる川を汚した罪で女たちに殺される。
彼の意志を継いだシャのシィのユウはそんな母権社会に激しい嫌悪感を抱き、最後には生け贄に選ばれたところで逆襲を始め、村人たちを虐殺し、深手を負いながら村から逃げ出す。
そして彼は旅に出て妻を持ち、女に支配されない父権社会を作り、その社会の下で治水事業を始めるための構想をねる。
この本のテーマは「母権社会から父権社会への移行」ではない。
テーマは「なぜ、世界は父権社会を選択したのか?」「父権社会であるということが世界にどのような影響を与えたのか」である。
更に言うならば、世界史は何故に「女の歴史」ではなく「男の歴史」になったのかという問いかけである。
酒見氏の問題意識を共有していると思われる文章を最近見つけたので、まずはそれを紹介したいと思う。
橋本治氏の「ぼくたちの近代史」からの一節である。
今までの歴史って“男の歴史”なんだよね。男の歴史だけで、女の歴史っていうのがないの。
女の歴史が何故ないのかっていうと、“変わった女の歴史”っていうのはあるんだよね。
だから女性の歴史っていうのは、その“変わった女の歴史”ばっかりで、そのエピソードの集成になっちゃうのね。
神武天皇だとか楠正成だとか、そういう偉人伝を女でやってるだけじゃないかって。
普通の歴史って人間の流れじゃない?女の歴史はなんで流れないの?
いつも変わった女がポンと出てきて、男と変わらないような権力を、男と変わらないような表現力を発揮したって、なんでそうなの?ったら、あることって、なんか七千年くらい変わっていないらしいのね。
つまり、人間であることの基準は男の観念世界から出てるものだからさ。
“女である”ってことは、そこには入らないんだよね。
人間として女は入らない。入らないから、流れないんだよね。
だから七千年くらいの間、女は進化してなかったと思うんだ。
女の歴史は日本の縄文式土器とか弥生式土器の時代のもんだよ。
時間がすっごく長いんだけど、書くべきエピソードがないもんだから「どこそこでなんとか土器発見される」とかさ、「どこそこでなんとか銅鐸(どうたく)発見される」っていう、それだと思うんだ。
だから女の歴史ってまだ始まってないんだと思うのね。
なんか、そのことを認めちゃえばいいんだけど、それ認めると女の今までがなんか劣ってるみたいな気がして、いやだって言うの。
劣ってるんじゃなくて、それは歴史の捉え方が変わっちゃって、今までが間違ってたんだから、やっとそのことが明らかになったんだから、もう認めちゃった方がいいじゃんて。
この先があんだし。
では「女の歴史」、「女の世界」とは一体どのようなものなのだろうか?
なぜ世界は母権ではなく父権でなくてはいけなかったのか?
酒見氏は後書きでこう述べている。
「それは月に行くためだ」
女の世界、女の歴史では人類は科学を進歩させ、ロケットを作り、月に行くことなどはできなかったと酒見氏は言うのだ。
この発言を念頭に置けば、シャのシィのグンが母権社会の中で治水工事を行い、それに失敗して八つ裂きにされたことも、シャのシィのユウが母権社会から逃げ出して父権社会の下で治水工事を行おうとしたことも、そのテーマがよく分かる。
確かに母権社会などというものは実際に存在しないので、この小説は事実ではない。
しかしもし母権社会が存在したらどうなるのか。その母権社会の下でも、私たちは現在のような文明を作ることが可能なのかどうか?
というifの世界、思考実験、センス・オブ・ワンダーとして、「童貞」は非常に魅力的な話なのである。
酒見氏は更に神話のようなSFのような話として「男と女のこれから」について述べているが、それは実際に読んで楽しんでいただきたい。
またこの小説の一番楽しい部分、小説のタイトル「童貞」に関わる部分については、わざと紹介しなかったので興味を持たれた方は実際に読んで確かめていただきたい。
(参考文献)
祖父江孝男 「文化人類学入門」
石田英一郎 「文化人類学入門」
ジョン・オルコック 「社会生物学の勝利」