前回の続きです。
ある理論(仮説)を理解するには、その対立仮説(対立理論)と比べて見るのもよい方法です。ダーウィンの5つの進化理論の主な対立理論を挙げてみましょう。
1)進化そのもの <==> 種の創造説
2)共通祖先 <==> ラマルク進化論、種の創造説
3)漸進性 <==> 跳躍説(突然変異説など)
4)個体変異による種分化 <==> 種自体の変化説
5)自然選択 <==> 定向進化説、用不用説など
1の進化するという理論の対立理論は、生物は進化せず過去から現在まで変化していないという理論で、天地創造以来同一の種がそのまま続いているという創造説が代表的です。
-------------Ref1,p136
一八五九年の直後では、ダーウィニズムという単語は単に特殊創造の否定を意味していた。だれかが特殊創造を否定し、かわりに種の非恒常性、共通起源、一般的な進化の流れのなかに人を含めること、これらを採用したとすれば、その人はダーウィン主義者だった。自然選択であれ種形成のどういう理論であれ、漸進進化、跳躍進化に対するその人の信念ですら、当時ダーウィン主義者と見なされるかどうかにはまったく無関係だった。
-------------
2の共通祖先を認めない対立理論のひとつとしてはラマルク進化論がわかりやすいでしょう。この理論では全ての生物が最下等の微生物から高等な生物へと進化し、現在の微生物も未来には多細胞生物へと進化の階段を登ると考えます。にもかかわらず現在でも最下等の微生物が存在するのは、現在も自然発生しているからだと考えます。したがって現在の異なる進化段階にある生物の祖先は、異なる時点で自然発生した異なる祖先であるということになります。
しかしひとたび共通祖先という仮定をおくと、多様な生物種の存在とそれらが似たもの同士に分類されるという事実が、一本の筋の通った形ですっきりと説明できました。そのために、多様な生物は共通祖先から分岐して生じたというダーウィンの説は生物学者達に急速に受け入れられたのです。これをマイアは第一次ダーウィン革命と呼んでいます。第一次ダーウィン革命により、生物の分類というものが単なる記述から理論科学になったと言えるでしょう。
-------------Ref1,p138
共通起源説こそが、ダーウィンがきわめて頻繁に語ったような、すべてをまとめる大きな統一力を持っていた。なぜなら共通起源説は、リンネ型の階層性、超越論的形態学者の原型、生物界の歴史など、多くの生物学的現象にただちに解答を与えたからである。
-------------
しかし進化は認めた上で、進化がどのように起きたのかという様々な理論が可能で3-5の仮説には様々な対立仮説が提案され、ダーウィン自身の説(3-5)が主流となったのは総合進化説の確立以降だとマイアは述べています。そして3-5が受け入れられにくかった背後にあったもののひとつは、種についての実在論哲学という信念だと述べています。
実在論と一口に言っても何が実在するという主張なのかを示さないと内容がわからないのですが、この場合は、生物個体を越えた種そのもの、つまりネズミ・牛・トラ・米・麦・花などというもの自体が実在するという主張で、歴史的に唯名論と対立してきたものです。ちょっと考えれば、我々が実際に感覚で捕らえられるのは分類集団に属する個々の個体であり分類集団そのもの、牛そのものなどというものは、我々の頭の中にしか存在しません。しかし思考する上では、これらの概念があたかも実在物のように考えた方が楽であり、それゆえ我々は分類集団そのものというものが単なる概念であり現実の存在ではないことを忘れがちなのです。
これに対して例えば素朴実在論というのは、我々が感覚で捕らえているものは実在するという主張です。これの対立理論は例えばプラトンのイデア論に代表される理論で、感覚で捕らえているものは影に過ぎず、その本体は例えば三角形そのものといったイデアであり、イデアこそが真に実在するものだという理論です。これはつまり上記の種などの分類集団そのもの、またはネズミ・牛・トラのイデアなどというものこそ真に実在するという理論と同根です。要するに種のような分類概念自体についての実在論は、素朴実在論の正反対の主張ということになります。もっとも分類概念自体の実在論と反素朴実在論とでは力点の置き場が異なりますが。
では、この実在論哲学という信念が理論3-5とどのように関連したのかは次回にお話しします。
ある理論(仮説)を理解するには、その対立仮説(対立理論)と比べて見るのもよい方法です。ダーウィンの5つの進化理論の主な対立理論を挙げてみましょう。
1)進化そのもの <==> 種の創造説
2)共通祖先 <==> ラマルク進化論、種の創造説
3)漸進性 <==> 跳躍説(突然変異説など)
4)個体変異による種分化 <==> 種自体の変化説
5)自然選択 <==> 定向進化説、用不用説など
1の進化するという理論の対立理論は、生物は進化せず過去から現在まで変化していないという理論で、天地創造以来同一の種がそのまま続いているという創造説が代表的です。
-------------Ref1,p136
一八五九年の直後では、ダーウィニズムという単語は単に特殊創造の否定を意味していた。だれかが特殊創造を否定し、かわりに種の非恒常性、共通起源、一般的な進化の流れのなかに人を含めること、これらを採用したとすれば、その人はダーウィン主義者だった。自然選択であれ種形成のどういう理論であれ、漸進進化、跳躍進化に対するその人の信念ですら、当時ダーウィン主義者と見なされるかどうかにはまったく無関係だった。
-------------
2の共通祖先を認めない対立理論のひとつとしてはラマルク進化論がわかりやすいでしょう。この理論では全ての生物が最下等の微生物から高等な生物へと進化し、現在の微生物も未来には多細胞生物へと進化の階段を登ると考えます。にもかかわらず現在でも最下等の微生物が存在するのは、現在も自然発生しているからだと考えます。したがって現在の異なる進化段階にある生物の祖先は、異なる時点で自然発生した異なる祖先であるということになります。
しかしひとたび共通祖先という仮定をおくと、多様な生物種の存在とそれらが似たもの同士に分類されるという事実が、一本の筋の通った形ですっきりと説明できました。そのために、多様な生物は共通祖先から分岐して生じたというダーウィンの説は生物学者達に急速に受け入れられたのです。これをマイアは第一次ダーウィン革命と呼んでいます。第一次ダーウィン革命により、生物の分類というものが単なる記述から理論科学になったと言えるでしょう。
-------------Ref1,p138
共通起源説こそが、ダーウィンがきわめて頻繁に語ったような、すべてをまとめる大きな統一力を持っていた。なぜなら共通起源説は、リンネ型の階層性、超越論的形態学者の原型、生物界の歴史など、多くの生物学的現象にただちに解答を与えたからである。
-------------
しかし進化は認めた上で、進化がどのように起きたのかという様々な理論が可能で3-5の仮説には様々な対立仮説が提案され、ダーウィン自身の説(3-5)が主流となったのは総合進化説の確立以降だとマイアは述べています。そして3-5が受け入れられにくかった背後にあったもののひとつは、種についての実在論哲学という信念だと述べています。
実在論と一口に言っても何が実在するという主張なのかを示さないと内容がわからないのですが、この場合は、生物個体を越えた種そのもの、つまりネズミ・牛・トラ・米・麦・花などというもの自体が実在するという主張で、歴史的に唯名論と対立してきたものです。ちょっと考えれば、我々が実際に感覚で捕らえられるのは分類集団に属する個々の個体であり分類集団そのもの、牛そのものなどというものは、我々の頭の中にしか存在しません。しかし思考する上では、これらの概念があたかも実在物のように考えた方が楽であり、それゆえ我々は分類集団そのものというものが単なる概念であり現実の存在ではないことを忘れがちなのです。
これに対して例えば素朴実在論というのは、我々が感覚で捕らえているものは実在するという主張です。これの対立理論は例えばプラトンのイデア論に代表される理論で、感覚で捕らえているものは影に過ぎず、その本体は例えば三角形そのものといったイデアであり、イデアこそが真に実在するものだという理論です。これはつまり上記の種などの分類集団そのもの、またはネズミ・牛・トラのイデアなどというものこそ真に実在するという理論と同根です。要するに種のような分類概念自体についての実在論は、素朴実在論の正反対の主張ということになります。もっとも分類概念自体の実在論と反素朴実在論とでは力点の置き場が異なりますが。
では、この実在論哲学という信念が理論3-5とどのように関連したのかは次回にお話しします。










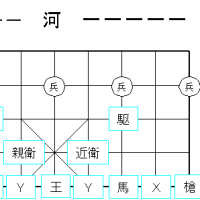
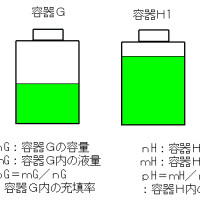
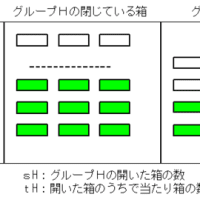
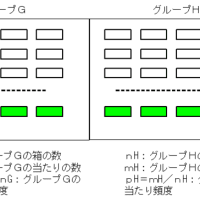
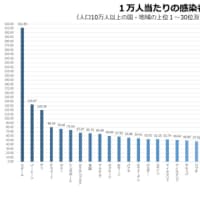
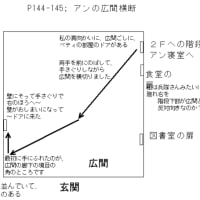
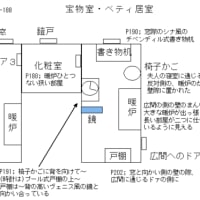
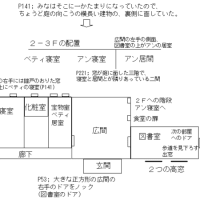
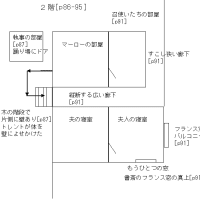
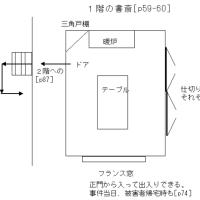
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます