前回のイスラエル・ボイコットの話につなげて。
そのイベント「スピークアウト for アクション」の翌々日、旅行ガイドブック『地球の歩き方』シリーズで有名なダイヤモンド・ビッグ社に赴いた。今年出版された『地球の歩き方 イスラエル』の7年ぶりの改訂版の内容について、会社側と話し合いを持つためである。
事の顛末はこう。今年1月、ガザ侵攻の真っ只中に配本となった『地球の歩き方 イスラエル』最新版の内容の一部をホームページで知ったパレスチナの平和を考える会の役重善洋さんは、その発売のタイミングもさることながら、パレスチナの歴史とその占領という現実を無視しているかのような内容に懸念を抱き、同社に申し入れ書を送った。たとえば、「イエスの足跡」の多くはイスラエルではなくパレスチナ被占領地にあるわけだが、同書ではそれを「イスラエル」として紹介してしまっている点など、イスラエル政府側の一方的な情報宣伝を真に受けているとしか考えられない、いわば「状況証拠」が目についたわけである。
数日後に、ダイヤモンド・ビッグ社より役重さんに書面による返答が来た。それによれば、自分達はあくまで旅行者の立場に立った旅行ガイドという中立的立場で書いているのであって、イスラエル側の意に即した内容にしようという意図は一切ないことを主張しながらも、掲載内容について意見をいただくのはやぶさかではない、弊社までお越しいただければ歓迎したいということだった。
そこで、その後電話での折衝なども経て、ちょうど5月31日のイベントで役重さんが上京することになったので、話し合いを実現する機会を持てることになったわけである。その際、最初の申し入れ書の差出人に名を連ねた人間として、僕ともう一人の人が同道することになった。といっても、役重さんと「もう一人の人」は、ともに現地パレスチナ/イスラエルに何度も足を運んでいる事情通であるのに対し、僕は一度も行ったことはない、単なる素人という違いはあることは言っておかねばならない。
「地球の歩き方」編集室を代表して僕らに応対したのは、ダイヤモンド・ビッグ社代表取締役社長の藤岡さんと、総務経理部マネージャーの大西さんという方。だが、ほとんどのやりとりは藤岡氏との間で行われた。本当はイスラエル編の担当者であるアジア・中近東・アフリカ事業部の部長さんも参加するはずだったのだけど、急な会議で出られないとのことだった。
藤岡氏はまず、「地球の歩き方」の企業理念として、「人々の役に立つ情報を提供すること」がある、という原則論について述べた。その観点から、ある国で戦争犯罪が行われていることが、その国の観光案内をしてはいけないことに即つながるだろうか、現に本で紹介しているルートは毎日何千何万の旅行者が歩いているものだ──そうである以上、その情報を提供するのが当社の役目ではないか、という。
対して、こちらが指摘したのは、そもそもそれが「役に立つ情報」になっているのか?という問題である。
この『地球の歩き方 イスラエル』では、一言で言って「パレスチナ自治区」の大きな部分が占領下に置かれているという認識が致命的に抜け落ちている。全体地図においてはガザを区切る線があたかもイスラエル国内の州境のようであるし、西岸にいたってはその本来の境界線であるグリーンラインがそもそも描かれていない。イスラエル史年表においても、1967年第三次中東戦争の「結果」としての西岸・ガザの占領という、現在に続く問題の発生が書かれていない。それでは本の中で聖地巡礼コースとして紹介されているエリコやベツレヘムが「パレスチナ自治区」にあることの意味、そこで大量に出会う「パレスチナ人」とはいったい何者なのか、ということがわからない。お定まりの観光コースをガイドに引き連れられてゾロゾロと移動するツアーなら、それでも仕方ないかも知れない。だけど、「地球の歩き方」を手に旅行する人は、もっと違う現地の人との触れ合いなどを求めているのではないか?そういう読者に対して、これでは不親切ではないか?
これについて藤岡社長が弁明した中で、面白かった話の一つは、いわゆるバックパッカーの減少についてである。「地球の歩き方」というとバックパッカーの味方、というのは過去の話で、今はバックパッカー自体が少ないし、現地でのトラブルに関して当社に苦情を言ってくる人も増えた・・・・それで、どうしても「安全第一」の情報提供に傾かざるを得ない、そういう時代なんだ、ということ。
しかしそれでも、いわゆる団体パッケージ・ツアーなどに参加する人は「地球の歩き方」などを必要としないわけで、大部分の読者はそうしたパッケージ・ツアーの利用者とバックパッカーの中間の層だろう。それを考えれば、「パレスチナ自治区」に関する情報の少なさはいかにも不親切だし、旅行者の危険につながる。たとえば、この本の情報だけでは、一般の人はまずエリコまでたどり着けない。東エルサレムなどにはパレスチナ人の運転する乗り合いタクシーがあり、西岸を訪れるならそれに乗るのが一番確実で、なおかつボラれる可能性が少ない。そうした情報をもっと充実できないだろうか、というのが役重さんの主張だった。
そんな具合に、どうもパレスチナ自治区(西岸)については、基本的で有用な情報が存在するにも関わらず、それが存在しないかのような印象をこの本から受けてしまう。そのあたりをめぐって、イスラエル側の公式説明に安易に乗っかっているからではないか、というこちらの示唆に対し、そんなことはないと藤岡氏が押し返す、ということが何度かくり返された。会社側としてはそれを単に「情報不足」と理解してほしいようなのだが、中にはそれでは済まないのではと思える「不足」があったりする。
その最たるものがエルサレムに関する誤記である。本ではエルサレムをイスラエルの首都と記述しているが、世界の中でエルサレムをイスラエルの首都だと承認している国は一つもない。イスラエルが一方的に宣言しているだけなのだ。
また、1948年当時から実効支配している西エルサレムに比べ、まごうことなき占領地の一部である東エルサレムは、街の雰囲気から住民から、ガラリと違う。こうした場所で、事情をわかっていない旅行者が、ピリピリしているイスラエル兵とパレスチナ住民の間にうかつに入り込んでしまうのは当然危険である。
また、たとえばイスラムの聖地として有名なアル・アクサー・モスク(通称「岩のドーム」)は(*下部コメント参照)アル・アクサー・モスクおよび「岩のドーム」は、現在礼拝所内にはムスリムしか入れない。これは2000年の第二次インティファーダ以降、イスラエル軍が敷地内を厳重管理している中で取られている措置なのだが、そのことが何も書かれていない本書を頼りにモスクを訪れた人が、中に入れないことを「イスラムが排他的であるため」などと誤解してしまう可能性もある。しかし、それはあくまで「占領」の副産物なのである。
結局のところ、「占領」という基本的視点が抜け落ちているがために、様々な点で情報が中途半端になっているというのが、この本の、少なくとも「パレスチナ自治区」に関する記述の背景にある問題のようだった。
その中途半端を補う、または修正するのに、膨大な資料を添付する必要はない。要所要所に適切な注釈を付け加えれば、あるいは今ある注釈をもう少しだけ詳しくすれば、ずいぶん「使える」ものになるだろう、というのが僕らの側が示した見解である。
そう、この本が本当の意味で「使える」ものになることは悪いことではない。心情的には、様々な国際法違反を複合的に犯している国に対しては「観光自粛」するべきだ!と思っていても、それがなかなかそうならない現状まで知っている身としては、よりましな「観光」を求めることは現実的に妥当、ということがある。
最初藤岡社長は、「政治的に中立」であるところの旅行ガイドを、「パレスチナ寄り」の内容にせんがために(悪い言葉をあえて使えば)僕らがケチをつけに来た、というように警戒しているフシがあったと思う。だが、話し合うにつれ、徐々にその警戒が(完全にではないにしろ)解けていったように、僕には感じられた。話し合いの前半には、何度も「それって旅行ガイドに求めることですか?(社会学や政治・歴史の本ならともかく)」と、やや機械的に頭ごなしに反論する場面があったけれど、後半になると「難しいなあ・・・」と言いながらも、「でもそれは直した方がいいかもね、うん・・・」と言ってくれるようになったからだ。
それはそうだろう。こちらはむしろ、現実離れしたイスラエル寄りの記述に対して、いわばもう少し「中立」になるよう求めていたようなものである。
その場合の「中立」とは、国際的に認知されているスタンダードな情報、というだけの意味である。今も着々と進んでいるのは、「占領」どころか「併合」のプロセスであり、それがイスラエル/パレスチナの各所で様々のレベルの軋轢・衝突を生んでいるわけだけど、そんなことまで説明するのはこの際無駄であることくらい、最初からわかっていた。ただせめて、まがりなりにも聖地を「共有」している一方の住民を視野に入れた情報を提供する、その程度には「中立」になってもらえば、旅行者がそれを通じてパレスチナを知ることにつながったり、パレスチナの経済活動に寄与したりすることができるかもしれない、という期待があるわけである。
『地球の歩き方 イスラエル』は、予定では再来年、次の改訂版を出す予定だという。その時に、今回の話し合いの内容を反映できるかどうか検討する、と藤岡社長は約束してくれた。大雑把に言えば①注釈を増やすこと、②パレスチナ被占領地の歴史的経緯をふまえたコラムのようなものを加えること、などによって、「イスラエル」でのより立体的な旅が促進されるようにする、ということらしい。
これは僕が後付けで考えたことも含まれていることを断っておくが、役重さんは元々イスラエルに対するボイコットの視点から、この本に対する抗議を発し、話し合いの機会を作った。ただ、ボイコットというのは、必ずしも何かをやめさせることだけではなく、今回のように、より妥当なものに作り変えるために働きかける、そうした側面がちゃんとあることを実感できて、それが僕には一番の収穫だった。
この機会を作ってくれた役重さんに、本当に感謝したい。そして一時間以上にわたって熱心に話し合ってくれた藤岡社長および大西マネージャー、そして「地球の歩き方」編集室の皆さんにお礼を申し上げたい。
そのイベント「スピークアウト for アクション」の翌々日、旅行ガイドブック『地球の歩き方』シリーズで有名なダイヤモンド・ビッグ社に赴いた。今年出版された『地球の歩き方 イスラエル』の7年ぶりの改訂版の内容について、会社側と話し合いを持つためである。
事の顛末はこう。今年1月、ガザ侵攻の真っ只中に配本となった『地球の歩き方 イスラエル』最新版の内容の一部をホームページで知ったパレスチナの平和を考える会の役重善洋さんは、その発売のタイミングもさることながら、パレスチナの歴史とその占領という現実を無視しているかのような内容に懸念を抱き、同社に申し入れ書を送った。たとえば、「イエスの足跡」の多くはイスラエルではなくパレスチナ被占領地にあるわけだが、同書ではそれを「イスラエル」として紹介してしまっている点など、イスラエル政府側の一方的な情報宣伝を真に受けているとしか考えられない、いわば「状況証拠」が目についたわけである。
数日後に、ダイヤモンド・ビッグ社より役重さんに書面による返答が来た。それによれば、自分達はあくまで旅行者の立場に立った旅行ガイドという中立的立場で書いているのであって、イスラエル側の意に即した内容にしようという意図は一切ないことを主張しながらも、掲載内容について意見をいただくのはやぶさかではない、弊社までお越しいただければ歓迎したいということだった。
そこで、その後電話での折衝なども経て、ちょうど5月31日のイベントで役重さんが上京することになったので、話し合いを実現する機会を持てることになったわけである。その際、最初の申し入れ書の差出人に名を連ねた人間として、僕ともう一人の人が同道することになった。といっても、役重さんと「もう一人の人」は、ともに現地パレスチナ/イスラエルに何度も足を運んでいる事情通であるのに対し、僕は一度も行ったことはない、単なる素人という違いはあることは言っておかねばならない。
「地球の歩き方」編集室を代表して僕らに応対したのは、ダイヤモンド・ビッグ社代表取締役社長の藤岡さんと、総務経理部マネージャーの大西さんという方。だが、ほとんどのやりとりは藤岡氏との間で行われた。本当はイスラエル編の担当者であるアジア・中近東・アフリカ事業部の部長さんも参加するはずだったのだけど、急な会議で出られないとのことだった。
藤岡氏はまず、「地球の歩き方」の企業理念として、「人々の役に立つ情報を提供すること」がある、という原則論について述べた。その観点から、ある国で戦争犯罪が行われていることが、その国の観光案内をしてはいけないことに即つながるだろうか、現に本で紹介しているルートは毎日何千何万の旅行者が歩いているものだ──そうである以上、その情報を提供するのが当社の役目ではないか、という。
対して、こちらが指摘したのは、そもそもそれが「役に立つ情報」になっているのか?という問題である。
この『地球の歩き方 イスラエル』では、一言で言って「パレスチナ自治区」の大きな部分が占領下に置かれているという認識が致命的に抜け落ちている。全体地図においてはガザを区切る線があたかもイスラエル国内の州境のようであるし、西岸にいたってはその本来の境界線であるグリーンラインがそもそも描かれていない。イスラエル史年表においても、1967年第三次中東戦争の「結果」としての西岸・ガザの占領という、現在に続く問題の発生が書かれていない。それでは本の中で聖地巡礼コースとして紹介されているエリコやベツレヘムが「パレスチナ自治区」にあることの意味、そこで大量に出会う「パレスチナ人」とはいったい何者なのか、ということがわからない。お定まりの観光コースをガイドに引き連れられてゾロゾロと移動するツアーなら、それでも仕方ないかも知れない。だけど、「地球の歩き方」を手に旅行する人は、もっと違う現地の人との触れ合いなどを求めているのではないか?そういう読者に対して、これでは不親切ではないか?
これについて藤岡社長が弁明した中で、面白かった話の一つは、いわゆるバックパッカーの減少についてである。「地球の歩き方」というとバックパッカーの味方、というのは過去の話で、今はバックパッカー自体が少ないし、現地でのトラブルに関して当社に苦情を言ってくる人も増えた・・・・それで、どうしても「安全第一」の情報提供に傾かざるを得ない、そういう時代なんだ、ということ。
しかしそれでも、いわゆる団体パッケージ・ツアーなどに参加する人は「地球の歩き方」などを必要としないわけで、大部分の読者はそうしたパッケージ・ツアーの利用者とバックパッカーの中間の層だろう。それを考えれば、「パレスチナ自治区」に関する情報の少なさはいかにも不親切だし、旅行者の危険につながる。たとえば、この本の情報だけでは、一般の人はまずエリコまでたどり着けない。東エルサレムなどにはパレスチナ人の運転する乗り合いタクシーがあり、西岸を訪れるならそれに乗るのが一番確実で、なおかつボラれる可能性が少ない。そうした情報をもっと充実できないだろうか、というのが役重さんの主張だった。
そんな具合に、どうもパレスチナ自治区(西岸)については、基本的で有用な情報が存在するにも関わらず、それが存在しないかのような印象をこの本から受けてしまう。そのあたりをめぐって、イスラエル側の公式説明に安易に乗っかっているからではないか、というこちらの示唆に対し、そんなことはないと藤岡氏が押し返す、ということが何度かくり返された。会社側としてはそれを単に「情報不足」と理解してほしいようなのだが、中にはそれでは済まないのではと思える「不足」があったりする。
その最たるものがエルサレムに関する誤記である。本ではエルサレムをイスラエルの首都と記述しているが、世界の中でエルサレムをイスラエルの首都だと承認している国は一つもない。イスラエルが一方的に宣言しているだけなのだ。
また、1948年当時から実効支配している西エルサレムに比べ、まごうことなき占領地の一部である東エルサレムは、街の雰囲気から住民から、ガラリと違う。こうした場所で、事情をわかっていない旅行者が、ピリピリしているイスラエル兵とパレスチナ住民の間にうかつに入り込んでしまうのは当然危険である。
また、たとえばイスラムの聖地として有名な
結局のところ、「占領」という基本的視点が抜け落ちているがために、様々な点で情報が中途半端になっているというのが、この本の、少なくとも「パレスチナ自治区」に関する記述の背景にある問題のようだった。
その中途半端を補う、または修正するのに、膨大な資料を添付する必要はない。要所要所に適切な注釈を付け加えれば、あるいは今ある注釈をもう少しだけ詳しくすれば、ずいぶん「使える」ものになるだろう、というのが僕らの側が示した見解である。
そう、この本が本当の意味で「使える」ものになることは悪いことではない。心情的には、様々な国際法違反を複合的に犯している国に対しては「観光自粛」するべきだ!と思っていても、それがなかなかそうならない現状まで知っている身としては、よりましな「観光」を求めることは現実的に妥当、ということがある。
最初藤岡社長は、「政治的に中立」であるところの旅行ガイドを、「パレスチナ寄り」の内容にせんがために(悪い言葉をあえて使えば)僕らがケチをつけに来た、というように警戒しているフシがあったと思う。だが、話し合うにつれ、徐々にその警戒が(完全にではないにしろ)解けていったように、僕には感じられた。話し合いの前半には、何度も「それって旅行ガイドに求めることですか?(社会学や政治・歴史の本ならともかく)」と、やや機械的に頭ごなしに反論する場面があったけれど、後半になると「難しいなあ・・・」と言いながらも、「でもそれは直した方がいいかもね、うん・・・」と言ってくれるようになったからだ。
それはそうだろう。こちらはむしろ、現実離れしたイスラエル寄りの記述に対して、いわばもう少し「中立」になるよう求めていたようなものである。
その場合の「中立」とは、国際的に認知されているスタンダードな情報、というだけの意味である。今も着々と進んでいるのは、「占領」どころか「併合」のプロセスであり、それがイスラエル/パレスチナの各所で様々のレベルの軋轢・衝突を生んでいるわけだけど、そんなことまで説明するのはこの際無駄であることくらい、最初からわかっていた。ただせめて、まがりなりにも聖地を「共有」している一方の住民を視野に入れた情報を提供する、その程度には「中立」になってもらえば、旅行者がそれを通じてパレスチナを知ることにつながったり、パレスチナの経済活動に寄与したりすることができるかもしれない、という期待があるわけである。
『地球の歩き方 イスラエル』は、予定では再来年、次の改訂版を出す予定だという。その時に、今回の話し合いの内容を反映できるかどうか検討する、と藤岡社長は約束してくれた。大雑把に言えば①注釈を増やすこと、②パレスチナ被占領地の歴史的経緯をふまえたコラムのようなものを加えること、などによって、「イスラエル」でのより立体的な旅が促進されるようにする、ということらしい。
これは僕が後付けで考えたことも含まれていることを断っておくが、役重さんは元々イスラエルに対するボイコットの視点から、この本に対する抗議を発し、話し合いの機会を作った。ただ、ボイコットというのは、必ずしも何かをやめさせることだけではなく、今回のように、より妥当なものに作り変えるために働きかける、そうした側面がちゃんとあることを実感できて、それが僕には一番の収穫だった。
この機会を作ってくれた役重さんに、本当に感謝したい。そして一時間以上にわたって熱心に話し合ってくれた藤岡社長および大西マネージャー、そして「地球の歩き方」編集室の皆さんにお礼を申し上げたい。


















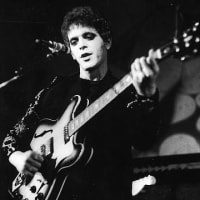

バックパッカーは今みたいなご時勢じゃ確かに減っているのかもしれません。でも必ずしもパックツアーで満足って人ばかりじゃないと思うんです。むしろ単純に海外に出かけることが出来る人が少なくなっているのが大きな原因なんじゃないかなという気がします。
私も海外は何度か行ったことがありますが、パック旅行はしたことがありません。フリーのほうが時間的な余裕があるので良い、と言う人は今でも若い人を中心に多いと感じてます。だから「地球の歩き方」には随分お世話になったし、これからもフリーツアーの旅行者を助けるものであってほしいと思います。
で、その「地球の歩き方」ですが、韓国とか台湾とか近い国については結構歴史とかにしっかりと触れているように感じます。日本語でうっかり悪口を言わないようにとまで書かれているくらいですからね。少なくとも日本との歴史について気を配っているのは確かでしょう。イスラエルのものは中を見たことがありませんが、もし上記の内容だとしたら韓国や台湾のものと比べてかなり不親切な内容だと言えると思います。紛争地域で対立の背景が書かれていないガイドブックなんて、利用する側にリスクを丸投げしたも同然です。私は外国に行った場合、宿や店がどうこうというよりもどんなリスクがあるのかということのほうが重要だと思っています。宿や店のトラブルなんて後で考えれば良い思い出だで済みます(地球の歩き方と現実が違うことなんて随分ありました)が、無知から現地の人と無用なトラブルを招くことは命に係る可能性もあります。それに背景を知っていると現状に対する理解度も上がって旅行者にとってとても有意義だと思うのです。
まあ経営者や担当者の苦悩も分からなくはないんですけどね。イスラエル寄りに書かないとイスラエルの取材協力が得られにくいこともあるでしょうし、また旅行者の質が落ちて責任を押し付けてくることも現実にあるのだとは思います。ただガイドブックとして他社との差別化や旅行者の啓蒙を図っていくんだ、くらいの気概を見せてほしいなぁと感じています。実際にそれくらいのことができる出版社だと思いますし。レイランダーさん達との話し合いが次の改訂で反映されていることを私も願っています。
長文にて失礼しました。
いつも戸惑うのですが、というのも、誰もが同じだと思っているようで。アル・アクサー・モスクと岩のドームは、実は別の建築物なのです。どちらもハラム・アッシャリフにあります。そして難民生活があまりに長く続いて、レバノンのパレスチナ人も岩のドームをアル・アクサーと呼びます。だから、パレスチナ人ならぬわたしたちが間違えたとしても責められることはないと思いますが「イスラム教徒は間違えてはいけません」と作られた教育ヴィデオを、以下のURLで見ることができます。「金」が岩のドーム、「銀」がアル・アクサーです。「間違えるな」「間違えるな」「間違えるな」と言われている気分になります、このヴィデオを観ていると。
http://video.google.com/videoplay?docid=-7792643585980807874
今年のイースターでも、世界中のクリスチャンがエルサレムを訪ねましたが、旧市街、聖墳墓教会へのアクセスが、イスラエル占領軍により制限されたとのニュースも届いています。クリスチャンがエルサレム詣でをしても、聖墳墓教会に入れないかも知れない、と、旅行案内書なら伝えるべき、と思います。占領地の移動に必要と思える「イスラエル軍検問所の位置を記した地図」とまでは言わないにしても(でも恐らく最も役立つ情報)。
僕も、実は『地球の歩き方』には昔中国に行った時にお世話になってて、本自体は好きなんですよ。天安門事件の翌年くらいでしたけど、ちゃんとその解説も載ってたましたね。
近い国というか、社長さんの話では日本人旅行者が多い国ほど、体験談とかのフィードバックも多くなるから詳しく作れる、みたいな面もあるそうです。イスラエルの場合、中国や韓国ほど行く人が多くはないけど、この久しぶりの改訂版はすごい売れ行きがいいそうだから、それで行った人たちが情報をフィードバックすれば、より詳しくなるのかも知れません。
とにかく、そうでなくても、既に現地のことをよく知っている人がこっちにはいるんだから、どんどん聞いてくれればいいのに、と思いました。今度の訪問で、そういうパイプが作れたのなら、それはそれで有意義なことでしょう。
ま、僕は本当にただのオマケでついて行ったようなもんですが。
>mizyaさん
恥ずかしながら、そもそもあの敷地内に別々の2つのモスクがあることを分かっていませんでした。どこかで読むか聞くかした記憶は、言われてみればかすかにあるんですが…教えていただいてありがとうございます。
ちなみにこの動画でも、ムスリムの頭にその2つのモスクを一つだと思わせること自体を「陰謀だ」と主張していますね。今ひとつピンと来ないんですが、後の方のコメントで説明してくださった東エルサレムの併合と、パレスチナ人からの観光収入を取り上げるみたいな意味合いがあるから、なんでしょうか?
聖墳墓教会まで行きづらくなっている…ただ、旅行ガイドブックを作る側の言い分としては、普通は数年単位の改訂だから、そんなにアップ・トゥ・デイトな情報の更新は無理だ、ということのようですね。
今度似たような企画がある時は、ぜひmizyaさんも援軍で来ていただきたいと思います。