中学の1年かそこいらの時、何かの拍子に父親と口喧嘩した。すでに親と口を聞くことが少なくなっていた頃だったから、自分から話を振ったわけではない。その頃の僕の生活態度、読んでいる本、音楽活動などから、世間のオーソリティや立身出世的価値観に対する反発の匂いを強く嗅ぎ取っていたであろう父親が、ええかっこしいの説教を試みてきたので、それを鼻であしらったら、こじれたのである。よくあるパターンだが。
その時の父の主張の骨子をいえばこうなる。世の中には資本主義と社会主義(共産主義)というものがあるが、日本は社会主義の良いところも多少取り入れた「修正資本主義」のスタイルで「発展」した。世界を見渡しても、どうやらこれが一番正しいモデルなのである。だからお前もその枠組みの中で出世を目指し、お国の「発展」に貢献するのが「国民」としてのまっとうな生き方である──と。
要は、自分のこれまでたどって来たサラリーマンとしての処世を正当化せんがための(実際それ以外のことなんか知らないし)持論の披瀝であって、○○主義だのをまともに論じられるほどの教養が父親にないことは当時の僕ですらうすうす勘付いていたので、そちらの方向で何か言い返すような愚は犯さなかった。ただ、僕が思わず言い返してしまったのは、今の日本のこの「発展」が完全無比のものであるかのような、様々に噴出する社会の矛盾をあっさり見落とせるようなおめでたさに、「馬鹿にするな」という気持ちが湧き上がったからである。すなわち、そうした「発展」が必ずしもバラ色だったわけじゃない、たとえば「公害」の問題はどうするんだ、と振り向けたのである。
これに父は極めて直情的に、間髪をいれずに、「お前にそれを言う権利はないぞ!」と怒鳴り返してきたのである。それを言うのはご法度だ、それだけは許さないぞと言わんばかりに。高度成長のためにたくさんの日本人が必死に働いた。そのおかげで、今お前は不自由ない生活ができている。その働いた人達をけなすことはお前にはできないぞ、と。…当時の僕には言い返せなかった。まだ中学生の者にとって、「お前は養われている身だ」という言葉に反論することは何より難しかったからだ(実際、父・母のおかげで飯が食えているのは紛うことなき現実であり──というか、要するに父はその一点を頼みに、強弁しているに過ぎないのだったが…だったらもったいぶった「世の中というものは」式の議論なんかふっかけてくんじゃねーよ、という話である^^)。
今ならこの父の言い分がいかに幼稚な、没論理的な反駁であるか、簡単に指摘できる。細かい点は置いても、上の「そのおかげで」論に従えば、後の世代の者は前の世代のやったことを、いつでも・何一つ批判できないことになってしまう。そんなアホな話があるか。「そのおかげで」ひどい目に会うことだってあるのに!(公害はまさにその一例だし。)
ただ、こうした論法は、何もうちの父親の特異な考え方だったわけではなく、多かれ少なかれ世間の同年代の大人たちの共有するところだったろう(そして3.11後の今ですら、そこから脱却できない人が多い)。今にして思えば、そうした父親世代の自己正当化に対する根本的な疑念が、自分をその後、たとえば「パレスチナ」の発見、こだわりに向かわせたのだと、決してこじつけでなく、そう思う。
父の世代は、日本が敗戦後の貧しい状態から、奇跡のような復興を成し遂げ、アジアどころか世界の一等国なみの西洋文明化を果たして久しい昭和後期の時点、つまり中学生の僕に説教を垂れていた時点で、すでにあらかたやることはやった、ゲームは日本の「勝利」で終わった、人生は意味があった、という感慨とともに暮らしていたのである。すでに「経済大国」になったあとの日本に生まれ落ちたこちらとは、物の見方に差があって当然だろう。
たとえば父からすると、「首都高速道路」が都内を縦横に駆け巡っている光景など、本や雑誌の挿絵に登場するだけの、遠い遠い未来の姿だと思っていた。それが眼前にある今というのは輝かしい時代であり、それを見ることはまずもって「いい気分」なのである。ところが僕は、あんなものの走っているそばに住んでいる人は騒音やら大気汚染やらで大変だろう、あんなとこには住みたくないな、という憂いの気分が先に立ってしまう。結局はそれを使って利便を図っている自分達がいる、という後ろめたさもありながら。
大なるものが小なるものを疎外したり、抑圧したりする。どんなにうまくやっても、心を砕いて配慮しても、「大」の図体がでかいだけに、結果としてそうなってしまうことが世の中にはある。あるならば、まずそれは正直に認めて、対策を別個に補う必要がある。それは○○主義とかいう問題とは関係ない。「大」と「小」がある限り、避けられない事柄だ。
しかし最初から犠牲(「小」が犠牲となって負担を背負う)を「よし」とするシステムを是認してしまう場合、質的にまったく異なる問題を孕む。ゴリ押しすればするだけ、システムは肥大化し──すなわち多数の豊かさのための自己正当化、美化(偽装)を肥大化させ、それがまた新たに社会の各層に「犠牲制」システムの増殖を促す、という悪循環が止まらなくなる。どこか一箇所の、ローカルな問題というにとどまらなくなる。──そうして社会はむしばまれる。
父の信奉する、そして自己をそこに託し一体化させて生きようとした(簡単に言えば、長いものに巻かれようとした)「発展」イデオロギーに、僕がどうしようもなく反発を覚えたのは、そうした悪循環の不気味さを、どこかで感じていた(一度や二度の出来事を通じてでなく、日常のなかで連続的に)からだと思う。
6月11日の新宿デモの際、手書きで「この国はおそろしい」と書いたプラカードを掲げて歩いている人がいた。共感したけれど、僕の場合ははるか昔から、「この国は気持ち悪い」のだった。きっとどこの国にいても、国を挙げての自画自賛言説の垂れ流しに付き合わされたら、誰だって気持ち悪くなってくるだろう。ただ日本は、それが経済の「発展」と二人三脚のようにして自画自賛言説の洗練のされ方も「発展」してきたような、言うなれば過剰な根拠を見込んで過剰な自負心を社会のなかに醸成してきたような感があって、独特に気持ちが悪い。
パレスチナ/イスラエルの問題にしろ、死刑制度の問題にしろ、原発にしろ、米軍基地の問題にしろ、内外の「貧困」問題にしろ、大なるものが小なるものを踏みつけにして「平和」やら「安全」やら「発展」やらを醸成するという実態構造を、聞こえのいいプロパガンダが覆い隠しているという意味で共通している。
これらがこんなにもはっきり共通しているというのは、自分としてはかなりな「発見」なのである。別に共通していると思って関心をもったわけではなく、なにやら惹きつけられ、こだわってしまったものが、今よく考えたら共通していた。そして、どうにかその世界の共通した不条理から身を引き剥がし、反撃に転じたいと思う気持ちは、それら不当な世界システムに対する怒りとか正義感からというよりは、もっとシンプルに、「(自分が)気持ち悪いからイヤだ」という、ほとんど本能的な直感に拠っている、つまり一種の自己防衛本能からくるものだ、ということがわかってきた。
3.11の巨大地震という、自然からの揺さぶりが、その「本能」をあらわにしてくれた。人はそういう形でも、自然とつながっている。それが救いだ。その感覚が途切れてしまった者は、「凧糸切れた凧」である。不意にどこかに墜落するだろう。
その時の父の主張の骨子をいえばこうなる。世の中には資本主義と社会主義(共産主義)というものがあるが、日本は社会主義の良いところも多少取り入れた「修正資本主義」のスタイルで「発展」した。世界を見渡しても、どうやらこれが一番正しいモデルなのである。だからお前もその枠組みの中で出世を目指し、お国の「発展」に貢献するのが「国民」としてのまっとうな生き方である──と。
要は、自分のこれまでたどって来たサラリーマンとしての処世を正当化せんがための(実際それ以外のことなんか知らないし)持論の披瀝であって、○○主義だのをまともに論じられるほどの教養が父親にないことは当時の僕ですらうすうす勘付いていたので、そちらの方向で何か言い返すような愚は犯さなかった。ただ、僕が思わず言い返してしまったのは、今の日本のこの「発展」が完全無比のものであるかのような、様々に噴出する社会の矛盾をあっさり見落とせるようなおめでたさに、「馬鹿にするな」という気持ちが湧き上がったからである。すなわち、そうした「発展」が必ずしもバラ色だったわけじゃない、たとえば「公害」の問題はどうするんだ、と振り向けたのである。
これに父は極めて直情的に、間髪をいれずに、「お前にそれを言う権利はないぞ!」と怒鳴り返してきたのである。それを言うのはご法度だ、それだけは許さないぞと言わんばかりに。高度成長のためにたくさんの日本人が必死に働いた。そのおかげで、今お前は不自由ない生活ができている。その働いた人達をけなすことはお前にはできないぞ、と。…当時の僕には言い返せなかった。まだ中学生の者にとって、「お前は養われている身だ」という言葉に反論することは何より難しかったからだ(実際、父・母のおかげで飯が食えているのは紛うことなき現実であり──というか、要するに父はその一点を頼みに、強弁しているに過ぎないのだったが…だったらもったいぶった「世の中というものは」式の議論なんかふっかけてくんじゃねーよ、という話である^^)。
今ならこの父の言い分がいかに幼稚な、没論理的な反駁であるか、簡単に指摘できる。細かい点は置いても、上の「そのおかげで」論に従えば、後の世代の者は前の世代のやったことを、いつでも・何一つ批判できないことになってしまう。そんなアホな話があるか。「そのおかげで」ひどい目に会うことだってあるのに!(公害はまさにその一例だし。)
ただ、こうした論法は、何もうちの父親の特異な考え方だったわけではなく、多かれ少なかれ世間の同年代の大人たちの共有するところだったろう(そして3.11後の今ですら、そこから脱却できない人が多い)。今にして思えば、そうした父親世代の自己正当化に対する根本的な疑念が、自分をその後、たとえば「パレスチナ」の発見、こだわりに向かわせたのだと、決してこじつけでなく、そう思う。
父の世代は、日本が敗戦後の貧しい状態から、奇跡のような復興を成し遂げ、アジアどころか世界の一等国なみの西洋文明化を果たして久しい昭和後期の時点、つまり中学生の僕に説教を垂れていた時点で、すでにあらかたやることはやった、ゲームは日本の「勝利」で終わった、人生は意味があった、という感慨とともに暮らしていたのである。すでに「経済大国」になったあとの日本に生まれ落ちたこちらとは、物の見方に差があって当然だろう。
たとえば父からすると、「首都高速道路」が都内を縦横に駆け巡っている光景など、本や雑誌の挿絵に登場するだけの、遠い遠い未来の姿だと思っていた。それが眼前にある今というのは輝かしい時代であり、それを見ることはまずもって「いい気分」なのである。ところが僕は、あんなものの走っているそばに住んでいる人は騒音やら大気汚染やらで大変だろう、あんなとこには住みたくないな、という憂いの気分が先に立ってしまう。結局はそれを使って利便を図っている自分達がいる、という後ろめたさもありながら。
大なるものが小なるものを疎外したり、抑圧したりする。どんなにうまくやっても、心を砕いて配慮しても、「大」の図体がでかいだけに、結果としてそうなってしまうことが世の中にはある。あるならば、まずそれは正直に認めて、対策を別個に補う必要がある。それは○○主義とかいう問題とは関係ない。「大」と「小」がある限り、避けられない事柄だ。
しかし最初から犠牲(「小」が犠牲となって負担を背負う)を「よし」とするシステムを是認してしまう場合、質的にまったく異なる問題を孕む。ゴリ押しすればするだけ、システムは肥大化し──すなわち多数の豊かさのための自己正当化、美化(偽装)を肥大化させ、それがまた新たに社会の各層に「犠牲制」システムの増殖を促す、という悪循環が止まらなくなる。どこか一箇所の、ローカルな問題というにとどまらなくなる。──そうして社会はむしばまれる。
父の信奉する、そして自己をそこに託し一体化させて生きようとした(簡単に言えば、長いものに巻かれようとした)「発展」イデオロギーに、僕がどうしようもなく反発を覚えたのは、そうした悪循環の不気味さを、どこかで感じていた(一度や二度の出来事を通じてでなく、日常のなかで連続的に)からだと思う。
6月11日の新宿デモの際、手書きで「この国はおそろしい」と書いたプラカードを掲げて歩いている人がいた。共感したけれど、僕の場合ははるか昔から、「この国は気持ち悪い」のだった。きっとどこの国にいても、国を挙げての自画自賛言説の垂れ流しに付き合わされたら、誰だって気持ち悪くなってくるだろう。ただ日本は、それが経済の「発展」と二人三脚のようにして自画自賛言説の洗練のされ方も「発展」してきたような、言うなれば過剰な根拠を見込んで過剰な自負心を社会のなかに醸成してきたような感があって、独特に気持ちが悪い。
パレスチナ/イスラエルの問題にしろ、死刑制度の問題にしろ、原発にしろ、米軍基地の問題にしろ、内外の「貧困」問題にしろ、大なるものが小なるものを踏みつけにして「平和」やら「安全」やら「発展」やらを醸成するという実態構造を、聞こえのいいプロパガンダが覆い隠しているという意味で共通している。
これらがこんなにもはっきり共通しているというのは、自分としてはかなりな「発見」なのである。別に共通していると思って関心をもったわけではなく、なにやら惹きつけられ、こだわってしまったものが、今よく考えたら共通していた。そして、どうにかその世界の共通した不条理から身を引き剥がし、反撃に転じたいと思う気持ちは、それら不当な世界システムに対する怒りとか正義感からというよりは、もっとシンプルに、「(自分が)気持ち悪いからイヤだ」という、ほとんど本能的な直感に拠っている、つまり一種の自己防衛本能からくるものだ、ということがわかってきた。
3.11の巨大地震という、自然からの揺さぶりが、その「本能」をあらわにしてくれた。人はそういう形でも、自然とつながっている。それが救いだ。その感覚が途切れてしまった者は、「凧糸切れた凧」である。不意にどこかに墜落するだろう。


















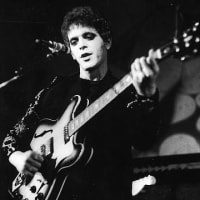

そして、レイランダーさんは、どういう一歩を踏み出されますか?私は、ひとりでも多くの子どもが、レイランダーさんのように自分の頭で考えられる子になれるようなお手伝いをすることかなぁ・・・と考えています。
本はたくさん読んでこられましたか?
どういう一歩を、と問われても、正直なところ明確な答えはありません。前にもどこかで書きましたが、ただ歩き出すだけ、ですね。何者かになろうとは思いません。たぶん、そのこと自体が何か自分という人間の「芯」みたいなもんで、それを言葉に言い表すことができないだけかもしれませんが…。
子どもにものを教える仕事を結構長く関わってきましたが(今はやってません)、いつも思い知らされてきたのは、こちらが教えようとしたことよりも、意識せずに伝わってしまうものの方がはるかに大きい、ということです。たとえば親御さんの、その背中を見て勝手に学ぶんですよね、子どもは。だから大人としては、生き様そのものを見てもらうしかないのかな、という気がします。だって、自分の子ども時代を思い返しても、やっぱりそうですからね。
本はたくさん読んだ方だと思いますが、それ以上にマンガも読みました(笑)。