アメリカ発、医療改革ののろしが上がった
だが、まだこれは氷山の一角だろう。
もうこれ以上金は出せない(国家)
じゃあ、とりあえずこれとこれを減らしますから(医師会)
ということで、医療各会で5つくらい出してみるか・・
25の分野×5つの無駄な医療 = 125の無駄な医療をまとめて100くらいにしました。
まあ、取りあえずどうしてもこんなのは要らないというハッキリとしたものだけを集めてみました。(笑い
さて、のろしを上げてしまった医療界だが、これに火がついてついに燎原の火のように拡大するとは想いもしなかっただろう(と未来予測)
日本人には通用するかなあ?
特に老人は信者さんとして第一級だからねえ。「先生様の言うことだから」と。
(医者はおと様がついて、神さまのごとく、いや、神さまでもお神様とは言わないか)
日刊読むラジオ
Shall We Read Radio?
TITLE:アメリカ医療界で広がる「Choosing Wisely」―その背景と日本医療界への影響 | 日刊読むラジオ
DATE:2014年8月21日(木)
URL:http://www.yomuradio.com/archives/58
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
アメリカ医療界で広がる「Choosing Wisely」―その背景と日本医療界への影響
2014/07/17 (木)
今、アメリカで、医師自らが率先して、無駄だと思われる医療行為を挙げる「Choosing Wisely」というキャンペーンが広がっている。この「Choosing Wisely」が広がる理由はなんなのだろうか? そして、日本もそこから、医者を施す者として、そして医療を受ける者として、なにか学べることがあるのだろうか? アメリカで広がる「Choosing Wisely」を紹介した本、「絶対に受けたくない無駄な医療」の著者で医療経済ジャーナリストの室井一辰が解説する。
アメリカで広がる「Choosing Wisely」とは?
野中英紀 (番組ナビゲーター・ミュージシャン 野中)
室井一辰 (医療経済ジャーナリスト 室井)
@ J-WAVE「JAM THE WORLD」 (2014/07/07)
以下、J-WAVE「JAM THE WORLD」2014年7月7日放送回から書き起こし
野中:
いまアメリカの医療界で「Choosing Wisely」 というキャンペーンが広がっているのをご存知でしょうか? 「賢く選択しよう」というような意味合いだと思いますけど、このキャンペーン、ちょっと面白いんですけど、アメリカの医療界が自ら率先してですね、無駄だと思われている医療行為を挙げているというものなんですが。で、アメリカでこの「Choosing Wisely」が広がっている理由はなんなんでしょう? そして今後、日本もここから学ぶ必要があるのでしょうか?
そこで、今夜はこの方をスタジオにお招きしてお話を伺いたいと思います。このアメリカで広がっている「Choosing Wisely」を本で紹介した、「絶対に受けたくない無駄な医療」 というタイトルの本を書かれた、医療経済ジャーナリストの室井一辰さんです。こんばんは、室井さん。ようこそJAM THE WORLDへ。よろしくお願いします。
室井:
こんばんは。今日はお招きいただいて、ありがとうございます。室井一辰です。
野中:
この「Choosing Wisely」って言葉、初めて聞いた方が多いんじゃないかと思うんですけども、実は僕もそのひとりなんですが(笑)、改めてこれこのどのようなキャンペーンなのか、教えていただけますか?
室井:
そうですね。アメリカで広がっている、無駄な医療撲滅キャンペーンですね。で、特徴的なのはお医者さんが自ら無駄な医療を挙げていくというところですね。
野中:
なるほど。
室井:
米国内科専門医認定機構財団 、ちょっと言いにくいんですけども、ABIM財団っていうところが、アメリカの医学会を束ねて、それぞれの学会に無駄な医療を項目として挙げさせるっていう、そういうちょっと変わった取り組みなんですね。
医者10人のうち8人が参加している「Choosing Wisely」
野中:
ほんとにユニークだと思ったのは、お医者さんが自ら無駄な医療を挙げて、それを撲滅しようというキャンペーンって、これほんとに興味深いんですけど、実際に全米の医師の中でどのくらいの割合の方が参加されてるんですか?
室井:
だいたい71の医学会が参加しているんですけども、その所属学会を通じて、だいたいアメリカ全体で60万人ぐらい医者がいるんですが、そのうちの8割ぐらいの50万人ぐらいが参加するっていう、そういうかなり大きなキャンペーンなんですね。
野中:
かなり多くの方が参加してるんですね。
「Choosing Wisely」がこれほどまでに広がる背景
野中:
これは、それにしても、アメリカの医療界で無駄な医療の撲滅をしようという機運が進んできた、この背景にはどういう事情があるんですか?
室井:
やっぱり日本と同じような感じで、医療費ですね、アメリカでもやっぱり増えてます。3兆ドル近くで、300兆円に迫るような水準になっているんですね。
そんな中で、無駄な医療撲滅の呼び水のひとつになっているのは「オバマケア」なのかなと。皆保険制度、今まで日本が世界に誇るといわれてたわけですけど、アメリカでもそれが広まろうとしています。だいたい5千万人ぐらいが今までアメリカで無保険だったわけですけれども、そういう人たちにも保険に入ってもらうと、で、保険料の上限を定めていく。
そういう結果として、もちろん良いわけですけれども、医療費の上昇をする方向になってしまうわけですね。で、全体としてはない袖が振れないというわけで、で、国としては医療費を出せないという面もある。無駄な医療を削んなきゃいけないっていうところが、国全体として広まっている。それを受けて医師から動き出したっていう、そういうことなんですね。
野中:
なるほど。確かマイケル・ムーア監督が「SiCKO」という映画で、アメリカの医療界の暗部っていうかそういうネガティブな、アメリカのそういう様々な医療業界あるいは保険業界に関わる様々なことを取り上げてですね、かなり話題になったとと思うんですけど。ご承知の通り、マイケル・ムーアさんはオバマの熱烈なフォロワーというか支持者で。こういったことももしかしたらオバマケアが誕生してくる背景にあったのかなとも思ったんですが。
日本だとちょっと想像がつかない、5千万人もの人がぜんぜん保険に入ってなくて、アメリカではしかも病院になるとちょっとした病気でもものすごいお金取られるじゃないですか。救急車で搬送してもらっただけでも何万円も取られるし、盲腸を手術しただけで300万とか400万とか請求くるしですね、とんでもない状況なわけですけど。そのめちゃくちゃ高額な医療費がかかってるアメリカで、これはさすがにこれ以上、今まで保険に入ってない人の分もカバーしようとすると、そもそも予算がないということになってきて、そもそもオバマケアも共和党からは批判されていたのはそこの部分だったわけですけども、そういったこともあって、こういう無駄を省いていこうという、極力、医師の側から動き出したっていうことなんですね?
室井:
ええ、そうですね。
「無駄な医療」か否かの判断基準
野中:
ところで、この無駄な医療かどうかっていうのは、どのような基準で判断しているんですか?
室井:
これは全て、臨床研究っていうですね、いわばA/Bテストみたいなもので、ランダムに患者を分けて、Aの治療がいいのかBの治療がいいのかっていう対決をさせる、そういう研究に基づいて、医学会が「これは無駄ではないか」っていう提案をしているっていう、そういうことなんですね。
野中:
なるほどね。これ、でも、患者にとっては大変有益な情報ってことになるわけですけれでも、でも一方で、お医者さんの側、医療業界から見れば、なんか自分で自分の首を絞めていってやろうっていうふうにも見えるんですが、そのへんはどうなんですかね?
室井:
そうですね。私にとっても最初これ出会ったとき、衝撃のリストだなと思ったのは、まさにそういうところがありました。なんで医師がこんなことやってるのかなっていうとこですね。結局ですね、さきほど申し上げたとおり、医療費の抑制圧力っていうのが強まっている中で、ない袖が振れないっていうふうなっているわけですね。そうすると、無駄なお金がまわってくるとまずいと。本当に必要な医療に金をまわしたいっていうことですね。
そうしたときに、医師側としては本当に必要な医療を自分たちはやりたいと。逆にいうと、無駄な医療に、いまお金がない中で、まわっていってしまうと、自分が本当にやりたい医療っていうのができなくなっちゃうわけで、そこを避けたいっていう、機先を制するみたいなところがあったんだと思うんですよね。
で、人によってはですね、そうすると医療側はですね、都合にいいようなそういう無駄な医療っていうのが挙げられてくるんじゃないかっていう話もあるんですね。
野中:
自分の都合のいいように?
室井:
そうですね。でも、そうもうまくいかなくてですね。最近アメリカでは「Self Referrer」ですね、そういう考えが出てきてまして、医療界が自分たちで自分たちの医療行為を評価して、言ってみれば、日本語で言えば「お手盛り医療」みたいなものをやってるんじゃないかっていう批判が結構高まってまして。そういう中で簡単に都合のいい医療をやっていけるかっていうとそうでもないということがあるんですよね。
それで最終的に社会の洗礼を、こうやって無駄なものはきちんと表明して、健全な仕組みに僕らもしますよ、と医師側は自分たちの利益にもなるし社会の利益にもなるしということで、この取り組みを広げているということですかね。
野中:
その全米に60万人もいる医者の、お医者さんの中の50万人、約8割が参加しているっていうんですから、そうとう大きな動きであることは間違いないと思うんですが、さてその中身は実際どうなのか、後半も詳しくお話を伺っていきます。
腰痛の画像診断やピル処方の内診を含む、250の医療が不必要と判断
野中:
さて、この「Choosing Wisely」なんですけども、2013年までに250前後の医療行為が不必要だというふう判断されたようなんですが、これ具体的にどのような医療が挙がってるんですか? 無駄だということで。
室井:
そうとう幅の広い分野について無駄だということを言ってるんですね。
例えば、ひとつふたつ、できるだけ紹介していければと思いますけれども、例えば腰痛なんかの診療でですね、無駄だって言われているのが、6週間以内の腰痛で画像診断が無駄だっていう話をしてますね。腰痛は日本のあらゆる症状の中でも最も多いっていうことで、厚生労働省の国民生活基礎調査っていうのがあるんですが、50歳以上の10人に1人が腰痛持ち、80歳以上になると5人に1人なんですね。だからこそ医療機関にも行っているはずですよね。もしかしたらX線を撮られたり、場合によってはそうとう悪いと、CT検査になったりMRIになったりして、結果として「なんともありませんよ」なんて言われたことがある方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、米国医学会は「基本的に無駄だ」っていうようなことを、今回大々的に言ってます。ほんとに動けないほど重症、ガンになったことがある、片足が全く動かないみたいな人に対しては、例外的に「赤い旗」っていうふうに表現しているんですけども・・・。
野中:
「Red Flag」ですね。
室井:
それがない限りは、6週間以内の症状であれば、X線、CT、MRIはしないで良し、というふうに注意をしてます。
野中:
なるほど。ほかにどういうものがあるでしょうか?
室井:
わりと女性にとって、最近だともしかしたら関係あるかもしれませんが、ピルを出すのに膣の内診が不要だっていう話をしています。ピルっていうのは、日本では比較的に縁遠い方も多かったと思うんですが、1999年に低容量ピルっていうのが出て、だんだん一般的になってきたかもしれないと思っているんです。
これ、抵抗のあるところもあるっていうのが、やっぱり内診ですね。単に薬をもらうだけなのに、下半身の検査を受けるっていうのはイヤだと思うんですけども。医療側にも、女性ホルモンが関係する問題なので、乳ガンであるとか、ピルを飲むと性的に活発になる、感染症になんかにもなりやすくなるっていうので、子宮頸ガンを調べるっていうような理由はあるんですけど、そこを今回アメリカの医療界は明確に「無駄ですよ」と言ってます。
若干面白いのは、実はこの7月に米国内科医学会っていうところは、「健康な人への内診はどんなときでも無駄だ」っていう指針を出しまして・・・。
野中:
そうなんですか? ほー。
室井:
ええ。やっぱり精神的な負担があるので、むしろ病気が見つかりにくくなるみたいな話があるということで。
野中:
足が遠のいてしまうっていうことですか? 病院から。
室井:
そうですね。臨床研究で検証した結果として「意味なし」っていうふうに言いました。
野中:
ほかにはどういう事例がありますか?
室井:
わりとやっぱり大きな問題としてはガンでしょうか。「いきなり手術はご法度」っていうのを出してますね。言ってみれば簡単なんけど「プランを作れ」って言ってます。ガンの診断、治療、予防っていうのは、医師がどうしても手術ばかりに目がいきがちっていうところがあると思うんですけど、ここでプランって言ってるのは、手術前後の色々なリハビリであるとか、あと自宅でどういうふうに介助するかとかですね、このガンの見通しはどうなのかっていうようなところをですね、ちゃんとプランに盛り込んで説明しましょうっていう。
裏返せばアメリカでもそういうことをやってないっていうとこがあると思うんですけども、日本では尚更かもしれません。そこをおろそかにする医療はまかりならんっていうことを改めて強調してるのは、ちょっと面白いかなと思いました。
「肺ガンのCT検査がほとんど無意味」
野中:
ほかには、ガン関係では?
室井:
ガン関係では「肺ガンのCT検査がほとんど無意味」って書いてあるんですね。
野中:
そうなんですか? それ、どうしてなんですかね?
室井:
そうですね、肺ガンのCT検診っていうのは、日本、アメリカでちょっと最近注目されているところでもあってですね、ヘビースモーカーには良いって言われてるんですけども、健康な人にとっては意味がないですよっていうことが言われています。CTっていうと日本ではほんとに年間1千万件単位で受けられているので、みなさんにとって身近な・・・。
野中:
そうですよね、なにかっていうとCT撮るような気がするんですけど。
室井:
実は私は調べててビックリしたのは、福島でいま原発の被爆で問題になりますが、第一原発のですね、東京電力がよく発表してるんですけども、その被爆量がだいたい最大値で作業員の方、1~10ミリシーベルトっていうふうな感じで発表が続いています。だいたいCT検査で受ける被爆量っていうのも、だいたいこの1~10ミリシーベルトと一緒なんですね。
野中:
なるほど。
室井:
で、緊急時被爆限度ってのが100ミリシーベルトなので、これCTってのはやっぱり意外とこれは大変なものなんだなって改めて調べてみて思いました。そう考えると、そう安易にCTを撮ってはいけなんだなって。
野中:
よほどのことがない限りっていうことですかね?
室井:
ええ。だから肺ガンを見つけるっていうことで、そもそもヘビースモーカーでもない方が受けるのは、ちょっとやりすぎなのではないかなっていうことは言えるのかなと思いますね。
野中:
それと日本はそのCTそのものがちょっとやり過ぎじゃないか、という・・・。
室井:
そういうのはありますね。
野中:
CTやることによって逆に病気になってしまうっていう、それがトリガーになってガンを誘発するケースもあるって言ってますけど。
室井:
ええ、実はそうなんですね。実際、CTを撮るとガンのリスクが上がるっていうのを、オーストラリアとたしかイギリスだったと思いますけど、臨床研究もあるぐらいなんですよね。
「医療側、患者側、両方ともの思考停止」
野中:
ところで、根本的な話になるんですけども、なぜそもそも無駄な医療っていうものが生まれてきたんですかね?
室井:
言い方はちょっときついかもしれませんけど、「医療側、患者側、両方ともの思考停止」が根底にあるかなと。
野中:
思考停止・・・といいますと?
室井:
医療側の要因としては、無駄だと知っている場合と知らない場合とがあると思います。一部紹介するとすれば、無駄だと知らない場合っていうのは単純で、言ってみれば知識不足ですね。新しい臨床研究が出てきて、これまで必要だと言われていたものが不要だと判明する場合があります。すごい分かりやすい話だと、傷口に消毒をするみたいなことなんですけど、最近はしないのが標準的になってきてます。
野中:
そうなんですか?
室井:
なんですけれども、場合によっては消毒を念入りに今でもしている方っていうのは、医療界にもいるかもしれません。そこを、臨床研究の結果を知っているかどうかっていうことで変わったりします。
で、知っていてやっている場合っていうのがあって、むしろそちらのほうがやっかいだ思います。先ほどのは知らないでしたけど。そういう場合っていうのは、知っていてやってるぐらいなんで、あまりやってもやらなくても影響がない場合ってのが多いと思います。先ほどのX線とかCTを腰痛にするかどうかっていうのは、ほとんどの場合、無駄と言っているぐらいなので、意味のある発見が出てこないっていうことで、医療側も実はそれを知ってたりするんですね。
野中:
なるほど。
室井:
だけれども、例えばX線であれば1回あたり5千円ぐらいの収入につながるとか、CTだと3万円ぐらいになるとかですね。しかもそれが患者も求める部分があって、もしかしたら重症な病気が潜んでいるかもしれないからということで、やってしまうと。知っていてもやってしまうということなんですね。
野中:
なるほどね。
「医療側と患者側とのコミュニケーションのツール」
野中:
そうするとやっぱり、医師の側も患者の側もこの無駄な医療を省く上で、積極的にこれをずっと呈示をしていくっていうことになるんでしょうけども、やっぱりそれ、情報が必要ですよね、そうなると。リテラシーっていうか、こういった医療行為に対する。
室井:
そうですね。
野中:
最近はインターネットがあるから、患者さんもだいぶ色んな自分の病気に対して調べてまくってからお医者さんに行くって人もいるみたいなんですけど。
室井:
まさにその通りですね。だからこういう「Choosing Wisely」みたいなものを示すことで、みなさんにとって考えるきっかけ、医療側と患者側とのコミュニケーションのツールっていうか、そういうふうに使われていく、問題提起っていう位置付けになってるんだろうなって思いますね。
日本で「Choosing Wisely」が広がる可能性は「無い」
野中:
ところで、アメリカではここまで8割近いお医者さんが参加して進んでいるこの「Choosing Wisely」の活動なんですけども、日本は当然のことながら医療費の増大が大きな社会問題になっているわけで、こういう日本でも「Choosing Wisely」の試みっていうのがスタートしたりあるいは広がりを見せる可能性っていうのはありますかね?
室井:
やっぱり日本ではですね、この「財政逼迫」と呼ばれる状態が行き着くところまで行くかどうかっていうところが、ちょっと残念ながら、そういうところが重要なのかなっと思いますね。
野中:
あー、そういうレベルですか、やはり。
室井:
ええ。お金の問題の問題を一切無視してしまうと、過剰検査とか過剰治療っていうものは、いくらあっても命に関わらない限り問題にはなりにくいんですね。
例えば、さっきのCT検査みたいなもので被爆をいくらするっていっても、ガンのリスクが高まったりするというのは事実なんでけども、直接的にそういうものが表れるものでもありません。薬でも、副作用が出て、死亡する人が中にはいるけども、すごい稀なので、直接的には影響しない、と。
結局、ない袖は振れない段階になって、ようやく医療費にかけられる上限が定まって、やっと動き始めるっていうことなのかなと。
野中:
でも、日本の保険費っていうか医療費の逼迫するところまでいかないと変えられないっていうのもちょっと由々しき問題だと思うので、ぜひアメリカに倣って、先に先に率先して、無駄な医療行為っていうのは医師の側から提言してもらいたいなって思うんですけど、やっぱり患者のほうも無駄な医療をむしろ求めるっていうところがあるのが問題なんですかね?
室井:
そうですね。ある程度情報を経てですね、ほんとに無駄なものがあるんであれば自分たちのほうから断るみたいな、勇気みたいなものも、これから必要になるんじゃないかなというふうには思いますね。
日本の医療界にこれから求められること
野中:
ところで最後になるんですけども、この欧米で広がっている「Choosing Wisely」っていう動き、これを受けて、いまTPPとかでも日本の保険制度とか医療制度が変わってくるんじゃないかっていう話もありますが、日本の医療界っていうのはどのように変わっていくべきだというふうに思われますか?
室井:
医療界、医療側っていうことで言いますと、自ら動き出すっていうことが必要だと思います。本来、やっぱり医療っていうのは医師、医療従事者が提供するものだと思いますので、いま国であるとか保険者みたいなものが口を出してきているわけですけれども、それで結果として必要な医療が提供できないっていう状況になるとすると、いくら無駄なものを省いたとしても不幸でしかない、と。
野中:
そうですよね。
室井:
やっぱり、その医療を提供している医療従事者こそが、ここのアメリカの動きを好機だとみて動き出していく、機先を制するみたいなものを決するといいんじゃないかなと。それで審判を受けていくっていう、社会と会話するっていうのが大切だなという気もします。
野中:
分かりました。この「Choosing Wisely」も含めて、この室井さんが書かれた本、「絶対に受けたくない無駄な医療」という本には、日経BPから出ているんですけど、非常に内容も興味深くてですね、いまお医者さんにかかってらっしゃる方とか、これからかかる予定のある人も含めてなんですけども、たぶんほとんどの方がこれ内容に興味持っていただける思うんで、ぜひ、今日この話を聴いて関心を持たれた方は、この「絶対に受けたくない無駄な治療」をチェックしてみていただければと思います。室井さん、今日はほんとにどうもありがとうございました。
室井:
こちらこそ、ありがとうございます。
以上、J-WAVE「JAM THE WORLD」2014年7月7日放送回から書き起こし
[ 書き起こし後記 ]
この問題は非常に興味深いと同時に、我々にも大きな挑戦となります。つまり、自分が受ける医療が本当に必要なものか否か、正確かつ最新の情報を自分で入手する必要に迫られるからです。なにか薬を出してもらうとか、なにか検査をしてもらうとか、そういうことによって得られる安心感は確かに私もあります。「とりあえず、お薬を出しておきましょうか」っていうのは、お医者さんの決まり文句のようなものです。本当に必要な医療を本当に必要な患者に届ける。当たり前のように思えることがなされてこなかった医療業界を変えるには、医者と患者の両方のリテラシーを高めていくこと、そしてそのコミュニケーションを高めていくこと、その両方が求められるということでしょう。(編集長)
絶対に受けたくない無駄な医療
著者室井 一辰
価格¥ 1,512(2014/08/21 08:35時点)
出版日2014/06/20
商品ランキング752位
単行本268ページ
ISBN-104822274497
ISBN-139784822274498
出版社日経BP社
TITLE:アメリカ医療界で広がる「Choosing Wisely」―その背景と日本医療界への影響 | 日刊読むラジオ
DATE:2014年8月21日(木)
URL:http://www.yomuradio.com/archives/58












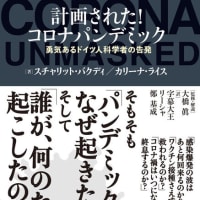
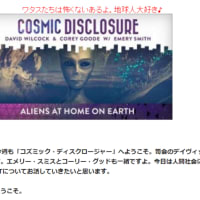
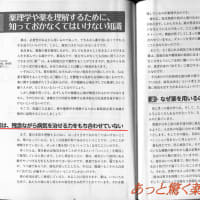
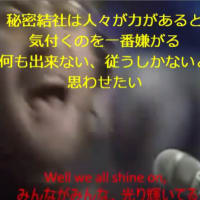
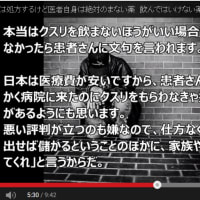

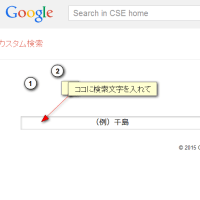
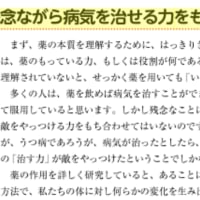






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます