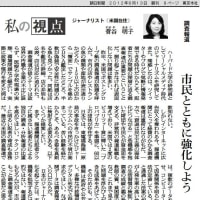昨年9月からMIT Media Labの所長に就任された、伊藤穣一さん。よくお話しを伺う機会が多いのですが、彼をみていると、この時代、いかに発想を大きく転換することが必要なのかを考えさせられます。
Joiさん(伊藤さんニックネーム、Twitter @Joi)は、まさに今の時代にふさわしいリーダー。決して肩書きや権力を行使するのではなく、誰とでもリスペクトを持って対等に接し、それぞれを尊重してくれるものの、卓越した知性と思考から、誰もが「この人こそリーダー」だと自然に感じてしまう「自然体のカリスマ」。一見すると、学生と見分けがつかなかったりするにも、逆にいい感じw
完璧なバイリンガルであることを遥かに越えて、日米文化を深く理解し、グローバルなビジョンを持つ、バランス感覚溢れるリーダー。今時の人らしく、マルチタスクにも長けていて、ミーティング中に携帯をチェックしたり、ipadをいじったりしているものの、ちゃんと話しは聞いていて、要所要所で鋭い指摘をするところなどは、さすが「現代の聖徳太子」(笑)と思ってしまいます。
Joiさんの話しから、いくつか心に残っているフレーズを、記憶を元にまとめてみました。
ー「上手くいくかどうかを考えるより、とりあえず始める」
ネットワーク時代、面白いアイディアがあれば、それがやるに値するかどうかを、時間とコストを使って調べるくらいなら、不十分でもいいから、とりあえず始めたほうが、コスト的にもずっとリスクが少ない。とりわけ、日本企業は失敗をあまりに恐れるために、上手くいくかどうかを調べることに力を注ぎすぎ、それでは時間の無駄であるばかりか、格好のタイミングを失ってしまうということ。「とにかく始める」は、個人にも当てはまると思うので、私もとにかくやってみようと発想を転換中w
ジャーナリズムで言えば、未完成な記事でも、どんどん公開していくほうが、何を追加作業しているのかを明確にしていれば、完璧な記事を書くべく作業し、タイミングを逃した後で公開するよりも、意味があるということかもしれません。実際、ニューヨークタイムズのオンライン版などは、「確認は取れていないが」「詳細がわかったところでまた伝えます」など、まさにリアルタイムにアップデートをするなど、まさにこうした方法をとっています。
ー「自分ができるよりも、できる人を知っていることに価値がある」
まさにご本人がこれを実践されているだけあって、説得力があります。東日本大震災後に、メールやスカイプで世界中の友人に声をかけ、あっという間に立ち上げた、世界中の放射線を共有できるプロジェクトSafecastもその一例。私もこれには深く共感。視点が違いますが、ネットワークの重要性については、以前、「国境を越えたネットワークを作る」(朝日新聞 Globe) を書いています。
ー「客観性とは透明性」。
ジャーナリストは、客観的であるというふりをするのをやめること。その代わりに情報源を全て示すなど、情報を透明化すること。市民は情報源に当たって、自分で判断できるのだからという考え。興味深いのは、JoiさんのWikipediaの使い方。本文の説明よりは、どう編集されてきたのか履歴をみたり、リンクをチェックするなど、情報が加工されるプロセスを重視しているようです。これは実践している人はそう多くないかもしれませんが、とても重要なこと。
ージャーナリストはテクノロジーを敵視し、自分でマスターして来なかった。またビジネスモデルにしても、経営と記事の分離と称して、ネット時代への対応を考えていない。そうすると結局は、自分たちの知らないところで、デジタル化への対応が決定され、コントロールを失って、ジャーナリズムの首を絞めることになる。
客観性については同感で、客観的であることは、目指すべきものであっても、完全に客観的になるということはありえないのですから。透明性についても同意しますが、Joiさんにようにリテラシーの高いかたならまだしも、一般市民が実際に情報源に当たって自分で判断するというのは、時間的にも、リテラシー的にも、実際は難しいという複数の調査結果があり、メディアや情報の特性を理解する、情報教育(メディアリテラシー)が改めて必要になるのではないかと思いました。
* * *
ラボの所長になってからも、ボストンにいるのは稀で、毎月地球を数周しているという、文字世界を通り飛び回っている。ご自分でも言われているように、小さい頃から、本や学校で学ぶタイプではなく、人に会って話しを聞き、自分で実際にやってみて、経験から学ぶタイプだそう。彼のこうした学びのスタイルは、既存の大学教育のあり方と必ずしもマッチせず、Joiさんは大学のような「狭い世界」では飽き足らなかったのかもしれません。こう考えるみると、今の教育のあり方が、多様な学びのスタイルを許容できていないという課題も浮き上がってきます。実際、先日、ハーバードの教授を対象にした、Harvard Initiative for Learning and Teachingでも、この点もテーマになっていました。(このシンポジウムもとても面白かったので、近くアップしたいです)
また、ノーベル賞化学賞を受賞された福井謙一教授が小さい頃からのメンターで、伊藤少年を色んな意味で励まし続けてくれたと聞いたことがありますが、ロールモデルとなるような人々へのアクセスも、Joiさんを勇気づけ、自信を持って前に進む原動力になったのかもしれません。
Joiさんの主張は常に明快でポジティブ。先日「エジプト革命」でFacebookを使って「革命」を後押ししたGoogle中東・北アフリカの地域幹部のワエル・ゴニムの話しを聞く機会がありましたが、彼もやはりネットワークに対して非常に前向きであり、時代を作って行く人というのは、自分が考えるものを信じて、どんどん突き進んで行くものなのだと考えさせられました。
そんなわけで、Joiさんは学ぶことがたくさん。
これからもずっと注目していきたい方です!
Joiさん(伊藤さんニックネーム、Twitter @Joi)は、まさに今の時代にふさわしいリーダー。決して肩書きや権力を行使するのではなく、誰とでもリスペクトを持って対等に接し、それぞれを尊重してくれるものの、卓越した知性と思考から、誰もが「この人こそリーダー」だと自然に感じてしまう「自然体のカリスマ」。一見すると、学生と見分けがつかなかったりするにも、逆にいい感じw
完璧なバイリンガルであることを遥かに越えて、日米文化を深く理解し、グローバルなビジョンを持つ、バランス感覚溢れるリーダー。今時の人らしく、マルチタスクにも長けていて、ミーティング中に携帯をチェックしたり、ipadをいじったりしているものの、ちゃんと話しは聞いていて、要所要所で鋭い指摘をするところなどは、さすが「現代の聖徳太子」(笑)と思ってしまいます。
Joiさんの話しから、いくつか心に残っているフレーズを、記憶を元にまとめてみました。
ー「上手くいくかどうかを考えるより、とりあえず始める」
ネットワーク時代、面白いアイディアがあれば、それがやるに値するかどうかを、時間とコストを使って調べるくらいなら、不十分でもいいから、とりあえず始めたほうが、コスト的にもずっとリスクが少ない。とりわけ、日本企業は失敗をあまりに恐れるために、上手くいくかどうかを調べることに力を注ぎすぎ、それでは時間の無駄であるばかりか、格好のタイミングを失ってしまうということ。「とにかく始める」は、個人にも当てはまると思うので、私もとにかくやってみようと発想を転換中w
ジャーナリズムで言えば、未完成な記事でも、どんどん公開していくほうが、何を追加作業しているのかを明確にしていれば、完璧な記事を書くべく作業し、タイミングを逃した後で公開するよりも、意味があるということかもしれません。実際、ニューヨークタイムズのオンライン版などは、「確認は取れていないが」「詳細がわかったところでまた伝えます」など、まさにリアルタイムにアップデートをするなど、まさにこうした方法をとっています。
ー「自分ができるよりも、できる人を知っていることに価値がある」
まさにご本人がこれを実践されているだけあって、説得力があります。東日本大震災後に、メールやスカイプで世界中の友人に声をかけ、あっという間に立ち上げた、世界中の放射線を共有できるプロジェクトSafecastもその一例。私もこれには深く共感。視点が違いますが、ネットワークの重要性については、以前、「国境を越えたネットワークを作る」(朝日新聞 Globe) を書いています。
ー「客観性とは透明性」。
ジャーナリストは、客観的であるというふりをするのをやめること。その代わりに情報源を全て示すなど、情報を透明化すること。市民は情報源に当たって、自分で判断できるのだからという考え。興味深いのは、JoiさんのWikipediaの使い方。本文の説明よりは、どう編集されてきたのか履歴をみたり、リンクをチェックするなど、情報が加工されるプロセスを重視しているようです。これは実践している人はそう多くないかもしれませんが、とても重要なこと。
ージャーナリストはテクノロジーを敵視し、自分でマスターして来なかった。またビジネスモデルにしても、経営と記事の分離と称して、ネット時代への対応を考えていない。そうすると結局は、自分たちの知らないところで、デジタル化への対応が決定され、コントロールを失って、ジャーナリズムの首を絞めることになる。
客観性については同感で、客観的であることは、目指すべきものであっても、完全に客観的になるということはありえないのですから。透明性についても同意しますが、Joiさんにようにリテラシーの高いかたならまだしも、一般市民が実際に情報源に当たって自分で判断するというのは、時間的にも、リテラシー的にも、実際は難しいという複数の調査結果があり、メディアや情報の特性を理解する、情報教育(メディアリテラシー)が改めて必要になるのではないかと思いました。
* * *
ラボの所長になってからも、ボストンにいるのは稀で、毎月地球を数周しているという、文字世界を通り飛び回っている。ご自分でも言われているように、小さい頃から、本や学校で学ぶタイプではなく、人に会って話しを聞き、自分で実際にやってみて、経験から学ぶタイプだそう。彼のこうした学びのスタイルは、既存の大学教育のあり方と必ずしもマッチせず、Joiさんは大学のような「狭い世界」では飽き足らなかったのかもしれません。こう考えるみると、今の教育のあり方が、多様な学びのスタイルを許容できていないという課題も浮き上がってきます。実際、先日、ハーバードの教授を対象にした、Harvard Initiative for Learning and Teachingでも、この点もテーマになっていました。(このシンポジウムもとても面白かったので、近くアップしたいです)
また、ノーベル賞化学賞を受賞された福井謙一教授が小さい頃からのメンターで、伊藤少年を色んな意味で励まし続けてくれたと聞いたことがありますが、ロールモデルとなるような人々へのアクセスも、Joiさんを勇気づけ、自信を持って前に進む原動力になったのかもしれません。
Joiさんの主張は常に明快でポジティブ。先日「エジプト革命」でFacebookを使って「革命」を後押ししたGoogle中東・北アフリカの地域幹部のワエル・ゴニムの話しを聞く機会がありましたが、彼もやはりネットワークに対して非常に前向きであり、時代を作って行く人というのは、自分が考えるものを信じて、どんどん突き進んで行くものなのだと考えさせられました。
そんなわけで、Joiさんは学ぶことがたくさん。
これからもずっと注目していきたい方です!