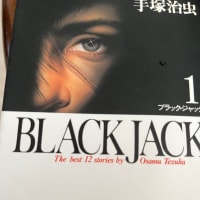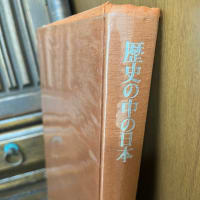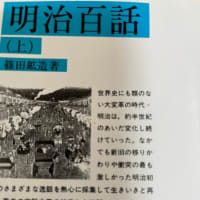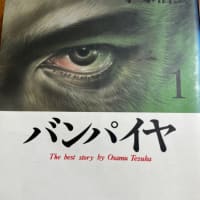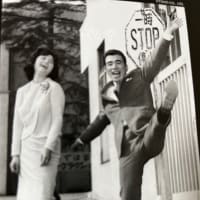愚痴っても、タイムスリップは絶対無理なんですから!
振り返りません。も、後はないのだ。
さて、人間は感情を持つ動物で、男女のいざこざにより世の中(どころか歴史)が狂っちゃうのは実は古今東西よくある事なのです。
古くはクレオパトラ、楊貴妃、みたいなのです。
私、読書体験を通してこの事実を知った。
特に古典からです。
日本文学に夢中になったのは本屋に並ぶ日本文学全集を読んだのがきっかけ。
小6の時、お小遣い貯めて立ち寄った東急線駅前の本屋さんは夢の宝庫でした。
手始めに読んだのが、、、
夏目漱石と芥川龍之介!大変面白かったです。
ただし、出版社側が子ども向けに編集したものです。

漱石の作品は『坊ちゃん』『吾輩は猫である』及び『草枕』など(いずれもエッセンスだけ入っている)が載ってました。その時は、夏目漱石は大学の先生をした優等生タイプの人物としか思えませんでした。

思い出と心象風景とが詰まってますが、特筆すべきはここに描かれた明治の東京の情景です。流石に漱石さん、江戸の名残りの東京の香りが伝わってくる文章であります。

この中村是公と言う方、満鉄総裁を退いた後に関東大震災後の東京市長に選ばれ、復興を成したそうです。

漱石の作品は『坊ちゃん』『吾輩は猫である』及び『草枕』など(いずれもエッセンスだけ入っている)が載ってました。その時は、夏目漱石は大学の先生をした優等生タイプの人物としか思えませんでした。
なので、後年『こころ』や『硝子戸の中』を読んで、鋭敏過ぎる神経と深い洞察力を持った人、だと認識を新たにしました。
『永日小品』は作家として地位がほぼ確立した漱石の日記風随筆集です。朝日新聞に連載されてます。

思い出と心象風景とが詰まってますが、特筆すべきはここに描かれた明治の東京の情景です。流石に漱石さん、江戸の名残りの東京の香りが伝わってくる文章であります。
漱石の親友が後の満鉄総裁中村是公です。永く親交を結んでます。
『永日小品』の『変化』に学生寮の(たった)二畳間で同室だった事が記されてます。粗末な食事と北向きの小さな窓、そこで貧乏暮らしをしながら大志(?)を抱く学生仲間でした。近くに住む女の子への青春の想いなどは、今も昔も変わらないようです。

この中村是公と言う方、満鉄総裁を退いた後に関東大震災後の東京市長に選ばれ、復興を成したそうです。
骨のある方だったらしい。
漱石自身、有為転変の幼少期を送っただけあって相当な負けず嫌いの意地っ張りだったらしい。
ペンネーム漱石の由来は「石に口をそそぐ」意味なんです。つまりへそ曲がり。という事で柔らかい物腰の人でなかったらしく、教師してた時、容赦ない厳しさに腹立てた学生の間で排斥運動が起きたとか。


『永日小品』はそれほど名作とは思えませんが、ほぼその頃のありのままの世間の様相が描かれて、漱石研究には参考になるかと思います。
漱石は多面的な人で非常に気難しく人嫌いかと思うと、慕ってくる人には優しく情の濃い懐の深い面があると感じました。
友人正岡子規が事情があって大学を退学しようとした時に翻意を促す手紙を出してます。
「鳴くならば 満月に鳴け ほととぎす」
ほととぎすは正岡子規の雅号です。その時の漱石は20代前半です。つまり世間で成功を収めた上で抵抗しろと言う句を送った。
この句にグッときました。漱石って頭良くて優しくてステキ❣️です。
男女のいざこざの話じゃなくてごめんなさい🙏