
暫く鑑賞感想をサボっていたので、いくつかキャッチアップ記事が続きます、すいません。まずはメトの椿姫。
(ホールのガレージが満杯で前半を聴き損ねた3月のドホナーニ&フィラ管はさほど言いたいことがないのでスキップしようと思います。)
オペラ好き女の子が憧れる3大ヒロインはやはり椿姫、カルメン、トスカじゃないでしょうか。わたし自身は最初のオペラ鑑賞が椿姫だったのでまずはまり、次にやっぱり歌に生き恋に生きだわよね、で、そして次に魔性の女のカルメンがかっこいい! なんて思ってました。中学に上がってからはもうオペラのヒロインに憧れるようなことはなくなったので、後は続きませんでしたし、椿姫は今でも特別な作品ですけれど、他の2作への思い入れは当時聴き過ぎてあれで一生分を使い果たしたんだか、今ではとても淡いものになってしまいましたけれど。しかしデュッセとかコジェナを見てると、自分の声の特質あるいは音楽家としての性質・特徴に合っていないのを承知でも、ソプラノは椿姫、メゾはカルメンをいつか一度はやってみたい、という女の子的憧れの気持ちって、もしかすると歌手の方々を含め、万国共通かもしれない、とも勝手に思ったりもします。
今回椿姫役デビュー、来シーズンはこれでスカラのシーズン・キックオフをするダムラウも、10代の頃にTVで見たゼッフィレッリのストラータス&ドミンゴ映画版で椿姫・オペラに夢中になってしまったらしいです。そんなダムラウのヴィオレッタ・デビューが、その因縁のドミンゴと共演、しかもドミンゴも年を重ね、かつて活躍した息子役の親の役で仲良く一緒に役デビュー!なんて、おもしろいもんです。既に「おめでとう」記事を出しましたけれど、ほんとよくやった!、でした。
Yannick Nézet-Séguin ヤニック・ネゼ・セガン 指揮
ヴィオレッタ・ヴァレリー: Diana Damrau ディアナ・ダムラウ
アンニーナ: Maria Zifchak マリア・ジフチャック
アルフレード・ジェルモン: Saimir Pirgu サイミア・ピルグー
ジョルジョ・ジェルモン: Plácido Domingo プラシド・ドミンゴ
フローラ・ベルヴォア: Patricia Risley
ガストーネ子爵: Scott Scully
ドビニー侯爵: Kyle Pfortmiller
ドゥフォール男爵: Jason Stearns
グランヴィル: James Courtney
Willy Decker ウィリー・デッカー 演出
3月14日に始まった椿姫の公演、わたしが見に行ったのは結局最終日の4月6日、この頃はもう暫く、一晩のうちに冬・春が入れ替るというようなかなり厳しい天候が続いていて、チェーザレ出演中のデュッセも調子を崩したり、ドミンゴも「アレルギーで調子が悪いけど歌います」なんていうアナウンスがあった日があったそうだし、元気いっぱいだったダムラウもとうとうこの日は風邪を引いていたそうです。確かに出だしのラジオでの印象と比べてちょっと声にハリがないような感じのところもありましたけれど、まぁそれにしても調子が悪いとは思えないほどの熱演でした。
彼女はとにかく歌唱が素晴らしいのもそうなんですけれど、解釈が自分のなかでしっかり練られているのがひしひしと伝わってくる、そしてその解釈に沿って思い切りのいい演技をするので、歌唱と演技がインテグラルになっている、のが、わたしはどうしてもひいきにしてしまう大きな魅力だと思うのですが、今回もまぁ感情表現・役作りが面白い!
ダムラウのヴィオレッタは、「椿姫だったらOXが理想、そうじゃないと認めない」というような方々からすると、産後太りで、デッカー演出の赤いドレスが似合わないとか、歌唱がキツイ・強くて、ヴィオレッタらしくない、とか言われてしまうかもしれません。

体型とか見かけの好みはその人の勝手で、わたしがどうこう言うような問題じゃありませんけど、歌唱がキツイというのは、それは確かにそうですよ、今回ダムラウが表現したのは、なんというか「怒れる若者」のヴィオレッタだったんじゃないか、なるほど面白い、彼女にあった役作りだな、わたしはいいな、と感じました。今回一週間だけデッカーもリハーサルに参加してくれたの!なんてダムラウはインタビューで嬉しそうに言ってましたので、デッカーとしても、ダムラウにしろドミンゴにしろ、それぞれの持ち味を活かした今回のこの解釈もあり、だったのかも、今回の二人の役作りも、きっと椿姫の時代社会の悪を描いたようなデッカー演出本来のこころには反さなかったのだ、とわたしは信じています。
生きたい!とダムラウ・ヴィオレッタが思うとき、それはただ単に生理的に死にたくない、というのではなくて、アルフレードとの愛に満ちた新しい人生を一人前の人間として歩きたい!ということなんだろうと思いますよ。なぜ「道を外した女」はしあわせになってはいけないのか!、そんな権利はどうして認められないのか!、わたしのような女はやはり一人さみしく犬死にするしかない(morro!)のか!、悲しみと同時に怒りも込み上げてくるヴィオレッタ。これだけ誠実な思いで幸せになりたいという自分の願いは、どうしてそんなに許されないことなのか、どうして神もそこまで無慈悲になれるのか、と、まだ全然若いこのヴィオレッタ(原作では23歳)は、神に憤りさえも覚えたりします。肉体は病に負けても、最後までどこか気持ちの上では芯の強さを感じるヴィオレッタ。競争も激しい中、ここまで人気者に上りつめたり、一人で独立した女としてやってきた人なんですから、強いちょっとキツイ印象がある女の子であってもいい、とわたしには納得いきます。
ヴィオレッタは、はかなげな薄幸美人、という解釈もそりゃあ素晴らしいです。例えば、先シーズンの本人自身が風邪で喉をやられていて悲惨だったデュッセ版、病気療養からの再起をかけてヴィオレッタが催したパーティだったのに、「友達」のフローラまで、わざわざ招待客の大半を自分のサロンに引き止めて遅刻させる、なんて意地悪したりもあったり、ひとり相撲で「だいじょうぶ」と言いながら無理して気を張ってても、風邪喉で歌唱がかなり悲惨、実際に今にも倒れそうなのに、共演者も誰も助けにならずにヴィオレッタがひとりぼっち、だったのは、公演自体は残念でしたですけれど、それはそれで椿姫らしかったのはいい点、とも言えるかもしれません。

けれど、今回のダムラウの描いた意思の強いヴィオレッタ像も、なかなか彼女の持ち味にも合ってるし、いいと思う。一幕の È strano 以降の葛藤なんかも、「あたしにはこの道でやってくしかない、だけどもしかして夢みてもいいのかな、いやそんな選択肢は馬鹿げてる、でもやっぱり・・・」という独白の部分も、この人物像だと、とても生きてきてよかったし、二幕ではそういう一幕のイケイケというか強い意思で自分自身で運命を切り開いて生きていくしかない高級娼婦の女の子の勢いから、がらっといきなり優しい甘い色合いでの「アルフレード」への呼びかけで始まるのもいい(幕の終わりの方の「アルフレード、あなたは分かっていない」のところの優しさと同じく一貫した愛情を感じさせてくれます。)
そしてジェルモン父との会話、これはこの二人がやるとちょっとなかなか聴けないような素晴らしく生きたやりとりなのですが、ここでも悲しみを表現すると同時に、ダムラウ・ヴィオレッタは怒ってます。これは元娼婦にまともな人生を歩むのを許さない社会に対する怒りなんじゃないか、とわたしは感じましたよ。それぞれの場面・場面では、演技も激しかったですけれど、表現したい内容に沿って音色やニュアンスの違いをくっきり出す工夫、ダイナミックな歌唱のドラマ表現には、いつもながらほんと感心するばかり。アルフレードを置いて出て行く前、気を張っていても、どうしても泣き崩れそうになってしまう、しかしそのかわりに愛を叫ぶ、ところなど、段取りを知っている観客としても、どうなっちゃうんだろうこの人、と思ってしまうようなはらはらする劇的な歌唱表現もよかった(ダムラウはブッフォでのうふふ、の笑いの歌唱表現もいいですけど、泣いてる歌唱表現はそれに比べると多少奇跡的ではないですが、なかなかやるな、でした。)
あぁ怒ってるといえば、最終幕の手紙朗読の場面の「È tardi!」は、ヴィオレッタのフラストが噴出してしまう場面ですけれど、それまでも上記の「やり場のない怒り」を見せてくれていたダムラウ版だと、あそこでの突発感がなくて、一貫性があったのも良かったです。
演技では、この演出だと、「替えがきく」娼婦には人間性など認めていない社会の描写の一環で、ヴィオレッタと同じドレスを着た「二代目ヴィオレッタ」と元祖ヴィオレッタが対面する場面がありますが、ここでも「わたしはただの駒に過ぎなかったんだ」というショックと虚しさの表情を見せる弱っちいヴィオレッタではなく、ダムラウ・ヴィオレッタには、はっと二代目の姿とその意味に気付いても、キリッとそれを受け入れているような強さがありました。
ということで、今回、ダムラウは椿姫もちゃんとこなせるというのを目の当たりにしたのも嬉しかったですが、相変わらず個性的な知的な解釈でしっかりやってくれたこともとても嬉しかった。ヴェルディは、人まねとかただ上手に歌えるという歌手じゃなくて、やっぱりこういう歌手に歌ってもらうとわたしは聴き応えを感じます。これから長いキャリアの中で、ダムラウの喉も、彼女の世界観や作品の解釈も変わっていくんだと思いますけれど、また時が経って、また違うダムラウのヴィオレッタ像をいつかまた聴かせてもらえるんじゃないかな、今後長い目でもお楽しみになったな、です。
そして彼のかた、最初の舞台登場時に嬉しくなってしまい、満場がつい拍手・喝采してしまう、そしてそれが許されていい数少ないマエストロ、プラシド・ドミンゴ!
わたしも出てきてくれただけで嬉しくってドキドキ、ニコニコしてしまう観客の一人です。かつてテナーで活躍して精通した作品に再びバリトンで戻ってきてくれるということ、この年(72歳)で役デビューを続けていて、しかも今回で142役目、なんてことだけでも凄いですけれど、そして前の記事でもドミンゴのパパ・ジェルモンは歌唱のドラマ力は絶品、的なことをお喋りしてましたけれど、実際はもう、なんというか、ちょっとバケモノ?のように凄いです。相変わらずの美しいテナー声が、人一倍りんりんと、ウワーン!とハウス中に鳴り響く迫力なんですから!!!

あぁこの人はほんと凄いわ。ラジオでもドラマ表現は伝わりますけれど、この響きの凄さは伝わってこないのが残念。元テナーなので、バリトン役にふさわしい低音の豊かさがなく、色々言われますけれど、そういう人たちの中でも、実際ライブで聴いたら、いやドミンゴの歌唱にはそれを凌駕する類いまれな魅力がある、と思い直す人も多いんじゃないかしら。少なくともわたしは実際のパフォーマンスがラジオの印象よりずっと凄いので、これはまたうれしいびっくり、でございました。
先シーズンの『魔法の島』でのお祭り的なドミンゴ大王登場!も楽しかったですけれど、この人はやっぱりヴェルディがいいんだわ。この高音部の美しい響き、しかも言い回しが完璧!ちょっとスタカートが入ったような独特の歌い回し、それをくっ、くっと顎を上にあげたりしながら歌うとか、なんだか長年妙になじみになっているしぐさと共にやってくれたりすると、あぁ今シーズンもまたメトで会えたんだ、しかもヴェルディで!、と涙腺もゆるみます。
先シーズン、ジェルモン親子がなぜか会社員同僚風で、冷血・鉄面皮のジェルモン父は歌唱は素晴らしかったけれど、なんだか歌唱表現も演技もジェルモン父らしくないような、言ってる内容が本気でなくイヤミにしか聞こえないような妙なちぐはぐ感がありましたけど、あの時おかしいと思った点、すべてドミンゴに今回ちゃんと解決してもらいましたから、わたしとしてはもはや言う事なし、そしてドミンゴに足りないところの重箱の隅をつつく必要なし、です。
ジェルモンはソロのアリアが上手に歌える、なんてことも大切なのですけれど、もっと肝心なのはヴィオレッタとのやりとりでの人間同士の感情の交感・変化を歌唱で描き出すこと、ここが作品全体のドラマのピークの一つだとわたしは思っていますけれど、ここまで深いエモーショナルな二人のやりとりが聴けたのは、ほんと貴重だった、歌唱演技力が抜群の二人、ダムラウとドミンゴだからここまで感動するのだろうな、です。ヴィオレッタもジェルモンの深い同情心は感じていたに違いありませんよ。一人でつっぱって生きてきた彼女にでさえ「せめて抱きしめて」と言わせるくらいの、何か人間的というか父親的な温かみのようなものがジェルモン・パパにはある筈、そんなのも、ドミンゴがやってくれると、ちゃんとしっかり聴こえてきますし、ヴィオレッタを見つめる眼にも、控えめながら彼女の尊厳を認めているような光りがありますから。
よくヴェルディは一言・一音も無駄がない、なんてわたしは言ってますけれど、それは逆に言って一言・一音が表現しているものが、その背後世界が非常に豊かだということでもあります。一音・一語も無駄になってないドミンゴ、この人はDNAにそのヴェルディ・ドラマの勘を持ってるんだろうな。色んな言葉を使ってわざわざ説明しなくとも、それが観客にピンと伝わってくるんだわ。
この間リゴレットの Maledizione! (のろい)へのこだわり、についてお喋りしてましたけれど、ヌッチは当然そうですけれど、ドミンゴだとMaledizione! と一言歌っただけで、それがドミンゴ・リゴレットにとってどういうことなのかが、本能的にパッと観客には通じてしまうところがあります。椿姫でもそれは変わらないです。
例えば (È grave) il sacrifizio の「犠牲」の一言の歌い方にも、あぁパパ・ジェルモンはちゃんと彼女が高潔な心の持ち主だということが分かってる人なんだ、でも家のためにこうするしかないんだ、こんな無理なお願いをして、彼も相反する思いを抱えて苦しいんだな、が伝わってきます。sacrifizioは、字面の意味を超えて、なんだか「お互いに分かり合えている」ということを象徴するパパ・ジェルモンとヴィオレッタの合言葉的なもの、にまでなっているようにわたしには聴こえました。
シモン・ボッカネグラでの Figlia…(娘・・・)の一言にも万感の思いが込められていて、わたしは泣いちゃいましたけれど、椿姫でもmio figlio は二度出てくるかな、これは息子にしっかり自分の立場と現実を見つめろ、の自覚を促すのもありますけれど、ドミンゴだと、同時に、息子に対する老いた父親の手放しの愛情にも溢れています。そして演技も素晴らしく歌ってることと合致してますよ。あさっての方を向いた息子に近づいて、やさしくそっと後ろ髪をなでたり、このデッカーの演出では、間違ったことは許せない、とつい息子を殴ってしまいますが、その後は、そんな乱暴をしてしまったこと、そしてこの状況がいかにもつらそう、息子がかわいくて大切でしょうがないパパでした。

そして最終幕では息せき切って駆けつけたニュアンス、しかもゾクゾクするテナー声で、「あぁヴィオレッタ!」と、ジェルモン・パパ登場(あはは、やったぁ、素敵すぎ!)。最初のその一言で、今パパはどんな心持ちだかピンとくる仕方で登場しますよ。ドミンゴ版だと本当に自分の選んだ選択肢を後悔し、苦悩している様子、こちらまで胸を締め付けられるよう、見ていて苦しいほどでした。
しかしここ、そういえばジェルモンが登場してから、ふっと、まるで安心したかのようにヴィオレッタは死と向かい合うのだわ。ここでダムラウの歌唱の色合いがまたがらっと変わったんです。ジェルモン・パパとの和解というか赦しで、これでもう思い残すことはない、だったのか・・・ 自分の恋や生への執着も、やり場のない怒りもなくなって、アルフレードが喜びそうなことを言ってあげようとかいう建前もとっぱわれて、ふっきれたというか、やっと素直にまっすぐに心の本音を語るようになった、このダムラウの変化は特筆したいです(この肖像画をあなたの将来の奥さんへ・・・の部分。)
今回の公演では、ジェルモン・パパはひとりぼっちのヴィオレッタにとって、最初から最後までたった一人の理解者だったのかも、この二人は口に出さずともお互い理解し合っているってこと感じてたのかもな、本音で語り合えていたのだものな、これには感動しました。原作にない最後の和解・救いの場面をヴェルディはわざわざ作ったそうですけれど、この公演ではヴェルディがそうしたことの意義が、斜な視点を通さずに、心から理解できる・感じられるようだったです。
オペラ鑑賞は(他の音楽作品もそうですけれど)知ってると思っていても、毎回なにかしらの発見があるのは嬉しい、そしてそういう発見をさせてくれる音楽家にはわたしはどうしても感謝してしまうのですが、ここはヴェルディ先生のそう解釈もできるようなつくりに再度脱帽、そしてドミンゴ&ダムラウのコンビが、あ、うんの呼吸で繰り広げてくれたダイナミックで味わい深いドラマにばんざい!でした。

ピルグーはオープニングの日のラジオでは全然話にならない、アルフレードもドミンゴの72歳の喉で歌ってもらった方がよかったりして、なんて思いましたけれど、その直後に病欠していたので、調子が悪かったんでしょう。しかし最終日はすっかり調子が戻っていた様子。たまに高音の音程が不安定になったりとか、「ここをそんな棒読みでやるかねぇ」あるいは「ここをそんなコントロールを失ったような表現でやるかねぇ」と思うような箇所(特に重唱部分では、息声での表現ではなく、しっかり歌ってアンサンブルを優先したほうがいいわよ)もあって、まだ改善の余地ありですけれど、なかなか通るいい声を持っているし、ニュアンスがとてもいいところもあった。こういう「坊やテナー」でもOKな役以上の役でも聴き応えのある歌手なのか、あるいはそう成長していくのか、はまだ分かりませんけれど、今後もどうぞご活躍のことを。
とにかくダムラウに感心したり、ドミンゴに涙したりしてても、もっとまともな人が振っていたらこの素晴らしい作品、もっと感動できた筈なのに、はっきり言って腹立たしいです。YNSは一言でいうと、つくりに節操というか discipline がない、「自分が自分が」な顕示欲ばかりで、これ見よがし、短絡的かつ短視眼的で浅薄な読み、みそもくそも一緒、なところが、どうしても鼻につく、納得がいきません。
初日のラジオでは、前記事にも書きましたが、とにかく走る、すべる、意味なくあおる、テンポコントロールがやたらと極端、ヴェルディをトムとジェリーの漫画の背景音楽みたいに陳腐でチープにしちゃってて、あんまりおかしいと思ったので、それまでヴォーカル・スコアしか手持ちがなかったのですが、思わずフル・スコアを取り寄せて次回のラジオ放送の時に検証してしまいましたよ。届いたのはリコルディの1914年版を復刻したドーヴァー譜だったのですけれど、まぁメトはあちこちかなりカットしているのだな、というのもよく分かったのですけれど、やはりYNSのつくりには納得いかない。ダンサンブルなところは相変わらず得意なのはいいですが、威勢よくやるところは突如としてやたら元気よくやっても、音量を抑えるところをちゃんと抑えてないんです。そしてクレッシェンドはいきなり音量が上がってる。どうもこの人は長いクレッシェンド、徐々に盛り上げていくつくり、長い弧が描けない人なんじゃないかしら、そういえばシンフォニーでもそれがやれているのを聴いた記憶がないかもなぁ、もしかすると、それだから、わたしがどうもYNSにクレヨンでべた塗りしたような塗り絵・お絵かき帳的なつまらなさを感じるのかも。
YNSのクレッシェンドが駄目なのは、ディミヌエンドや弱音が駄目だからでもあって、第一ピアノ以下の指示の部分も大抵メゾフォルテぐらいのまま、思いを無理やり抑えこんだ様子が表現されているような緊張感などは全くないですから。元気なところはそりゃあ生き生きとしていて、その部分だけを取り出して聴くと悪くはないんですけれど、音量を抑えるところはいかにもつまらなそうに単調にウンパの伴奏してて、次の元気に活躍できる機会をただ待ってるじゃないか、という印象なんだよなぁ。ほんとはそのウンパがじわじわと込み上げてくる熱い思いやだんだんと早まる鼓動を表現してくれたりしないといけないのにね。抑えが効いていないと、当然そこでテンションが溜まっていくような長い緊張感とそれが噴出すような流れ、なんて作れませんから。
前にノセダに関して「弱音部分で小っちゃく屈んでみせても、この指示には、いかにも次に爆発しそうな堪えたエネルギーが込められている」、なんて言ったことがありますけれど、YNSの弱音には表現の機微なんてなくて、ちょっとだけ音量が下がるだけ。この人は弱音記号に関しても、他のヴェルディの指示と同じく、そこになんの思いも意味深さも見出していないんだろうよ、「早い」「フォルテッシモ」部分にしか面白さを見出していないんじゃないかい? ちぇっ。
また細かいところでいうと、「人間の感情の大家」だとわたしは思うヴェルディ先生は、例えば同じメロディの繰り返しの部分にわざわざ最初はスタカート、次はスラーの指示をつけてくれてたりなんて親切なのも、うんうんそりゃ人間の感情や思考も全く同じ繰り返しがありえないように、変化していくのは本能的にしっくりくる、自分もそう演奏しようと思うのが音楽家だったら自然じゃないか、そして指揮者だったらどうしてヴェルディはそこにそういう違いをつけたかまで考えるのが当然なんじゃないか、とわたしなどは思います。まぁそんなのもヴェルディのドラマの山なり大無視でへいき、なYNS&メト・オケは、さらーっと無視、まぁーったく同じに意味ない無駄な繰り返しの如く扱ってますから、あきれたものです。
そして一番これはどうにも致命的に酷いな、と思った部分は、二幕二場のパーティのおふざけというかワルノリが終わってアルフレードが登場してからの流れ。椿姫は全編感動的な部分が多いのですけれど、アルフレードが男爵相手の賭けで無茶をやり出すあたりから、幕閉めの合唱までのドラマのピーク、ここの流れはわたしは非常に好きで、一気に合唱まで弧を描く、という流れをもってやってもらいたいもの。これがまぁとことん酷かった。
例をあげて細かくその理由を説明すると、ここの最初の賭けのところは、8分の6拍子で、
1)アルフレードその他の会話の部分のバックではオケが密やかにpppで、あやしく高まるヴィオレッタの動悸でもあるんじゃないかと思う、4分音符と16分音符のコンビのタッタッ、タリラリラリラ、
次に2)ヴィオレッタの「あぁ死んでしまいそう、神様たすけて!」の符点4分音符の緩やかな上昇&下降のメロディがきます。
そしてその1)2)が交互に繰り返されます。2)の部分は1)よりも少し音量の抑えが大きくないppの指示で、しかも自己完結的に<>がついていて、3回ほど繰り返される度に段々緊迫していくような。
1)の16分音符の部分と2)の符点4分音符の部分は、当然音符の長さのニュアンスの違いが出て、趣きの違いが、いとおかし、です。この1)と2)の部分は風情の違いがありますけれど、これは音符の長さの違いで感じるマジック、テンポ自体は変わらないのに、聴き手にはペースが変わったような印象を与える、というマジックですから、全体的には長いひと息というか一筆書きで緊張感が盛り上がっていける、のがまたいいんです。実際スコアには1)と2)のそれぞれの部分で速度を変える指示なんてありません。
それをまぁ、なんとしたことか、YNSは1)の部分を張り切って生き生きとやたら速くやるかと思えば、2)ではがらっとテンポをぐっと落として神妙にやってる。ばたばたモードやシーンが変わるようなおふざけ漫画じゃないんだから・・・ テンポを人工的に誇張しているのもおかしいし、ニュアンスもそうですが、音量も指示と逆にやっていて、なぜこんな妙な勝手な編曲をするのか、もうこれによって、ドラマの流れ、緊張感の盛り上がりもばらばらに寸断・陳腐化されますので、わたしにはグロテスク!としか思えません。
そしてここも後の部分と同じく、なんてことないように、ふーっと終わらせて完結感を持たせている。ほんとはそのテンションの余韻を引きずったまま、次のヴィオレッタとアルフレード(この演出では間にお医者さんだったか)との会話部分に進んで欲しいのに、あたかもそれ以前に何もなかったように新たに気持ちを切り替えたようなモードの場面として始めてる、まぁ突如として連続性もないという、いつもの調子。
そしてさらにまた例によって例のごとく、ffとppなんてヴェルディ先生の指示は相変わらず、まあーったく無視の「のっぺり」さんで、ただ元気で威勢がよい、です。YNSはなに考えてこんなことやってんのだか、それとも何も考えてないで場当たり的にやってんのか、わたしにはちょっと理解できません。
ちょっとしつこく言い過ぎ? でもネゼ・セガンは、天下のフィラ管の音楽監督、そして(音楽監督が実質的に不在でおかしな具合とはいえ)世界の桧舞台のメトに頻繁に招聘されるような、そして(どうも採用基準がおかしい様子であっても)誉れ高きDGとも契約を結んでいる指揮者なのですから、「まだ若いから」で許されていい段階はとっくに過ぎてますよ。おかしいと思ったところはバシバシ指摘したくなってもしょうがないでしょう。
蓼食う虫も好き好き、わたしのようにおかしいと思うのも、これが斬新でいいと思うのも両方あり、には違いないです。音楽についての感想は主観的でしかありえないですから、様々な意見が出るのが当たり前、なので、さらに言わせて貰えば。ヴェルディに関してはこの谷もある山なりの音楽のダイナミクスがきちんと描けない指揮者は、わたしは「お話にならない」と思います。YNSのこの奇妙なヴェルディ解釈は、シーズン始めのレクイエムでも感じましたけれど、この人は音楽的なヴェルディ・ドラマがちっとも分かっちゃあいない、です。
実演では部分的に良くなったというか、歌手が歌わない部分がやたら元気だったり思い入れたっぷりだったりの自己顕示欲的な部分がさすがに多少改善されているところもありましたけれど、この人の姿勢で絶対的に間違っている、と思った点が一つあります。YNSはどうやら全編リブレットを暗記したようで、わたしが目をやる時はいつでも口づさんでいて、それはそれで頑張ってるな偉いぞ、ですし、合唱部分ではそれは有効な手段だとわたしも思います。しかし前の記事で紹介したクリップで、うーんもうちょっとドミンゴの表現、あのスタッカート気味でちょっと勢いが出る部分なんかは、それに沿わせて欲しかったなぁと思ったのですが、YNSにはなぜそれが不可能なのだか、実際見ているとよく分かりました。
この人はソロリストのアリアの時でさえも自分で歌っていて、しかもそれが自分独自の「歌い」で、舞台上の歌手と頻繁に合わなくなるのだわ。これにはびっくり。最終日にもなってるのに、例えばドミンゴのプロヴァンスなんかは、かなりドミンゴの歌唱とYNSの口パクがずれている! いやぁドミンゴよりも自分の方がこのアリアの解釈が分かってるとでも思って、これが正しいんだ!と思って自分の口づさむ方を基準にしているんだったら、坊ちゃん、そいつは百万年はやいぜ、というもんです。自分で読解できないならば、せめて優秀なベテラン歌手が表現してるものに合わせてくれたら、少しはまともかもしれないのに、それをちゃんと聴く姿勢でもないとは、あぜん・・・
もともとウェストミンスターで合唱指揮を学んだそうですけれど、合唱指揮とソロイストの歌唱を同じように扱って「リード」してもらっちゃあ困ります。そしてそれならまた合唱指揮が得意であってよさそうな筈ですけれど、急にオケを走らせ過ぎちゃって合唱を置いていくとか、自分でも歌ってるのならホントにここまで急にペースをあげてコーラスが付いてけるもんなのだか、できないもんだか、分かってもよさそうなものなのに。
そしてリブレットを暗記する余裕があるくらいなら、もっと指揮者としてやるべきこと、ヴェルディ先生の譜面の指示をちゃんと読みこんで出直してよ!、と思います。
そういえば、休憩中、「でもメトだとヤニックのあのかわいいおしりが見れないからフマーン」なんて会話している人の脇を通って、うふぉと思いましたけれど、そういや、それもありか、小太りなのにいつもピッチピッチのスーツを着て、シームがびりっと破れたりしないの、だいじょうぶ?、とこちらが思うくらい指揮台で激しく踊りまくるYNSには、そういうところにも魅力を感じるファンがいるのでしょうかね。人間だれしも異性の魅力に弱いところはあって、なによ、男はピナスで考えてるんじゃない、というのに対して、女だって子宮で考えてるじゃないか、なのですけれど、もう一つ、ゲイはおケツで考える、なのか・・・
それもありですよ、クラシック業界・オペラ界存続には、清き1チケット購買の積み重ねが大切ですから、どんな理由でもどうぞどうぞ、応援を続けてもらいたいです。ただおしりのかわいさ?如何と今回の公演の指揮者としての力量は比例しませんから、その点に関してはわたしの意見は変わりませんよ、というだけです。
まぁだけどYNSは才能がないとは思っていないです。今までメトで振ったカルメンやファウストのような次から次に有名なメロディが登場するアンソロジー的な性格の作品だと、あまり上にしつこく語った弱点も浮き出てこずに、ビート感やノリのよいドライブのYNSの長所が味わえますから、悪かあない。あぁオッフェンバックあたりもいいかも。そして「解釈」がおかしい、とこちらが感じるのは、まだその人には何らかの「解釈」があるわけですので、それが一致するというか、納得できるようなものを聴かせてくれる可能性はいつでもあるわけですし。
こういうところはYNSは、わたしが「オケにも歌手にも引きずられるオペラ好きおっさん」と呼ぶメト常連の某指揮者なんかとは全くタイプが違うと思うところ。おっさんは、一見歌手に合わせてくれるようなつくりなので、内輪の人気が高いのでしょうが、あの人は歌手にもオケ奏者にもただ引きずられてるだけで機会主義的、後追い風にすぐダレダレになってくるから、おかしげで退屈なんです。「ここはこうであるべき」というような指揮者としての解釈もオケ統制力も、わたしには聴こえてきません。(だから「指揮者」じゃなくて「おっさん」と呼んでしまうのですが)。
要は歌手の個性を活かしたアンサンブルと、「自分はこう解釈したのでこう聴かせる」、の両方のコントロールのバランスがちゃんと取れている、というのが、優秀なオペラ指揮者の第一歩なのではないでしょうか (歌手や振るオケによってはバランスを取るための技術的・表現上の妥協も必要でしょう。) これがどちらか一方に偏っていると、やっぱり演奏がおかしく聴こえます。
紙上では「YNSはフレッシュな解釈で好演」なんていうのが大半でしたけれど、そりゃあ楽譜を無視して勝手にスカッとすっ飛ばす人は「楽譜に忠実」な時代、珍しいですから、「フレッシュ」というのは間違いでも嘘でもないのだけれど、ふふ、物は言いようもここまでくるとちょっとデマゴーグ的すぎです。
そうそう友人からのまた聞きですけれど、ラジオでYNSは、今回は「室内楽的アプローチ」で臨んだと言っていたそうですけれど、ヴェルディと室内楽のコンセプトって、「オマール海老のチョコレートソース添え」的じゃないの?
修行が足りないあたしにゃあさっぱり「室内楽的アプローチのヴェルディ」の意味がわからへんどす。ちょっと「室内楽的アプローチ」に関してはどなたかに説明していただかないと、訳が分かりません。
うーん、「見通しがいいつくり」という意味かなぁ、だけど音として何かYNSの洞察力を感じるような、きらっと光る点があった覚えもないです。例えば、先の二幕の賭けの部分で言うと、1)の部分でヴェルディ先生は急にチェロを符点2分音符でレガートで歌わせる箇所を設けていて、これなんかは先シーズン、ルイージはちゃんとチェロが浮き上がって聴こえるように意味深くハイライトさせてましたけれど、そんな工夫をYNSがしてたような記憶はわたしにはないです (そういえば、ルイージはしかも、わたしの理解と同じく、ここからちゃんと一気の流れで進んで、幕締めの合唱までの弧をきちんと描いてくれていたような、どうにもヴェルディの素晴らしさに堪らず、ぼろぼろ泣いてしまった記憶。)
しかし室内楽的アプローチだと言うなら、それをもっと突きつめて、指揮者なしでコンマス中心に演奏すればよかったのに、と言うのはちょっと意地悪すぎかな?
さ来シーズン、メトではカウフマン、キーンリサイド、フルラネットの豪華なドン・カルロをやるという噂がありますけれど、ゲルブ・メトの哀しいサガで、これもまたYNSが振るらしい。ドンCをネゼ・セガンがメトで振るのは初めてではないし、こうなってくると世間では「メトのような世界的なハウスが自信を持ってendorseしている指揮者」ということになるのかな。メトでの公演記録と紙面の高評価は事実として一人歩きしますから、YNSはそのうちまことしやかに「・・・さらにオペラの分野では、ヴェルディ解釈の若手第一人者・・・」なんて宣伝されるのでしょうか、それはとてもおそろしいような。
あんまり今回の指揮者に関して長くなりましたが、できればそんなことは忘れて、ダムラウとドミンゴありがとう!のことだけ、わたしは長く記憶にとどめておきたいです。

★★★☆☆










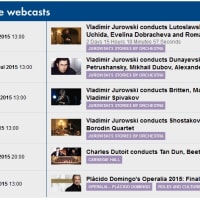

![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7e/75/86269acbcad34761132575feb03d125f.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/79/07/0c1611b6ea026eed0a0b094175423d2c.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/03/7b/050b793778320ffdd0ee65e474b84a24.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0b/1f/86664af8b7c7633697df5b104d2e7724.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/66/e2/b84c41a2579268d55f363286f23b1002.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/18/08/c4d0391455c0920b0ec523a41cd3d726.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/52/23/d9c577dfb8141fea8bd128d6023cd6cd.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/36/7b199e47cf9aaa3c0353f6d09f978e83.jpg)