
アメリカではクラシック番組が極端に少なくて、まぁ独立記念日とか大統領開催もののポップス系というかクロスオーバー的なものなどを抜かしたら、たまに放送してくれるのはPBSという昔のNHKみたいな局のみでしょうか。ここではメトのHDものやウィーン・フィルのお正月や夏のコンサート、そしてPBS系の地元局のWNETでは、NYフィルの大晦日コンサートなどを配信してくれます。
前にもサンフランシスコ響のMTT氏の Keeping Score という名作を紹介するPBSの番組をご紹介しましたが(まだ7本オンディマンド配信中)、今シーズン、WNETによる新しいクラシック音楽もののシリーズが本日から始まりました。シアトル響のジェラード・シュワルツ(2011年に退任、現在の監督はルドヴィク・モルロー)率いるオール・スター管弦楽団の新旧交えて20近くの作品を8つのテーマで辿る音楽番組。
シュワルツは特に解釈が面白いとか、話が大変興味深いということは、第一回目だけを鑑賞したわたしには感じられませんでしたが、この番組のミソはなんといってもオール・スター管弦楽団のジャム・セッション。音楽解説やドキュメンタリーの側面が充実していた啓蒙的な Keeping Score よりも、ずっと演奏中心です。一時間のうち、大して面白みのない作品説明は最小限で、中断なしの演奏のみの部分をたっぷり45分間くらいはとっていた、それにソロを取る団員たちの素の発言も聞けて、一回目の構成は、わたしは好ましかったです。
NYC近辺では毎週日曜12:30からの放送、そのうちまたPBSのサイトなどでインターネット配信もされてアメリカ国外でも視聴できるようになるのではないかと思っています。また将来、今シーズンの放送が終わってからになるでしょうが、DVDの発売予定もあるよう。こちらは番組宣伝クリップ。
追記: 放送になったエピソードは順次こちらのウェブサイトで視聴できます
オール・スター管弦楽団、なんだかスポーツみたい、あるいは往年のジャズバンドみたいな名前ですけれど、多くのオケのスター団員が夏休みを削って撮影に参加したそう。このTV企画もんのオケ、半数がNYCの音楽団体、NYフィル、メト、オルフェウス室内管、セント・ルークス管、アメリカ響、NYシティオペラ、NYシティバレエ、NYポップスからの参加。
その他シカゴ響やクリーヴランド管やボストン響(この3つからはちょっと少なくて寂しいですけれど)、フィラ管などの長年アメリカを代表するビッグなオケを始め、ピッツバーグ響、サンフランシスコ響など20以上のアメリカ全土のオケからの団員もこの企画のために集まってきたそうです。
いや不公平なので、もう少しあげましょう、ニュージャージー響、ヒューストン響、ミネソタ管、シアトル響、LAオペラ管、ナッシュビル響、オレゴン響、ダラス響、フロリダ管、ジャクソンヴィル響、ユタ響、シンシナティ響、ワシントン・ナショナル響などなど。
(それにしても今回4人参加しているミネソタ管の行く末はどうなってしまうんでしょう、団員も地元ファンもかわいそうですが、長期に渡って身動きが取れないヴァンスカが大変気の毒です。)
寄せ集めとはいえ、モーストリー・モーツァルトやアスペンなどの音楽祭などで定期的に顔を合わせているメンツも多いようだし、以前同じオケにいたとか、ジュリアードやカーティスの学友だったとか、東海岸だと、大人数編成の作品で他のオケ団員が補填メンバーとして入るなんてこともあったりするし、相性は悪くないんじゃないかと。

レス・ロージス(ジャクソンヴィル響)、ジェフリー・ケイナー(フィラ管); ジョン・フェリロ(ボストン響)、ランドール・エリス(MM祝祭管)のセクション内でのボンディング風景
それにしてもカメラがフィラ管のジェフリー・ケイナー(フルート主席)を映して横に滑ると、ボストン響のジョン・フェリロ(オーボエ主席)とか、なんか面白い図です。
コンマスはフィラ管のディヴィッド・キムさん。そしてなんだか大胆な演奏をするのがわたしは好きなので何度かこのブログでも名前を出したキンバリー・フィッシャーも第二バイオリンの共主席だったり、上記のケイナーやデイヴィッド・ビルガー(トランペット主席)とか、飛行機の中で室内楽ものを聴かせてくれたうちの一人、ダニエル・ハン(クリップの一番手前)など、フィラ管からは6人参加してます。
クラシックはあんまり見ないけれど、メトのHD上映、ビデオやDVDは鑑賞してる、という方でも、あれ、この人知ってる、という団員もいるかも。95人のオール・スター管メンバーのうち、一番多いのはNYフィルの18人ですが、メトからはチェロ主席のジェリー・グロスマンなど、現団員だけでも16人参加。
メト・オケからビッグ5などに巣立っていく音楽家も少なからずいて、オーボエ主席のフェリロなんかは、レヴァイン、バルツァ、カレーラスのカルメンのソロなど、若いころの活躍ぶりをご覧になっているのでは。
またメト初の女性コンマスだったエルミーラ・ダルヴァローヴァも第一ヴァイオリンに入ってます。
(ちなみに女性のコンマスに関して、女性形のコンサート・ミストレスとかコンミスとかの呼び方、あれは本人が使っていない限り、わたしは個人的には使うのを避けています。オケの方も本人にどっちで呼ばれたいか一応確認する、なんていう話を確か前に聞いたような覚えも。日本やその他の国の事情は分かりませんが、少なくとも英語圏では、こんにちでは一般的にマスター/ ミストレスとわざわざ性によって言い換えているのを見たり聞いたりしないような気がします。)

左から、ダニエル・ハン(フィラ管)、エマニュエル・ボワスヴェール(ダラス響副コンマス、前のデトロイトではアメリカ史上初の女性コンマス)、
ダルヴァローヴァ(NY室内音楽祭監督、元メト・コンマス)
あと元NYフィル・元LAフィル・元シアトル響のホルン主席のジョン・セルミナーロも顔なじみだったりしますか?

しっかしほんと、キンバリー・フィシャー(フィラ管)とマーク・ギンズバーグ(NYフィル)が隣同士の図、なんてのも、少なくともわたしにとっては非常に面白い・・・

オール・スター管のフル・メンバー表はこちら。
オケの演奏は、2012年8月のとある4日間、NYCミッドタウンのマンハッタン・センターで観客なしで録画したそう。前にフィリーのメトロポリタン・オペラハウスのことを喋ってましたが、ここもあそこと同じくオスカー・ハマースタイン1世がマンハッタン・オペラ・ハウスとして設立。マンハッタン・オペラがあんまり人気が出てしまったのにメトが困って、10年間オペラ上演をしないという約束でハマースタインに120万ドルを払ったとか。今の換算で言うと1億2千万円くらい?、20世紀初頭のあの当時だったら凄い金額だったのでは。マンハッタン・センターは今ではクラシック・オペラもの以外のイヴェントや録音スタジオとして使われているようです。
リハーサル期間の短さは、シュワルツの書き込みした楽譜をそれぞれ事前に予習することで補ったよう。各オケでしょっちゅうやってるかもしれない作品の数々だったりするかもしれませんが、4日間で20近くの作品の演奏を録音、なんて、こんな不可能なようなことが可能になったのも、今回集まった音楽家たちの実力の証明だったりするかも。
今回8つのエピソード、これはシーズン1、ということなのでまだまだ続けてくれる予定なのでしょう。この番組の特徴は、テーマを決めて歴史的名曲を辿るだけじゃなくて、テーマに沿った現代音楽ピースも紹介して、過去と現在をつなげてバランス感をとろうとしているところ。ちょっと内容を紹介します。
エピソード1:劇場の音楽
火の鳥組曲、ダフネスとクロエ、ブライト・シェンのブラック・スワン前奏曲
ペテルスブルグ、パリ、そしてNYCを席捲したディアギレフ&バレエ・リュスの影響というくくりでしょう。
シェンは、ディアギレフ一派のバランシンが創立したNYシティ・バレエのアーティスト・イン・レジデンスだったそうです。このブラックスワン前奏曲はオリジナル作品でなく、ブラームスのピアノ曲「6つの小品」の間奏曲(Op.118/1, 2)をオケ用に編曲したもの。
エピソード2:傑作とは何か?
ベートーヴェン5番、フィリップ・グラスの Harmonium Mountain (ハルモニウム山?)
短いリズムやメロディ(モチーフ)が壮大な交響的生命体に進化したのが5番、なんてことが書いてあります。グラスの作品はこれまた同名の映画があったのですね、わたしは見逃してます。
エピソード3:新世界とその音楽
ドヴォルジャーク9番、エレン・ターフィ・ツウィリッヒ作曲の Avanti!
ふふ、アメリカですからこれは欠かせないかと。女性初のピューリッツァー音楽賞受賞者のツウィリッヒの作品、アヴァンティ!は、典型的なアメリカっぽい「前に突き進んでいく」スピリットの現代的解釈だ、ということです。
エピソード4:政治と芸術
ショスタコーヴィッチ 5番
エピソード5:音楽における人間(恋愛)関係
大学祝典序曲、シューマン 3番「ライン」
ブラームスやシューマンとそのミューズ的なクララ、ということなんでしょうけれど、お手柔らかに!
エピソード6:生きた芸術形態
リチャード・ダニエルプールのピアノ協奏曲4番から「英雄の旅 A Hero’s Journey」、サミュエル・ジョーンズのチェロ協奏曲、ジョセフ・シュワントナーの「詩人の時 The Poet's Hour」
前二回は現代音楽がリストされてませんでしたが、“ソリスト達の役割”にフォーカスしたこの回は、若手ソリストやアメリカの作曲家のインタビューも盛りだくさんのよう。
エピソード7:音楽の感情的衝撃
チャイコフスキー 4番、デイヴィッド・ストック Blast!
チャイコフスキの私生活(破綻した結婚、4番を捧げたフォン・メック夫人との文通等)を辿りつつ、ということらしいです。運命を象徴しているかのような管のファンファーレは、ストックのBlast!(なんというか「爆!」と訳す?)に通じるところもあるそうです。
エピソード8:マーラー、愛、悲しみ、超越
マーラーのリュッケルト歌曲集、2番から葬礼、オーガスタ・リード・トーマス作曲の Of Paradise and Light、そしてトーマスの旦那のバーナード・ランズ作曲の Adieu
そういえばLAからの参加は薄いですが、なかなか全国区で放送されるクラシック番組が少ない中、アメリカ全土のおらが村のオケのメンバーが出て、地元ファンも嬉しいでしょうし、実際に教わった・教わっている生徒さんたちも多いでしょうし、見るのが楽しみな人も結構いるかも。
また番組を見て、地元のオケ、今まで聴きに言ってなかったけれど、なかなかいい演奏・面白い話をする団員もいるのだな、今度生で聴いてみるか、という効果もあるかもしれないし、宜しいんじゃございませんか? まぁ通には物足りないのかもしれませんけれど、アメリカのオケが今まで以上に元気になるかもしれない今回のシュワルツ氏の企画、わたしは応援してます。
こちらは来週のベートーヴェン&フィリップ・グラスの回のちらみせクリップ










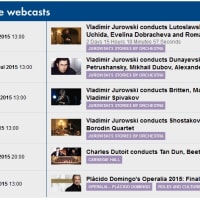

![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7e/75/86269acbcad34761132575feb03d125f.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/79/07/0c1611b6ea026eed0a0b094175423d2c.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/03/7b/050b793778320ffdd0ee65e474b84a24.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0b/1f/86664af8b7c7633697df5b104d2e7724.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/66/e2/b84c41a2579268d55f363286f23b1002.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/18/08/c4d0391455c0920b0ec523a41cd3d726.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/52/23/d9c577dfb8141fea8bd128d6023cd6cd.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/36/7b199e47cf9aaa3c0353f6d09f978e83.jpg)