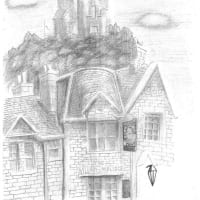さて次は共産主義と社会主義の違いを説明します。 これは経済学、政治学もしくは社会学を勉強された方々以外には具体的な違いがうまく理解できないかもしくは表現し難い方々が多いようです。
ちなみに社会主義と共産主義の違いですが、まあどちらにしても権威形と自由形の歩合にもよりますが...;
共産主義は真に平等の社会という目的を掲げ個人の所有をなくし一貫して全ての所得の共有化および金銭による経済取引の廃止を促す集産主義の端に位置する経済的極左思想です。
マルクス主義が一番有名ですね。 もとのマルクス主義の中では資本主義社会の中で社会主義への革命が起きその後社会主義社会の中で共産主義革命が起きた後に迎える社会で無政府社会革命が起きる前の課程社会であるという理念です。
現代社会でよくマルクス主義について誤解されることはマルクス・レーニン主義とソビエトおよび中国共産党が元来のマルクス主義と完全に同じものではないということが解らない人が多いということです。 マルクス主義が労働者階級の教育水準の向上および生産階級からの支配に対する反乱による革命遂行を原論としているがレーニンは超インフレーションによる経済構造の崩壊および軍事力による旧専制君主儀体制の打破による革命遂行をおこなったことが事実です。 そしてレーニンはマルクス主義を掲げていたが実際に彼の思想とは違っていたため平等社会はまったく達成されなかったのです。 これらの事実はもとのマルクス主義に立ち返り現代社会の経済構造においての新思想という構想に基づいた『新マルクス主義』によっても批判されています
他にも無政府理論共産主義や原始共産主義や真キリスト教的共産主義などがあります。 共産主義を考案した人はマルクスやレーニンだけではないのです。 古代ギリシアの有名な哲学者プラトンも最も著名な共産主義者の一人でシチリア島に実験的に共産主義社会を築いたりしました。 もともとキリスト教自体も新約聖書の文献からも伺えるよう金銭交換と個人所得を廃止し全ての所得の共有を促しています。 そのもとのキリスト教の考え方を近代の世で実践しようと考察したのがトルストイという穏健派無政府共産主義者です。 また工業文明に染まった国での共産主義理念の発達にしごく懐疑的で政府および経済機構の破壊を行うことによる闘争と団結による革命を支持したロシア貴族の血を引くミハイル・バクーニンという過激派無政府共産主義者もいます。 このマルクス、トルストイおよびバクーニンについては【無政府理論とマルクス主義:ヘーゲル左派】でまたくわしく述べます。 無論、新マルクス主義者達のなかにも元来のマルクス主義で触れられていた共産主義を主張するものもいます。
そして東西冷戦後期に活躍した暗鬱なスターリン主義に染まったソ連的共産主義とは異色を放つオリーブ色をモチーフとした明るい『ラテン系共産主義』を誇示したキューバ革命のフィデル・カストロも忘れてはいけません。 キューバはもともと米国と地理的に近い位置にあり以前から米国からの干渉が強い状態にありましたが、国民はスペイン語を話し米国との貧富差は歴然でして反米的アイデンティティは強烈でした。 無論それらの事実には世界大戦以前からの植民地政策による歴史的拝啓があり、また東西冷戦のさなか米国とソ連の陣取り合戦の渦に巻き込まれていました。 その拝啓のさなかキューバの経済的独立を掲げたカストロ率いる革命ゲリラ勢力によりキューバ革命が遂行されました。 彼は大統領に就任してからも共産主義理念にもとづき統治者でありながら国の平民と同じく質素な食事をとり生活を送っていることから現代社会においても共産主義者たちから英雄視されています。 しかし、彼の政治的思想に感化されているいくつかの南米諸国、たとえばベネズエラ、は市場経済を完全に否定した共産主義のもと豊富な油田を所持し穀物自給率を上げるだけの可能性がありながら経済発展が停滞気味で共産主義を唱えながらも今だ貧富さは必然的に肥大しています。
以上述べた共産主義者達および現代に生きる元来のマルクス主義的共産主義者達およびアナコ・シンディカリスト(無政府革命主義者)達は金銭による生産物の流通および個人の所得独占を廃止し聖書やプラトンのイデア理論に書かれた政治経済組織のなく個人の力関係が均一である『ユートピア(楽園)社会』の建設を夢見ていました。 虐げられてきた多数派の被支配階級に位置する個人を社会的苦しみから開放することが彼らの理想でした。 確かに彼らの生きていた時代は封建時代から残る貴族階級の富の独占のなごみがあり、また市場経済における賃金の循環および地方においての競争状態も発展途上でした。その現実の中で生まれた社会階層が個人の人生の可能性を大きく決定していました。
しかし、彼らはは現代の世に仲においてのより循環的な経済基盤の発達による富の再分割および経済力以外の個人の社会的地位を左右する力の存在の理解にかけているという批判があります。 元来のマルクス主義に基づいた大半の新マルクス主義者達はスターリン主義や早熟な共産主義革命の遂行よりも経済構造の改革を重視した緩やかな課程を支持しています。 しかも共産主義理念を支えている哲学的拝啓は『人間性強説』、つまりは人間とは元来強い精神生命体であり精神的に計画性があり、宗教や超自然的な権威に依存せずとも独立し秩序を保てるという理念、に基づいています。 これは近代ヨーロッパで起こった啓蒙主義思想で培われた理念で封建時代的旧体制からの打破を目指すものでした。 そしてそれはベルリン学生運動で活発化しパリコミューンで開花した『ヘーゲル左派』が発展させていきました。 そして当時『ヘーゲル左派』の一員をなしていたカール・マルクスはその『ヘーゲル左派』よりも更に『人間性強説』を誇示していきました。
* 人間の性にての他の理念は、キリスト教が唱える罪の意識を誇示する『人間性悪説』、イスラム教徒の聖典による教化を唱える『人間性弱説』、多神教を信じ神と人間を同等なものと考え人間の間での契約よりも信頼と和を重んじる日本社会に根付く『人間性善説』などがあります。
この文章をお読みになって筆者が『反共産主義者』であることをお見受けされるとおもいます。 一つ重要なことは、ヒトラー率いるナチス党よりも多数のかけがえのない個人達の命を横暴に奪っていった『ソ連』およびその他『スターリン主義者』に対しては非常に強い憎悪を抱いていますが、筆者は決して全ての『共産主義』を憎むというステレオタイプ的な行為は行いたくはありません。 現にキリスト経典やプラトンのイデアも別の形の共産主義色をはなっておりますし、元来のマルクス主義も被支配者階級の『誤った良識(False Consciousness)』からの開放による革命を強調しています。 ただ筆者は凝固な『人間性強説』を唱える『共産主義』および『(新旧)マルクス主義』が明示する以上に人間とは強く計画性のある精神生命体なのであろうかという疑問があります。 経済と社会がともに『完全に計画的』に動く・・・果たして人間的かつ動物的な欲望や懐疑心、非完全さはどのようにして解消されるという疑問が彷彿されます。 人間をここまで『強く』するそのような社会がいずれくるか否かは予想できませんが、このサイトの『自由主義』はそもそも『性強』でなければ『性悪』、『性弱』でも『性善』とも異をなす人間の性に対しての理念に基づいています。
それでは次は定義にて『多岐にわたる社会主義』について説明です。 日本では『冷戦時代の共産主義国』が『社会主義』となのっていたことにより『社会主義の定義』について誤解が生じているようですので次の章は「その『社会主義』とは何をさすのか?」という課題に迫りたいとおもいます。
次に:【多様な社会主義】
戻る:【直接民主主義と間接民主主義および官僚主義】
ちなみに社会主義と共産主義の違いですが、まあどちらにしても権威形と自由形の歩合にもよりますが...;
共産主義は真に平等の社会という目的を掲げ個人の所有をなくし一貫して全ての所得の共有化および金銭による経済取引の廃止を促す集産主義の端に位置する経済的極左思想です。
マルクス主義が一番有名ですね。 もとのマルクス主義の中では資本主義社会の中で社会主義への革命が起きその後社会主義社会の中で共産主義革命が起きた後に迎える社会で無政府社会革命が起きる前の課程社会であるという理念です。
現代社会でよくマルクス主義について誤解されることはマルクス・レーニン主義とソビエトおよび中国共産党が元来のマルクス主義と完全に同じものではないということが解らない人が多いということです。 マルクス主義が労働者階級の教育水準の向上および生産階級からの支配に対する反乱による革命遂行を原論としているがレーニンは超インフレーションによる経済構造の崩壊および軍事力による旧専制君主儀体制の打破による革命遂行をおこなったことが事実です。 そしてレーニンはマルクス主義を掲げていたが実際に彼の思想とは違っていたため平等社会はまったく達成されなかったのです。 これらの事実はもとのマルクス主義に立ち返り現代社会の経済構造においての新思想という構想に基づいた『新マルクス主義』によっても批判されています
他にも無政府理論共産主義や原始共産主義や真キリスト教的共産主義などがあります。 共産主義を考案した人はマルクスやレーニンだけではないのです。 古代ギリシアの有名な哲学者プラトンも最も著名な共産主義者の一人でシチリア島に実験的に共産主義社会を築いたりしました。 もともとキリスト教自体も新約聖書の文献からも伺えるよう金銭交換と個人所得を廃止し全ての所得の共有を促しています。 そのもとのキリスト教の考え方を近代の世で実践しようと考察したのがトルストイという穏健派無政府共産主義者です。 また工業文明に染まった国での共産主義理念の発達にしごく懐疑的で政府および経済機構の破壊を行うことによる闘争と団結による革命を支持したロシア貴族の血を引くミハイル・バクーニンという過激派無政府共産主義者もいます。 このマルクス、トルストイおよびバクーニンについては【無政府理論とマルクス主義:ヘーゲル左派】でまたくわしく述べます。 無論、新マルクス主義者達のなかにも元来のマルクス主義で触れられていた共産主義を主張するものもいます。
そして東西冷戦後期に活躍した暗鬱なスターリン主義に染まったソ連的共産主義とは異色を放つオリーブ色をモチーフとした明るい『ラテン系共産主義』を誇示したキューバ革命のフィデル・カストロも忘れてはいけません。 キューバはもともと米国と地理的に近い位置にあり以前から米国からの干渉が強い状態にありましたが、国民はスペイン語を話し米国との貧富差は歴然でして反米的アイデンティティは強烈でした。 無論それらの事実には世界大戦以前からの植民地政策による歴史的拝啓があり、また東西冷戦のさなか米国とソ連の陣取り合戦の渦に巻き込まれていました。 その拝啓のさなかキューバの経済的独立を掲げたカストロ率いる革命ゲリラ勢力によりキューバ革命が遂行されました。 彼は大統領に就任してからも共産主義理念にもとづき統治者でありながら国の平民と同じく質素な食事をとり生活を送っていることから現代社会においても共産主義者たちから英雄視されています。 しかし、彼の政治的思想に感化されているいくつかの南米諸国、たとえばベネズエラ、は市場経済を完全に否定した共産主義のもと豊富な油田を所持し穀物自給率を上げるだけの可能性がありながら経済発展が停滞気味で共産主義を唱えながらも今だ貧富さは必然的に肥大しています。
以上述べた共産主義者達および現代に生きる元来のマルクス主義的共産主義者達およびアナコ・シンディカリスト(無政府革命主義者)達は金銭による生産物の流通および個人の所得独占を廃止し聖書やプラトンのイデア理論に書かれた政治経済組織のなく個人の力関係が均一である『ユートピア(楽園)社会』の建設を夢見ていました。 虐げられてきた多数派の被支配階級に位置する個人を社会的苦しみから開放することが彼らの理想でした。 確かに彼らの生きていた時代は封建時代から残る貴族階級の富の独占のなごみがあり、また市場経済における賃金の循環および地方においての競争状態も発展途上でした。その現実の中で生まれた社会階層が個人の人生の可能性を大きく決定していました。
しかし、彼らはは現代の世に仲においてのより循環的な経済基盤の発達による富の再分割および経済力以外の個人の社会的地位を左右する力の存在の理解にかけているという批判があります。 元来のマルクス主義に基づいた大半の新マルクス主義者達はスターリン主義や早熟な共産主義革命の遂行よりも経済構造の改革を重視した緩やかな課程を支持しています。 しかも共産主義理念を支えている哲学的拝啓は『人間性強説』、つまりは人間とは元来強い精神生命体であり精神的に計画性があり、宗教や超自然的な権威に依存せずとも独立し秩序を保てるという理念、に基づいています。 これは近代ヨーロッパで起こった啓蒙主義思想で培われた理念で封建時代的旧体制からの打破を目指すものでした。 そしてそれはベルリン学生運動で活発化しパリコミューンで開花した『ヘーゲル左派』が発展させていきました。 そして当時『ヘーゲル左派』の一員をなしていたカール・マルクスはその『ヘーゲル左派』よりも更に『人間性強説』を誇示していきました。
* 人間の性にての他の理念は、キリスト教が唱える罪の意識を誇示する『人間性悪説』、イスラム教徒の聖典による教化を唱える『人間性弱説』、多神教を信じ神と人間を同等なものと考え人間の間での契約よりも信頼と和を重んじる日本社会に根付く『人間性善説』などがあります。
この文章をお読みになって筆者が『反共産主義者』であることをお見受けされるとおもいます。 一つ重要なことは、ヒトラー率いるナチス党よりも多数のかけがえのない個人達の命を横暴に奪っていった『ソ連』およびその他『スターリン主義者』に対しては非常に強い憎悪を抱いていますが、筆者は決して全ての『共産主義』を憎むというステレオタイプ的な行為は行いたくはありません。 現にキリスト経典やプラトンのイデアも別の形の共産主義色をはなっておりますし、元来のマルクス主義も被支配者階級の『誤った良識(False Consciousness)』からの開放による革命を強調しています。 ただ筆者は凝固な『人間性強説』を唱える『共産主義』および『(新旧)マルクス主義』が明示する以上に人間とは強く計画性のある精神生命体なのであろうかという疑問があります。 経済と社会がともに『完全に計画的』に動く・・・果たして人間的かつ動物的な欲望や懐疑心、非完全さはどのようにして解消されるという疑問が彷彿されます。 人間をここまで『強く』するそのような社会がいずれくるか否かは予想できませんが、このサイトの『自由主義』はそもそも『性強』でなければ『性悪』、『性弱』でも『性善』とも異をなす人間の性に対しての理念に基づいています。
それでは次は定義にて『多岐にわたる社会主義』について説明です。 日本では『冷戦時代の共産主義国』が『社会主義』となのっていたことにより『社会主義の定義』について誤解が生じているようですので次の章は「その『社会主義』とは何をさすのか?」という課題に迫りたいとおもいます。
次に:【多様な社会主義】
戻る:【直接民主主義と間接民主主義および官僚主義】