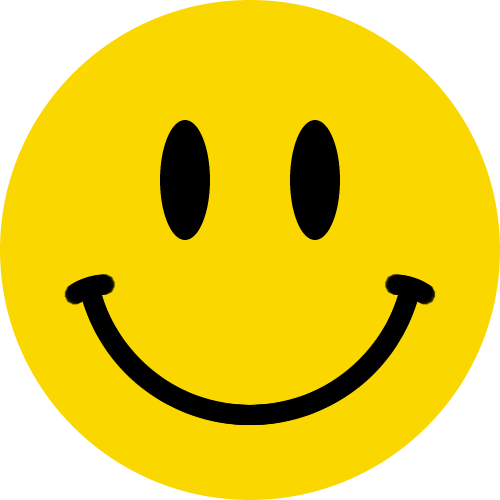所在地:埼玉県さいたま市岩槻区本町4-8-9
遷喬館は、岩槻藩に仕えていた儒者・児玉南柯(こだまなんか)が岩槻城外郭内裏小路の
一角に開いた家塾で、後に藩校になりました。最盛期には梅林を伴った広大な敷地の中に、
武芸稽古所、菅原道真を祀る菅神廟、児玉南柯の自宅、築山・池泉、観望台などが、
設けられていました。藩校は全国にも多くありましたが、埼玉県内において保存されている
藩校はこの遷喬館が唯一のものです。埼玉県指定史跡に選ばれています。
遷喬館の名は詩経の「出自幽谷 遷干喬木」に由来します。意味としては、
学問を欲し友を求めることを鳥が明るい場所を求めて暗い谷から高い木に
飛び遷(移)ることにたとえ、ここで学ぶ者に高い志を持つことを促したのです。
児玉南柯は、甲府の豊島家に生まれ、11歳で岩槻藩士・児玉親繁の養子となりました。
「南柯」は儒者としての名で、本名は「(そう)」といいます。16歳のとき、藩主・大岡
忠義の御中小姓となり、向井一郎太のもとで儒学を学びつつ、禅の修業なども積みました。
18歳で神田一ツ橋邸に勤務し、若殿・忠要の素読相手となり、以後郡奉行、御側用人、
御勝手向取締方などを歴任しました。房州領内(千葉県)に清国船が漂着したときは
その処理に活躍するなど藩務への貢献は大きいものでした。
しかし、43歳のとき、前任者の不正の責任を取る為職を辞し、以後研究生活を続ける
かたわら、藩主の侍読も勤めました。そして、寛政11年(1799年)、家塾遷喬館を開設し、
岩槻藩の子弟の教育に情熱を注ぎました。児玉南柯の関連資料は「岩槻郷土資料館」に
一部展示されています。墓石は、浄安寺に眠っています。
江戸末期には「岩槻に過ぎたるものが二つある 児玉南柯と時の鐘」と謳われた。
遷喬館は、岩槻藩に仕えていた儒者・児玉南柯(こだまなんか)が岩槻城外郭内裏小路の
一角に開いた家塾で、後に藩校になりました。最盛期には梅林を伴った広大な敷地の中に、
武芸稽古所、菅原道真を祀る菅神廟、児玉南柯の自宅、築山・池泉、観望台などが、
設けられていました。藩校は全国にも多くありましたが、埼玉県内において保存されている
藩校はこの遷喬館が唯一のものです。埼玉県指定史跡に選ばれています。
遷喬館の名は詩経の「出自幽谷 遷干喬木」に由来します。意味としては、
学問を欲し友を求めることを鳥が明るい場所を求めて暗い谷から高い木に
飛び遷(移)ることにたとえ、ここで学ぶ者に高い志を持つことを促したのです。
児玉南柯は、甲府の豊島家に生まれ、11歳で岩槻藩士・児玉親繁の養子となりました。
「南柯」は儒者としての名で、本名は「(そう)」といいます。16歳のとき、藩主・大岡
忠義の御中小姓となり、向井一郎太のもとで儒学を学びつつ、禅の修業なども積みました。
18歳で神田一ツ橋邸に勤務し、若殿・忠要の素読相手となり、以後郡奉行、御側用人、
御勝手向取締方などを歴任しました。房州領内(千葉県)に清国船が漂着したときは
その処理に活躍するなど藩務への貢献は大きいものでした。
しかし、43歳のとき、前任者の不正の責任を取る為職を辞し、以後研究生活を続ける
かたわら、藩主の侍読も勤めました。そして、寛政11年(1799年)、家塾遷喬館を開設し、
岩槻藩の子弟の教育に情熱を注ぎました。児玉南柯の関連資料は「岩槻郷土資料館」に
一部展示されています。墓石は、浄安寺に眠っています。
江戸末期には「岩槻に過ぎたるものが二つある 児玉南柯と時の鐘」と謳われた。