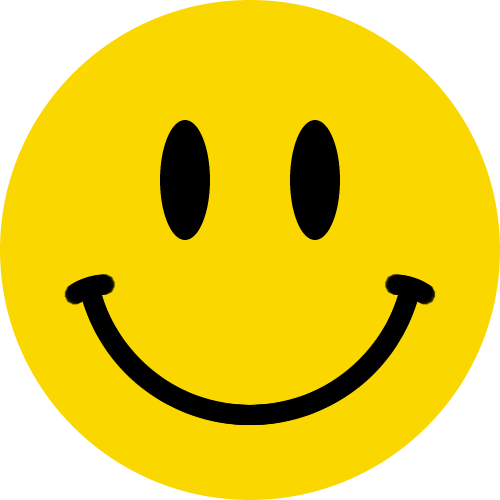所在地:栃木県栃木市
栃木県栃木市は、蔵の街としても知られ、巴波川(うずまがわ)沿いに蔵や商家が多く残る。
蔵の街遊歩道も整備され、記念館などの観光施設や、かつての県庁所在地であった跡地など、
かずかずの歴史を探索できる一大観光名所である。
1617年、徳川家康の霊柩が日光山へ改葬され、勅使が日光東照宮へ毎年参拝するようになり、
その勅使を例幣使ということから、通る道は例幣使街道と呼ばれました。栃木はこの街道の
宿場町となり、そして巴波川の船運で江戸と交易して、商都として発展しました。
その豪商達が白壁土蔵を巴波川両岸沿いに沿って建てていきました。
栃木市の蔵の街並みは、かつての栄華を極めた歴史が築いてきたものなのです。


文豪・山本有三氏は明治二十年に栃木市の呉服商の長男として生まれ、
芝居好きの母と芝居を見ることが劇作家のきっかけとなり、のちに小説家となる。
東京都三鷹市の山本有三記念館に初めて行った時に、有名な「路傍の石(ろぼうのいし)」の
一節「たった一人しかない自分を、たった一度しかない一生を、ほんとうに生かさなかったら
人間生まれてきたかいが ないじゃないか」が心に残った。そして、栃木市内では山本有三
ふるさと記念館があり、文学碑が至る所に建っているので、改めて有三氏の偉大さを感じた。

「下野新聞」の前身である「栃木新聞」発祥の地。この建物は元肥料豪商で知られた毛塚惣八が
建てた蔵屋敷を修復したものである。1999年3月の創刊115周年を記念して当見世蔵を支局とした。

例弊使街道


国登録有形文化財「栃木病院」。大正二年築。

栃木県指定文化財「県庁掘 附 漕渠」
明治4年(1871年)廃藩置県の後、下野国は栃木県と宇都宮県に分かれ、ついで明治6年栃木県は
宇都宮県と合併し、この地に栃木県庁が置かれ、栃木町は政治・経済・文化の中心として栄えました。
来たる明治17年、県令三島通庸は強引(←説明文に書かれていた文字。栃木市は宇都宮市に県庁が
移ったことをよほど根に持っている模様)に県庁を宇都宮に移しましたが、県名は栃木県として残りました。
栃木県庁には、幅約6mの堀を東西約246m、南北約315mの矩形にめぐらしました。巴波河との間には
運河が作られ、式内には舟の荷揚げ場が設けられました。このような例は、全国にはありません。

巴波川の鯉のぼり

日本全体で蔵の街並みや古い建物が恥ずかしいという風潮の時期もあったと
いわれるが、この平成の世にこれだけの街並みが残っていることに感謝である。
蔵の街のんびり散策マップを片手に栃木の街並みを歩いてみましたが、
2008年現在で重要伝統的建造物群保存地区に選出されていないので
はじめはどうかなと思っていましたが、街の努力も見られるし、古い商家や
蔵の街並みが散在して多く残っていたので来て良かったです。
関東にもまだこんな場所が残っていたのがまず驚きました。
個人的には、川越と佐原ほど突出した部分はありませんが、
両街の持ついいところをあわせ持った街並みだと感じました。
栃木県栃木市は、蔵の街としても知られ、巴波川(うずまがわ)沿いに蔵や商家が多く残る。
蔵の街遊歩道も整備され、記念館などの観光施設や、かつての県庁所在地であった跡地など、
かずかずの歴史を探索できる一大観光名所である。
1617年、徳川家康の霊柩が日光山へ改葬され、勅使が日光東照宮へ毎年参拝するようになり、
その勅使を例幣使ということから、通る道は例幣使街道と呼ばれました。栃木はこの街道の
宿場町となり、そして巴波川の船運で江戸と交易して、商都として発展しました。
その豪商達が白壁土蔵を巴波川両岸沿いに沿って建てていきました。
栃木市の蔵の街並みは、かつての栄華を極めた歴史が築いてきたものなのです。


文豪・山本有三氏は明治二十年に栃木市の呉服商の長男として生まれ、
芝居好きの母と芝居を見ることが劇作家のきっかけとなり、のちに小説家となる。
東京都三鷹市の山本有三記念館に初めて行った時に、有名な「路傍の石(ろぼうのいし)」の
一節「たった一人しかない自分を、たった一度しかない一生を、ほんとうに生かさなかったら
人間生まれてきたかいが ないじゃないか」が心に残った。そして、栃木市内では山本有三
ふるさと記念館があり、文学碑が至る所に建っているので、改めて有三氏の偉大さを感じた。

「下野新聞」の前身である「栃木新聞」発祥の地。この建物は元肥料豪商で知られた毛塚惣八が
建てた蔵屋敷を修復したものである。1999年3月の創刊115周年を記念して当見世蔵を支局とした。

例弊使街道


国登録有形文化財「栃木病院」。大正二年築。

栃木県指定文化財「県庁掘 附 漕渠」
明治4年(1871年)廃藩置県の後、下野国は栃木県と宇都宮県に分かれ、ついで明治6年栃木県は
宇都宮県と合併し、この地に栃木県庁が置かれ、栃木町は政治・経済・文化の中心として栄えました。
来たる明治17年、県令三島通庸は強引(←説明文に書かれていた文字。栃木市は宇都宮市に県庁が
移ったことをよほど根に持っている模様)に県庁を宇都宮に移しましたが、県名は栃木県として残りました。
栃木県庁には、幅約6mの堀を東西約246m、南北約315mの矩形にめぐらしました。巴波河との間には
運河が作られ、式内には舟の荷揚げ場が設けられました。このような例は、全国にはありません。

巴波川の鯉のぼり

日本全体で蔵の街並みや古い建物が恥ずかしいという風潮の時期もあったと
いわれるが、この平成の世にこれだけの街並みが残っていることに感謝である。
蔵の街のんびり散策マップを片手に栃木の街並みを歩いてみましたが、
2008年現在で重要伝統的建造物群保存地区に選出されていないので
はじめはどうかなと思っていましたが、街の努力も見られるし、古い商家や
蔵の街並みが散在して多く残っていたので来て良かったです。
関東にもまだこんな場所が残っていたのがまず驚きました。
個人的には、川越と佐原ほど突出した部分はありませんが、
両街の持ついいところをあわせ持った街並みだと感じました。