甲南大の合宿所についた。息を切らしながら、関係者に松本譲先生(この時点で先生・・・でした)についてお尋ねすると、すぐに先生が来られ、「ああ、やっぱり来たか」という感じの笑みを浮かべられた。我々も、何から言ったらいいのか分からなかったが、簡単な自己紹介の後、
私、「あのー、先ほどは、松本先生と分からずに、大変失礼しました。それで、先生に先ほどの演奏について御意見をいただきたいと思いまして・・・。」
いやー、自分から仕掛けてしまったのである。
先生は、「はあ、そうですか。まあ、こっちへ来てください。」
とおっしゃい、私とコンマスを、会議室のような場所へ導かれた。そして、先ほどの「ヴェニスの1日」について、事細かく指示を出して頂いた。18年前のことなので、指示された内容はあまり覚えていないが、これまで受けたことのない、的確な指示であった記憶はある。私は、正直「いやー、今からこれを直すのは難しいな。時間がない。」と心の中で思っていた。スプリング・コンサートまで、あと1週間程度なのである。さらに松本譲先生には、指揮の仕方まで指導してもらった。「もっと左手を軽くせなあきませんで。こうやわらかくしてやな。ちょこんと添える程度でよろしいのや。」こてこての京都弁だ。ご指導していただいた喜びはもちろんあったが、それよりも、これまで自分なりに解釈してきたこと。練習してきたことがあまり評価されておらず、かなり落ち込んだという思いの方が強かった。そして・・・
先生、「実はな、去年の冬、あんたらの演奏会を聞きに、森ノ宮(※注1)へ行ったんですわ。」とおっしゃた。
えーっ!松本譲先生ともあろうお人が、自分から好んで演奏会に来て頂けた。しかも、去年の演奏会のメインは、「バーレスク(大栗裕)」と「ハ短調の序曲(帰山栄治)」だ。そんな邦人バリバリのエグイ曲を、松本先生のような同志社イタオリ(※注2)系の方に聞いて頂けるなんて不思議だな~と思いながらも、ちょっと喜んでいた。しかし、その喜びも長くは続かなかった。
先生、「あんたら、去年、カペレッティーの劇的序楽を演奏しはったやろ?」
「・・・劇的???そっ、それ、俺がサブコンとして1部で振ったやつやん。」と心の中で思いながら、
先生、「わしな、あれを聞きに森ノ宮へ行ったんですわ。」
私、「えー!そうなんですか。ありがとうございます。」と言った。
先生、「あの難曲をどう演奏するんか、興味がありましてな。対位法があらゆるところに出てきて、難しい曲なんですわ。案の定、あんたらの演奏も難しそうでしたな。」そして、ちょっと言いにくそうに「・・・悪いけど、途中で帰りましたわ。」
私、心の中で「ガーン!!」
松本先生、決して落ち込ませようと思っておっしゃった分けではない。それだけははっきりさせておこう。言葉にも優しさは現れていた。しかし、この場合の優しさは、「あんたら、もっとしっかり演奏せんとあかんよ!」という激励の込められたものだ。・・・しかし、私は表情は変えなかったものの、さすがに落ち込んだ。経験の浅いまま、「劇的」を振るのは、いま思えばかなりの無茶であったかも知れない。当時の選曲会議は、石橋駅近くの「大関旅館」の2階の畳部屋で行われ、カセットテープとスコアで一曲一曲、確かめながら行った。サブコン用の曲は、先輩が「おまえ、どんな曲がええねん?」と聞かれながら、「んー、今度は、なんやドーンと終わるやついきたいですね!」なんて、言いながら決めていた。その結果、「劇的序楽」になったのである。スコアなんて二の次であった。しかし、練習に入ってからというもの、なんかイメージと違うな、違うな・・・という日々が続いたのである。それは、演奏者側にもあったようだ。指揮そのものに、クレームが付いたことも多々ある。そして、自分にも自信が無くなっていった。どう指示したら良いのかが分からなかったのだろう。
松本先生、「まあ、あんたら、いうてもあんまりマンドリンの曲知らんやろ?世の中には、もっともっとええマンドリンの曲があるんやで。よかったらな、一度うちに遊びに来はったら?」
私、「いいんですか?是非寄らせてもらいます。」
と松本先生からのご指導が終わり、丁重にお礼を言って甲南大の合宿所を後にした。
そして、数日後、京都にある松本譲先生のお宅を、コンマスと一緒に訪問した。先生は、ご高齢のお母様と一緒に暮らしておられた。そのお母様が、お茶をだしてくれた。松本先生は、笑顔の時に、お顔のシワがクシャーとなりすごく優しい表情になられる。そこでは、本当にいろんなお話をしていただいた。実は、先生宅におじゃましたもう一つの理由は、松本先生からお話のあった当クラブの「技術顧問」としての打診を、丁重にお断りすることでもあった。指導者あるいは音楽監督を置いたマンドリンクラブの演奏の出来は非常に良いのは知っていた。しかし、自分たちで選曲し、作り上げるという部分が、小さくなってしまう危機感を、部員のほとんどが思っていたようで、みんなに打診したが、反対意見が大多数であった。
その後、ときどき演奏会場で松本先生をお見かけしては、ご挨拶をすることがあった。3年生の冬でクラブは引退したが、まだマンドリンへの興味は続いていた。1990年、私が大学院生の時の夏、「第20回全国中高ギターマンドリンフェスティバル(全フェス)」が、やはり森ノ宮の青少年会館で行われ足を運んだ。そのときの「全フェス」の講評者はすごいメンバーだった。中野二郎先生、比留間絹子先生、そして、松本譲先生がおられた。松本先生、いくつもの学校の演奏を聴いては、的確に講評を述べられる。当時、森龍彦先生率いる雲雀丘学園の演奏を「べたぼめ」されていたことを思い出す。しかし、私が松本先生にお目にかかったのは、残念ながらそれが最後であった。それから研究職を目指すことを決意し、しばらくマンドリンに全く触れなくなって、数年が過ぎたころ、何かのきっかけで、松本譲先生がお亡くなりになったことを聞きました。しかし、先生のマンドリン界へのご貢献は周知の通り高く、いまでも「編曲・松本譲」の曲が演奏会で多く見受けられる。ボッシ作品集なんか、松本先生の大ヒットではないかと思う。「トリプティーク(芥川)」はたくさんの方の手で編曲されているが、松本先生の編曲版が、一番評価が高い。たばこをふかしながら、微笑まれる姿がいまでも思い出される。
(東広島の自宅にて)
------------------------------------
(※注1)森ノ宮・・・「大阪府立青少年会館文化ホール」
(※注2)イタオリ・・・「イタリアマンドリンオリジナル」の略。類義語に「イタメシ」。(←全然違うけど。)
私、「あのー、先ほどは、松本先生と分からずに、大変失礼しました。それで、先生に先ほどの演奏について御意見をいただきたいと思いまして・・・。」
いやー、自分から仕掛けてしまったのである。
先生は、「はあ、そうですか。まあ、こっちへ来てください。」
とおっしゃい、私とコンマスを、会議室のような場所へ導かれた。そして、先ほどの「ヴェニスの1日」について、事細かく指示を出して頂いた。18年前のことなので、指示された内容はあまり覚えていないが、これまで受けたことのない、的確な指示であった記憶はある。私は、正直「いやー、今からこれを直すのは難しいな。時間がない。」と心の中で思っていた。スプリング・コンサートまで、あと1週間程度なのである。さらに松本譲先生には、指揮の仕方まで指導してもらった。「もっと左手を軽くせなあきませんで。こうやわらかくしてやな。ちょこんと添える程度でよろしいのや。」こてこての京都弁だ。ご指導していただいた喜びはもちろんあったが、それよりも、これまで自分なりに解釈してきたこと。練習してきたことがあまり評価されておらず、かなり落ち込んだという思いの方が強かった。そして・・・
先生、「実はな、去年の冬、あんたらの演奏会を聞きに、森ノ宮(※注1)へ行ったんですわ。」とおっしゃた。
えーっ!松本譲先生ともあろうお人が、自分から好んで演奏会に来て頂けた。しかも、去年の演奏会のメインは、「バーレスク(大栗裕)」と「ハ短調の序曲(帰山栄治)」だ。そんな邦人バリバリのエグイ曲を、松本先生のような同志社イタオリ(※注2)系の方に聞いて頂けるなんて不思議だな~と思いながらも、ちょっと喜んでいた。しかし、その喜びも長くは続かなかった。
先生、「あんたら、去年、カペレッティーの劇的序楽を演奏しはったやろ?」
「・・・劇的???そっ、それ、俺がサブコンとして1部で振ったやつやん。」と心の中で思いながら、
先生、「わしな、あれを聞きに森ノ宮へ行ったんですわ。」
私、「えー!そうなんですか。ありがとうございます。」と言った。
先生、「あの難曲をどう演奏するんか、興味がありましてな。対位法があらゆるところに出てきて、難しい曲なんですわ。案の定、あんたらの演奏も難しそうでしたな。」そして、ちょっと言いにくそうに「・・・悪いけど、途中で帰りましたわ。」
私、心の中で「ガーン!!」
松本先生、決して落ち込ませようと思っておっしゃった分けではない。それだけははっきりさせておこう。言葉にも優しさは現れていた。しかし、この場合の優しさは、「あんたら、もっとしっかり演奏せんとあかんよ!」という激励の込められたものだ。・・・しかし、私は表情は変えなかったものの、さすがに落ち込んだ。経験の浅いまま、「劇的」を振るのは、いま思えばかなりの無茶であったかも知れない。当時の選曲会議は、石橋駅近くの「大関旅館」の2階の畳部屋で行われ、カセットテープとスコアで一曲一曲、確かめながら行った。サブコン用の曲は、先輩が「おまえ、どんな曲がええねん?」と聞かれながら、「んー、今度は、なんやドーンと終わるやついきたいですね!」なんて、言いながら決めていた。その結果、「劇的序楽」になったのである。スコアなんて二の次であった。しかし、練習に入ってからというもの、なんかイメージと違うな、違うな・・・という日々が続いたのである。それは、演奏者側にもあったようだ。指揮そのものに、クレームが付いたことも多々ある。そして、自分にも自信が無くなっていった。どう指示したら良いのかが分からなかったのだろう。
松本先生、「まあ、あんたら、いうてもあんまりマンドリンの曲知らんやろ?世の中には、もっともっとええマンドリンの曲があるんやで。よかったらな、一度うちに遊びに来はったら?」
私、「いいんですか?是非寄らせてもらいます。」
と松本先生からのご指導が終わり、丁重にお礼を言って甲南大の合宿所を後にした。
そして、数日後、京都にある松本譲先生のお宅を、コンマスと一緒に訪問した。先生は、ご高齢のお母様と一緒に暮らしておられた。そのお母様が、お茶をだしてくれた。松本先生は、笑顔の時に、お顔のシワがクシャーとなりすごく優しい表情になられる。そこでは、本当にいろんなお話をしていただいた。実は、先生宅におじゃましたもう一つの理由は、松本先生からお話のあった当クラブの「技術顧問」としての打診を、丁重にお断りすることでもあった。指導者あるいは音楽監督を置いたマンドリンクラブの演奏の出来は非常に良いのは知っていた。しかし、自分たちで選曲し、作り上げるという部分が、小さくなってしまう危機感を、部員のほとんどが思っていたようで、みんなに打診したが、反対意見が大多数であった。
その後、ときどき演奏会場で松本先生をお見かけしては、ご挨拶をすることがあった。3年生の冬でクラブは引退したが、まだマンドリンへの興味は続いていた。1990年、私が大学院生の時の夏、「第20回全国中高ギターマンドリンフェスティバル(全フェス)」が、やはり森ノ宮の青少年会館で行われ足を運んだ。そのときの「全フェス」の講評者はすごいメンバーだった。中野二郎先生、比留間絹子先生、そして、松本譲先生がおられた。松本先生、いくつもの学校の演奏を聴いては、的確に講評を述べられる。当時、森龍彦先生率いる雲雀丘学園の演奏を「べたぼめ」されていたことを思い出す。しかし、私が松本先生にお目にかかったのは、残念ながらそれが最後であった。それから研究職を目指すことを決意し、しばらくマンドリンに全く触れなくなって、数年が過ぎたころ、何かのきっかけで、松本譲先生がお亡くなりになったことを聞きました。しかし、先生のマンドリン界へのご貢献は周知の通り高く、いまでも「編曲・松本譲」の曲が演奏会で多く見受けられる。ボッシ作品集なんか、松本先生の大ヒットではないかと思う。「トリプティーク(芥川)」はたくさんの方の手で編曲されているが、松本先生の編曲版が、一番評価が高い。たばこをふかしながら、微笑まれる姿がいまでも思い出される。
(東広島の自宅にて)
------------------------------------
(※注1)森ノ宮・・・「大阪府立青少年会館文化ホール」
(※注2)イタオリ・・・「イタリアマンドリンオリジナル」の略。類義語に「イタメシ」。(←全然違うけど。)










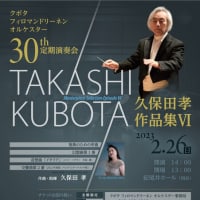

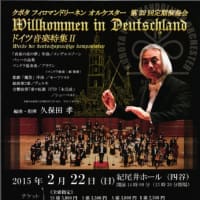
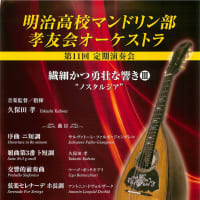

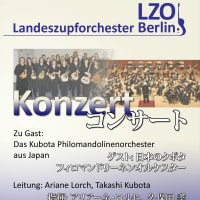

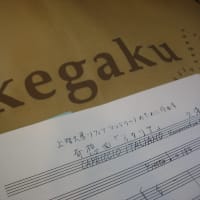
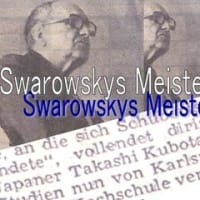
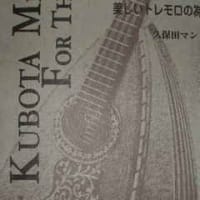
現役のときは僕も『感覚』でやってました。勉強してない・・・。当時、対位法とか言われてもおそらく『体位法?どういうんだ、それは?』とか絶対シモに走ってましたよ!
ところで、修道大って西の方にあるらしいね。今度、わけ合って、大学に行くかもしれません。西条から遠いんでしょうね。