ビジネスコンテスト」勝ち抜く人の明確な共通点 プレゼンの「方向性」から「立ち居振る舞い」まで2025/03/31 14:30 様記事抜粋<
様記事抜粋<
さまざまなビジネスコンテストに参加してみて、受賞者の傾向を分析してわかったことがあります――。こう語るのは、日本の伝統を暮らしに活かしながら次世代につなぐ事業を展開し、注目の若手起業家のひとりと目される矢島里佳氏。
そんな矢島氏が提唱する、「ビジコン」を勝ち抜くためのポイントについて、同氏の著書『ブレずに「やりたいこと」で食べていく起業』から、一部を抜粋・編集してお届けします。
「相性のいいコンテスト」を徹底的に研究する
あなたは、人の心を動かすためにどのようなことを意識していますか?
ビジネスコンテストで勝つには、自分のビジネスが魅力的であることはもちろんですが、私がさまざまなビジネスコンテストに参加してみて、受賞者の傾向を分析してわかったことがあります。
勝ちパターンの大前提となるのは、まず、自分のビジネスモデルと相性のいいコンテストに参加することです。
そのために、コンテストの趣旨や主催団体、審査員、過去の受賞した内容を徹底的に調べ上げて研究します。
ビジネスコンテストごとに審査の基準や表彰する内容が異なるので、その基準や趣旨から外れていると、いくら優れたビジネスモデルだとしても、箸にも棒にもかからないこともあり得ます。
また、過去の受賞内容に近いプランだと、新規性がないので評価が下がってしまいます。
そこで、私はコンテストの要綱を読み込んで、「このコンテストでは、どんなところに価値を置いて表彰するのか」「そのために、どういう審査員をそろえているのか」「過去、すでに表彰されているビジネスモデルと自社がバッティングしていないか」などを調べ上げます。
結果、相性が良ければ参加し、相性が良くないと判断すれば、応募の優先順位を下げます。
審査員に「実現したい未来」に共感してもらう
ビジネスコンテストは、一般的には「書類審査」と「プレゼン審査」があり、書類審査に通過できた出場者が、対面で審査員にビジネスプランをプレゼンできます。
その際に大きなポイントとなるのは、審査員がそのビジネスの先にある未来を見てみたいと思うかです。
そのために、自分のビジネスプランではどんな課題を解決しようとしていて、具体的にどのようなアプローチをしようとしているのか。多様な背景を持つ審査員が自らの立場で「このビジネスプランを表彰することで、今後より良い未来がやってくる」ということを想起していただけるプレゼンの構成にします。
たとえば私が起業後に出場した、日本政策投資銀行の「第4回DBJ女性新ビジネスプランコンペティション」(DBJ)では女性起業大賞を、APEC(アジア太平洋経済協力会議)のビジネスプランコンテストには日本代表として推薦いただき「APEC Best Award2017」に参加し、大賞とオーディエンス賞をダブル受賞しています。
DBJは日本国内の女性経営者を対象としたビジネスプランコンテストでしたので、「日本にとって、未来の経済を育む自国の文化が失われることは課題ですよね」、しかも「女性経営者ならではの視点だからこそ気づけた」という構成で、「経済、文化、女性」というキーワードを意識してプレゼンしました。
「APEC Best Award」は世界が舞台なので、「世界の人たちから見て、日本という国の1つの会社のビジネスモデルが、世界のほかの地域の社会課題、背景と合致し、それらの解決のヒントになるようなロールモデルとなるビジネスモデルであることを証明すれば、選ばれる可能性が高いだろう」という仮説を立てました。
「自国の文化が消えていくということは、全世界の課題である」と、文化が失われることが、未来の経済や心の豊かさにどのような影響を及ぼすのか。文化を次世代につなぐことの重要性を共通認識として感じていただけるように、プレゼンの冒頭は質問形式で自分ごととして考えながら聞いていただけるよう、構成を工夫しました。
「ああ、そうか。これはうちの国の課題でもあるな。その課題を日本の『和える』という会社が先だって、ビジネスという手法を用いて、自国の伝統文化を次世代につなぐビジネスモデルをつくったらしい。これは1つのロールモデルとして、全世界で知ってもらうべきビジネスモデルだよね」と理解してもらえるように話しました。
ビジネスコンテストの舞台が変われば、もちろん主旨や審査員も変わるので、プレゼンの構成や訴えかけるポイントも変えなければいけません。
けれども、どんなビジネスコンテストでも、共通しているのは、「提案している未来がきてほしいと、多くの人に感じてもらえるプレゼンをすること」です。
そして、いくつもコンテストに挑戦してみることが大切です。場数を踏むことで感覚値を得られ優勝に1歩ずつ近づいていけます。
実際に私自身、最初は入賞すらできませんでしたが、出場したコンテストで審査員の方からいただくフィードバックに真摯に向き合い改善し、何度も挑戦しました。
そうすることで自分なりの勝ちパターンを見出すことができるようになり、高確率で優勝をつかめるようになりました。
プレゼン上達の近道は「まねぶ(真似て、学ぶ)」こと
自分のプレゼンにまだ自信がない人は、お手本となるプレゼンの手法を取り入れるなど表現豊かに審査員に伝えることを意識し、「このコンテストにふさわしいビジネスプランである」と感じてもらえるように伝え方を工夫すると良いでしょう。
プレゼンは「どんな構成で」「どう話すか」という内容だけでなく、表現力も重要なため、私もお手本となるプレゼンをよく観察・分析して、話し方、立ち居振る舞いを真似するようにしています。
たとえば、APECのビジネスプランコンテストは英語でのプレゼンのため、日本語とはリズムやロジック展開が異なります。
そこで、話し方のお手本になりそうな英語のプレゼンテーションの動画として「TED Talks」を観て、「どんな構成で話せばいいのか」「どんな場面で、どんな話し方や立ち居振る舞いをすればいいのか」ということを分析し取り入れて本番に臨みました。
数々の賞を受賞している起業家の友人たちと話をしていても、この話は共通で、みなコンテストの過去の傾向と対策を研究し、プレゼン、ピッチが上手な人の真似を徹底的にする、と言います。
評価されるポイントと自分の良さを「マッチング」
ただし、お手本をただ真似するだけではなく、自分らしさを内在させることも重要です。お手本の評価されるポイントと自分の良さを、うまくマッチングさせる、そう、和えるのです。
真似しきったうえで、自分のオリジナリティを載せていきます。お手本を分析し取り入れつつ、自分のやりたいことで賞を取りにいくのです。
最後にビジネスコンテストで最も気をつけるべきことは、コンテストに迎合しないことです。それは本末転倒です。
要項を読み込んでいくと、ついつい自分のビジネスプランを要項に寄せていってしまい、結果として本来自分のやりたいことと本質がずれてしまっていた……ということは往々にしてあります
すると、どこかで自分の中で矛盾や引っ掛かりができてしまい、真に力を発揮することができないですし、仮に入賞したとしても、それは自分が本当にやりたいことではないということがあります。
だからこそ、コンテストを徹底的に分析して、自分に合っているコンテストであるかどうかを見極め、真に理解したうえでプレゼンを構成すること。そこで求められるお題には答えつつ、自分らしいプレゼンで、審査員の方々に納得・共感していただければ、「やりたいこと」に素直に優勝をすることができるのです。著者:矢島 里佳氏












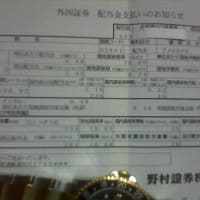

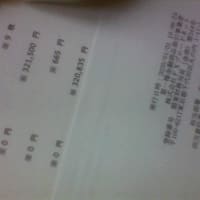
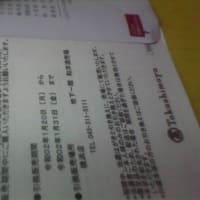

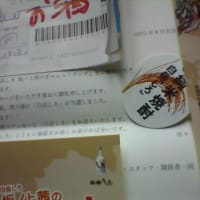

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます