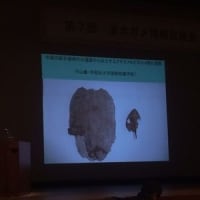小さな公園のように囲った土地に不釣り合いなサイズの石碑には、「海軍大将大勲位伯爵樺山資紀邸趾」の文字。“あっ!”と思わず小さな声を上げる。樺山資紀(かばやま すけのり/参考:Wiki樺山資紀)。白洲正子のお祖父さんだ。そうか、ここが。
『白洲正子自伝』の頁をめくると、まず最初の章が「祖父・樺山資紀」。その若き日のエピソードは凄まじいの一言だ。
…示現流というのは、薩摩の島津藩で行われていた剣道で、その使い手
の指宿藤次郎が、京都祇園の石段下で見廻組に殺された。むろん幕末
のことである。
その時、前田某という若侍が同行していたが、彼はいち早く遁走した。
指宿は五人の敵を唐オたが、下駄の鼻緒が切れて転唐オ、無念の最期を
とげたという。
その葬儀の場に、橋口覚之進という気性のはげしい若侍がいて、焼香
の時が来ても、棺の蓋を覆わず、指宿の死顔を灯びのもとにさらしてい
た。彼は参列者の中から前田を呼んでこういった。
「お前が一番焼香じゃ。さきィ拝め」
ただならぬ気配に、前田はおそるおそる進みでて焼香し、指宿の死体
の上にうなだれた。その時、橋口は腰刀をぬき、一刀のもとに首を
斬った。首はひとたまりもなく棺の中に落ちた。
「こいでよか。蓋をせい」
この橋口覚之進がのちの樺山で、正子さんはそんな祖父の血を継いでいること、薩摩隼人の裔であることを、強烈に意識し続けたらしい。(『白洲正子自伝』の表紙の写真は、祖父に抱きかかえられた幼少時のもの)

石碑の裏手に回ると「地神」と書かれた石造物があった。ヂノカンサァ(地の神さま)と呼ばれるもので、かつて鹿児島の古い家には当たり前にあるものだった…と、これも『白洲正子自伝』中に書かれてあった、いわば書物の上での知識だ。
実際にそれを目にすることで、「自分の目で確かめることの大切さ」を諭されているような、そんな気がした。そう、彼女は自分が書く場所には、必ず足を運んだ作家なのであった…

鹿児島を散策中に、白洲正子ゆかりの地に接する。これぞ亀歩当棒。「結果オーライ」といわれればそれまでだが、とにかく嬉しかった。