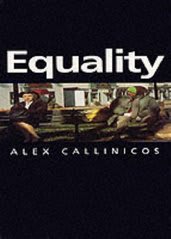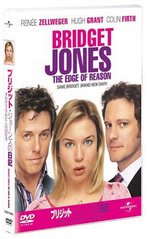昨日5月1日は、水俣病の公式確認50年の日だった。水俣病は私が生まれるずっと以前に発見された事件だが、いくつか新聞を読み比べて分かってくるのは、水俣病の問題がいまも全く終わっていないということだ。多くの患者の人々の苦しみも、加害企業のチッソや政府による謝罪・補償問題もすべて、今も変わらず存在し続けているということが分かる。
とりわけ今も根強い水俣病患者への差別や、認定申請を踏みとどまらせる要因でもある障害に対する偏見の問題を考えると、水俣病はすぐれて現代的な問題であることが分かる。1日付朝日新聞の「私の視点」では、小規模通所授産施設代表の加藤たけ子氏による「水俣病問題を社会福祉の先進モデル構築のために生かすべき」との議論が紹介されていた。
「(発症当時胎児だった)胎児性患者は(現在)40代から50代になったが、通常の加齢では考えられない急速な身体機能の低下が目立つ。・・・全身に及ぶ重い障がいを負いながら、介護は高齢化する家族に委ねられ、地域で半孤立状態になっている。・・・ 地域に福祉施設がないわけではない。偏見と差別を背景に人との信頼関係が持てなくなり、そうした専門機関とつながっていけないところに水俣病の根深さがある。・・・対策の基本的方向は、住み慣れた地域で、人々とのつながりの中で暮らしていくことができる社会的条件=地域福祉システムをつくることである。具体的提案として、いつでもだれでも、通えて泊まれ、相談にのってくれる人がいる場が必要である。働くことを中心に創造的な活動に取り組める場、仲間や地域の人との交流の輪を広げる場であり、生活の場としてのグループホームもある。自宅に顔なじみのヘルパーを派遣したり、介護で疲れた家族を癒したりすることも必要だ。こうした多機能で小規模な施設が地域に開かれてほしい。行政はいまこそ、水俣病の教訓を生かし、社会福祉を具現化した先進モデルとなる地域づくりに貢献することが求められている。」(5月1日付朝日新聞朝刊「私の視点」より)
ここで挙げられているモデルはもはや水俣病問題にとどまらず、他の身体的・知的障害者に対する福祉サービス問題や、高齢者介護問題、ホームレスの自立生活支援問題など、いわば社会福祉一般にも関わってくる事柄である。水俣の問題と向き合うことなくして、21世紀の日本社会における福祉の充実は願うべくもないだろう。
ちなみに先月28日、小泉首相は水俣病について「政府の責任を痛感し、率直にお詫びしたい」との談話を発表したそうだ。
「政府は28日、5月1日で水俣病の公式確認から50年になることを受け、「長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて、政府としてその責任を痛感し、率直にお詫(わ)びを申し上げます」として政府責任を認める首相談話を発表した。 首相談話では「このような悲劇を二度と繰り返さないために、その教訓をいかし、環境を守り安心して暮らしていける社会を実現すべく、政府を挙げて取り組んでいく決意」を表明している。」
(記事全文はこちら)
言葉通りの実行責任が伴っていることを願いたい。しかし下のような記事を読むと、そんな願いもむなしくなってくるが・・・。
「…石綿に目を転じると、石綿工場周辺で、石綿関連がんの中皮腫にかかった「公害」とみられる患者の数はこれまでに100人を超えた。潜伏期間が30~50年と長い中皮腫は、2040年までに10万人が死亡するとの予測もある。水俣病に学び、行政が初期対応をきちんとすれば、被害はここまで広がらなかった可能性が高い。
旧環境庁が発足したのは、水俣病公式確認から15年後の71年。その翌年、国際労働機関(ILO)などで石綿の危険性が指摘された。旧労働省や旧環境庁もその危険性を認識していた。だが原則禁止は04年10月まで遅れた。…(中略)…被害が広がり始めてからの動きも鈍かった。国が石綿対策に本腰を入れたのは、兵庫県尼崎市のクボタ旧神崎工場周辺での事態が昨年6月に報道されてからだ。」(記事全文はこちら)
いっぽう民主党は「水俣病被害救済特別措置法案」(仮称)の制定をめざしているそうだ。内容は患者の認定基準を拡大して、国による補償額を引き上げるもので、早ければ秋の臨時国家で法案を提出するとのこと(5月1日付毎日新聞朝刊社会面)。野党にはこの問題をもっとクローズアップして突いていってほしい。
とりわけ今も根強い水俣病患者への差別や、認定申請を踏みとどまらせる要因でもある障害に対する偏見の問題を考えると、水俣病はすぐれて現代的な問題であることが分かる。1日付朝日新聞の「私の視点」では、小規模通所授産施設代表の加藤たけ子氏による「水俣病問題を社会福祉の先進モデル構築のために生かすべき」との議論が紹介されていた。
「(発症当時胎児だった)胎児性患者は(現在)40代から50代になったが、通常の加齢では考えられない急速な身体機能の低下が目立つ。・・・全身に及ぶ重い障がいを負いながら、介護は高齢化する家族に委ねられ、地域で半孤立状態になっている。・・・ 地域に福祉施設がないわけではない。偏見と差別を背景に人との信頼関係が持てなくなり、そうした専門機関とつながっていけないところに水俣病の根深さがある。・・・対策の基本的方向は、住み慣れた地域で、人々とのつながりの中で暮らしていくことができる社会的条件=地域福祉システムをつくることである。具体的提案として、いつでもだれでも、通えて泊まれ、相談にのってくれる人がいる場が必要である。働くことを中心に創造的な活動に取り組める場、仲間や地域の人との交流の輪を広げる場であり、生活の場としてのグループホームもある。自宅に顔なじみのヘルパーを派遣したり、介護で疲れた家族を癒したりすることも必要だ。こうした多機能で小規模な施設が地域に開かれてほしい。行政はいまこそ、水俣病の教訓を生かし、社会福祉を具現化した先進モデルとなる地域づくりに貢献することが求められている。」(5月1日付朝日新聞朝刊「私の視点」より)
ここで挙げられているモデルはもはや水俣病問題にとどまらず、他の身体的・知的障害者に対する福祉サービス問題や、高齢者介護問題、ホームレスの自立生活支援問題など、いわば社会福祉一般にも関わってくる事柄である。水俣の問題と向き合うことなくして、21世紀の日本社会における福祉の充実は願うべくもないだろう。
ちなみに先月28日、小泉首相は水俣病について「政府の責任を痛感し、率直にお詫びしたい」との談話を発表したそうだ。
「政府は28日、5月1日で水俣病の公式確認から50年になることを受け、「長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて、政府としてその責任を痛感し、率直にお詫(わ)びを申し上げます」として政府責任を認める首相談話を発表した。 首相談話では「このような悲劇を二度と繰り返さないために、その教訓をいかし、環境を守り安心して暮らしていける社会を実現すべく、政府を挙げて取り組んでいく決意」を表明している。」
(記事全文はこちら)
言葉通りの実行責任が伴っていることを願いたい。しかし下のような記事を読むと、そんな願いもむなしくなってくるが・・・。
「…石綿に目を転じると、石綿工場周辺で、石綿関連がんの中皮腫にかかった「公害」とみられる患者の数はこれまでに100人を超えた。潜伏期間が30~50年と長い中皮腫は、2040年までに10万人が死亡するとの予測もある。水俣病に学び、行政が初期対応をきちんとすれば、被害はここまで広がらなかった可能性が高い。
旧環境庁が発足したのは、水俣病公式確認から15年後の71年。その翌年、国際労働機関(ILO)などで石綿の危険性が指摘された。旧労働省や旧環境庁もその危険性を認識していた。だが原則禁止は04年10月まで遅れた。…(中略)…被害が広がり始めてからの動きも鈍かった。国が石綿対策に本腰を入れたのは、兵庫県尼崎市のクボタ旧神崎工場周辺での事態が昨年6月に報道されてからだ。」(記事全文はこちら)
いっぽう民主党は「水俣病被害救済特別措置法案」(仮称)の制定をめざしているそうだ。内容は患者の認定基準を拡大して、国による補償額を引き上げるもので、早ければ秋の臨時国家で法案を提出するとのこと(5月1日付毎日新聞朝刊社会面)。野党にはこの問題をもっとクローズアップして突いていってほしい。