
去る3月8日、日本画家(*1)にして真宗大谷派僧侶・畠中光享先生の講演会を拝聴してきました。:)
この講演は、東本願寺北海道教区坊守会連盟の主催で行われたもので、人の生き方と絵画表現との関わりについて、随処に仏教の教えや先生の宗教観についての平明な紹介を織りこみつつのお話でした。
思わず惹きこまれる語り口で楽しく伺いましたが、内容は深く広く、全て覚えてはいられずに、多くは頭からこぼれおちてしまいました。また、何とか覚えていられたことも、とても全てここに書くことはできません。
けれど、「インド美術研究家・お坊さん・日本画家の3つの顔を持ち、そのどれもが自分にとっては、どれが主でどれが従もない等しいもの」と仰る先生のお話の中から、特に印象に残ったことのうちのいくつかを書き留めておこうと存じます。



 日本では1970年代の後半から心の時代と言われ、多くの宗教書が出版されながら、人々は決して満たされておらず、却って、何かの宗教に入っているというと怪しまれる向きもある。けれど、宗教とは、真には人が幸せになるためにすること。
日本では1970年代の後半から心の時代と言われ、多くの宗教書が出版されながら、人々は決して満たされておらず、却って、何かの宗教に入っているというと怪しまれる向きもある。けれど、宗教とは、真には人が幸せになるためにすること。
(初めに先生の紹介に立たれた僧侶の方は、先生が「真の宗教とは優しさである(*2)」というダライラマ14世の言葉をとても大切になさっている旨仰っていました。)
 もともとの仏教は「原因を辿ってゆけば分かる」というとても合理的な考え方を持つ。
もともとの仏教は「原因を辿ってゆけば分かる」というとても合理的な考え方を持つ。
 絵を描くことは身体表現である。
絵を描くことは身体表現である。
(人には五感があるが、そのどれかひとつに偏ってものをみるのは間違い。また、ひとつのことにとらわれてものを見るのも間違い。何にでもアンテナを張ろう。)
 「ドメスティックでないとインターナショナルになれない」
「ドメスティックでないとインターナショナルになれない」
 絵を描くとき、無理にオリジナリティを出そうと思わないこと。仕事も一緒。人に喜んでもらえるようにする。そうすればきっと平和になる。
絵を描くとき、無理にオリジナリティを出そうと思わないこと。仕事も一緒。人に喜んでもらえるようにする。そうすればきっと平和になる。
 暗い絵は描かない。人に夢を与える所が無ければ駄目。
暗い絵は描かない。人に夢を与える所が無ければ駄目。
 絵は、写生を大事にし、自然に教えてもらいながら、線を大切にして描くこと。「塗るのではない。描く。」
絵は、写生を大事にし、自然に教えてもらいながら、線を大切にして描くこと。「塗るのではない。描く。」
 昔は絵の具はみな天然で、貴重なものだった。今でもその頃と同じように、良い絵の具を慈しんで使うことが大事。失敗したら洗えば良いなどと思わない。良いものを慈しんで使えば上手になる。
昔は絵の具はみな天然で、貴重なものだった。今でもその頃と同じように、良い絵の具を慈しんで使うことが大事。失敗したら洗えば良いなどと思わない。良いものを慈しんで使えば上手になる。



そうしてお話は、
「あんまり若い頃から宗教なんて入りこまなくてもよろしい。良い心、大事にする気持ち、慈しんで描く気持ち、自然から教えてもらう気持ちを持つこと。『私が私が』などという気持ちがあるうちは駄目。個性なんて悪い癖とおんなじなんです。宗教は道徳ではなく生き方。仕事をする時も、宗教心が無ければ良いものは作れない。」
というお言葉に集約されたように思われました。
特定の宗教の信者ではない私にも、一言一言が厳しく温かく心に響き、時に耳が痛く(^^;、けれども同時に心洗われました。時折あちらこちらへ脱線しかけてはまた戻る、そのお話の枝葉の先まで、受けとめたいと思いながら叶わず、そのことがとても勿体なく歯がゆく思える、それだけに貴重な時間でした。
(*1)ただし「日本画」とは、日本に西洋画が入ってきた明治期以降に、それとの対比のために作られた言葉であり、先生は「日本画なんて本当はない。ぼくは『日本画』なんて言葉は好きじゃない」と仰っています。
(*2)「真の宗教とは優しさである。生きている限り、学問をしていようといまいと、来世を信じていようといまいと、仏陀を信じていようといまいと、優しい人になること。そのためにはどんな仕事であろうと、プロフェッショナルな仕事をすること。そうすることで心の底から優しい人になれる。」
この講演は、東本願寺北海道教区坊守会連盟の主催で行われたもので、人の生き方と絵画表現との関わりについて、随処に仏教の教えや先生の宗教観についての平明な紹介を織りこみつつのお話でした。
思わず惹きこまれる語り口で楽しく伺いましたが、内容は深く広く、全て覚えてはいられずに、多くは頭からこぼれおちてしまいました。また、何とか覚えていられたことも、とても全てここに書くことはできません。
けれど、「インド美術研究家・お坊さん・日本画家の3つの顔を持ち、そのどれもが自分にとっては、どれが主でどれが従もない等しいもの」と仰る先生のお話の中から、特に印象に残ったことのうちのいくつかを書き留めておこうと存じます。



 日本では1970年代の後半から心の時代と言われ、多くの宗教書が出版されながら、人々は決して満たされておらず、却って、何かの宗教に入っているというと怪しまれる向きもある。けれど、宗教とは、真には人が幸せになるためにすること。
日本では1970年代の後半から心の時代と言われ、多くの宗教書が出版されながら、人々は決して満たされておらず、却って、何かの宗教に入っているというと怪しまれる向きもある。けれど、宗教とは、真には人が幸せになるためにすること。(初めに先生の紹介に立たれた僧侶の方は、先生が「真の宗教とは優しさである(*2)」というダライラマ14世の言葉をとても大切になさっている旨仰っていました。)
 もともとの仏教は「原因を辿ってゆけば分かる」というとても合理的な考え方を持つ。
もともとの仏教は「原因を辿ってゆけば分かる」というとても合理的な考え方を持つ。 絵を描くことは身体表現である。
絵を描くことは身体表現である。(人には五感があるが、そのどれかひとつに偏ってものをみるのは間違い。また、ひとつのことにとらわれてものを見るのも間違い。何にでもアンテナを張ろう。)
 「ドメスティックでないとインターナショナルになれない」
「ドメスティックでないとインターナショナルになれない」 絵を描くとき、無理にオリジナリティを出そうと思わないこと。仕事も一緒。人に喜んでもらえるようにする。そうすればきっと平和になる。
絵を描くとき、無理にオリジナリティを出そうと思わないこと。仕事も一緒。人に喜んでもらえるようにする。そうすればきっと平和になる。 暗い絵は描かない。人に夢を与える所が無ければ駄目。
暗い絵は描かない。人に夢を与える所が無ければ駄目。 絵は、写生を大事にし、自然に教えてもらいながら、線を大切にして描くこと。「塗るのではない。描く。」
絵は、写生を大事にし、自然に教えてもらいながら、線を大切にして描くこと。「塗るのではない。描く。」 昔は絵の具はみな天然で、貴重なものだった。今でもその頃と同じように、良い絵の具を慈しんで使うことが大事。失敗したら洗えば良いなどと思わない。良いものを慈しんで使えば上手になる。
昔は絵の具はみな天然で、貴重なものだった。今でもその頃と同じように、良い絵の具を慈しんで使うことが大事。失敗したら洗えば良いなどと思わない。良いものを慈しんで使えば上手になる。


そうしてお話は、
「あんまり若い頃から宗教なんて入りこまなくてもよろしい。良い心、大事にする気持ち、慈しんで描く気持ち、自然から教えてもらう気持ちを持つこと。『私が私が』などという気持ちがあるうちは駄目。個性なんて悪い癖とおんなじなんです。宗教は道徳ではなく生き方。仕事をする時も、宗教心が無ければ良いものは作れない。」
というお言葉に集約されたように思われました。
特定の宗教の信者ではない私にも、一言一言が厳しく温かく心に響き、時に耳が痛く(^^;、けれども同時に心洗われました。時折あちらこちらへ脱線しかけてはまた戻る、そのお話の枝葉の先まで、受けとめたいと思いながら叶わず、そのことがとても勿体なく歯がゆく思える、それだけに貴重な時間でした。
(*1)ただし「日本画」とは、日本に西洋画が入ってきた明治期以降に、それとの対比のために作られた言葉であり、先生は「日本画なんて本当はない。ぼくは『日本画』なんて言葉は好きじゃない」と仰っています。
(*2)「真の宗教とは優しさである。生きている限り、学問をしていようといまいと、来世を信じていようといまいと、仏陀を信じていようといまいと、優しい人になること。そのためにはどんな仕事であろうと、プロフェッショナルな仕事をすること。そうすることで心の底から優しい人になれる。」
















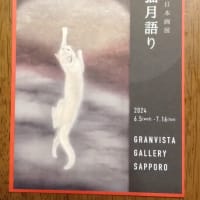









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます