二年前の夏休み(2019年7月~8月)に日本に一時帰国した後、次の4か月は授業に追われていて、冬休みになってから中国国内旅行をしようと思っていた。春節に楊州へ旅行し、日本へ一時帰国しようと思っていたところ、コロナが発生したので、急遽とりやめにした。その後は、コロナの影響で中国での観光は行えなくなってきた。それでこのブログも更新できなくなっている。この状況はまだまだ変わらないようなので、ブログの趣旨を一時的に変更して、読書日記にしてみようと思う。私の書く読書日記など誰も興味を持たないだろうけど、もともとアクセス数は少ないブログなので、とにかく日本語の文章を日本人ネイティブにむけて書いていこう。
李琴美『彼岸花が咲く島』
今回は、一回目。第165回芥川賞を受賞した李琴美の「彼岸花が咲く島」。
小説は、「プロローグ、1、2、3、4」という構成になっている。プロローグでは、真っ白な白いワンピースを着た少女(あとで宇美と名付けられる)がある島の砂浜にたおれているところを游娜という島の少女に助けられる。二人の言葉は類似しているところが多く、どうにかコミュニケーション可能だった。
島は女権社会で、年老いた巫女のような女性が最高権威者であり、島へ漂着してきた主人公の少女、彼女を助けた同年代の島の少女の二人が「巫女」を目指す。この二人に、「巫女」にあこがれる同年代の少年、三人の友情などを織り交ぜて物語は進行していく。主人公は「日本」「中国」「台湾」とおぼしき勢力に影響されている島、日本語に中国語がまざりあってできている島の言語。物語はそれなりに惹きつけられるものがあるが、言葉を作る努力までしていても、どこか既視の物語で読むのに「だるさ」が感じられた。
同じく芥川賞を受賞した作家楊逸が、『ワンちゃん』でしようした「玉の汗が光る」といった表現で、批評家によって新鮮な表現として賞賛されたことがあった。おそらくはたんに中国語表現に引きずられて書いただけだったのだろう。それに比べて、この作品は言語のことを意識して書いていることがわかるが、横山悠太の『吾輩ハ猫ニナル』が日本語の中に容易に入ってくる中国語を表現していることほどのインパクトもない。この作りこまれた言語環境も読んでいて「だるさ」を感じさせられた。
島の置かれた「日本」「中国」との地勢的状況、女権社会、島の言語世界、青春物語と様々な要素が詰め込まれるが、どれにも「だるさ」を感じさせるのは、この作品に「既視感」が漂っているからで、それは通俗性と呼ばれるものかもしれないと思った。
【以上、2021.9.20 更新】


















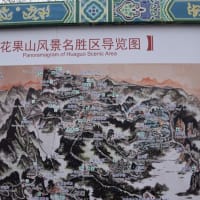

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます