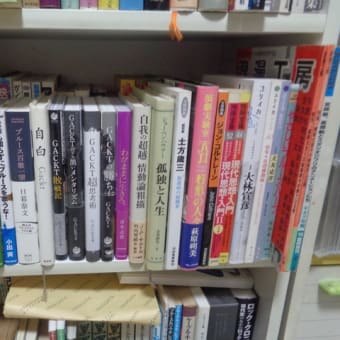私には今付き合って居る通称『妹』と読んでいる女性が居ます。彼女は私の事を気遣ってくれます。私に取って掛けがいの無い人です。彼女は某アニメーションの制作会社で、アニメの仕上げ担当のチーフをして居ます。今まで紹介しようとして居ましたが、彼女からの許可が無かったものでして。ようやく彼女から許可が取れましたから、此処に『妹』のTikTokを上げて置きます、ご覧下さい。リンクを貼って置きます、、クリックで見れます。宜しく。(((o(*゚▽゚*)o)))♡
「動物化するポストモダン」
70年代までの「大きな物語」が有効だった時代に対し、80年代はイデオロギーや「大きな物語」が消失し、その空白を埋めようとして生じた「物語」消費の時代となった。しかしポストモダンが全面化した90年代に入るとそうした「物語性」ではなく、深層にある情報(データベース)とその情報の組み合わせである「小さな物語」を消費するというデータベース・モデルに移行した。
では、70年代までを支配した行動原理・世界観とはどの様なものだったのか。
東氏は「一方には、私たちの意識に映る表層的な世界があり、他方にその表層を規定している深層=大きな物語」があり、70年代までの近代的世界観では「その深層の構造を明らかにする」事が求められて居たのだと語る。
例えば自分たちの身近にあった裕福な家庭と貧しい家庭。こうしたものもかってであればマルクスによる階級闘争に歴史の1断片として取り扱う事も出来ただろうし、それを克服するものとしての「共産主義」が信仰されただろう。あらゆる「小さな物語」は背景にある「大きな物語」の表象であり、常に「大きな物語」とつながって居たのだ。
しかしこうした「大きな物語」に対する信頼は、ベトナム戦争や共産主義国家の現実、あるいは「連合赤軍」の終焉など、70年代を通じて失墜して行く事になる。
現実には「大きな物語」は凋落して仕舞ったものの、とは言え「大きな物語」を求める心性はそう簡単に無くなるものではない。例えば79年から放送され未だに根強いファンを有する「機動戦士ガンダム」。この「ガンダム」のファンたちは単に「ガンダム」のストーリーを追いかけて居るだけではない。その背景に広がる「世界観」こそを求めており、それこそが《架空の》大きな物語として消費されたのだ。
こうした状況を大塚英志は「消費されて居るのは、1つ1つの<ドラマ>や<モノ>ではなく、その背後に隠れて居たはずのシステムそのもの」だとし、このシステム=「(架空の)大きな物語」を消費する為に、1つ1つの「小さな物語」=「1話」やそれぞれの「商品」を購入する様子を「物語消費」と呼んだ。これが80年代のスタイルとなった。
しかしこのモデルはポストモダンの本当の姿ではない。連合赤軍が「理想の時代」の終焉を告げた様に「オウム事件」が「虚構の時代」の終焉を告げる事になる。
90年代に注目を集めたものとして「萌えキャラ」がある。こうした萌え系のキャラクターは、メイド服、ネコ耳、ネコしっぽ…。などの形式化した「萌え要素」の組み合わせで構成されており、オタクたちがそうした萌えキャラに「萌えた」のは、キャラクター(シュミラークル)への盲目的な没入や感情移入と同時に、その対象を「萌え要素」に分解しデータベースの中で相対化しようと試みたからだった。
「同人誌」やマッド・ムービーの制作など、本来の「ストーリー」とは別に、個々の要素を抽出・マッシュ・アップし、盗作やパロディやサンプリングとは違う原作と同じ価値をもつ「別バージョン」を生み出そうと言う欲望が背景にあったのだ。
此処にポストモダンの行動原理である「データベース消費」の構造が見られる。萌え要素のようなデータベース(大きな非物語)から必要な「情報」を読み込み、「小さな物語(シュミラークル)」を作り続ける。それは近代のツリー・モデルのように「小さい物語」の背後に「大きな物語」がある訳ではない、そこにあるのはあくまで意味を持たないデータベースであり、即時的な「小さな物語」が無限に生産・消費され続けるのだ。
こうした変化は「大きな物語」が失われた後に登場した「日本的スノビズム」から「動物の時代」へ移行したと言う事も出来る。コジェーヴによれは人間は「欲望」を持つが動物は「欲求」しか持たないと言う。「欲求」とは、空腹→食べる→満足と言う様に、ある対象の欠乏とそれを補う事で完結する単純な回路だ。これに対して「欲望」は満たされる事がない。
学校で1番の美人を彼女に出来たとしよう。それで満足するかと言うとそうではない。彼女に自分の事だけを思って欲しいとか、他人から羨ましく思って欲しい・自慢したいとか「他者の欲望を欲望する」と言う間主体的な感情を持って仕舞う。これを動物的な「欲求」と対比して「欲望」と言う。
かっての様に深層に「大きな物語」が存在しない以上、ポストモダンに生きる人々が「生きる意味」を与えてくれるのは表層の「小さな物語」だけである。データベースは意味を与えてくれない以上、そこから紡ぎ出される「小さな物語」によるお手軽な「感動」を楽しみ、感情移入するしかない。こうして「ポストモダンの人間は『意味』への渇望を社交性を通しては満たす事が出来ず、むしろ動物的な欲求に還元する事で孤独を満たして居る。」「世界全体はただ即物的に、誰の生にも意味を与えず漂って」居るのだ。
---
今、この著を読み返す意味は、1つにはインターネットを含めた現代の状況を確認する事だ。先日読んだ「東京から考える」では、経済のグローバリズム化や消費社会の進展にともない都市そのものも動物化した時代に即した「ジャスコ的郊外」が広がって行くとあった。
確かにそうだろう。インターネット上でのサービス・IT技術の進展はそうした状況をますます加速させるのだろう。人は便利なものに慣れ、手軽じゃないないものは避けるかも知れない。エンターテインメント分野では1つの「ヒット」をもとに要素の組み合わせで無数の類似作品が生み出されるかも知れない。
しかし同時に20年代に来た今、それだけでは物足りない動きも感じられはしないか。
コンビニでは店員とお客さんとの関係が「冷めた」ものから「声を掛け合うもの」・「手を包むようにお釣りを渡すもの」へと変わり。J・POPの世界では、「大塚愛」「オレンジレンジ」のような即時的なバカ騒ぎ系から「コブクロ」「倖田來未」「絢香」のような「関係性」や「生」「つながり」を求めるものへ。あるいは東氏が「人文系が語るネット」で記したように、ニコ動の盛り上がりは人と人との繋がりを希求して居るのかも知れない。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ー 原田芳雄さんの思い出。ー
下北沢に原田芳雄さんは住んでいた。毎年12月の終わり頃に原田邸で餅つきをやっていた。いろんな人が来て居た。芸能人は勿論の事。近所の人たちも来ていた。一度だけ餅つきに参加した事がある。餅つきには、大人餅と子供餅があったと思う。私は芳雄さんを兄貴と慕って居た。勿論本人に言った事は無かったけど。
はじめ私は松田優作を好きになった。そして優作が芳雄さんを尊敬していると知ってから、彼の映画「反逆のメロディー」「やさぐれ刑事」「君よ憤怒の河を渡れ」などをミニシアターで見て、ファンに成って行った。1980年代はライブハウスで彼のブルースを聴いた。歌が上手い。ライブに行くと会場にはいつも原田芳雄の格好をして居る、そっくりさんが結構いたものだ。私も芳雄さんが来て居るアメカジやらを真似て着て居た。1990年代に成ると芳雄さんの映画が立て続けに公開された。聞く処に寄ると、1980年代は映画から遠ざかって居たそうだ。

われに撃つ用意あり 🎵「新宿心中」原田芳雄 🔻桃井かおり・蟹江敬三
Yokohama Honky Tonk Blues
原田芳雄 ブルースで死にな
原田芳雄さんの「無宿人御子神の丈吉シリーズ」のPAL盤DVD。



1990年代は「われに撃つ用意あり」「シンガポール・スリング」「浪人街」「寝取られ宗介」2000年代に「ざわざわ下北沢」「鬼火」それから変わった処では「パーティ7」などの映画に出演している。どれも滅法面白い。私は特に若松孝二監督と組んだ「われに撃つ用意あり」「シンガポール・スリング」「寝取られ宗介」「キスより簡単」が好きな映画だ。若松監督との思い出もある。丁度、2011年公開の「11・25、自決の日!三島由紀夫と若者たち」を見に行った時だ。若松孝二の名は昔から知っていた。『ピンク映画の黒澤明』と言われていた。ピンク映画はセックスシーンがある。要するにお色気映画だ。しかし若松孝二の作品は単なるポルノではない。制約としてのセックスシーンはあるがそれで見せる映画ではない。どれも低予算映画なれども若松孝二の反骨精神、いや反逆精神か、それが漲って居る。でも私は実はピンク映画時代の若松監督の映画のDVDは「胎児が密漁する時」「腹貸し女」「新宿ジャック」ぐらいしか持っては居ない。どれも強烈な作品ですが。。。
「11・26、自決の日。三島由紀夫と若者たち」のトーク・ショーにて撮影。


若松孝二は震災後に何を撮ったのか?
でも。私は若松監督が、一般映画を撮るようになった頃からの作品をよく観て居る。交通事故で死ぬまでに撮った映画だ。「飽食」「17歳の風景・少年は何を見たのか」「実録・連合赤軍浅間山荘への道程」「キャタピラー」「11・26、自決の日 三島由紀夫と若者たち」「海燕ホテル・ブルー」そして遺作と成った「千年の愉楽」などです。「11・25、自決の日・三島由紀夫と若者たち」を当時既に認知症だった母を連れて見に行ったのだが、トーク・ショーが上映後にあって、主演の井浦新さんやらと若松監督のトークが聞けたのだけれども。私は拍手をしていたら、監督が気付いて、時間も押しているからと行って次回作の「千年の愉楽」の予告編を掛けたのだけども、映画館の暗闇の中で予告編が掛かる前に、ふと人の気配がして横を向いたら、監督が温和な笑顔で立って居た事があった。その時に私は立ち上がり握手をして。サインをパンフレットにして貰った。監督はその時、「東電を叩く映画を作るよ。」と言って居たが、新宿の道を横断中に左からきたタクシーに跳ねられて亡く成ってしまった。芳雄さんはその前に映画「大鹿村騒動記」の舞台挨拶に車椅子で現れてから、間も無く亡くなって居る。二人は今は天国で映画を撮って居る事だろう。
ピンク映画時代の逸話を映画にした映画「止められるか、俺たちを」がDVD発売されました。詳しくはこの記事の前の私のBlogで詳細を乗っけています。
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『火の魚』
さて、原田芳雄さんの晩年のTVドラマです。あまりの評判の為、1時間余りながら劇場公開もされました。DVDはAmazonで購入出来ます。名作ドラマです。海外の賞も受賞しました。下の映像はダイジェストです。この映像だけで判断するのではなく、レンタルで良いので見て下さいね。
Image of 火の魚
瀬戸内・大崎下島を舞台に、世間から取り残された孤独な老人と、
時を慈しむように生きる若い女性が、心を通わせていく「命」の物語。
【ストーリー】
広島の小さな島から届けられる物語。テーマは「命の輝き」。島に住む老作家・村田省三(原田芳雄)のもとに、原稿を受け取るため東京の出版社から女性編集者・折見とち子(尾野真千子)が通ってくる。小説家と編集者は、年は違うがプロ同士。たがいに一歩も譲らず、丁々発止のバトルが繰り広げられる。あるとき小説の想定を、燃えるような金魚の「魚拓」にしたいと思いついた村田は、折見に魚拓を作ることを命じる。魚拓を取るには、金魚を殺さなければならない。小さな命をめぐって、二人の間にさざ波が立つ。
やがて村田は、折見の“秘密”を知ることになる…。
【キャスト】
原田芳雄、尾野真千子、高田聖子、岩松了 ほか
【スタッフ】
原作:室生犀星
脚本:渡辺あや
音楽:和田貴史
監督:黒崎博
<受賞歴>
★平成21年度(第64回)文化庁芸術祭大賞
★第36回放送文化基金賞優秀賞、演技賞(尾野真千子)、脚本賞(渡辺あや)、演出賞(黒崎博)
★平成21年度芸術選奨文部科学大臣新人賞(演出:黒崎博)
★ヒューゴ・テレビ賞奨励賞
★第50回モンテカルロ・テレビ祭・ゴールドニンフ賞(テレビ映画部門)
★第62回イタリア賞・単発ドラマ部門・最優秀賞(イタリア賞)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「ケロベロス・地獄の番犬」
同じ押井守の作品である『紅い眼鏡』の続編。物語は前作の続きではなく、冒頭部の都々目の国外脱出から、帰国するまでの中間に当たる。
低予算であった前作から大幅にスケールアップしており、前作では3体しか製作されなかったプロテクトギアは、本作では2000万円の予算をかけてケルベロスの頭部の数にちなみ50体が造られた。香港や台湾での長期ロケも敢行され、香港では銃器メーカー寶力道具有限公司の協力により日本では不可能な実銃による撮影が行われた。
「ストーリー」
荒廃と腐敗にまみれた近未来都市・東京。従来の自治体警察の治安力をはるかに越えた組織的な犯罪がはびこる中で、「首都警」こと首都圏治安警察機構が生まれた。首都警は次第に強力な権力を発揮するようになり、外部からの批判も高まるが、核部隊ケルベロスの批判は激しかった。そしての50名の特機隊からなるケルベロスが解体の危機に瀕する中で何人かが反乱を起こした。乾もその一人だったが、彼らの力も治安部の膨大な力の前では無力に過ぎず、ただ一人国外逃亡を果たした都々目を除いて、全員鎮圧されてしまう。三年後、出所した乾は、都々目の居所に関する情報を得て出国する。乾にとって都々目は兄と慕うほどの存在だった。謎めいた白服の男の手引きで、乾は都々目のアジトを訪ねたが、そこには都々目の姿はなく、彼の愛人だという少女・タンミーがいた。都々目の行方を追い、旅に出る二人と、その後を密かに追う白服の男。やがて思いがけない場所で都々目と再会した乾は、しばらくそこで幻想的な日々を送るが、次第に都々目の裏切りという真実か明らかになる。それを知って激しいショックを受ける乾。そんな時、白服の男によって、彼らに攻撃を仕掛けてくる特殊公安部を相手に、乾はプロテクト・ギアを身につけ、ただ一人破滅に向かっていく。そして、そんな乾の最後を見届けた都々目は東京へと舞い戻るのだった。
Stray Dog (映画本編ノーカットです)
主を失った犬の放浪。女に拾われた犬の放浪。犬が最期に選んだ主とは一体なんだったのか。ケルベロスサーガ全般に、言える事ですけど、彼らは前提からして敗者と言うか、「もう必要がない。」と言う烙印を押されてしまって居る訳ですが。そんな彼らがそれでも何か行動を起こそうとする。それで別に何かが変わる訳でも無いのだけど……とにかく、客観的に観てお薦めって映画では全く無いんです、でも。しみじみ「いいなぁ」と思えますね。押井さんは、とにかく広角レンズをローアングルで撮る撮影が楽しくて仕方なかったとの事。押井監督に言わせると、野良犬の目線で撮った映画だそうだ。「紅い眼鏡」の方は哲学的と言うか、この「ケロベロス・地獄の番犬」は一遍の「詩」見たいな映画。「紅い眼鏡」の前日談だけども、この映画だけ観ても解ります。