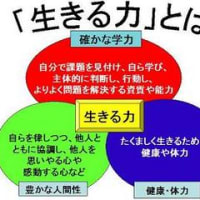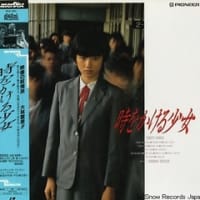曇天の空。雨の薫りが立ち込めています。少し気分が晴れませんが、仕事先に向かうために散歩がてら出かけましたが、たまたま入った喫茶店で、コーヒーを頼みます。さりげなく出されてきたのは、アンティークものと思しきコーヒーカップ。
思わず、「ほうっ」と感嘆の声をあげる。
19世紀頃のカップかなと、ツタや薔薇で縁取られた美しいカップにしばらく見とれて、ふと前を見上げると、店長が察してか説明してくれました。
19世紀ベル・エポックの頃の陶器で、西洋と東洋の文明的交流が見事に陶器に反映されていますと。
思わず、感嘆をあげたのは、やはり美しいものは美しいから。
それにしても、こういう貴重なカップを出すと、割られたりして心配になりませんかと尋ねる池田。
冗談交じりに次のように店長が語る。わたしが提供したいのはコーヒーだけではありません。時間と場所。お客様の心を察してそれにふさわしいカップでお出しするのが私のできるささやかなこと。
失礼ながらお客様を拝見してお似合いかと思ったのが、このカップでしたので。カップも使って眺めるから価値があるので、ただ眺めるものでもありません。
お客様が思わずため息を漏らされたので、こちらの心も豊かに満たされました。ありがとうございますと。
この一言に胸が熱くなるのでした。このお店のおかげで心が満ち歴史の一幕に身がおけた心になれたのですから。
美とは歴史を超えて受け継がれる普遍的なものだと改めて実感できた一時でした。
ところで、歴史といえば、NHKで放映されている「そのとき歴史は動いた」。
基本的に一事件や一人物を取り上げて、その一事例があたかも歴史の全体が動いて印象を与えるため、池田は好みません。
歴史は諸要素がもっと複雑に絡み合って動いていくものだと考えているから。
とはいえ、昨日の古事記成立に関わるテーマは考えさせました。
古事記研究は、成立論(いつ誰によって書かれたか、偽書かどうか等)と作品論(作品内容、メッセージの分析)に分かれます。
番組では、その両者に触れながら、古事記が歴史に与えた影響について説明しようというもの。
『古事記』は壬申の乱に勝利した天武天皇が歴史を編纂するよう命じられてから取り組まれ、天皇の死後、しばらく中断しましたが、元明天皇の命令で再開され、太安万侶と稗田阿礼によって作られたと言います。
番組を要約すると、古事記の機能は以下の三点。
(1)壬申の乱によって天智系と天武系に二分された結果、国の統一が豪族間の意識のレベルでも図られないことから、共通の歴史を作成することで意識の上で国家の統一を図ろうという意図があった。
(2)内容については、王朝の正当性、権力秩序を示すことを意図していた。以下の4点が示される。
(a)多くの土着の伝承や豪族たちがもっていた歴史を『古事記』に取り込み、天皇家の歴史のもとに組み直し歴史の共有化を狙った。
(b)古事記のなかの神々の住う高天原の登場は、絶対的な存在である神を祖先に頂く天皇家の正当性を暗示している。
(c)天の岩戸の物語は太陽神天照大神が岩戸に隠れたが、神々の協力で天照大神を引き出すのに成功し、世界の秩序が保たれた。つまり、天皇を中心とする国の秩序が豪族の協力によって保持されることを暗示。
(d)天孫降臨では、神の子であるににぎのみことを地上の神である猿田彦が迎える。天皇は諸豪族を専制的に支配したのではなく、豪族らが進んで迎えたことによって支配の正当性を確保したのだという暗示。恐らく、事実というよりも政治的正当性を示すイデオロギーとしての役割を果たしたのでしょうね。
(3)編纂にあたって、稗田阿礼が大安万侶に語り聞かせたり、「読み方を教えた」ことになっているが、恐らくは多くの読み方や記述のされ方のあった表記を誰も読めるように統一をしたのだろう。ここには、改めて、それまで漢字が当てはめられなかった言葉に漢字をあてるという日本語創出作業が伴ったことは言うまでもありません。
だとしてみると、国家の歴史の編纂は、自らの権力の正当性を示しながら、同一の歴史と言葉をもっているという意識を人々に植え付けながら、統一を果たそうとする機能にほかなりません。
実は、この機能。明治期に同じ歴史と言葉をもった国民を育成するために、国家が学校教育に「国史」と「国語」を導入した経緯に似ています。
思わず考えさせられたのだよね。
思わず、「ほうっ」と感嘆の声をあげる。
19世紀頃のカップかなと、ツタや薔薇で縁取られた美しいカップにしばらく見とれて、ふと前を見上げると、店長が察してか説明してくれました。
19世紀ベル・エポックの頃の陶器で、西洋と東洋の文明的交流が見事に陶器に反映されていますと。
思わず、感嘆をあげたのは、やはり美しいものは美しいから。
それにしても、こういう貴重なカップを出すと、割られたりして心配になりませんかと尋ねる池田。
冗談交じりに次のように店長が語る。わたしが提供したいのはコーヒーだけではありません。時間と場所。お客様の心を察してそれにふさわしいカップでお出しするのが私のできるささやかなこと。
失礼ながらお客様を拝見してお似合いかと思ったのが、このカップでしたので。カップも使って眺めるから価値があるので、ただ眺めるものでもありません。
お客様が思わずため息を漏らされたので、こちらの心も豊かに満たされました。ありがとうございますと。
この一言に胸が熱くなるのでした。このお店のおかげで心が満ち歴史の一幕に身がおけた心になれたのですから。
美とは歴史を超えて受け継がれる普遍的なものだと改めて実感できた一時でした。
ところで、歴史といえば、NHKで放映されている「そのとき歴史は動いた」。
基本的に一事件や一人物を取り上げて、その一事例があたかも歴史の全体が動いて印象を与えるため、池田は好みません。
歴史は諸要素がもっと複雑に絡み合って動いていくものだと考えているから。
とはいえ、昨日の古事記成立に関わるテーマは考えさせました。
古事記研究は、成立論(いつ誰によって書かれたか、偽書かどうか等)と作品論(作品内容、メッセージの分析)に分かれます。
番組では、その両者に触れながら、古事記が歴史に与えた影響について説明しようというもの。
『古事記』は壬申の乱に勝利した天武天皇が歴史を編纂するよう命じられてから取り組まれ、天皇の死後、しばらく中断しましたが、元明天皇の命令で再開され、太安万侶と稗田阿礼によって作られたと言います。
番組を要約すると、古事記の機能は以下の三点。
(1)壬申の乱によって天智系と天武系に二分された結果、国の統一が豪族間の意識のレベルでも図られないことから、共通の歴史を作成することで意識の上で国家の統一を図ろうという意図があった。
(2)内容については、王朝の正当性、権力秩序を示すことを意図していた。以下の4点が示される。
(a)多くの土着の伝承や豪族たちがもっていた歴史を『古事記』に取り込み、天皇家の歴史のもとに組み直し歴史の共有化を狙った。
(b)古事記のなかの神々の住う高天原の登場は、絶対的な存在である神を祖先に頂く天皇家の正当性を暗示している。
(c)天の岩戸の物語は太陽神天照大神が岩戸に隠れたが、神々の協力で天照大神を引き出すのに成功し、世界の秩序が保たれた。つまり、天皇を中心とする国の秩序が豪族の協力によって保持されることを暗示。
(d)天孫降臨では、神の子であるににぎのみことを地上の神である猿田彦が迎える。天皇は諸豪族を専制的に支配したのではなく、豪族らが進んで迎えたことによって支配の正当性を確保したのだという暗示。恐らく、事実というよりも政治的正当性を示すイデオロギーとしての役割を果たしたのでしょうね。
(3)編纂にあたって、稗田阿礼が大安万侶に語り聞かせたり、「読み方を教えた」ことになっているが、恐らくは多くの読み方や記述のされ方のあった表記を誰も読めるように統一をしたのだろう。ここには、改めて、それまで漢字が当てはめられなかった言葉に漢字をあてるという日本語創出作業が伴ったことは言うまでもありません。
だとしてみると、国家の歴史の編纂は、自らの権力の正当性を示しながら、同一の歴史と言葉をもっているという意識を人々に植え付けながら、統一を果たそうとする機能にほかなりません。
実は、この機能。明治期に同じ歴史と言葉をもった国民を育成するために、国家が学校教育に「国史」と「国語」を導入した経緯に似ています。
思わず考えさせられたのだよね。