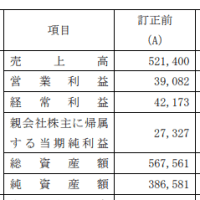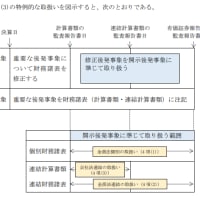「形ばかりの役員会に出席し、高額報酬を受け取る社外取締役がうようよいる」という一般向け解説記事。
取り上げている企業は、日産自動車、本田技研工業、曙ブレーキ工業などです。曙ブレーキの社外取締役だった一橋大学の伊藤邦雄教授(会計学)のことも批判的に書いています(逃げないでコメントしているのは立派)。
まず、日産について。
「日産元幹部はこう憤っている。
「本来、社外取締役には『空気』を読まずに、社長に対して耳の痛いことを意見具申する機能が求められる。しかし今回の日産の人選を見ると、西川(廣人)社長に意見するどころか、忖度しそうなメンバーばかりではないか」
カルロス・ゴーン前会長による事件を受け、日産は、ガバナンス改革の目玉として、社外取締役が中心となる「指名委員会等設置会社」への移行を打ち出した。
選任された11人の取締役のうち7人が社外取締役となる。6月25日の定時株主総会で、移行のための定款変更が承認された。」
「3委員会のうち2委員会のトップが経済産業省関係者だ。指名委員会委員長には、同省で事務次官に次ぐナンバー2・経済産業審議官をかつて務めた豊田正和氏、報酬委員会委員長には元同省産業構造審議会委員でレーサーの井原慶子氏がそれぞれ就任した。」
「ゴーン氏の事件では、日産は検察庁と一体となって立件に協力し、今後の裁判でも引き続き協力し合う関係にある。経産省や同省関係者を社外取締役の主要ポストに就けたのは、「政府への忖度」と見られても仕方ない。」
「監査委員会委員長には、かつての日産のメーンバンク・旧日本興業銀行出身の永井素夫氏が選任された。
バブル崩壊まで、日本経済を牛耳る象徴は「興銀、日産、通産省(現経産省)」と揶揄された。時代は変わったとはいえ、永井氏の選任は、一種の「身内人事」と映る。」
曙ブレーキについて。
「今年1月29日、自動車部品大手の曙ブレーキ工業が事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)を申請、経営破綻に近い状況に追い込まれた。社長の信元久隆氏は、トヨタの取引先部品メーカーでつくる「協豊会」会長も務めた、業界の名門企業だ。」
「経営悪化の表向きの理由は米国事業の低迷だが、同社の元役員はこう打ち明ける。
「信元さんの独裁体制が続いたからです。秘書部の予算が無尽蔵にあり、工場に投資するよりも派手な接待が大好きな経営者だった。しかし、信元氏への反対意見を言おうものなら、執行役員でもすぐに退任させられた」
この元役員は「社外取締役も意味をなしていなかった」と断言する。
同社で社外取締役を務めてきたのが、「ミスター社外取締役」の異名を持つ一橋大学特任教授(会計学)の伊藤邦雄氏だ。
これまで東京海上ホールディングス、住友化学、東レ、セブン&アイ・ホールディングスなど日本の有名企業に社外取締役として名を連ねてきた。
しかし伊藤氏は、曙ブレーキの苦境が伝えられるやいなや、今年6月で社外取締役を退任した。
「信元社長は聞く耳をもたないうえ、学者だから火中の栗を拾う覚悟もないので辞めたのでは」(同社関係者)という。」
「現在も東レほか3社の社外取締役を務める伊藤氏を取材すると、自ら退任したことを認めたうえで、こう語った。
「僕自身は、すみずみまで監査に行くことはできないが、主要な会議に出て、経営トップがどのような発言をしているか、他のボードメンバーに威圧的な言い方をしていないか、企業風土は見るようにしています」」
兼務している会社数が多い社外取締役について。
「今年2月に報じられた東京商工リサーチと朝日新聞の調査によれば、東証一部の社外取締役のうち、4社以上兼務する社外取締役がいる企業は約300社にのぼる。兼務社数の最多は8社で3人。」
結論は...
「よそからやってきて、都合が悪くなれば逃げ出せる社外取締役に、企業の重要な決定を任せようとすること自体が間違っているのではないか。
企業の側も本音ではそう思っているから、お飾りで無害な社外取締役を選ぼうとする構図が浮かぶ。
日本の企業をダメにするのは、それを食い物にする社外取締役である。」
企業をダメにするほどの影響力はないように思われますが...。
このインタビュー記事の意見の方が正論なのでしょう。
↓
「出世して取締役」の勘違い おかしな日本の企業統治
カルビー元会長 松本晃氏(日経)
「日本では、経営の執行役と取締役会が一体化してしまっている。これはガバナンスの点では明らかにおかしいんです。だから僕は、カルビーで「本来のガバナンスをやります」と念押しし、松尾家の了承を得たわけです。その結果、当時の「役員」には、仕事に専念するために執行役員になってもらい、取締役は辞めてもらいました。代わりに社外取締役を大幅に増やしたんです。
取締役と執行役では、どちらが偉いと思いますか。会社のかじを取る、ビジネスを進めるという意味では、執行役の方がはるかに偉いんです。取締役は、名前の通り取り締まる役、お目付け役です。場合によっては、会社のやり方に異議を唱え、改めさせる力を発揮するし、株主に対する重い責任も負っていますが、実際に会社を動かすのは執行役なんです。日本では長く、取締役のことを重役と呼んできました。だからサラリーマンは出世して取締役になるのが偉いと勘違いしてしまった。当たり前のことがわからなくなるんだから、不思議ですよね。
ただ、取締役を全員社外にすると、会社のことをよく知る人がいなくなってしまいます。だから1人か2人は社内から出してもいいんです。カルビーに入ったとき、僕はスナックのことはまったくわからなかったので、伊藤秀二社長にも取締役になってもらいました。結局、社内の取締役は9人から2人に減らし、社外取締役を2人から5人に増やしました。」
「(社外取締役の)人選で一番大切なのは、とにかくうるさい人を選ぶことです。当たり前ですよ、株主に代わって経営を監視するんだから。監視役がおとなしくしていたら何の意味もありません。」
「カルビー時代、僕は社外取締役への事前の根回しは一切しませんでした。「今度の取締役会でこんな案件を出しますから、ひとつよろしく」というようなまねは、絶対しなかった。だから案件がなかなか通らなくて、3件に1件くらいは却下されたと思います。特に新規の案件は通らなかった。うるさい社外取締役から「顔を洗って出直してこい」と言われる。「わかりました」と言って、次の会議に出し直すんです。
社外取締役と食事をしたことも、ほとんどありません。宮内さんと雑誌の企画で対談したときに一度あったくらいで、茂木さんとも高原さんともなかった。議論は取締役会ですればいいので、場外で僕が何か言う必要はない。従って飯を食う必要もない。これも当たり前のことですよ。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事