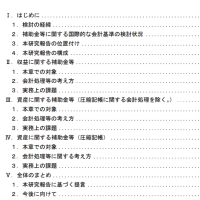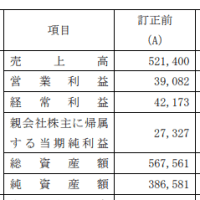日本公認会計士協会は、米国財務会計基準審議会(FASB)が公表したコメント募集「識別可能な無形資産及びのれんの事後の会計処理」に対して提出したコメントを、ウェブサイト上で公開しました。
主な質問項目とそれに対するコメント(一部抜粋)は以下のとおり。
「2. 現行ののれんの減損モデルによって提供される情報の便益は、当該情報の提供のコストを正当化するか。賛成又は反対の理由をコストと便益の文脈で説明されたい。
【コメント】
のれんの減損テストは、のれんが配分された単位から生じるキャッシュ・フローの予測など、経営者の見積りが関与する割合が大きい手続きである。会計上の見積りは、監査上最も慎重な対応が求められる領域の一つであり、のれんの減損テストはその代表格である。
減損のみモデルと減損テスト付きののれん償却モデルを比較すると、以下のとおり、減損のみモデルの方が、のれんの減損テストに関する監査上のリスクが大きいことが考えられる。減損のみモデルでは、のれんの価値の減少が減損テストを通じてしか財務諸表に反映されないため、会計上の見積りの結果が財務諸表に与えるインパクトが大きくなる。また、のれんが償却されないことにより、減損テストが要求される期間が長期にわたるケースがあるが、一般的に、企業結合後一定期間が経過すると、事業の統合や変化などにより、のれんの減損テストに要する見積りの要素がより大きくなることが多い。 」
「3. コストと便益のベースで、現行の減損のみのモデルと比較して、減損テスト付きののれん償却を支持するか(又は反対するか。)。回答において理由を説明されたい。
【コメント】
減損テスト付きののれんの償却を支持する。
我々は、取得日に認識されたのれんの価値は、企業結合後の期間にわたって減少すると考えるため、償却を通じて価値の下落を財務諸表に認識すべきであると考える。のれんの減損テストには、取得日後に生じた自己創設のれんによって、取得したのれんの減損が覆い隠される構造的な問題があるため、減損のプロセスのみを通じて、自己創設のれんの認識を排除することができない。のれんの償却は、当該構造的な問題を緩和する効果があると考えられる。
なお、質問2で言及した監査上のリスクは、減損のみのモデルと比較すると、減損テスト付きののれんの償却モデルの方が低くなると考える。」
このほかの、のれんの償却期間やのれん減損テストの頻度・グルーピングといった論点についても、ほぼASBJのコメントと同じなようです。ただし、償却期間の10年という上限は示していません(現行日本基準の 20 年以内という規定を紹介しているだけ)。
最近の「日本公認会計士協会(会計)」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事