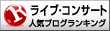久しぶりに登場したコーラスワークが光るR&Bグループ。
ミネアポリス出身のパリス&アンバー・ストローザーの双子姉妹とコンプトン出身のアニタ・バイアスによるガールズ・グループ“キング”の初来日公演がビルボードライブ東京で行なわれた。会場はビルボードライブ東京。
2016年のR&Bシーンで話題のグループとはいえ、1st、2ndショウともにソールドアウトという人気ぶりに少しばかり驚いていたのだが、平日月曜の夜といってもゴールデンウィークの真っただ中ということもあってほぼ満席。BGMにミュージック・ソウルチャイルドが流れる中、会場を見渡してみると、(外見で判断してはいけないのだが)おそらくあまりブラック・ミュージックを聴いていないのだろうと思しき観客がそこそこ席を埋めていた感が。目下、その悲しきニュースによって話題が絶えないプリンスが熱烈に支持してオープニングアクトに起用したとか、ロバート・グラスパーが『ブラック・レイディオ』でフィーチャーしたとかという話の流れで注目を浴びたのかもしれない。
そのロバート・グラスパー・エクスペリメントやアヴィーチー、ビラルらの作品への参加、エリカ・バドゥ、ケンドリック・ラマーほかが絶賛するなど軒並み評判の高い彼女たちが、デビュー・アルバム『ウィー・アー・キング』を引っ提げての来日。ノスタルジックなR&Bをベースにネオソウルやエレクトロニックなアプローチを施した楽曲が特色だが、そのサウンドをライヴでどのように表現するのかを非常に楽しみにしながら、彼女らの登場を待った。

ステージに置かれたのは前方に2本のスタンドマイクと中央に4、5台のキーボードとラップトップ(Mac)を据えているのみ。ベースもドラムもなく、キーボード系で全てを構築してしまおうというのが今っぽい“構築”なのだろうか。単純にミニマムといってしまえばそれまでだが、全てのプロデュースおよびエンジニアリングと演奏のほとんどをパリスが担い、ライヴパフォーマンスではサポートを入れずに3人で完遂するという姿勢は、他の誰にもコントロールされないという意志を込めて名付けたそのアーティスト名からも窺える。
全員総立ちの大ダンス・パーティや煽るようなシャウト、ステージを所狭しと動き回る激しいパフォーマンスなどは一切ない。パリスがおもむろに指を置いてから鳴り出す鍵盤とアンバー、アニタのコーラスだけが空間を埋めていく。だが、その音空間は決して“ミニマム”ではなく広がり豊かなもの。しかも、ソウルというよりアーバン・コンテンポラリーな正統派R&Bに近く、実に耳や肌に滑らかに溶け込んでいく。2曲目に懐かしいTVゲーム風の8ビット画像を駆使したPVが印象的で、モハメド・アリ賛歌にもとれる「ザ・グレイテイスト」を出し惜しみすることなく披露。その後、「ザ・ライト・ワン」などデビュー・アルバムの楽曲をしっとりとしたゆるやかな時間を漂わせながら、しかしながらも内なる炎を燃やすかの如く静かな熱情を発していく。

この日の最大のトピックは、何といってもプリンスへ捧げられた時間だろう。中盤で「スーパーナチュラル」を終えると、パリスが私たちをファミリーへと迎え入れたプリンスへ捧げると語ってから「ヘイ」へ。星空を映し出したかのようなライティングに変わるやいなや、アンバーは涙を拭いながら、主旋律を歌うアニタは努めて平静を装うように屈託ない清澄なヴォーカルで、かの地へ旅立った天才に思いを馳せる。“シューティングスター”というリリックがあるものだから、プリンスへ少なくない思いを持つ観客もきっと心に流れ星を描いたことだろう。演奏に徹しようとしていたパリスは演奏後に涙を拭いていた。その後、すぐに「キャリー・オン」へ移ったのは、このままだと涙に暮れてしまうかもしれないということだったのだろう。
もう一つのトピックは、スティーヴィー・ワンダーのカヴァー。1976年の『キー・オブ・ライフ』に収録された「オール・デイ・サッカー」だが、原曲とは異なるエレクトロR&B的なスタイルでのカヴァーで、そのあたりは80~90年代の音を咀嚼して新たに彩色していく2010年代以降の手法か。大きな影響を与えた人物のなかにもちろんスティーヴィ・ワンダーも入っているのだが、このスティーヴィーの原曲は、どこかミネアポリス的なファンクネスが包含しているようで、そんなプリンスやジャム&ルイスが垣間見られるような選曲をするところにも彼女らなりの“意図”があったのかもしれない。

「ネイティヴ・ランド」で本編を終えると、アンコールではロバート・グラスパー作品より「ムーヴ・ラヴ」を。ドリーミーなライティングもあって、静かなる海中で海中散歩をしている錯覚に陥りそうな深くミステリアスなムードが満ちていく。コーラスワークにはゴスペルの土台を感じるも暑苦しさは皆無で、空間をソフトに包み込んでいくハーモニーが実に耳当たり良い。ネオソウルの濃密さを湛えながらもエレクトロニックにフィットする煌びやかな音鳴りは、“R&Bの未来を背負える申し子”と言えそうなほど。プリンス以下が絶賛したのも頷けるというものだ。メロウながらも漆黒の低音ボトムとコーラスを携えて繰り広げられる音絵巻は、下品な絢爛さではなく趣きに溢れた華やかな美しさ。肉体的な激しさはなくとも、見事に多種多彩に心情を揺り動かした、刺激的なステージだったといえよう。
敢えて足りないところを言えば、経験値が少ない分、初々しさが露見した。とはいえ、そのこなれた感覚を掴むのも時間の問題だと思う。最後に各自の名前を伝えてから、“ウィー・アー・キング”と声を揃えてステージ・アウトしていった彼女たち。自ら自分たちがやるべき世界観を理解し、それを背伸びや理想だけに囚われることなく、やるべきこと、やるべき音楽を構築・表現することに精を出す彼女たちが、女性グループでありながらも“キング”と名乗る意味が、少しだけ分かったような気がした。

◇◇◇
<MEMBER>
KING are:
Paris Strother
Amber Strother
Anita Bias
◇◇◇