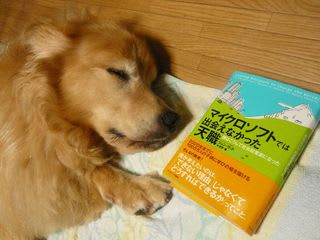
再び「鰻」の話から始まる。どうも周辺にいる学生どもは、鰻という食べ物を、あまり好まないらしい。普通、「鰻、食べよう」とかって言えば、飛んで火に入る夏の虫みたいに喜ぶはずだと思うのだが、鰻はあまり食べたくないとか、鰻のタレなら好きですとか、うちは土用は中華丼を食べるとか、まったく日本古来の伝統をバカにしてるかのような言い分である。我々は、子どもの頃、近所の川に夜釣りに出て鰻を釣るのが楽しみだったし、釣った鰻を蒲焼に捌いてしまう父親の包丁捌きに尊敬の念を抱いたものである(私の中では、鰻や鱧を捌けるというのが、包丁使いの目標であったが、未だそのような機会は与えられずにいる・・・)。
尤も食べ過ぎると体を壊すのが鰻であるから、程ほどにしなきゃならない・・・無念でものである。
* * * * * * * * * *
さて、ジョン・ウッドの書いた『マイクロソフトでは出会えなかった天職』って本を読んでました。面白い本ですので、暇な人は、時間があったら御一読を。暇だから本を読む・・・って、いい感じです。暇だからボランティアをする、ってのと同じくらいに素敵です。夢を探す若者も、こーいう本を読むべきだし、夢を失いつつある成人全般も、こーいう本に出会うべきですね。
面白いもので、暇だから・・あるいは暇じゃなくても取り組んだことが、どんどん加速度的に進行して手放せなくなってくる・・・そーいうことって、あるでしょ。何でもいいんだけど、そーいう高揚感がないと、やはり人生はつまならい。
ちょうど、考えてることと、取り組んでることと、やってることと、やらなきゃならないこと・・・それがうまく一致しないで動いてることが多い昨今なので、ついつい現実と違うことに目が行くわけです。でも、やらなきゃならないことばかり考えてたら、きっっと行き先が詰まってしまうし、現に行き詰まっている。そう、跳ぶための、何らかの追い風がどっからか吹いて来ないか・・・いつもぼんやりしながらでも夢見てないと、それが吹いてたときにも気付かなかったりするわけで、結局どこかでガツガツ飢えてなければならない☆ってなるわけです。まぁ、「現実と違うこと」に目が行ってしまってたって、どうせしっかりループ状に繋がってることばかりなので。結局は同じことを考え続けてるし、やり続けているだけなんだけどね。
最近は、「活動の振り返り」をやらなくなった(やれなくなった)ので、イマイチ読み切れないことがあるんだけど、活動の評価は、微妙な判断を強いられることがあるのだが、参加のリピート率によって問うことができる。「もっとうまくやれる方法がある」のは分かってるので、そんな技術論をしたいわけじゃない。テクニカルな部分で話をしても構わないけど、じゃぁ、こっちの希望に応じられるだけの力量と融通性と、何よりも忍耐力があるか?となると難しいので、そこは伏せてるわけです。
自分たちがやってることが、どんなふうに繋がって行くのか・・・を、希望を持って考えてもらえると、ちょっと嬉しい。どうせ、あまり大きな規模の活動になんかやらないので(そーいう組織的な活動は、今のところ違うところでやってもらえればOKなので)、小さいアクションの中で・・・小さい規模だからこそ、今動いてることの大枠を捉えること、個々の状況がどうなっているかを予習復習していくこと、これがしっかりやれると、どんな方向へ動いているのかが分かる。分かると、意味が変わってくる。変わってくれば、多分やってることの意義が、少なくとも自分の意識レベルでは変わってくる。・・以前はここまで強いたんだけど、今はそこまで強いないでやってる。自分の意識が低くなったとも言っちゃってもいいんだけど、それよりは「ステップの歩幅を自由に設定して良いよ」って暗黙で伝えている・・・つもりなのである。
* * * * * * * * * *
「夢と希望と可能性」を提示することは、実は難しい。様々な非営利団体があって(営利でも構わないが)、それらがきっと、同じように「夢と希望と可能性」を唱え続けている。でも、そんなにそれらが実感できることはない。ほら、夢と希望を語っていた非営利団体は、いつしか財政問題と人材についての嘆きを語ることに追われ続けてしまう・・という話は、未だに尽きることじゃない。挙句の果てに日本では、あれだけ騒いだNPO法人を、認定公益法人に書き換えようとするわけで、別にそれは精査するのだから悪いことじゃないんだろうけど、まぁ、淘汰されちゃうか、見切りを付けさせるって部分も多いんでしょう。きっちりした形じゃなくても、いろんなことができる可能性はあった方がいいのに、日本はやたらと枠組みがきっちりしてることを好むので、結局「力の、ある部分」を削いでしまっちゃうことがあるように思うわけです。
ただ、思うのは、「夢と希望と可能性」のうち、どれかを持って、何かをやろうとした記憶があると、それって案外奥底に残っているもので、いつかそのアイディアを実現しようと、事有る毎にそれが甦ってくるものなわけです。
フローとストックみたいなものです、はい。活動自体は、人が入れ替わっても全然問題ないし、活動レベルが高かろうが低かろうが、そんなに意味はない。大事なのは、それが個々レベルで構わないので記憶や体験として、しっかり蓄積されていくかどうかなので、ついでに言えば、その蓄積を元に、自分がいつかどのようなことをやり始めるか・・・こそが大きいことなわけです。
主催者というか、「この指とまれ」で行ってる活動は、どうしても「この指とまれ」を掲げた人の声が、大体一番大きい。でもそれは、フォロワーにとって、いつも決してベストとは限らない(勿論、掛け声を掛けてる者にとってもベストとは限らない)。だから平然と「駒」とか「兵隊」と言う。今は「乗ってる」ことで十分かもしれないが、いつかそれで十分じゃなくなったら、「この指とまれ」を掲げればいい。その時、プロトタイプとしての経験や体験が、ほんの少し役に立てばいいなーって思う。
・・・・でも、毎日思ってることは、「組織事業は疲れるなー」ってことです。
「いま、やれる」志がある人たちと、しっかりゲリラ活動ができるのなら、多少の御幣はあるかもしれないけど、協力者の置かれている状況を踏まえて、なお、社会的にも意味のある活動と役割を、しっかり提示し、実践できる自負がある。でも世の中は、往々にして目指すものとか取り組みたいと思えるものへ最短コースで進むことを認めてはくれない。
まぁ、空から兵隊が降ってくるのはパラシュート部隊が攻めてくる時くらいなものなので、やはり耐え難きを耐え、苦労に打ち拉がれながら、兵隊を揃えていかなきゃ、戦力は揃わないし、何よりも戦力を揃えるに値するだけの力が伴って来ない。いつもと同じことです、やはり図面を描き続け、地上戦に臨むための準備をして、「さぁ、行こう」と声を挙げる以上に、面白いことも意味のあることも、ないのだ。
尤も食べ過ぎると体を壊すのが鰻であるから、程ほどにしなきゃならない・・・無念でものである。
* * * * * * * * * *
さて、ジョン・ウッドの書いた『マイクロソフトでは出会えなかった天職』って本を読んでました。面白い本ですので、暇な人は、時間があったら御一読を。暇だから本を読む・・・って、いい感じです。暇だからボランティアをする、ってのと同じくらいに素敵です。夢を探す若者も、こーいう本を読むべきだし、夢を失いつつある成人全般も、こーいう本に出会うべきですね。
面白いもので、暇だから・・あるいは暇じゃなくても取り組んだことが、どんどん加速度的に進行して手放せなくなってくる・・・そーいうことって、あるでしょ。何でもいいんだけど、そーいう高揚感がないと、やはり人生はつまならい。
ちょうど、考えてることと、取り組んでることと、やってることと、やらなきゃならないこと・・・それがうまく一致しないで動いてることが多い昨今なので、ついつい現実と違うことに目が行くわけです。でも、やらなきゃならないことばかり考えてたら、きっっと行き先が詰まってしまうし、現に行き詰まっている。そう、跳ぶための、何らかの追い風がどっからか吹いて来ないか・・・いつもぼんやりしながらでも夢見てないと、それが吹いてたときにも気付かなかったりするわけで、結局どこかでガツガツ飢えてなければならない☆ってなるわけです。まぁ、「現実と違うこと」に目が行ってしまってたって、どうせしっかりループ状に繋がってることばかりなので。結局は同じことを考え続けてるし、やり続けているだけなんだけどね。
最近は、「活動の振り返り」をやらなくなった(やれなくなった)ので、イマイチ読み切れないことがあるんだけど、活動の評価は、微妙な判断を強いられることがあるのだが、参加のリピート率によって問うことができる。「もっとうまくやれる方法がある」のは分かってるので、そんな技術論をしたいわけじゃない。テクニカルな部分で話をしても構わないけど、じゃぁ、こっちの希望に応じられるだけの力量と融通性と、何よりも忍耐力があるか?となると難しいので、そこは伏せてるわけです。
自分たちがやってることが、どんなふうに繋がって行くのか・・・を、希望を持って考えてもらえると、ちょっと嬉しい。どうせ、あまり大きな規模の活動になんかやらないので(そーいう組織的な活動は、今のところ違うところでやってもらえればOKなので)、小さいアクションの中で・・・小さい規模だからこそ、今動いてることの大枠を捉えること、個々の状況がどうなっているかを予習復習していくこと、これがしっかりやれると、どんな方向へ動いているのかが分かる。分かると、意味が変わってくる。変わってくれば、多分やってることの意義が、少なくとも自分の意識レベルでは変わってくる。・・以前はここまで強いたんだけど、今はそこまで強いないでやってる。自分の意識が低くなったとも言っちゃってもいいんだけど、それよりは「ステップの歩幅を自由に設定して良いよ」って暗黙で伝えている・・・つもりなのである。
* * * * * * * * * *
「夢と希望と可能性」を提示することは、実は難しい。様々な非営利団体があって(営利でも構わないが)、それらがきっと、同じように「夢と希望と可能性」を唱え続けている。でも、そんなにそれらが実感できることはない。ほら、夢と希望を語っていた非営利団体は、いつしか財政問題と人材についての嘆きを語ることに追われ続けてしまう・・という話は、未だに尽きることじゃない。挙句の果てに日本では、あれだけ騒いだNPO法人を、認定公益法人に書き換えようとするわけで、別にそれは精査するのだから悪いことじゃないんだろうけど、まぁ、淘汰されちゃうか、見切りを付けさせるって部分も多いんでしょう。きっちりした形じゃなくても、いろんなことができる可能性はあった方がいいのに、日本はやたらと枠組みがきっちりしてることを好むので、結局「力の、ある部分」を削いでしまっちゃうことがあるように思うわけです。
ただ、思うのは、「夢と希望と可能性」のうち、どれかを持って、何かをやろうとした記憶があると、それって案外奥底に残っているもので、いつかそのアイディアを実現しようと、事有る毎にそれが甦ってくるものなわけです。
フローとストックみたいなものです、はい。活動自体は、人が入れ替わっても全然問題ないし、活動レベルが高かろうが低かろうが、そんなに意味はない。大事なのは、それが個々レベルで構わないので記憶や体験として、しっかり蓄積されていくかどうかなので、ついでに言えば、その蓄積を元に、自分がいつかどのようなことをやり始めるか・・・こそが大きいことなわけです。
主催者というか、「この指とまれ」で行ってる活動は、どうしても「この指とまれ」を掲げた人の声が、大体一番大きい。でもそれは、フォロワーにとって、いつも決してベストとは限らない(勿論、掛け声を掛けてる者にとってもベストとは限らない)。だから平然と「駒」とか「兵隊」と言う。今は「乗ってる」ことで十分かもしれないが、いつかそれで十分じゃなくなったら、「この指とまれ」を掲げればいい。その時、プロトタイプとしての経験や体験が、ほんの少し役に立てばいいなーって思う。
・・・・でも、毎日思ってることは、「組織事業は疲れるなー」ってことです。
「いま、やれる」志がある人たちと、しっかりゲリラ活動ができるのなら、多少の御幣はあるかもしれないけど、協力者の置かれている状況を踏まえて、なお、社会的にも意味のある活動と役割を、しっかり提示し、実践できる自負がある。でも世の中は、往々にして目指すものとか取り組みたいと思えるものへ最短コースで進むことを認めてはくれない。
まぁ、空から兵隊が降ってくるのはパラシュート部隊が攻めてくる時くらいなものなので、やはり耐え難きを耐え、苦労に打ち拉がれながら、兵隊を揃えていかなきゃ、戦力は揃わないし、何よりも戦力を揃えるに値するだけの力が伴って来ない。いつもと同じことです、やはり図面を描き続け、地上戦に臨むための準備をして、「さぁ、行こう」と声を挙げる以上に、面白いことも意味のあることも、ないのだ。



















