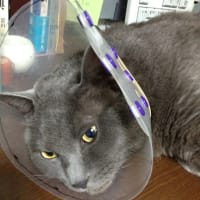***
「それだけ」
「それだけ? 続きはないの?」
「あるといえばあるけれど」
「何?」
「例えば、同じようなことが一週間続いて・・・」
「それで?」
「でも、わたしは二度と踊ったりはしなかった。その老人の前で、有名な詩を朗読したり、歌をうたったりはしたけれど」
「それだけ?」
「うん、それだけ。
それが7日間続いて、8日目の朝、とてもたくさんの花とドレスと靴がアパートに届けられた。その老人からだった。今着ている洋服もそうなんだけれど。
それから、銀行口座にちょっと信じられないくらいのお金が振り込まれていた。金額を言っても、あなた信じないんじゃないかしら」
「それできみはコールガールの仕事をやめることができた」
「そう。それでわたしはすぐに仕事をやめたの。だって、もう働く意味がなくなっちゃったから」
彼女はにっこり笑いながら言った。とても素敵な笑顔だった。本物の夏がそこにはあった。
「だからお礼にその屋敷にもう一度行ってみたの、老人のためにプレゼントを持って。どうなっていたと思う?」
「話の展開からすると、きっと何もなかったんだろうね」
「やっぱりあなたには分かるのね。
そのとおり。そこにはそもそもの最初から何もなかったの。
訪ねていった場所は20年以上前からずっと空き地で、ダコタハウスに似た建物なんて建っていなかった。バーリントンで一番有名な老人なんて住んでいなかったし、そんな老人が本当にいたかどうかさえもあやしいものだった」
「ふうむ」思わず僕はうなってしまった。
「でもね」彼女は続けた。
「うん、でも、ちゃんとメッセージカードも届いたのよ。一週間後に届けられた贈り物といっしょに」
「何て書いてあったの?」
「恥ずかしい」
「ここまでしゃべったんだから言いなよ」
「『私の天使のコールガールへ』って」
僕は思わず噴出してしまった。
「ほんとにそう書いてあったの?」
「うん」
「ふうむ」
僕はもう一度、彼女の前でうなるしかなかった。
「じゃあ、きみはその老人にとって天使であり、コールガールでもあったってこと?」
「多分、そういうことなんじゃないかしら? ねえ、寒いからベッドに入ってもいい?」
「もちろん」
何もかも完璧な夜だった。
彼女の肌はいつもどおりとてもすべすべしていて、僕はその細い腰に何度もしがみつきながら、心のどこかで彼女の話とその老人のことと、老人が話したというシチリア人とムーア人の戦争のことを思い起こしていた。それらを通して、老人が僕にも何かを語りたがっているように思えてならなかった。
でも一体、何を?
老人と僕には、或いは彼女と僕には、共通点は皆無といってよい。それがどうしてこんなに気になるのだろう? 何が引っ掛かっているんだ?
僕は彼女の体を起こし、自分が下になった。乳房の形がとてもきれいだった。そう言うと彼女は首を横に振り、指先を僕の唇に当てた。やさしい仕草だった。
彼女は老人の屋敷で不思議な体験をした。そして仕事をやめることができた。メッセージカードには老人の言葉があった。それだけの話なのに、そのせいで彼女の中で何かががらりと音をたてて崩れていったのだ。或いは彼女の中で何かがぜんぶそっくり入れ替わったのかもしれない。彼女の話(とその老人)には、それくらい暴力的な感触があった。
僕は下から彼女の両方の乳房をつかみ、流れに身を任せた。その瞬間、深くて真っ暗な溝が脳裏に見えた気がした。覗いてみても、中には漆黒の闇があるだけだった。
終わったあと、煙草を吸いながら、スライ・ストーンがつくったそのアルバムを今聴いてみようかとさえ僕は思った。でも妻はどう思うだろう? せっかくいい気分で実家から帰ってきて、見たくもないレコードジャケットがその辺りに転がっているのを見つけたら、妻はまたひどく混乱するに違いない。僕がそんなものを聴いていることを何よりも恥ずかしく思い、嫌味のように兄貴に相談するはずだ。
「ねえ、こんなのを聞いていたのよ」と。それから「だからあなたはいつまで経っても・・・」と妻は言うだろう。その表情が脳裏にはっきりと浮かんだ。明日の午後には妻は帰ってくる予定なのだ。
コールガールの彼女は鼻を僕の左腕にくっつけるようにして眠っていた。
僕は彼女を起こさないように、そっと腕だけを動かして、吸殻を灰皿に押し付けた。
彼女が目覚めたら、僕が感じていることを正直に話してみよう、そして彼女がどうして平気でいられるのか訊いてみよう、僕がそう考えていると、「ねえ」と彼女のくぐもった声がした。
「びっくりしたなあ。寝てたんじゃなかったの?」
「ねえ、あなたいつか小説を書きたいって言ってたわよね?」
「うん。それがどうしたの?」
「この話を小説にできる?」
「老人とのことを?」
「そう」
「できるけれど、僕の場合、実際の話を文章にすると、登場人物が誰か、周囲に必ずバレてしまうんだ。どんなに脚色していても。いままで書いてきた小説はみんなそうだ。だからすべてお蔵入りした。きっときみと僕のこともそれとなく伝わってしまうことのなるよ? それでもきみは大丈夫?」
「だいじょうぶ。そんなことはへっちゃらよ。わたしが我慢できないことは、もっと別のことよ」
「何?」
「わたしはこの話がこのまま埋もれちゃうのが我慢できないの。そんなのとても悲しいことよ、そう思わない?」
「うん、そうかもしれない」
「だから、あなたがきちんとこの話を文章に置き換えて、形を与えて欲しいの。そしてそれをしかるべきところに発表して欲しいの。それがわたしの願い。どう、できそう?」
「文章にすることは可能だと思う」
「よかった」
「でも、きみの気に入るかどうかは保証できないよ。僕は何しろ不器用だし、それに・・・」
「しっ」
そう言って彼女は僕の頭の裏に、褐色の両腕を回し、長い長いキスをした。
季節が一巡りしてしまいそうなほど長いキスだった。それから彼女はとても不思議なことを言った。
「ねえ、わたしたちはみんな誰かのためのコールガールだし、誰かのための天使なのね。気づいていないだけで。きっとあなたの奥さんも、生まれてくるあなたの女の子も。みんな誰かのためのコールガールで天使なのよ、それは生まれるずっと前から決まっていることなのね」
僕はそれきり彼女には会っていない。
携帯の番号に何度電話しても通じなかったし、だから連絡の取りようがないのだ。
彼女はきっと、天使になるべき他の誰かを見つけたのだろう。そう思うと、とてもいたたまれない気持ちになった。
妻もまだニューポートの実家から戻ってきていない。季節は冬から春になって、気がつけば、僕は一冬をまるまるひとりで暮らしたことになる。妻に電話をするたびに、「お願いだから、もう少しこっちにいさせて」と言われ、僕はその言葉に対する返答をいつまでも見つけられずにいた。それは何かの暗号のようにも聞こえたけれど、何が隠されているのかさっぱり分からなかったし、その考え自体がばかばかしかった。
あまりに人恋しいときには、僕は夜中にスライ・ストーンのアルバムを聴くようになった。特に「セックスマシーン」を繰り返し聴く。老人が内緒で残していったヒントがあるんじゃないかと思って。でも、もちろんヒントなんてない。それは僕が自分ひとりで読み解かなければいけない種類の問題なのだ。そんなふうに僕はひとりぼっちになっていった。
時々、暗い夢を見て飛び起きた午前3時なんかに、妻の兄貴ののっぺりとした顔ときつい言葉を思い出した。
お前は何も生み出さないし、お前の中にあるもの、お前の中にあると私の妹が思っているものは、すべてガラクダだ、いや、無だ、お前は私の妹を幸せにすることはできないだろうし、お前自身さえ幸せにすることはできないだろう、或いは生まれてくる赤ん坊はさっさと堕胎するべきだったんだ、お前と話していると、おもちゃの人形を相手にしているようだ、人形が赤ん坊なんか育てられるわけがない。
彼の顔には表情がなかった。それは喜びも確信も、はたまた憎しみも軽蔑も不幸さえも映していなかった。
コールガールの彼女を責める気には、とてもなれなかった。
というよりも、誰のことも責めたくはなかった、たとえ僕がこの世界にたった一人で取り残されたとしても、それから僕が自分のための天使をただのひとりも見つけられなかったとしても、だ。
僕はベッドに横になり、天井を眺めた。天井の壁に、彼女たちの顔を思い浮かべ、その表情を指先に感じ取ろうとした。
でも、ダメだ。
どんなに手を伸ばしても届くわけがない。
なぜなら彼女たちは、今この瞬間にも、僕からますます遠ざかり、別々の部屋のようなところに隔たれようとしているからだ。
僕にはそのことがはっきりと分かった。
それからというもの僕は、眠れない夜に、街をさ迷い歩くようになった。
そしてシチリア島のムーア人のことを思った。いつでも多くの流血があり、暴力に塗れ、あたたかさもかけらもない、そこは僕がいつか見た場所だった。
小説はまだ書いていない。
「それだけ」
「それだけ? 続きはないの?」
「あるといえばあるけれど」
「何?」
「例えば、同じようなことが一週間続いて・・・」
「それで?」
「でも、わたしは二度と踊ったりはしなかった。その老人の前で、有名な詩を朗読したり、歌をうたったりはしたけれど」
「それだけ?」
「うん、それだけ。
それが7日間続いて、8日目の朝、とてもたくさんの花とドレスと靴がアパートに届けられた。その老人からだった。今着ている洋服もそうなんだけれど。
それから、銀行口座にちょっと信じられないくらいのお金が振り込まれていた。金額を言っても、あなた信じないんじゃないかしら」
「それできみはコールガールの仕事をやめることができた」
「そう。それでわたしはすぐに仕事をやめたの。だって、もう働く意味がなくなっちゃったから」
彼女はにっこり笑いながら言った。とても素敵な笑顔だった。本物の夏がそこにはあった。
「だからお礼にその屋敷にもう一度行ってみたの、老人のためにプレゼントを持って。どうなっていたと思う?」
「話の展開からすると、きっと何もなかったんだろうね」
「やっぱりあなたには分かるのね。
そのとおり。そこにはそもそもの最初から何もなかったの。
訪ねていった場所は20年以上前からずっと空き地で、ダコタハウスに似た建物なんて建っていなかった。バーリントンで一番有名な老人なんて住んでいなかったし、そんな老人が本当にいたかどうかさえもあやしいものだった」
「ふうむ」思わず僕はうなってしまった。
「でもね」彼女は続けた。
「うん、でも、ちゃんとメッセージカードも届いたのよ。一週間後に届けられた贈り物といっしょに」
「何て書いてあったの?」
「恥ずかしい」
「ここまでしゃべったんだから言いなよ」
「『私の天使のコールガールへ』って」
僕は思わず噴出してしまった。
「ほんとにそう書いてあったの?」
「うん」
「ふうむ」
僕はもう一度、彼女の前でうなるしかなかった。
「じゃあ、きみはその老人にとって天使であり、コールガールでもあったってこと?」
「多分、そういうことなんじゃないかしら? ねえ、寒いからベッドに入ってもいい?」
「もちろん」
何もかも完璧な夜だった。
彼女の肌はいつもどおりとてもすべすべしていて、僕はその細い腰に何度もしがみつきながら、心のどこかで彼女の話とその老人のことと、老人が話したというシチリア人とムーア人の戦争のことを思い起こしていた。それらを通して、老人が僕にも何かを語りたがっているように思えてならなかった。
でも一体、何を?
老人と僕には、或いは彼女と僕には、共通点は皆無といってよい。それがどうしてこんなに気になるのだろう? 何が引っ掛かっているんだ?
僕は彼女の体を起こし、自分が下になった。乳房の形がとてもきれいだった。そう言うと彼女は首を横に振り、指先を僕の唇に当てた。やさしい仕草だった。
彼女は老人の屋敷で不思議な体験をした。そして仕事をやめることができた。メッセージカードには老人の言葉があった。それだけの話なのに、そのせいで彼女の中で何かががらりと音をたてて崩れていったのだ。或いは彼女の中で何かがぜんぶそっくり入れ替わったのかもしれない。彼女の話(とその老人)には、それくらい暴力的な感触があった。
僕は下から彼女の両方の乳房をつかみ、流れに身を任せた。その瞬間、深くて真っ暗な溝が脳裏に見えた気がした。覗いてみても、中には漆黒の闇があるだけだった。
終わったあと、煙草を吸いながら、スライ・ストーンがつくったそのアルバムを今聴いてみようかとさえ僕は思った。でも妻はどう思うだろう? せっかくいい気分で実家から帰ってきて、見たくもないレコードジャケットがその辺りに転がっているのを見つけたら、妻はまたひどく混乱するに違いない。僕がそんなものを聴いていることを何よりも恥ずかしく思い、嫌味のように兄貴に相談するはずだ。
「ねえ、こんなのを聞いていたのよ」と。それから「だからあなたはいつまで経っても・・・」と妻は言うだろう。その表情が脳裏にはっきりと浮かんだ。明日の午後には妻は帰ってくる予定なのだ。
コールガールの彼女は鼻を僕の左腕にくっつけるようにして眠っていた。
僕は彼女を起こさないように、そっと腕だけを動かして、吸殻を灰皿に押し付けた。
彼女が目覚めたら、僕が感じていることを正直に話してみよう、そして彼女がどうして平気でいられるのか訊いてみよう、僕がそう考えていると、「ねえ」と彼女のくぐもった声がした。
「びっくりしたなあ。寝てたんじゃなかったの?」
「ねえ、あなたいつか小説を書きたいって言ってたわよね?」
「うん。それがどうしたの?」
「この話を小説にできる?」
「老人とのことを?」
「そう」
「できるけれど、僕の場合、実際の話を文章にすると、登場人物が誰か、周囲に必ずバレてしまうんだ。どんなに脚色していても。いままで書いてきた小説はみんなそうだ。だからすべてお蔵入りした。きっときみと僕のこともそれとなく伝わってしまうことのなるよ? それでもきみは大丈夫?」
「だいじょうぶ。そんなことはへっちゃらよ。わたしが我慢できないことは、もっと別のことよ」
「何?」
「わたしはこの話がこのまま埋もれちゃうのが我慢できないの。そんなのとても悲しいことよ、そう思わない?」
「うん、そうかもしれない」
「だから、あなたがきちんとこの話を文章に置き換えて、形を与えて欲しいの。そしてそれをしかるべきところに発表して欲しいの。それがわたしの願い。どう、できそう?」
「文章にすることは可能だと思う」
「よかった」
「でも、きみの気に入るかどうかは保証できないよ。僕は何しろ不器用だし、それに・・・」
「しっ」
そう言って彼女は僕の頭の裏に、褐色の両腕を回し、長い長いキスをした。
季節が一巡りしてしまいそうなほど長いキスだった。それから彼女はとても不思議なことを言った。
「ねえ、わたしたちはみんな誰かのためのコールガールだし、誰かのための天使なのね。気づいていないだけで。きっとあなたの奥さんも、生まれてくるあなたの女の子も。みんな誰かのためのコールガールで天使なのよ、それは生まれるずっと前から決まっていることなのね」
僕はそれきり彼女には会っていない。
携帯の番号に何度電話しても通じなかったし、だから連絡の取りようがないのだ。
彼女はきっと、天使になるべき他の誰かを見つけたのだろう。そう思うと、とてもいたたまれない気持ちになった。
妻もまだニューポートの実家から戻ってきていない。季節は冬から春になって、気がつけば、僕は一冬をまるまるひとりで暮らしたことになる。妻に電話をするたびに、「お願いだから、もう少しこっちにいさせて」と言われ、僕はその言葉に対する返答をいつまでも見つけられずにいた。それは何かの暗号のようにも聞こえたけれど、何が隠されているのかさっぱり分からなかったし、その考え自体がばかばかしかった。
あまりに人恋しいときには、僕は夜中にスライ・ストーンのアルバムを聴くようになった。特に「セックスマシーン」を繰り返し聴く。老人が内緒で残していったヒントがあるんじゃないかと思って。でも、もちろんヒントなんてない。それは僕が自分ひとりで読み解かなければいけない種類の問題なのだ。そんなふうに僕はひとりぼっちになっていった。
時々、暗い夢を見て飛び起きた午前3時なんかに、妻の兄貴ののっぺりとした顔ときつい言葉を思い出した。
お前は何も生み出さないし、お前の中にあるもの、お前の中にあると私の妹が思っているものは、すべてガラクダだ、いや、無だ、お前は私の妹を幸せにすることはできないだろうし、お前自身さえ幸せにすることはできないだろう、或いは生まれてくる赤ん坊はさっさと堕胎するべきだったんだ、お前と話していると、おもちゃの人形を相手にしているようだ、人形が赤ん坊なんか育てられるわけがない。
彼の顔には表情がなかった。それは喜びも確信も、はたまた憎しみも軽蔑も不幸さえも映していなかった。
コールガールの彼女を責める気には、とてもなれなかった。
というよりも、誰のことも責めたくはなかった、たとえ僕がこの世界にたった一人で取り残されたとしても、それから僕が自分のための天使をただのひとりも見つけられなかったとしても、だ。
僕はベッドに横になり、天井を眺めた。天井の壁に、彼女たちの顔を思い浮かべ、その表情を指先に感じ取ろうとした。
でも、ダメだ。
どんなに手を伸ばしても届くわけがない。
なぜなら彼女たちは、今この瞬間にも、僕からますます遠ざかり、別々の部屋のようなところに隔たれようとしているからだ。
僕にはそのことがはっきりと分かった。
それからというもの僕は、眠れない夜に、街をさ迷い歩くようになった。
そしてシチリア島のムーア人のことを思った。いつでも多くの流血があり、暴力に塗れ、あたたかさもかけらもない、そこは僕がいつか見た場所だった。
小説はまだ書いていない。