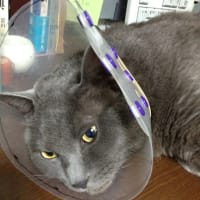わざわざ、遠いところから。
どのくらい遠いところか、きっとあんたには想像もつかないだろうよ」、ブルーが鏡の前でネクタイを直しながら言った。
「あんたはね、これから誰からも愛されず、誰も愛さず、一生、ひとりぼっちで暮していくんだ。あんたの体には、孤独が嫌な匂いになって染み付いていく。なんかのしるしみたいにね。そのうち、みんな、あんたのその匂いから顔を背け、次第にあんたのことを憎むようになる。あんたと口もききたくないし、あんたの話は誰も聞きたくない。
そういうふうにして、あんたは冷蔵庫の中のしなびたきゅうりみたいになって暮していくんだ。ずっとだよ」
ぼくの人生は冷蔵庫の中のきゅうりみたいなもの?
誰も愛してくれない? なんだかとても不思議な響きだ。
老人たちの言葉を聞いていると、自分が絵の中の一部みたいに思えてくる。すうっと現実感が薄れていくのだ。
「また来るよ」、ピンクのマフラーが言った。
「我々四人は、しばらくしたらまた来る。我々はあんたが振り切りたくても、絶対に振り切れない影のようなものだと思ってくれていい。名まえのないよっつの影だ、交換可能なんだよ、ずっとあんたにまとわりつくよ、ずっとあんたにまとわりついているよ、ずっとあんたにまとわりついているんだよ、ずっとあんただけにまつわりついているんだよ」
そう言って四人は帰っていった。結局、紅茶もカントリーマアムも必要なかった。もてなし? ぼくは母親の言葉を思い出した。なぜ母親はぼくにもてなせなんて言ったんだろう?
父親か母親に電話してみようかと思った。何となく、電話をした方がよさそうだったから。でも、電話は通じなかった。
当たり前だ。
彼らはこの時間には携帯電話は鞄の奥の奥の方にしまい込んで、ちゃんと働いているのだ。
アップライトピアノの横にある鏡に、ぼくの姿が映っていた。
鏡の中のぼくは昨日までのぼくと、ほとんど変わっていないように見えた。でも、それは真実ではない。いくら否定しようとも、ぼくは歳をとり、衰えているのだ。
そして醜くなっていく。
あの四人の老人たちと同じように。
ずい分と迷ったけれど、けっきょくミュージアムには行くことにした。誰でもいいから、誰かがちゃんと二本の足で歩き、働いている姿を見たかったからだ。
平日の昼間、雨も降っているということもあって、ミュージアムはとても空いていた。ほとんど客は誰もいないと言ってもいいくらいだった。がらんとしている。そしてやはり静かだ。
ぼくはそのカメラマンのファンタジックな写真をとても楽しみにしていた。
でもそこに展示されていたは、ファンタジックなものなんかではなく、四人の老人を主題にした隠微な写真だった。
燕尾服や夜会服を着て、高い塔の屋上で下界を見下ろしながらグラスを傾けている老人、得意気に大きなお腹をゆすりながら騙し階段を歩く老人、鏡に姿を映して隣の人形に化粧を直している老女、それから、テラスの椅子に立ち上がってうとうと眠りかけている老人。四人の等身大の姿がミュージアムの部屋いっぱいに飾られ、こっちの世界を見据えている。
あの四人だ。間違いない。
彼らは写真であることに、そんなに不便を感じていないようだ。いつでも好きなときに、こっちの世界に抜け出すこともできるし、気が向かなければ、写真のふりをしていればいいのだからというふうに、彼らは口元に薄笑いさえ浮かべている。
そして、もっと驚いたことは、ひとつひとつの写真に、必ず、ぼくに似た少年の姿があったことだ。グラスの中を金魚のように泳ぐぼく、窓から階段を眺めているぼく、鏡の隅に映っているぼく、テラスの向かい側の椅子に座っているぼく、後ろ姿のぼく、女装したぼく、大人になったぼく、成長しないぼく、ぼくではないぼく。
世界には、ぼくと、その四人の老人しかいないようだった。
ぼくは紫の蝶ネクタイの老人の言葉を思い出した。
「あんたのお父さんね、ほんものの女の子みたいな声を出していたんだよ。
それからあんたのお母さんはきっと今頃、別の男の子を息子にしていっしょに暮し始めているよ。
あんたはね、これから誰からも愛されず、誰も愛さず、ずっとひとりぼっちで暮していくんだよ」
ミュージアムから帰って、ひとりで夕食を作ってひとりで食べた。魚介類のパスタ。ぼくの大好物だ。でもパスタは何の味もしなかった。これじゃ砂を食べているのと何も変わらない。
半分ほど食べて、残りは捨てた。
自分の部屋に戻ってベッドに寝転び、今日一日のことを思い出そうとした。少し状況を整理する必要もあるだろう。でも、大切なことを思い出そうとすると、両方のこめかみがずきずきと痛んだ。
お父さんは、ほんとうに女の子みたいになったのかもしれないな。
お母さんは、ほんとうに別の男の子と暮し始めているのかもしれない。
犬もネコもぼくに愛想をつかして逃げていったのだ。
ぼくはほんとうにこのままずっとひとりぼっちなのかもしれない。
「ただいまー」と、玄関の鍵を開ける音がして、お母さんが叫んだ。
帰ってきた! あれはお母さんだ。やっぱりぼくを見捨ててなんかいなかったんだ! ぼくのことが大事なんだ。
どこからか犬とネコもやってきて、犬が甘える鳴き声、ネコの首輪の鈴が鳴る音がぼくの部屋にも聞こえてきた。お父さんが「よしよし」と犬の首元を撫でる声が聞こえる。なんだか声のトーンが三音ほど高くなったようだ。でも、そんなに気にするほどでもない。
ぼくはベッドから飛び起き、部屋を出て階段を駆け下りた。
お父さん! お母さん!
ぼくは精一杯叫んだ。でもぼくの声は、現実の空気を震わせることができなかった。ぼくの声はぼくにしか聞こえないようだった。
お父さんもお母さんもこっちを振り向かない。ぼくがそばに近寄っても、見ようともしない。丁寧にぼくを避けて、荷物を片付け、眠る準備をしている。ぼくはふたりに触れることもできないのだ。
お母さん、お母さんが言っていた友達、ちゃんと、ぼく、もてなしたよ。お父さん、今日はぼくの誕生日だよ。
でも、だめだ、お父さんにもお母さんにもぼくはまったく見えていない。
「疲れたね」、声のするほうを見ると、それはぼくだった。ぼくにとてもよく似た少年だった。
お母さんはぼくに似た少年に向かって言った、「誕生日、おめでとう。プレゼント、早く開けてみてね」。
「お父さん、お母さん、どうもありがとう」
ぼくに似た少年がそう言うと、犬とネコが駆け寄ってきた。犬もネコもぼくに似た少年が大好きなようだった。
ぼくは部屋の風景から、家族という風景からどんどん遠ざかっていった。
ぼくは鏡にしか映らないぼくだった。
ぼくは、窓の外から部屋の中を見つめるだけのぼくだった。
寝ている人の前にしか現れることができない、ぼくだった。
グラスの中で金魚のようになって泳ぐことしかできない、ぼくだった。
あの写真の中のぼくが、ぼくの真実の姿だったのだ、ぼくが知らなかっただけだ。
それがぼくにとっての十五歳の誕生日。
それからというもの、ぼくはそこにいながら、そこにはいない存在として生活するようになった。それしか選択肢がなかったから。まさに、あの四人の老人が予言したとおり。
夕方になると、ぼくは床に座り、居間の窓から庭の芝生をぼんやり見て過ごすようになった。もう学ぶことも感動することもない。
沈黙が、目に見えない細かい塵のようにぼくの周りに降り積もり、風景が少しずつ色を失い崩れていった。
雨が降っていたりすると、なおさらだった。
ぼくは自分がかつて、両親と仲良く暮していたことを思い出した。そして、いつか再び、両親といっしょに仲良く暮すようになることを何度も何度も想像した。
でも、それらのイメージはずっと昔の出来事のように、ぼくの目には霞んでみえた。そんなふうにして、ぼくは歳をとっていった。そして今、自分が何歳なのかも正確には分からない。
今度、いつ、あの四人の老人が、ぼくのところにやってくるのか、それから、どんなことをぼくに告げるのか、分からない。でもいつであれ、それから告げる内容がどんなことであれ、そのとき、ぼくは、自分も仲間に入れてくれるよう頼むつもりだ。洋服は貸してもらう。たぶん、ぼくはイエローだ。そして、十五歳の少年のもとに向かう。
そこでかつての自分を取り戻すのだ。
どのくらい遠いところか、きっとあんたには想像もつかないだろうよ」、ブルーが鏡の前でネクタイを直しながら言った。
「あんたはね、これから誰からも愛されず、誰も愛さず、一生、ひとりぼっちで暮していくんだ。あんたの体には、孤独が嫌な匂いになって染み付いていく。なんかのしるしみたいにね。そのうち、みんな、あんたのその匂いから顔を背け、次第にあんたのことを憎むようになる。あんたと口もききたくないし、あんたの話は誰も聞きたくない。
そういうふうにして、あんたは冷蔵庫の中のしなびたきゅうりみたいになって暮していくんだ。ずっとだよ」
ぼくの人生は冷蔵庫の中のきゅうりみたいなもの?
誰も愛してくれない? なんだかとても不思議な響きだ。
老人たちの言葉を聞いていると、自分が絵の中の一部みたいに思えてくる。すうっと現実感が薄れていくのだ。
「また来るよ」、ピンクのマフラーが言った。
「我々四人は、しばらくしたらまた来る。我々はあんたが振り切りたくても、絶対に振り切れない影のようなものだと思ってくれていい。名まえのないよっつの影だ、交換可能なんだよ、ずっとあんたにまとわりつくよ、ずっとあんたにまとわりついているよ、ずっとあんたにまとわりついているんだよ、ずっとあんただけにまつわりついているんだよ」
そう言って四人は帰っていった。結局、紅茶もカントリーマアムも必要なかった。もてなし? ぼくは母親の言葉を思い出した。なぜ母親はぼくにもてなせなんて言ったんだろう?
父親か母親に電話してみようかと思った。何となく、電話をした方がよさそうだったから。でも、電話は通じなかった。
当たり前だ。
彼らはこの時間には携帯電話は鞄の奥の奥の方にしまい込んで、ちゃんと働いているのだ。
アップライトピアノの横にある鏡に、ぼくの姿が映っていた。
鏡の中のぼくは昨日までのぼくと、ほとんど変わっていないように見えた。でも、それは真実ではない。いくら否定しようとも、ぼくは歳をとり、衰えているのだ。
そして醜くなっていく。
あの四人の老人たちと同じように。
ずい分と迷ったけれど、けっきょくミュージアムには行くことにした。誰でもいいから、誰かがちゃんと二本の足で歩き、働いている姿を見たかったからだ。
平日の昼間、雨も降っているということもあって、ミュージアムはとても空いていた。ほとんど客は誰もいないと言ってもいいくらいだった。がらんとしている。そしてやはり静かだ。
ぼくはそのカメラマンのファンタジックな写真をとても楽しみにしていた。
でもそこに展示されていたは、ファンタジックなものなんかではなく、四人の老人を主題にした隠微な写真だった。
燕尾服や夜会服を着て、高い塔の屋上で下界を見下ろしながらグラスを傾けている老人、得意気に大きなお腹をゆすりながら騙し階段を歩く老人、鏡に姿を映して隣の人形に化粧を直している老女、それから、テラスの椅子に立ち上がってうとうと眠りかけている老人。四人の等身大の姿がミュージアムの部屋いっぱいに飾られ、こっちの世界を見据えている。
あの四人だ。間違いない。
彼らは写真であることに、そんなに不便を感じていないようだ。いつでも好きなときに、こっちの世界に抜け出すこともできるし、気が向かなければ、写真のふりをしていればいいのだからというふうに、彼らは口元に薄笑いさえ浮かべている。
そして、もっと驚いたことは、ひとつひとつの写真に、必ず、ぼくに似た少年の姿があったことだ。グラスの中を金魚のように泳ぐぼく、窓から階段を眺めているぼく、鏡の隅に映っているぼく、テラスの向かい側の椅子に座っているぼく、後ろ姿のぼく、女装したぼく、大人になったぼく、成長しないぼく、ぼくではないぼく。
世界には、ぼくと、その四人の老人しかいないようだった。
ぼくは紫の蝶ネクタイの老人の言葉を思い出した。
「あんたのお父さんね、ほんものの女の子みたいな声を出していたんだよ。
それからあんたのお母さんはきっと今頃、別の男の子を息子にしていっしょに暮し始めているよ。
あんたはね、これから誰からも愛されず、誰も愛さず、ずっとひとりぼっちで暮していくんだよ」
ミュージアムから帰って、ひとりで夕食を作ってひとりで食べた。魚介類のパスタ。ぼくの大好物だ。でもパスタは何の味もしなかった。これじゃ砂を食べているのと何も変わらない。
半分ほど食べて、残りは捨てた。
自分の部屋に戻ってベッドに寝転び、今日一日のことを思い出そうとした。少し状況を整理する必要もあるだろう。でも、大切なことを思い出そうとすると、両方のこめかみがずきずきと痛んだ。
お父さんは、ほんとうに女の子みたいになったのかもしれないな。
お母さんは、ほんとうに別の男の子と暮し始めているのかもしれない。
犬もネコもぼくに愛想をつかして逃げていったのだ。
ぼくはほんとうにこのままずっとひとりぼっちなのかもしれない。
「ただいまー」と、玄関の鍵を開ける音がして、お母さんが叫んだ。
帰ってきた! あれはお母さんだ。やっぱりぼくを見捨ててなんかいなかったんだ! ぼくのことが大事なんだ。
どこからか犬とネコもやってきて、犬が甘える鳴き声、ネコの首輪の鈴が鳴る音がぼくの部屋にも聞こえてきた。お父さんが「よしよし」と犬の首元を撫でる声が聞こえる。なんだか声のトーンが三音ほど高くなったようだ。でも、そんなに気にするほどでもない。
ぼくはベッドから飛び起き、部屋を出て階段を駆け下りた。
お父さん! お母さん!
ぼくは精一杯叫んだ。でもぼくの声は、現実の空気を震わせることができなかった。ぼくの声はぼくにしか聞こえないようだった。
お父さんもお母さんもこっちを振り向かない。ぼくがそばに近寄っても、見ようともしない。丁寧にぼくを避けて、荷物を片付け、眠る準備をしている。ぼくはふたりに触れることもできないのだ。
お母さん、お母さんが言っていた友達、ちゃんと、ぼく、もてなしたよ。お父さん、今日はぼくの誕生日だよ。
でも、だめだ、お父さんにもお母さんにもぼくはまったく見えていない。
「疲れたね」、声のするほうを見ると、それはぼくだった。ぼくにとてもよく似た少年だった。
お母さんはぼくに似た少年に向かって言った、「誕生日、おめでとう。プレゼント、早く開けてみてね」。
「お父さん、お母さん、どうもありがとう」
ぼくに似た少年がそう言うと、犬とネコが駆け寄ってきた。犬もネコもぼくに似た少年が大好きなようだった。
ぼくは部屋の風景から、家族という風景からどんどん遠ざかっていった。
ぼくは鏡にしか映らないぼくだった。
ぼくは、窓の外から部屋の中を見つめるだけのぼくだった。
寝ている人の前にしか現れることができない、ぼくだった。
グラスの中で金魚のようになって泳ぐことしかできない、ぼくだった。
あの写真の中のぼくが、ぼくの真実の姿だったのだ、ぼくが知らなかっただけだ。
それがぼくにとっての十五歳の誕生日。
それからというもの、ぼくはそこにいながら、そこにはいない存在として生活するようになった。それしか選択肢がなかったから。まさに、あの四人の老人が予言したとおり。
夕方になると、ぼくは床に座り、居間の窓から庭の芝生をぼんやり見て過ごすようになった。もう学ぶことも感動することもない。
沈黙が、目に見えない細かい塵のようにぼくの周りに降り積もり、風景が少しずつ色を失い崩れていった。
雨が降っていたりすると、なおさらだった。
ぼくは自分がかつて、両親と仲良く暮していたことを思い出した。そして、いつか再び、両親といっしょに仲良く暮すようになることを何度も何度も想像した。
でも、それらのイメージはずっと昔の出来事のように、ぼくの目には霞んでみえた。そんなふうにして、ぼくは歳をとっていった。そして今、自分が何歳なのかも正確には分からない。
今度、いつ、あの四人の老人が、ぼくのところにやってくるのか、それから、どんなことをぼくに告げるのか、分からない。でもいつであれ、それから告げる内容がどんなことであれ、そのとき、ぼくは、自分も仲間に入れてくれるよう頼むつもりだ。洋服は貸してもらう。たぶん、ぼくはイエローだ。そして、十五歳の少年のもとに向かう。
そこでかつての自分を取り戻すのだ。