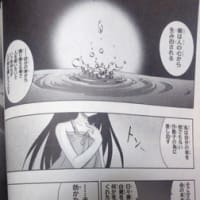作家小野不由美さんの『屍鬼』 は、人間を吸血し絶命させて生き延び続ける異能者-屍鬼(しき)-をめぐる物語です。ここには様々な人物達の様々な生き方、価値観がでてきます。特に、一人の少女-屍鬼。名は沙子(すなこ)-の生き様と、彼女と触れ合う一人の若いお坊さん(室井静信)の生き方、感じ方、そして静信の旧友であり、長年にわたり信頼関係を築いてきた尾崎俊夫の、やがて静信との決定的断絶を生じることとなる価値観、倫理観は作品の白眉の一つと覚えます。
二人の対蹠的な価値観をテクストは描破しており、「生きるということ」、畢竟するに、「生」そのものへの関心と、自らの依拠する立場を考える契機となるのに冠絶な作品の一つと言えるでしょう。
・屍鬼と人間の関係
屍鬼とは、わかりやすく言えば吸血鬼のような存在であり、作中では人間を狩る存在として登場することとなります。異常に連続する村人の死が屍鬼の仕業であると気づいた人間達は、村と自分の生命を守る為に屍鬼を倒そうとします。しかし全ての人間が賛同することはありませんでした。それは以下の理由に因るものです。
屍鬼は吸血され絶命した人間が再び起き上がった存在(村には「起き上がり」の伝承があります。)なのですが、異形の者とはいえその姿形はほぼ人間と同様であり、それは思考とて例外ではありません。そんな、人間とほぼ変わらない、しかも元々は自分たちの家族であったり、友人、知人であったりする屍鬼を殺すことなどとても出来るものではないと考える人々がいたからであります。
・屍鬼の少女沙子
沙子は静信と深い関係をもつ少女であり、彼女について思いを馳せることは、この授業で皆さんが考えていくことに大きな示唆を与えるでしょう。
彼女は生きることに必死でした。自分が生きるために人間を吸血し続ける彼女は、そうしないと自分が空腹で死んでしまうから仕方がないと自らに言い聞かせることで己を納得させます。しかし同時に、彼女はそんな自身の存在に苦しむのです。生きるために人を殺めることは、人間が生存のために他の生命体を食すことと同じことだと捉え深く考えない同属のなかで、彼女は自らの「罪深き」存在に悩み悲しむのです。
・尾崎と静信-二人の考え-
この作品には、二人の正反対な考え方の人物がでてきます。一人は尾崎敏夫という医者です。彼は、代々村の医師として住人の生命を守ってきたことを誇る尾崎家の嫡子です。代々村の医師として住人の生命を守ってきたと自負する尾崎家の矜持を受け継ぐ人物である尾崎俊夫は、屍鬼がたとえ人間と思考も感情も類似した生命体であろうと、村民の命を脅かす限り徹底的な殺戮をもって対抗することを誓う強靱な意志を抱懐しています。彼は「村を守る」という崇高な指名の為ならば、手段を選ばず、憐憫の情ももたず、ただただ己の目的に向かって邁進します。そうしなければ、自分たちが営々暮らしてきた村が滅びてしますと考えるからです。人間を吸血せざるを得ない屍鬼という存在が人間と共存することは不可能であり、不可能である限り、生存の為に戦うことは正義であると考える彼にとって、屍鬼とは村人達の命を脅かす敵以外の何物でもなかったのです。
一方の室井静信は、屍鬼は自らの在りように従って生きている存在として、その手段であるところの人間を捕食して生命を維持していかなければならない宿命を肯定します。人間を含め、生存の為に他の命を狩る行為に生物の本能を認めつつも、静信は人間による屍鬼の殺戮を認めることができないでいます。そこには、人が他の生命を殺め自らの糧とすることにあまり苦悩を覚えたりはしないのとは異なり、人間を殺めることでしか己の生を存続させることが出来ず、そしてその宿業に悲哀を覚えてしまう異形の者達に哀切しながらも共鳴する静信の惻隠の情があるのです。
静信はそんな屍鬼を殺すことは出来ないし、己の道義心と異なるものと考えます。そして、屍鬼の尊厳を認め、具体的な解決法を提示することが出来ない自分をふがいなく感じつつも、殺戮に関わることなく、ただ生きていくことを模索してゆくこととなります。
この作品は屍鬼を中心にした、尾崎と静信という二人の対立する価値観をはじめ、様々な見方が可能な物語であります。
二人の対蹠的な価値観をテクストは描破しており、「生きるということ」、畢竟するに、「生」そのものへの関心と、自らの依拠する立場を考える契機となるのに冠絶な作品の一つと言えるでしょう。
・屍鬼と人間の関係
屍鬼とは、わかりやすく言えば吸血鬼のような存在であり、作中では人間を狩る存在として登場することとなります。異常に連続する村人の死が屍鬼の仕業であると気づいた人間達は、村と自分の生命を守る為に屍鬼を倒そうとします。しかし全ての人間が賛同することはありませんでした。それは以下の理由に因るものです。
屍鬼は吸血され絶命した人間が再び起き上がった存在(村には「起き上がり」の伝承があります。)なのですが、異形の者とはいえその姿形はほぼ人間と同様であり、それは思考とて例外ではありません。そんな、人間とほぼ変わらない、しかも元々は自分たちの家族であったり、友人、知人であったりする屍鬼を殺すことなどとても出来るものではないと考える人々がいたからであります。
・屍鬼の少女沙子
沙子は静信と深い関係をもつ少女であり、彼女について思いを馳せることは、この授業で皆さんが考えていくことに大きな示唆を与えるでしょう。
彼女は生きることに必死でした。自分が生きるために人間を吸血し続ける彼女は、そうしないと自分が空腹で死んでしまうから仕方がないと自らに言い聞かせることで己を納得させます。しかし同時に、彼女はそんな自身の存在に苦しむのです。生きるために人を殺めることは、人間が生存のために他の生命体を食すことと同じことだと捉え深く考えない同属のなかで、彼女は自らの「罪深き」存在に悩み悲しむのです。
・尾崎と静信-二人の考え-
この作品には、二人の正反対な考え方の人物がでてきます。一人は尾崎敏夫という医者です。彼は、代々村の医師として住人の生命を守ってきたことを誇る尾崎家の嫡子です。代々村の医師として住人の生命を守ってきたと自負する尾崎家の矜持を受け継ぐ人物である尾崎俊夫は、屍鬼がたとえ人間と思考も感情も類似した生命体であろうと、村民の命を脅かす限り徹底的な殺戮をもって対抗することを誓う強靱な意志を抱懐しています。彼は「村を守る」という崇高な指名の為ならば、手段を選ばず、憐憫の情ももたず、ただただ己の目的に向かって邁進します。そうしなければ、自分たちが営々暮らしてきた村が滅びてしますと考えるからです。人間を吸血せざるを得ない屍鬼という存在が人間と共存することは不可能であり、不可能である限り、生存の為に戦うことは正義であると考える彼にとって、屍鬼とは村人達の命を脅かす敵以外の何物でもなかったのです。
一方の室井静信は、屍鬼は自らの在りように従って生きている存在として、その手段であるところの人間を捕食して生命を維持していかなければならない宿命を肯定します。人間を含め、生存の為に他の命を狩る行為に生物の本能を認めつつも、静信は人間による屍鬼の殺戮を認めることができないでいます。そこには、人が他の生命を殺め自らの糧とすることにあまり苦悩を覚えたりはしないのとは異なり、人間を殺めることでしか己の生を存続させることが出来ず、そしてその宿業に悲哀を覚えてしまう異形の者達に哀切しながらも共鳴する静信の惻隠の情があるのです。
静信はそんな屍鬼を殺すことは出来ないし、己の道義心と異なるものと考えます。そして、屍鬼の尊厳を認め、具体的な解決法を提示することが出来ない自分をふがいなく感じつつも、殺戮に関わることなく、ただ生きていくことを模索してゆくこととなります。
この作品は屍鬼を中心にした、尾崎と静信という二人の対立する価値観をはじめ、様々な見方が可能な物語であります。