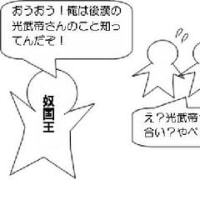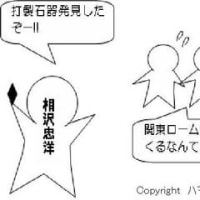今日から中国の歴史書からみる日本についてやっていこうと思います。
中国では、劉邦が漢を建国していました。一時中断していた時期がありますが、後に後漢として復活します。この漢の歴史書に日本に関する記述があるのです。
最初は『漢書』地理志です。後漢の班固が著述した漢の歴史書です。なんで後漢の人が漢の歴史書を書いてんの?それは同時代の人間が書くと、時の権力者のことを意識せずに書けないからです。一応、後の時代の人が書いた方が公平な目でみられるということらしいです。
さて、日本に関する記述は一行です。
「夫れ楽浪海中に倭人有り。分れて百余国と為る。歳時を以て来り献見すと云ふ。」
はい、これだけです。紀元前1世紀、日本は倭国とよばれ、国内が100カ国以上に分裂していた。定期的に漢の武帝が朝鮮半島に設置した楽浪郡に朝貢していた、ことが読みとれます。
これで終わりにしちゃってもいいんだけど、最初に読む史料だし、これから歴史を見ていく前提知識も仕入れてほしいので少し詳しく話をしますね。
まず、最初の文章。朝鮮半島の楽浪郡(現在の平壌付近にあった)の海の向こうに倭人が住んでいる、という意味です。倭人とは日本人のことです。「倭」というのは中国が日本をよぶときに使った呼称で、実はあまりいい漢字ではありません。「ちいさい」「きたない」などの意味を含んでいます。なぜそんな扱いを受けるのかというと、世界の中心は中国だ・・・と中国人が考えていたからです。この考えは、漢の時代もその後もほとんどそのまま引き継がれていきます。この考え方を中華思想といいます。世界の中心に位置する国は中国だと考える思想です。そもそもなんで中国とよぶのか?世界の中心の国だからです。厳密に言えば、世界で国は中国だけなんです。中国の北は北狄、南は南蛮、東は東夷、西は西戎とよばれる「化外の民」、つまり野蛮人の土地であり、中国だけが文明の中心としての国だという考え方なのです。当時の中国、つまり漢からみて日本は東にあたります。東夷、つまり東の野蛮人としてみられていたわけです。だから、あまりよい意味を持たない「倭」という字をあてられていたのでしょう。まあ、とにかく朝鮮半島のさらに向こうに「倭」という国があるということが、『漢書』地理志から読みとれます。
次の文章です。「倭」は100カ国以上に分裂していた、という意味です。これは前回の授業を思い出してください。弥生時代は平和な時代じゃなかったんですよね?小さなクニに分かれて争っていたんですよね。争いがあったからこそ、高地性集落や環濠集落なんてものが存在したのですよね。『漢書』地理志の記述は、こうした遺跡の発掘結果を裏付けるものです。
最後の文章です。「倭」は定期的に漢に朝貢していた、という意味です。はい、朝貢ってなんでしょう?貢物をおくる、という意味です。つまり、野蛮人の集団である「倭」は、文明の進んだ漢に「どうぞよろしくお願いいたします」って意味をこめて贈り物(貢物)をしていたということです。で、貢物をおくると漢は「よしよし、お前は家来にしてやるからな」と認めてくれるんです。なにせ世界にひとつしかない国である漢が、野蛮人である「倭」人を認めてくれるなんて、まあうれしい!!(苦笑。いやいや笑いごとではありません。実際、当時の日本と漢では文化・文明の進歩に大きな開きがあります。絶対的に進んでいた漢と交流を持つことは当時の日本の権力者にとって、クニをまとめ、他のクニと争ううえで必要不可欠なことだったんです。
おそらく『漢書』地理志にでてくる倭人というのは九州の小国の人間でしょう。地理的にも九州と朝鮮半島は近いですからね。今でも福岡からだったら、東京へ行くよりもソウルへ行く方が距離的には近いですから。だから大陸・朝鮮半島の影響はまず九州に波及するんです。縄文時代晩期に稲作のこん跡が残っているのは、福岡県の板付遺跡でしたよね?弥生時代に朝鮮半島の影響と見られる箱式石棺墓がつくられたのは九州から西日本でしたよね?以前に学習したことも、今日の知識と結びつけながら聞いてもらえれば、さらによく理解できると思います。
んじゃ、今日はここまでっていうことで。
中国では、劉邦が漢を建国していました。一時中断していた時期がありますが、後に後漢として復活します。この漢の歴史書に日本に関する記述があるのです。
最初は『漢書』地理志です。後漢の班固が著述した漢の歴史書です。なんで後漢の人が漢の歴史書を書いてんの?それは同時代の人間が書くと、時の権力者のことを意識せずに書けないからです。一応、後の時代の人が書いた方が公平な目でみられるということらしいです。
さて、日本に関する記述は一行です。
「夫れ楽浪海中に倭人有り。分れて百余国と為る。歳時を以て来り献見すと云ふ。」
はい、これだけです。紀元前1世紀、日本は倭国とよばれ、国内が100カ国以上に分裂していた。定期的に漢の武帝が朝鮮半島に設置した楽浪郡に朝貢していた、ことが読みとれます。
これで終わりにしちゃってもいいんだけど、最初に読む史料だし、これから歴史を見ていく前提知識も仕入れてほしいので少し詳しく話をしますね。
まず、最初の文章。朝鮮半島の楽浪郡(現在の平壌付近にあった)の海の向こうに倭人が住んでいる、という意味です。倭人とは日本人のことです。「倭」というのは中国が日本をよぶときに使った呼称で、実はあまりいい漢字ではありません。「ちいさい」「きたない」などの意味を含んでいます。なぜそんな扱いを受けるのかというと、世界の中心は中国だ・・・と中国人が考えていたからです。この考えは、漢の時代もその後もほとんどそのまま引き継がれていきます。この考え方を中華思想といいます。世界の中心に位置する国は中国だと考える思想です。そもそもなんで中国とよぶのか?世界の中心の国だからです。厳密に言えば、世界で国は中国だけなんです。中国の北は北狄、南は南蛮、東は東夷、西は西戎とよばれる「化外の民」、つまり野蛮人の土地であり、中国だけが文明の中心としての国だという考え方なのです。当時の中国、つまり漢からみて日本は東にあたります。東夷、つまり東の野蛮人としてみられていたわけです。だから、あまりよい意味を持たない「倭」という字をあてられていたのでしょう。まあ、とにかく朝鮮半島のさらに向こうに「倭」という国があるということが、『漢書』地理志から読みとれます。
次の文章です。「倭」は100カ国以上に分裂していた、という意味です。これは前回の授業を思い出してください。弥生時代は平和な時代じゃなかったんですよね?小さなクニに分かれて争っていたんですよね。争いがあったからこそ、高地性集落や環濠集落なんてものが存在したのですよね。『漢書』地理志の記述は、こうした遺跡の発掘結果を裏付けるものです。
最後の文章です。「倭」は定期的に漢に朝貢していた、という意味です。はい、朝貢ってなんでしょう?貢物をおくる、という意味です。つまり、野蛮人の集団である「倭」は、文明の進んだ漢に「どうぞよろしくお願いいたします」って意味をこめて贈り物(貢物)をしていたということです。で、貢物をおくると漢は「よしよし、お前は家来にしてやるからな」と認めてくれるんです。なにせ世界にひとつしかない国である漢が、野蛮人である「倭」人を認めてくれるなんて、まあうれしい!!(苦笑。いやいや笑いごとではありません。実際、当時の日本と漢では文化・文明の進歩に大きな開きがあります。絶対的に進んでいた漢と交流を持つことは当時の日本の権力者にとって、クニをまとめ、他のクニと争ううえで必要不可欠なことだったんです。
おそらく『漢書』地理志にでてくる倭人というのは九州の小国の人間でしょう。地理的にも九州と朝鮮半島は近いですからね。今でも福岡からだったら、東京へ行くよりもソウルへ行く方が距離的には近いですから。だから大陸・朝鮮半島の影響はまず九州に波及するんです。縄文時代晩期に稲作のこん跡が残っているのは、福岡県の板付遺跡でしたよね?弥生時代に朝鮮半島の影響と見られる箱式石棺墓がつくられたのは九州から西日本でしたよね?以前に学習したことも、今日の知識と結びつけながら聞いてもらえれば、さらによく理解できると思います。
んじゃ、今日はここまでっていうことで。