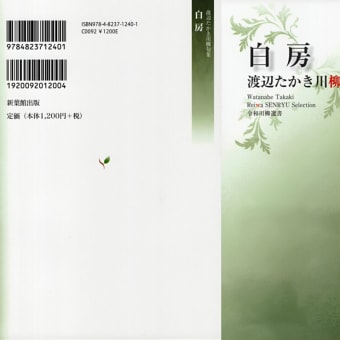□本日落語三席。
◆三遊亭笑遊「片棒」(NHK-Eテレ『日本の話芸』)。
東京霞が関イイノホール、令和2(2020)年11月13日収録(第737回「NHK東京落語会」昼公演)。
◆林家つる子「反対俥」(読売テレビ第108回『平成紅梅亭』※将来の落語界を背負う若手スター大集合SP!)。
読売テレビ新社屋1階10ホール、令和2(2020)年11月25日収録(12月9日OA)。
つる子が大阪で落語を披露するのは初めてなんだろうかどうだろう。ここ数年は、東西交流が頻繁だから、たまに来ているものか。いずれにしても、昭和の時代のように、東京の落語家が大阪で演るときには緊張や気負いがあるみたいなことはもうなくなっているのかもしれない。また、その反対も。ただ、聞くがわとしては、初めて聞く大阪でのつる子だったので、ちょっと興味深くておもしろがれる。
ちなみに、つる子の「反対俥」は、以前『桂文珍の演芸図鑑』で一度聞いている。今年の8月だ。そのとき、つる子は老人の車屋のプロットを演らなかったので、「日記」にも、(『演芸図鑑』という番組のつごう上)「たぶんカットしたのだろうと思うが、もしかしたら、全体的に再構成された内容だったから、ふだんから老人パートは演っていないのかもしれない」と書いた。
◆三遊亭笑遊「片棒」(NHK-Eテレ『日本の話芸』)。
東京霞が関イイノホール、令和2(2020)年11月13日収録(第737回「NHK東京落語会」昼公演)。
◆林家つる子「反対俥」(読売テレビ第108回『平成紅梅亭』※将来の落語界を背負う若手スター大集合SP!)。
読売テレビ新社屋1階10ホール、令和2(2020)年11月25日収録(12月9日OA)。
つる子が大阪で落語を披露するのは初めてなんだろうかどうだろう。ここ数年は、東西交流が頻繁だから、たまに来ているものか。いずれにしても、昭和の時代のように、東京の落語家が大阪で演るときには緊張や気負いがあるみたいなことはもうなくなっているのかもしれない。また、その反対も。ただ、聞くがわとしては、初めて聞く大阪でのつる子だったので、ちょっと興味深くておもしろがれる。
ちなみに、つる子の「反対俥」は、以前『桂文珍の演芸図鑑』で一度聞いている。今年の8月だ。そのとき、つる子は老人の車屋のプロットを演らなかったので、「日記」にも、(『演芸図鑑』という番組のつごう上)「たぶんカットしたのだろうと思うが、もしかしたら、全体的に再構成された内容だったから、ふだんから老人パートは演っていないのかもしれない」と書いた。
そして、今日それが確認できた。つる子はふだんから老人パートは演っていなかったのである。なるほど、この演りかたもなかなかおもしろいと思う。他の落語家でも、「反対俥」について、時間のつごうとかでなく意図的に老人パートをカットする向きはあるのだろうか。
これはじっくり時間のある高座の際でなければ判断できないが、自分の記憶ではちょっといなかったのではという気がするが、どうだろう。
つる子は、終盤で、車屋が芸者を池に落して、客から「早く水からあげてやれ」と言われて、「芸者をあげることができるくらいなら、車屋なんかやってねえ」というなつかしいギャグを入れていた。これは、八代目橘家圓蔵でよくおぼえているが、昭和の落語家が使っていたものだ。つる子は「反対俥」を誰に教わったのだろう。
「水あげ」のギャグを一瞬落げと思わせておいて、まださきを続けていたが、これは圓蔵なんかだったらどうしていただろう。本当にここで切ったこともあったっけ。
今回は、大阪での会ということで、勢いのある車屋が大阪まで来てしまったというサービスを入れていた。でも、東京で群馬へ行こうとしていた客が「反対まで来てしまった」というのは、あれ?なんかへんだなと。まあ、いいか。
落げは、この前後の内容を省いて言葉だけ記せば、(懐に)「鰻が入っていた」だった。『演芸図鑑』で聞いたときは、「穴子が入っていた」だった。これは、群馬が穴子で名の知れたところからの落げだったようだが、今回鰻にかえたのはどういう意味からだったろう。
◆『笑点』大喜利:五代目三遊亭圓楽(司会)/三遊亭小遊三・三遊亭好楽・林家木久蔵(現木久扇)・桂歌丸・三遊亭楽太郎(現六代目円楽)・林家こん平(BS日テレ『笑点 水曜なつかし版』)。
後楽園ホール、平成11(1999)年9月19日OA(『笑点』第1682回)。
これはじっくり時間のある高座の際でなければ判断できないが、自分の記憶ではちょっといなかったのではという気がするが、どうだろう。
つる子は、終盤で、車屋が芸者を池に落して、客から「早く水からあげてやれ」と言われて、「芸者をあげることができるくらいなら、車屋なんかやってねえ」というなつかしいギャグを入れていた。これは、八代目橘家圓蔵でよくおぼえているが、昭和の落語家が使っていたものだ。つる子は「反対俥」を誰に教わったのだろう。
「水あげ」のギャグを一瞬落げと思わせておいて、まださきを続けていたが、これは圓蔵なんかだったらどうしていただろう。本当にここで切ったこともあったっけ。
今回は、大阪での会ということで、勢いのある車屋が大阪まで来てしまったというサービスを入れていた。でも、東京で群馬へ行こうとしていた客が「反対まで来てしまった」というのは、あれ?なんかへんだなと。まあ、いいか。
落げは、この前後の内容を省いて言葉だけ記せば、(懐に)「鰻が入っていた」だった。『演芸図鑑』で聞いたときは、「穴子が入っていた」だった。これは、群馬が穴子で名の知れたところからの落げだったようだが、今回鰻にかえたのはどういう意味からだったろう。
◆『笑点』大喜利:五代目三遊亭圓楽(司会)/三遊亭小遊三・三遊亭好楽・林家木久蔵(現木久扇)・桂歌丸・三遊亭楽太郎(現六代目円楽)・林家こん平(BS日テレ『笑点 水曜なつかし版』)。
後楽園ホール、平成11(1999)年9月19日OA(『笑点』第1682回)。