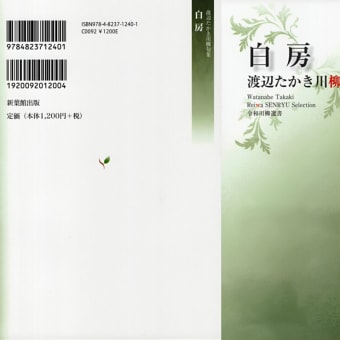□本日落語一席。
◆九代目林家正蔵「おかめ団子」(TBSチャンネル『落語研究会』)。
東京三宅坂国立劇場小劇場、令和2(2020)年12月25日(第630回「TBS落語研究会」※無観客)。
大根屋の泥棒がおかめ団子へ盗みに入り、たまたま自殺しようとしていた娘を見つけて助けることになるという噺。おかめ団子の主人は、大根屋の泥棒を見のがしてやり、その後、大根屋と娘の縁談へと発展する。
もともと大根屋の泥棒は、貧しいくらしのなかで、母親の布団を買ってやりたいがために、盗みをはたらいたのだが、おかめ団子の主人は、娘が大根屋と夫婦になったら、さぞかし孝行をするだろう、根が大根屋だからという、孝行と香々に掛けた地口落ちである。
今回、正蔵は、主人が大根屋に縁談をもちかけるも、大根屋は家柄のつりあいがとれないからと固辞するという筋にしていた。すると、主人はそんなに固辞するのなら、盗みのかどで訴えるぞと言う。大根屋は、自分は結局何も盗らなかったのにと言うと、主人がうちの娘の心を盗んだと言って落げていた。
正蔵のオリジナルだろうか。当代の落語家としては、林家たい平と八代目橘家圓太郎で聞いているのだが、落げはどうだったかおぼえていない。ちなみに、昭和の名人としては、彦六の八代目林家正蔵は、さきに記した落げ、五代目古今亭志ん生はおおむね落げをつけていなかったようだ。
これは、設定が江戸時代だと思うのだが、この時代の人々の発想として、「心を盗む」などという言葉があったのかと思ってしまうところに違和感があった。いや、これは自分が無知なだけであったのかもしれないが、どうだろう。いったい「心を盗む」などという表現の出どころはどうなのだということが、とても気になり出した。
◆九代目林家正蔵「おかめ団子」(TBSチャンネル『落語研究会』)。
東京三宅坂国立劇場小劇場、令和2(2020)年12月25日(第630回「TBS落語研究会」※無観客)。
大根屋の泥棒がおかめ団子へ盗みに入り、たまたま自殺しようとしていた娘を見つけて助けることになるという噺。おかめ団子の主人は、大根屋の泥棒を見のがしてやり、その後、大根屋と娘の縁談へと発展する。
もともと大根屋の泥棒は、貧しいくらしのなかで、母親の布団を買ってやりたいがために、盗みをはたらいたのだが、おかめ団子の主人は、娘が大根屋と夫婦になったら、さぞかし孝行をするだろう、根が大根屋だからという、孝行と香々に掛けた地口落ちである。
今回、正蔵は、主人が大根屋に縁談をもちかけるも、大根屋は家柄のつりあいがとれないからと固辞するという筋にしていた。すると、主人はそんなに固辞するのなら、盗みのかどで訴えるぞと言う。大根屋は、自分は結局何も盗らなかったのにと言うと、主人がうちの娘の心を盗んだと言って落げていた。
正蔵のオリジナルだろうか。当代の落語家としては、林家たい平と八代目橘家圓太郎で聞いているのだが、落げはどうだったかおぼえていない。ちなみに、昭和の名人としては、彦六の八代目林家正蔵は、さきに記した落げ、五代目古今亭志ん生はおおむね落げをつけていなかったようだ。
これは、設定が江戸時代だと思うのだが、この時代の人々の発想として、「心を盗む」などという言葉があったのかと思ってしまうところに違和感があった。いや、これは自分が無知なだけであったのかもしれないが、どうだろう。いったい「心を盗む」などという表現の出どころはどうなのだということが、とても気になり出した。