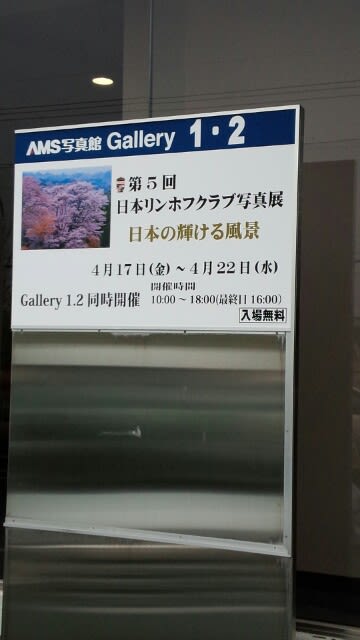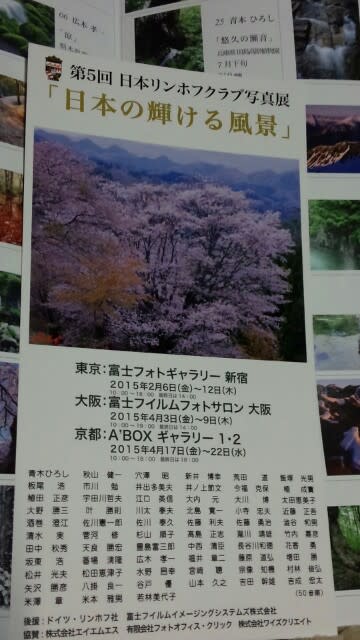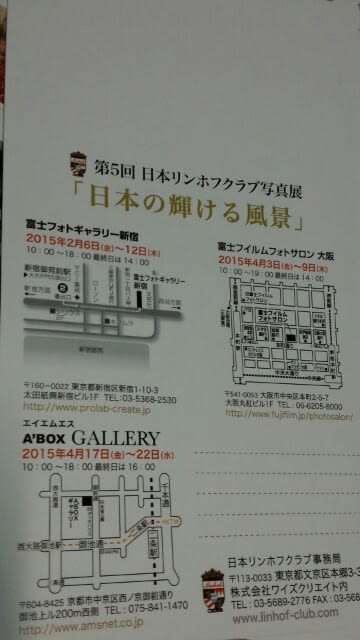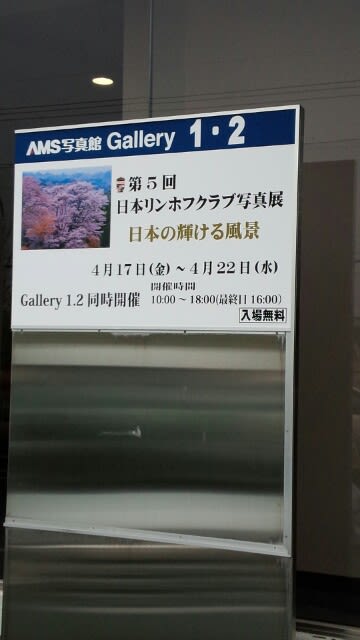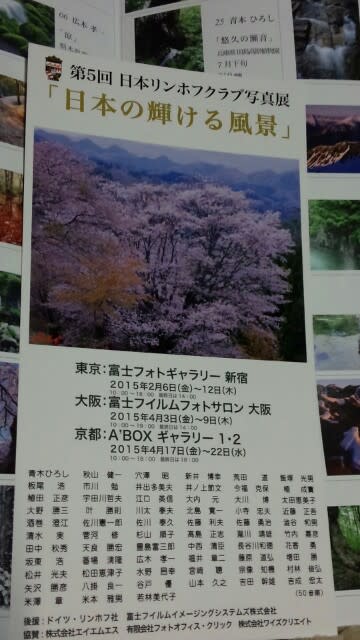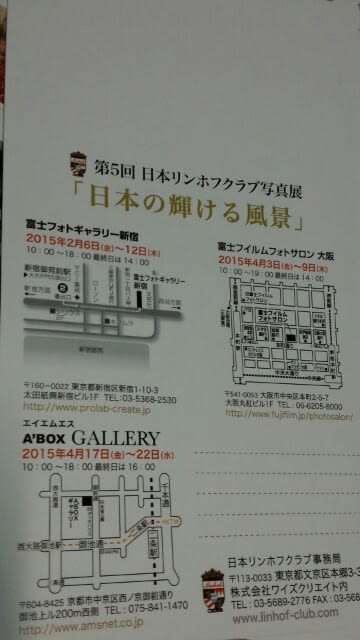マミヤプレス スーパー23

とうとう買ってしまいました。
絶対に手を出さないつもりでいたのですが、以前見た事のあるマミヤプレスファンクラブというサイトをまた見てしまったのと、その時には分からなかったマミヤプレスの魅力に気づいてしまったのです。
35㎜と4×5に加えて中判カメラ(マミヤ RB プロ SD+KLレンズなど)では選択肢があり過ぎて荷が重いので、中判カメラを全部手放す予定ですが、リンホフ以外にブローニーフィルムを使える、しかも気軽に、カメラの必要性を感じていました。
カメラ本体はかなり程度の良い物で、おまけに付属していたオリジナルのキャリングケースが素晴らしく綺麗で古臭い臭いすらありませんでした。
ロールフィルムホルダーのモルトが傷んでいるので交換した方が良いでしょう。
セットされてたレンズはセコールの90㎜でした。
スーパー23からは標準レンズが100㎜/F3.5に変更されているのでどうして90㎜なのかよく分かりません。
そうかと言って使えない訳でなく、その際ファインダーから見える視界全てが写る範囲となります。
100㎜を選択

ファインダーの中

外側は6×9、内側は6×7。枠の外側が要するに90㎜レンズの視野。
ちなみにファインダーは100㎜の他に


残念な事にこの90㎜レンズは1秒の
シャッタースピードが長くて使えませんので、90㎜か100㎜/F3.5を探しています。
1/30秒は何度も切っている内にそれらしいスピードになってましたきましたが、1秒は何度やっても1.5秒位にしかなりません。
まあその分絞りで調整すれば良いだけですが。
100㎜レンズには他にF2.8タイプもありますが、あおり撮影には対応しません(近距離撮影?では可能か?)。
あおり撮影と言いましたが、スーパー23は初期型マミヤプレス同様バックあおり機構が設けられています。
あおり撮影には90㎜と100㎜/F3.5のみが対応します。
この2つのレンズは沈胴式になっていて
、沈胴させる事によって無限遠が出るようになっています。
沈胴させない時は近距離のみのあおり撮影に対応するという事です。
あおり使用時(当然マクロ撮影時も)はファインダーではなくピントグラスを用いるからです。
バックあおりは蛇腹を約30㎜まで引き出せます。
全部引き出すだけで90㎜レンズで最大0.47倍(ワーキングディスタンス26.6㎝、露出倍数2.1)の近接撮影が出来ます。
更に専用接写チューブを使えば最大1.59倍(ワーキングディスタンス13㎝、露出倍数6.7)の近接撮影が可能との事です。
接写チューブに蛇腹を全部引き出した数字だそうです。
あおりを使った近接撮影では当然蛇腹を引き出さないので倍率はこれより低いでしょう。
また最大15°まで傾ける事が出来るあおりは、ピントの合っている範囲を調節してパンフォーカスから狙った部分のみ強調まで色々使えます。
更にすぼまりなどの形を調整する事も出来ます。
当然ながらあおり量も多くないので自ずから限度はありますし、バックあおりのみなのでパンフォーカス写真を撮る時は形が変わってしまう欠点があります。
それがまた逆に遠近感を強調するとして時には効果的となると言われております。
マミヤプレスはレンジファインダー式のカメラなので、あおり撮影(または近接撮影)を行う時はロールフィルムホルダーとピントグラスを付け替えて構図やピント合わせしたりします。
撮影する時はピントグラスと再び付け替えます。
ファインダーを覗いて構図やピント合わせをする通常の撮影では、レンズキャップの外し忘れに注意しなくてはなりません。
本体サイドに大きな手持ちグリップがスクリュー留めにて装着されています。
グリップ下部からレリーズケーブルが出ていてレンズのシャッターレリーズホールにネジ込まれています。
そしてグリップ上部のボタンを親指で押し込むとシャッターが切れます。
マミヤプレスはレンズシャッター式のカメラです。