●歴史は、破産するまで終わらないゲームなのだ

「若い頃は歴史家になりたかった」 老将軍がつぶやく。
「なぜ、ならなかったんですか」と、若い士官が聞く。
老将軍は滔々と語り始める。
「戦争が起きた…それで軍人になった。同胞を異民族の侵略から守るため、必死で戦った。しかしそれが正義などではなく、太古の昔から繰り返されて来た殺戮の歴史をなぞっているだけであることも、よく知っていた。悲しかったよ…いや軍人になったことじゃない。歴史を勉強したことがだ。…歴史は破産するまで終わらないゲームなのだ。たぶん、間抜けなサルが始めたに違いない…」
高校1年くらいの頃、だったと思う。金曜日の夜だった。なんとなしにテレビで放映されたアニメーション映画を観ていて、気づくと僕は静かで激しい感動に心をゆだねていた。それは内気だった僕が描いていた、自分だけの心象風景に、すっぽりとはまってくるストーリーだった。
その映画?「王立宇宙軍 オネアミスの翼」が、無名でかつ気鋭の若手映像作家たちによって作られた作品だということを 僕が知ったのはだいぶ後のことだ。
その映画を第一回の作品として産声を上げたガイナックスは、その後「不思議の海のナディア」や「新世紀エヴァンゲリオン」など、アニメーション史上の金字塔に残る作品を生み出すことになる。
架空の王国オネアミスを舞台に、落ちこぼれ集団である宇宙軍の若者たちが、世界初の有人宇宙飛行計画を達成する姿を描いたのが、「オネアミスの翼」の物語だ。
そのなかで、行軍する兵士と女神を描いた木彫りのレリーフを前に、主人公であり宇宙飛行士となる士官と老将軍が、戦争、それから歴史について語ったくだりは、いつまでも僕の印象に残っている。
当時の僕は?いまもだけど、歴史が好きで学校では最も得意な科目だった。高校3年になって大学進学を考える頃になると、史学科に進もうとした。実際には僕の地元に史学科のある大学はそれほど多くなく、たまたま文化人類学の講座をもつ地元の私立大学に合格して、そこで4年間民族学を勉強した(これはこれで歴史以上に面白い学問だった)。
そんなわけで、いまに至るまで歴史の本を読むのを僕は日常的な趣味としている。
2005年10月17日、小泉総理大臣が5回目の靖国神社参拝を行なったその日に読み終えたのは、世界史をテーマにした書物だった。

人間ものがたり?石器時代から現代までのわたしたちの歴史
ジェイムズ C.デイヴィス (著), 布施 由紀子
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/414081067X/
タイトルの通り、石器時代から現代までを俯瞰した通史の本。
通史といえば、数年前に刊行されていた中央公論新社版「世界の歴史」を僕は一冊一冊購入して、ついに全30巻を揃えた。本棚に並んでいるのを眺めるのは壮観だ。ただ、全30巻というのは気軽に読み返せる量ではない。
だいたい本の内容からして押し並べて硬いし、それなりにかしこまって対峙しなければならない。僕と彼ら本たちはけっこう気が張る関係なのだ。だから、たとえば僕が死ぬまでの間かけても再びこれらの巻を全てひもとくことができるかは、大いに疑問である。
それに比べると、このたび手にした「人間ものがたり」はかなりくだけた部類の本ということになる。もちろんけっこうページ数があって、単体の本としてはかなり分厚いものになるだろう。でも、書名を人間ものがたりと掲げて、「石器時代から現代までのわたしたちの歴史」とサブタイトルをつけるあたり、だいぶん肩の力を抜いてページを開いてほしいという姿勢がいかにもみてとれる。
ページを開けば章のタイトルもまたユニークでユーモラスなのだ。「戦争を終わらせるための戦争」とか「理想郷が悪夢に転じる」とか「人類、信じられないことをする」とかね。万事がこんな感じで24コのテーマが設定されている。ちょっと読んでみたくなるでしょう?
歴史書としてみると、部分部分では、筆者の解釈の都合よくあわせるように史実が選び取られたり、順序が入れ替わっていたりする。もっともそれはある程度歴史への理解を深めたからわかる話。この本は学術書ではない。最初のとっかかりとしてはこういう本が必要であり、わかりやすい記述を駆使して目をひくべきなんだろう。
それで、そもそも自分が歴史好きだからよくわからなかったけど、冷静になって見渡してみると歴史についての知識を得ていない人はけっこういるものだ。とくに受験科目にそれがなかった理系出身の人たちに多い。これは不思議なことだ。頭がそれなりにいいのに、ある分野がすっぽり抜け落ちている。まあ、彼らも物理や数学の知識がまるでない僕は同じように映っているのかもしれないけど。
そういう、歴史の教科を履修する過程を経てこなかった人たちでも、この人類が積み上げてきたことに好奇心を有している人たちはそれなりにいる。
歴史に興味があるけれど、どこから入ったらいいのかわからない人。あるいはかつて学校時代に学んだことを、経験を積んだいまだからこそおさらいしてみたい人。そんな人たちにピッタリだと僕は思った。とてもわかりやすく、かなりわくわくとさせられる本だった。
冒頭に掲げた会話。
その舞台となった作品世界に、僕は虜になった。
世の中にDVDというものが出回り始めた頃、プレイヤーもないのに「王立宇宙軍 オネアミスの翼」のディスクを買ったのは、僕だ。
だが、いま考えてみるとこれ、同胞のため戦った老軍人のセリフとしては、いささかストイックにすぎるだろう。
もちろん、その語りは深淵に富み、戦争なるものへの評価のしかたとしては全く正しいスタイルである。
といって、では実際に生死を賭して人びとを守るために戦った軍人が、自分の戦績を振り返ってそれが「殺戮の歴史をなぞっているだけ」なんて感想を吐露するだろうか。そこまで相対的なポジションに身を置けるだろうか。たとえかつて歴史家を志していたとしても。
そう、現在の(現在に限らず過去も、そしておそらく未来も?)論壇というものを眺めればわかる。偏差値の高い大学に籍を置き、知的探求の道をきわめた御仁たちが、いかにも特定の主義主張に拘泥していることがある。同じ史実の羅列を前に、保守派になるやつもいれば左翼になるやつもいる。なかにはトンデモ史観に走ってしまう輩もいないわけではない。歴史を知る人がことさらクールになり、達観できるかというと、どうやらそれはアプリオリではないよ。
平和な時代の知識人ですらそうだ。ましてや職業として軍人という立場に身を置いたのなら、若かりし折に学んだことよりも、戦争の論理のなかで刷り込まれた正義のほうを絶対視してしまうであろうことは、想像に難くない。
仮に傍からそれが偏狭な信念に映ったとしても、そんなことは当事者たちには意味をもたない。それを責めることはできないだろう。戦争だったのだ。

そして全ては、老将軍のこぼした一言にたどりつく。あたかも自己撞着であるかのような、このつぶやきに。
「われわれ人類は原始時代の地獄から抜け出し、10万年かかってここまでたどりついた。しかしここはどうだ…根本的には何も変わらんじゃないか」

「若い頃は歴史家になりたかった」 老将軍がつぶやく。
「なぜ、ならなかったんですか」と、若い士官が聞く。
老将軍は滔々と語り始める。
「戦争が起きた…それで軍人になった。同胞を異民族の侵略から守るため、必死で戦った。しかしそれが正義などではなく、太古の昔から繰り返されて来た殺戮の歴史をなぞっているだけであることも、よく知っていた。悲しかったよ…いや軍人になったことじゃない。歴史を勉強したことがだ。…歴史は破産するまで終わらないゲームなのだ。たぶん、間抜けなサルが始めたに違いない…」
高校1年くらいの頃、だったと思う。金曜日の夜だった。なんとなしにテレビで放映されたアニメーション映画を観ていて、気づくと僕は静かで激しい感動に心をゆだねていた。それは内気だった僕が描いていた、自分だけの心象風景に、すっぽりとはまってくるストーリーだった。
その映画?「王立宇宙軍 オネアミスの翼」が、無名でかつ気鋭の若手映像作家たちによって作られた作品だということを 僕が知ったのはだいぶ後のことだ。
その映画を第一回の作品として産声を上げたガイナックスは、その後「不思議の海のナディア」や「新世紀エヴァンゲリオン」など、アニメーション史上の金字塔に残る作品を生み出すことになる。
架空の王国オネアミスを舞台に、落ちこぼれ集団である宇宙軍の若者たちが、世界初の有人宇宙飛行計画を達成する姿を描いたのが、「オネアミスの翼」の物語だ。
そのなかで、行軍する兵士と女神を描いた木彫りのレリーフを前に、主人公であり宇宙飛行士となる士官と老将軍が、戦争、それから歴史について語ったくだりは、いつまでも僕の印象に残っている。
当時の僕は?いまもだけど、歴史が好きで学校では最も得意な科目だった。高校3年になって大学進学を考える頃になると、史学科に進もうとした。実際には僕の地元に史学科のある大学はそれほど多くなく、たまたま文化人類学の講座をもつ地元の私立大学に合格して、そこで4年間民族学を勉強した(これはこれで歴史以上に面白い学問だった)。
そんなわけで、いまに至るまで歴史の本を読むのを僕は日常的な趣味としている。
2005年10月17日、小泉総理大臣が5回目の靖国神社参拝を行なったその日に読み終えたのは、世界史をテーマにした書物だった。

人間ものがたり?石器時代から現代までのわたしたちの歴史
ジェイムズ C.デイヴィス (著), 布施 由紀子
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/414081067X/
タイトルの通り、石器時代から現代までを俯瞰した通史の本。
通史といえば、数年前に刊行されていた中央公論新社版「世界の歴史」を僕は一冊一冊購入して、ついに全30巻を揃えた。本棚に並んでいるのを眺めるのは壮観だ。ただ、全30巻というのは気軽に読み返せる量ではない。
だいたい本の内容からして押し並べて硬いし、それなりにかしこまって対峙しなければならない。僕と彼ら本たちはけっこう気が張る関係なのだ。だから、たとえば僕が死ぬまでの間かけても再びこれらの巻を全てひもとくことができるかは、大いに疑問である。
それに比べると、このたび手にした「人間ものがたり」はかなりくだけた部類の本ということになる。もちろんけっこうページ数があって、単体の本としてはかなり分厚いものになるだろう。でも、書名を人間ものがたりと掲げて、「石器時代から現代までのわたしたちの歴史」とサブタイトルをつけるあたり、だいぶん肩の力を抜いてページを開いてほしいという姿勢がいかにもみてとれる。
ページを開けば章のタイトルもまたユニークでユーモラスなのだ。「戦争を終わらせるための戦争」とか「理想郷が悪夢に転じる」とか「人類、信じられないことをする」とかね。万事がこんな感じで24コのテーマが設定されている。ちょっと読んでみたくなるでしょう?
歴史書としてみると、部分部分では、筆者の解釈の都合よくあわせるように史実が選び取られたり、順序が入れ替わっていたりする。もっともそれはある程度歴史への理解を深めたからわかる話。この本は学術書ではない。最初のとっかかりとしてはこういう本が必要であり、わかりやすい記述を駆使して目をひくべきなんだろう。
それで、そもそも自分が歴史好きだからよくわからなかったけど、冷静になって見渡してみると歴史についての知識を得ていない人はけっこういるものだ。とくに受験科目にそれがなかった理系出身の人たちに多い。これは不思議なことだ。頭がそれなりにいいのに、ある分野がすっぽり抜け落ちている。まあ、彼らも物理や数学の知識がまるでない僕は同じように映っているのかもしれないけど。
そういう、歴史の教科を履修する過程を経てこなかった人たちでも、この人類が積み上げてきたことに好奇心を有している人たちはそれなりにいる。
歴史に興味があるけれど、どこから入ったらいいのかわからない人。あるいはかつて学校時代に学んだことを、経験を積んだいまだからこそおさらいしてみたい人。そんな人たちにピッタリだと僕は思った。とてもわかりやすく、かなりわくわくとさせられる本だった。
冒頭に掲げた会話。
その舞台となった作品世界に、僕は虜になった。
世の中にDVDというものが出回り始めた頃、プレイヤーもないのに「王立宇宙軍 オネアミスの翼」のディスクを買ったのは、僕だ。
だが、いま考えてみるとこれ、同胞のため戦った老軍人のセリフとしては、いささかストイックにすぎるだろう。
もちろん、その語りは深淵に富み、戦争なるものへの評価のしかたとしては全く正しいスタイルである。
といって、では実際に生死を賭して人びとを守るために戦った軍人が、自分の戦績を振り返ってそれが「殺戮の歴史をなぞっているだけ」なんて感想を吐露するだろうか。そこまで相対的なポジションに身を置けるだろうか。たとえかつて歴史家を志していたとしても。
そう、現在の(現在に限らず過去も、そしておそらく未来も?)論壇というものを眺めればわかる。偏差値の高い大学に籍を置き、知的探求の道をきわめた御仁たちが、いかにも特定の主義主張に拘泥していることがある。同じ史実の羅列を前に、保守派になるやつもいれば左翼になるやつもいる。なかにはトンデモ史観に走ってしまう輩もいないわけではない。歴史を知る人がことさらクールになり、達観できるかというと、どうやらそれはアプリオリではないよ。
平和な時代の知識人ですらそうだ。ましてや職業として軍人という立場に身を置いたのなら、若かりし折に学んだことよりも、戦争の論理のなかで刷り込まれた正義のほうを絶対視してしまうであろうことは、想像に難くない。
仮に傍からそれが偏狭な信念に映ったとしても、そんなことは当事者たちには意味をもたない。それを責めることはできないだろう。戦争だったのだ。

そして全ては、老将軍のこぼした一言にたどりつく。あたかも自己撞着であるかのような、このつぶやきに。
「われわれ人類は原始時代の地獄から抜け出し、10万年かかってここまでたどりついた。しかしここはどうだ…根本的には何も変わらんじゃないか」










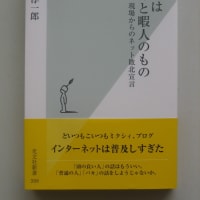


![[政治] 官邸主導 小泉純一郎の革命](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/25/9b/c6fccc6e75e41c41d401fa5951bdb509.jpg)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます