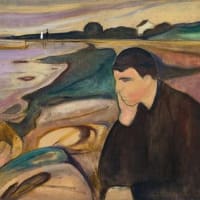高台寺を見る予定はなかったのですが、高台寺の前の観光案内のおじさんに3カ所共通拝観券はお得だよと薦められて、圓徳院で券を購入。「高台寺」、「高台寺掌美術館」、「圓徳院」の3カ所の拝観のほかに絵葉書セットか手ぬぐいのサービスがついてきました。これで900円とはかなりお買い得でした。
高台寺を見る予定はなかったのですが、高台寺の前の観光案内のおじさんに3カ所共通拝観券はお得だよと薦められて、圓徳院で券を購入。「高台寺」、「高台寺掌美術館」、「圓徳院」の3カ所の拝観のほかに絵葉書セットか手ぬぐいのサービスがついてきました。これで900円とはかなりお買い得でした。
圓徳院は伏見城にあった化粧御殿を東山に移築したものです。北政所はここで19年間余生を送り、北政所を慕った大名や禅僧、茶人、歌人、画家などの多くの文化人が訪れた場所でもあります。中に入ってみると、驚くほど視界が開けた部屋がありました。あまりの切り取られた風景の美しさに思わず立ち尽くしてしまったくらいです。大原にある宝泉院の風景の切り取られ方もすばらしいのですが、それに劣らないすばらしさでした。北庭は伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したもので、当時の原型をほぼそのまま留めています。代表的な桃山時代の庭園のひとつで、賢庭作で後に小堀遠州が手を加えました。この庭を効果的に見せるために方丈の柱は最小限にしているのでしょう。それにしても、細い柱でどのように建物を支えているのか気になります。
ここの見所はもうひとつあります。それは障壁画です。たまたま長谷川等伯の襖絵が公開されていたので拝見。やはり時がたっていたため色あせていていました。それにしても桐紋の唐紙に描くのはどうなのだろうかという疑問があったのですが、それはパンフレットを読んで解決。襖絵制作をしたいと思っていた等伯は住職から許可がもらえなかったので、住職の留守中に勝手に襖絵を描いたからだそうです。等伯さんってお茶目な人だったようです。今回は長谷川等伯の襖絵公開のため、通常飾られている襖はいくつか取り払われていましたが、通常飾られている襖絵も迫力がありステキでした。普通、床の間には掛軸を飾るため絵は描かれませんが、木に掛軸をぶら下げるようなデザインで描かれているのを見て、日本美術の豊かな遊び心を感じました。
高台寺
高台寺は、パンフレットで見た傘亭が気になっていました。でも、傘亭があるのは一番奥。傘亭を目指しながら、所々にある重要文化財を見学。
開山堂は、高台寺第一世の住持を祀る塔所で、左右の壇上にはねねの兄夫婦の像が安置されています。しかし、見所はそれだけではありません。彩色天井がすばらしいのです。日本画でよく描かれるような美人画に翼が生えた絵。ある意味、ツボにはまります。
臥龍廊はその名のとおり龍の背に似ていることからつけられた名前で開山堂と霊屋を結んでいます。
霊屋は、秀吉と北政所をお祀りしている所で厨子内には秀吉と北政所の木像が安置されています。扉の都合上、秀吉と北政所の木像を同時に見ることはなかなか難しいのが少々残念。ここは、秀吉と北政所を祀っているだけあって、贅沢な蒔絵で飾られています。
やっとたどりついた傘亭。内側の放射状の竹が写真では美しかったのですが、わずかな開口部からはそれを確認できませんでした。ん~残念。時雨亭も内部をよく見ることができませんでした。これらは写真の方が楽しめるものなのかもしれません。
高台寺掌美術館
高台寺ゆかりの品々が展示されています。ここで展示されているものでやはり目を引くのは蒔絵です。黒に浮かび上がる金色が美しかったです。こういう美しいものに囲まれてみたいです。でも、実際囲まれたらどぎまぎするでしょうけどね。