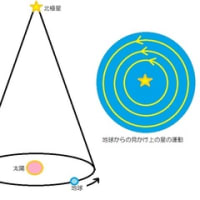1 始めたきっかけと「目標」
早いもので、このブログを始めてから1年間が過ぎてしまった。
こんな形と内容で文章を書こうと思ったのは、じつは、こういう傾向の文章を私が読みたかったからだ。読みたかったのだが、ざっと見渡したところ、なさそうだった。では仕方がない、自分でリサーチし、検討・考察を加えて書くしかない。「読みたい文章を、自分で書く」という動機で始めた。
ただし、その動機どおりに、ことが進んだかどうかは、よくわからない。大雑把には、動機に沿って制作したとは思うが、思い通りに行かなかったこともそれなりに多い。
当初の目標では、「1月に1回分」くらいでいいか、だったが、ずいぶんペイスが上がって駆け抜けるように、突っ走ってしまった。その分、荒削りに過ぎたかもしれない。
2 めざしたもの
英語版のWikipediaには、映画のストーリーやプロットを紹介した記事の集成がある。現在も、世界中の書き手や批評家、あ映画ファンが、得意な分野について書き加え、記事項目も膨張している。
それらについては、以前から読んでいて知っていた。
だから、同じような調子、構成の記事にはしたくなかった。
だから、普通の「映画批評」「映画紹介」にはしたくなかった。
その大向こうを張ろうと、見得を切った。
自分の得意なスタイルで挑戦しようと思った。
映画とは、映像による「同時代」の(過去や未来や現在、あるいは荒唐無稽な空想などについての)精神の具現化、イメイジの投影だといえる。制作者の「世界」についてのイメイジ(考え方、批判精神)が表現されているものだ。
だとすれば、その物語と背景について、社会学的、社会史的な視点で考察し、同時代=「現代という時代」(歴史)の人類の歴史意識や社会意識についての記録として、記述できないか。そう考えた。
ただし、それだけだと扱い方が狭いので、作品の物語そのものについても、その流れを追いながら、できるだけ説明することにした。私の主観や評価を織り交ぜて。
映画の物語の流れを追いかける手法には、メリットがある。その流れは、かなり熟達した脚本家や演出家が、さらに原作がある場合には優れた作家が、観客へのアピール度や映像効果を考え抜いてつくり上げたものだ。起承転結やメリハリがしっかりしている。
ゆえに、私の文章作成能力の限界を超えることができる。つまり、物語の展開をそのまま追いかければ、それだけでもある程度読みやすい文章、起承転結がしっかりした文脈が形成される。そうすれば、私は筋立てにあまり悩まなくて済む。
3 歴史的資料としての映画
それぞれ1つの作品としての映画は、それがファンタジーやフィクションであっても、すぐれた歴史的資料だといえる。かならず、その映画がつくられたときの社会の文化や価値観だけでなく、政治や経済なども、何ほどかは反映している。
そして、映画は、映像そのものだけでなく、音楽、演劇、文学、絵画などの要素を重要な構成要因として含んでいる。つまりは、一種の総合芸術をなしている。
それゆえに、十分に社会科学や社会学、歴史学の研究対象になる。
しかし、これまでのところ、そういう扱いは十分されてこなかった。
もとより、映画人を育てるための素材として、映像作成の方法論・手法それ自体を検討し、洗練させるために研究されることは、かなりの精力をかけて、取り組まれてきた。社会評論の素材にもなってきた。だが、学問の1分野としては、まだ成り立っていない。
「たかが映画」にそれだけの価値はない、というアカデミズムの側の判断があったのか。
しかし、私としては、映画は総合芸術であるがゆえに、社会と歴史の総合的な考察のすぐれた素材となると考える。
その最大の長所は、映像=画像が主体(最重要の構成要素)となっていることだ。
このブログの記事ですでに述べてきたように、従来の歴史学や社会学、社会科学は、訓練された専門家向けのもので、一般社会や民衆からのアプローチを拒んできた。拒んでいるあいだに、時代遅れになったり、普通の人びとの生活実感や人生観、世界観から遠いものになってしまった。とくに日本では。
アカデミズムは、具体的な名前のカテゴリーを記述し操作しても、一般の人びとの体感や実感にも照応するような歴史や社会のイメイジをうまく提示できなかった。抽象的な理論や論理の構築で終わっていた。
しかも、一見、複雑で抽象的な論理の操作や構築にかかわっているかに見える外観のもとで、アカデミズムでは、問題の立て方や方法、結論について、「論理のすりかえ」、「論点ずらし」をおこなうことができた。
素朴な疑問は、「門外漢の素人考え」や「低次元の無理解」だとして、門前払いや切捨てができた。
たしかに、博覧強記、牽強付会をこととする学者先生が相手では、素朴な疑問は入り口の前で追い払われるのも仕方がない。アカデミズムは、自己防御の構造として、建設業界や土建業界も顔負けの、より手の込んだ業界談合システムを、幾重にも張りめぐらせている。
じつのところかなり重要な問題を提起したり、学説の欠陥をついている素朴な疑問は、こうしてアカデミズムの検討課題から、慇懃無礼に外される。
けれども、ごく素朴な疑問が、一見すきまなく構築された学術理論をいとも簡単に突き崩してしまう「蟻の一穴」になることを、私自身体験している。だから、アカデミズムのある部分は、素朴な疑問を排除する仕組みを備えている。
ところが、映像を中心的な分析素材に据えれば、少なくとも、映画に登場した限りで具体的な人物や人間関係、社会状況、人びとの行動様式、意識などについては、かなりの程度つかむことができる。
映画を素材にすることで、少なくとも映画作品を観た人たちとのあいだでは、共通の出発点、話題や材料の共有ができる。
映像で現に観ているものについて感想を述べたり、考察を開始することは、学者先生でも一般の「門外漢」でも、同じようにできる。むしろ、「象牙の塔」の外部で、世間の荒波をくぐっている一般人の方が、問題や状況を素直に捉えることができるかもしれない。
あとは、アカデミズムでの権威ではなく、それぞれの人びとが提示する「言葉」「文章」の説得力が、いずれのとらえ方がより「正しそうか」と判断するうえでの材料になる。
ただし、映像を対象にしても、その背後にある歴史的な文脈や社会状況については、それなりの深い分析や洞察が必要になる。それは、一定の訓練が必要になる。野球やサッカー、スキーなどと同じことだ。
以上のような意図を背後に置きながら、その試みの1つとしてとにかく始めてみた。
4 たかがブログ、されどブログ
と、いっぱし肩肘張ってみても、ただの「田舎おやじ」のやれることはタカが知れている。それに、そんなブログを一生懸命つくってみても、誰が読むの? とは思う。おそらく、限られたごく少数の読者に向けて発進する「超零細メディア」にとどまることになるだろう。
それでいいと思う。しょせん、余暇時間におこなう趣味にすぎない。注ぎ込む時間もたかが知れている。
いまのところ、ブログ作成に使っている1日当たりの平均時間は、せいぜい1時間もあればましな方だ。
毎日こつこつと考え、調べ、書き込んでいる。だが、少しずつでも日課として続ければ、かなりの量になる。1年間に三十数回分で、だいたい1回当たり1万7000字くらいだから、50~60万字くらいの文字量にはなった。
そうなると、どういうメディアを利用するにしろ、映画作品を観るときは、かなり意識的に登場人物や背景、状況設定について「まじめに」考えるようになった。で、気づいたことは、これまではかなりいい加減に映画を観てきたということだ。
ブログの内容はともかく、それだけは大きな成果だったいえる。
ただし、作品がブログに取り上げるつもりがいなくても、これまでのように、あまり意識せずにただ楽しんで観るということができなくなってしまった。
5 題材と内容について
ブログが氾濫する現在、自分なりにこのブログの存在意味を考える(自己満足のために)と、「ほかではまずは目にすることがない記事」を提示する、ということになってくる。つまりは、「へそ曲がりに徹する」ということだ。
もっとも、映画の設定した物語や状況設定の社会史的意味や歴史的文脈、政治的背景を探り描くということ方法自体が、たぶん目新しいではあろう。だが、発想だけ新しくても、内容が従来の通俗的な歴史観や教科書的な説明では、要するに「同工異曲」でしかない。
そこで、「世界のアカデミズム」でも先端の問題領域に踏み込むことにおそらくはなるであろう事件や状況を扱うようにしようと企図した。それで、《新しい世界観》《ちょっとひねった歴史観》を提起しようと考えた。
そのくらい映画の状況描写、背景描写には、映像制作者たちの鋭い感性や洞察がたたみ込まれている。なかなかバカにならない。大学での講義よりもはるかに内容が充実していて、しかも面白い。
ただ、そういう材料が「しょせん娯楽作品だ」という扱いで、本格的な社会学的・社会史的な分析の対象となっていない。
ブログでは、そういう問題を「できるだけ簡略に」記述しようと思った。だが、問題それ自体の意味や性格をある程度きちんと提示して、起承転結をつけて説明しなければいけない。しかも、扱う内容はポレーミッシュ(論争百出)の問題だから、いくつもの事柄が複雑に絡み合っている場合が多い。
で、説明にかなりの文字量を要することになる。文章が長く、複雑になる。
それで、私がよって立っている認識論や文章技術を理解してもらう場として、「文章技術コース」を連載することにした。なぜ、どのようにして、こんな文章を書くのか、そんな問題の立て方をするのか、どうして説明の組み立てがそうなっているのか、を知ってもらおうと意図したのだ。が、それがうまくいっているかは自信がない。
だが、それらは、私から見て、現在の日本の教育や高等教育で、一番弱いというか欠落している「ミッシングリンク」だといえる。業績や成績のの優劣、つまり競争のなかで地位ではなく、「自分の頭でものを考えること」を最重視する心性というか態度だ。
つまり、私のこのブログの中身も含めて、世の中に発信され飛び交っている情報の内容は、すべからく疑わしい、ということだ。疑わしいからといって、私たちにとっては、そういう材料を使って考え、自分なりの価値観に沿ってイメイジを描くしかない。とすれば、それらを吟味したり、比較考量したり、ようするに批判し、解体し、創造的に再利用する術を模索するしかない。
そのための、ただし「疑わしい」材料を提示しようとしている。
私の言説の「少なくとも半分」は疑わしい、という視点で見てほしい。
もっとも、それは、私に限らず、意見を表明するすべての人に対してなのだが。
よくても、正しいのは「半分だけ」なのだ、と。
■作品自体が呼び起こす視座■
それにしても、映画作品のうち歴史や哲学、政治経済の問題に絡められるものの数はあまりない。ゆえに、いつもこういう調子の記述になるわけではない。
だから、映画の物語や「語り口」そのものを楽しむ記事も多くなる。そうなれば、作品の見方、つまり考察の視点や視座、眼差しについて、いろいろ工夫を凝らす必要がある。
その場合、私としては「こじつけ」のように映画に私の価値観を持ち込むことになるかもしれない。が、私自身としては(主観的には)、映画作品を何度も繰り返し観るなかで、自然に浮かび上がった「論点」を設定しようと考えた。作品が、私の脳のなかに収納されている何かに「語りかけてくるもの」を感じ取ろうとしたつもりだ。
結局、それは私の主観のなかでのインターコーズなのだが。
早いもので、このブログを始めてから1年間が過ぎてしまった。
こんな形と内容で文章を書こうと思ったのは、じつは、こういう傾向の文章を私が読みたかったからだ。読みたかったのだが、ざっと見渡したところ、なさそうだった。では仕方がない、自分でリサーチし、検討・考察を加えて書くしかない。「読みたい文章を、自分で書く」という動機で始めた。
ただし、その動機どおりに、ことが進んだかどうかは、よくわからない。大雑把には、動機に沿って制作したとは思うが、思い通りに行かなかったこともそれなりに多い。
当初の目標では、「1月に1回分」くらいでいいか、だったが、ずいぶんペイスが上がって駆け抜けるように、突っ走ってしまった。その分、荒削りに過ぎたかもしれない。
2 めざしたもの
英語版のWikipediaには、映画のストーリーやプロットを紹介した記事の集成がある。現在も、世界中の書き手や批評家、あ映画ファンが、得意な分野について書き加え、記事項目も膨張している。
それらについては、以前から読んでいて知っていた。
だから、同じような調子、構成の記事にはしたくなかった。
だから、普通の「映画批評」「映画紹介」にはしたくなかった。
その大向こうを張ろうと、見得を切った。
自分の得意なスタイルで挑戦しようと思った。
映画とは、映像による「同時代」の(過去や未来や現在、あるいは荒唐無稽な空想などについての)精神の具現化、イメイジの投影だといえる。制作者の「世界」についてのイメイジ(考え方、批判精神)が表現されているものだ。
だとすれば、その物語と背景について、社会学的、社会史的な視点で考察し、同時代=「現代という時代」(歴史)の人類の歴史意識や社会意識についての記録として、記述できないか。そう考えた。
ただし、それだけだと扱い方が狭いので、作品の物語そのものについても、その流れを追いながら、できるだけ説明することにした。私の主観や評価を織り交ぜて。
映画の物語の流れを追いかける手法には、メリットがある。その流れは、かなり熟達した脚本家や演出家が、さらに原作がある場合には優れた作家が、観客へのアピール度や映像効果を考え抜いてつくり上げたものだ。起承転結やメリハリがしっかりしている。
ゆえに、私の文章作成能力の限界を超えることができる。つまり、物語の展開をそのまま追いかければ、それだけでもある程度読みやすい文章、起承転結がしっかりした文脈が形成される。そうすれば、私は筋立てにあまり悩まなくて済む。
3 歴史的資料としての映画
それぞれ1つの作品としての映画は、それがファンタジーやフィクションであっても、すぐれた歴史的資料だといえる。かならず、その映画がつくられたときの社会の文化や価値観だけでなく、政治や経済なども、何ほどかは反映している。
そして、映画は、映像そのものだけでなく、音楽、演劇、文学、絵画などの要素を重要な構成要因として含んでいる。つまりは、一種の総合芸術をなしている。
それゆえに、十分に社会科学や社会学、歴史学の研究対象になる。
しかし、これまでのところ、そういう扱いは十分されてこなかった。
もとより、映画人を育てるための素材として、映像作成の方法論・手法それ自体を検討し、洗練させるために研究されることは、かなりの精力をかけて、取り組まれてきた。社会評論の素材にもなってきた。だが、学問の1分野としては、まだ成り立っていない。
「たかが映画」にそれだけの価値はない、というアカデミズムの側の判断があったのか。
しかし、私としては、映画は総合芸術であるがゆえに、社会と歴史の総合的な考察のすぐれた素材となると考える。
その最大の長所は、映像=画像が主体(最重要の構成要素)となっていることだ。
このブログの記事ですでに述べてきたように、従来の歴史学や社会学、社会科学は、訓練された専門家向けのもので、一般社会や民衆からのアプローチを拒んできた。拒んでいるあいだに、時代遅れになったり、普通の人びとの生活実感や人生観、世界観から遠いものになってしまった。とくに日本では。
アカデミズムは、具体的な名前のカテゴリーを記述し操作しても、一般の人びとの体感や実感にも照応するような歴史や社会のイメイジをうまく提示できなかった。抽象的な理論や論理の構築で終わっていた。
しかも、一見、複雑で抽象的な論理の操作や構築にかかわっているかに見える外観のもとで、アカデミズムでは、問題の立て方や方法、結論について、「論理のすりかえ」、「論点ずらし」をおこなうことができた。
素朴な疑問は、「門外漢の素人考え」や「低次元の無理解」だとして、門前払いや切捨てができた。
たしかに、博覧強記、牽強付会をこととする学者先生が相手では、素朴な疑問は入り口の前で追い払われるのも仕方がない。アカデミズムは、自己防御の構造として、建設業界や土建業界も顔負けの、より手の込んだ業界談合システムを、幾重にも張りめぐらせている。
じつのところかなり重要な問題を提起したり、学説の欠陥をついている素朴な疑問は、こうしてアカデミズムの検討課題から、慇懃無礼に外される。
けれども、ごく素朴な疑問が、一見すきまなく構築された学術理論をいとも簡単に突き崩してしまう「蟻の一穴」になることを、私自身体験している。だから、アカデミズムのある部分は、素朴な疑問を排除する仕組みを備えている。
ところが、映像を中心的な分析素材に据えれば、少なくとも、映画に登場した限りで具体的な人物や人間関係、社会状況、人びとの行動様式、意識などについては、かなりの程度つかむことができる。
映画を素材にすることで、少なくとも映画作品を観た人たちとのあいだでは、共通の出発点、話題や材料の共有ができる。
映像で現に観ているものについて感想を述べたり、考察を開始することは、学者先生でも一般の「門外漢」でも、同じようにできる。むしろ、「象牙の塔」の外部で、世間の荒波をくぐっている一般人の方が、問題や状況を素直に捉えることができるかもしれない。
あとは、アカデミズムでの権威ではなく、それぞれの人びとが提示する「言葉」「文章」の説得力が、いずれのとらえ方がより「正しそうか」と判断するうえでの材料になる。
ただし、映像を対象にしても、その背後にある歴史的な文脈や社会状況については、それなりの深い分析や洞察が必要になる。それは、一定の訓練が必要になる。野球やサッカー、スキーなどと同じことだ。
以上のような意図を背後に置きながら、その試みの1つとしてとにかく始めてみた。
4 たかがブログ、されどブログ
と、いっぱし肩肘張ってみても、ただの「田舎おやじ」のやれることはタカが知れている。それに、そんなブログを一生懸命つくってみても、誰が読むの? とは思う。おそらく、限られたごく少数の読者に向けて発進する「超零細メディア」にとどまることになるだろう。
それでいいと思う。しょせん、余暇時間におこなう趣味にすぎない。注ぎ込む時間もたかが知れている。
いまのところ、ブログ作成に使っている1日当たりの平均時間は、せいぜい1時間もあればましな方だ。
毎日こつこつと考え、調べ、書き込んでいる。だが、少しずつでも日課として続ければ、かなりの量になる。1年間に三十数回分で、だいたい1回当たり1万7000字くらいだから、50~60万字くらいの文字量にはなった。
そうなると、どういうメディアを利用するにしろ、映画作品を観るときは、かなり意識的に登場人物や背景、状況設定について「まじめに」考えるようになった。で、気づいたことは、これまではかなりいい加減に映画を観てきたということだ。
ブログの内容はともかく、それだけは大きな成果だったいえる。
ただし、作品がブログに取り上げるつもりがいなくても、これまでのように、あまり意識せずにただ楽しんで観るということができなくなってしまった。
5 題材と内容について
ブログが氾濫する現在、自分なりにこのブログの存在意味を考える(自己満足のために)と、「ほかではまずは目にすることがない記事」を提示する、ということになってくる。つまりは、「へそ曲がりに徹する」ということだ。
もっとも、映画の設定した物語や状況設定の社会史的意味や歴史的文脈、政治的背景を探り描くということ方法自体が、たぶん目新しいではあろう。だが、発想だけ新しくても、内容が従来の通俗的な歴史観や教科書的な説明では、要するに「同工異曲」でしかない。
そこで、「世界のアカデミズム」でも先端の問題領域に踏み込むことにおそらくはなるであろう事件や状況を扱うようにしようと企図した。それで、《新しい世界観》《ちょっとひねった歴史観》を提起しようと考えた。
そのくらい映画の状況描写、背景描写には、映像制作者たちの鋭い感性や洞察がたたみ込まれている。なかなかバカにならない。大学での講義よりもはるかに内容が充実していて、しかも面白い。
ただ、そういう材料が「しょせん娯楽作品だ」という扱いで、本格的な社会学的・社会史的な分析の対象となっていない。
ブログでは、そういう問題を「できるだけ簡略に」記述しようと思った。だが、問題それ自体の意味や性格をある程度きちんと提示して、起承転結をつけて説明しなければいけない。しかも、扱う内容はポレーミッシュ(論争百出)の問題だから、いくつもの事柄が複雑に絡み合っている場合が多い。
で、説明にかなりの文字量を要することになる。文章が長く、複雑になる。
それで、私がよって立っている認識論や文章技術を理解してもらう場として、「文章技術コース」を連載することにした。なぜ、どのようにして、こんな文章を書くのか、そんな問題の立て方をするのか、どうして説明の組み立てがそうなっているのか、を知ってもらおうと意図したのだ。が、それがうまくいっているかは自信がない。
だが、それらは、私から見て、現在の日本の教育や高等教育で、一番弱いというか欠落している「ミッシングリンク」だといえる。業績や成績のの優劣、つまり競争のなかで地位ではなく、「自分の頭でものを考えること」を最重視する心性というか態度だ。
つまり、私のこのブログの中身も含めて、世の中に発信され飛び交っている情報の内容は、すべからく疑わしい、ということだ。疑わしいからといって、私たちにとっては、そういう材料を使って考え、自分なりの価値観に沿ってイメイジを描くしかない。とすれば、それらを吟味したり、比較考量したり、ようするに批判し、解体し、創造的に再利用する術を模索するしかない。
そのための、ただし「疑わしい」材料を提示しようとしている。
私の言説の「少なくとも半分」は疑わしい、という視点で見てほしい。
もっとも、それは、私に限らず、意見を表明するすべての人に対してなのだが。
よくても、正しいのは「半分だけ」なのだ、と。
■作品自体が呼び起こす視座■
それにしても、映画作品のうち歴史や哲学、政治経済の問題に絡められるものの数はあまりない。ゆえに、いつもこういう調子の記述になるわけではない。
だから、映画の物語や「語り口」そのものを楽しむ記事も多くなる。そうなれば、作品の見方、つまり考察の視点や視座、眼差しについて、いろいろ工夫を凝らす必要がある。
その場合、私としては「こじつけ」のように映画に私の価値観を持ち込むことになるかもしれない。が、私自身としては(主観的には)、映画作品を何度も繰り返し観るなかで、自然に浮かび上がった「論点」を設定しようと考えた。作品が、私の脳のなかに収納されている何かに「語りかけてくるもの」を感じ取ろうとしたつもりだ。
結局、それは私の主観のなかでのインターコーズなのだが。