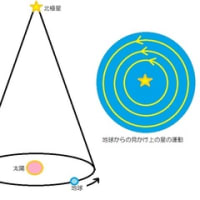●2009年12月20日(日)●
■遅れたが、ついに初滑り■
昨日、ようやく今シーズンのスキーの初滑りに行くことができた。長野県内のスキー場はどこでも解禁になったのだが、例年通り、野沢温泉スキー場に行った。
そこでは、今回からティケットに関して新しい管理システムが導入されていた。昨シーズンまでは、滑走=リフト券は電子チップだったが、今シーズンからは、昔風の紙の印刷物になった。
要するに、電子制御システムはハードとソフトの購入・運営管理に金がかかるからだろう。昨シーズンまでのシステムもかなり老朽化していた。これを最新システムに更新すると、何億円以上の単位の出費になる。スキー客がどんどん減っている現状では、リスクとコストがまかないきれないのだろう。
人間の視覚による確認で十分なことだし、昔に戻ってよかったのかもしれない。
さて、スキー場のコンディションだが。
昨日滑走可能になったところは、標高1000m以上のゲレンデ・コース。そして、昼頃から、日影ゲレンデ。急に積雪が増えたので、一気に前部のゲレンデ・コースを稼働させるわけにはいかなかったのだろう。でも、この時期のスキー客数は限られているので、それでも贅沢な空間が用意されていた。
ほとんどゲレンデ・コースでは、私は「貸切り」のようにほとんど人影が見えない雪原を滑ることができた。人が行かないところに行ったのかもしれない。でも、せっかくリフトが動いているのだから、行かないと係員に悪いような気がして、ほとんどの場所を回った。
積雪は、山頂部付近で、だいたい1.5~2.0mくらいか。ピステ圧雪状態で60~100cmというところか。ブナ林の木々の埋もれ具合から、そんなふうに推定した。雪の状態は、この時期としてはまあ良好。軽くて軟らかい雪の状態だった。
で、圧雪していない新雪の斜面を滑ることができた。
本当は、圧雪の上で身体のバランスの基本を確かめたかったが、雪の状態が良すぎた。贅沢な言い分だが。
新雪だと、どうしてもスキーを浮かせて加速させるために、膝から下は前のめりに、腰から上は後傾気味にしなければならない。すると、シーズン初めに身体全体を斜面の下に向かって落としていくイメイジのトレイニングがしにくい。最初のイメイジが浮かし気味で、後ろに逃げ気味で体に刷り込まれてしまうのだ。
その修正には、丸2時間(正味で1日)くらいはかかる。
それにしても、山頂部の雪化粧をしたブナ林は美しかった。
ごく当たり前に、雪が降ることのありがたさよ。
●2009年12月25日(金)●
■「歴史というもの」について■
私は、このブログで、映画作品を人間社会(たまには生物や宇宙などの自然現象)の歴史を物語として描く映像芸術・映像表現だと意味づけている。
では、歴史って何なんだ、と問われると、深くは考えていなかったと答えるしかない。「社会史」という語を使っても、用語事典程度の意味にしか考えていなかった。
その、深く考えていない浅い考えのまま、ここで「歴史」というものを考えてみよう。
日本語では、歴史とは、時間とともに変化する人類社会の経過、営みや仕組みの変移というものとして考えられている。
そのさい、「歴」という漢語は、順序を追った物事の経過を意味する。古代中国での漢字の成り立ちについての、ある事典解説では、もともとは人間の農作業の順序だった動きや流れ、手順を意味する語としてでき上がったと書かれている。つまりは、多少とも秩序だった、前後の順序が整然と並んだ状態を意味するようだ。
ただし、「歴」には多少の波乱や「行きつ戻りつ」の余地が残された語のようで、同じように時間経過を現す「経」が直線的で完全に順次や序列が整った動きだというのとは、少し意味が変わるらしい。経には、ピンと張られた(琴などの)縦糸という源義があるから、直線的な状態を意味するようになったのかもしれない。
「史」は、歴史を含めて、文字に記録された物語という意味らしい。が、古代中国では、「ふびと」、すなわち王宮にあって文書の作成や管理をつかさどる官吏を意味し、そこから王朝の歴史や事件を文字記録・編集する仕事を意味するようになり、「歴史」を意味する語となったという。
さて、ヨーロッパではどうか。
英語の《history》にも、もちろん、時間経過にともなう事象の変移、順序を追った人間社会の経過という意味がある。
ただし、グレコローマン以来の語義の伝承という視点で見ると、《hi+story》という文脈でヒストリーという語が成立したという流れと、《histo》という語から派生した流れとがあるようだ。
「ハイ+ストーリー」の文脈では、当然、「組み立てられた物語」という意味合いが込められる。
「ヒスト」の文脈では、この語がもともと生物の組織や岩石などの組成を意味する語なので、人類社会や事物の変化運動を系統立て、組織だてて記述・編成したものという意味になる。
フランス語では、私見では、「歴史」と「物語」とは同じものの2つの位相であるように解釈されてように思える。とはいえ、ラテン語系の言語なので、英語と基本的に同じような考え方かもしれない。
だが、ヒストリーを、《hi+store》から派生したものと考える立場もある。ここで「ストアー」とは、地層の構造(累層的なもの)とか建築の階層構造を意味する語だ。つまりは、事象の層の積み重なりを意味するようだ。
これはゲルマン語的流れからの派生らしい。というのも、ドイツ語では、歴史は《Geschicht》(物語という意味もある)で、《Schicht》はストアーと同じように層とか階層の累積、階層構造を意味する。で、《Ge》とは、「集合」とか統合された構造・系統を意味する接頭語だから、仕組みや変化の累層構造を意味するようになる。
どうやら、東洋では、経過や流れ=動き、変移を重視するのに対して、ヨーロッパでは、構造論的な見方が強いようだ。つまりは、単なる記録ではなく、記述を編集=構成して提示する方法論や仕組みについて注目するらしい。どちらにしても、因果連関を示したいという意図がうかがえる。
そのさい、東洋では因果関係は、「時系の前後関係そのもの」のなかに含まれていると見るのに対して、ヨーロッパでは時系の順序それ自体は外観的な位相であって、分析し再構成して文脈を描き出さなければならないという課題意識が含まれているようだ。
ところで、ヨーロッパでは、近代啓蒙思想や自然法史観で、理想とすべき「近代社会レジーム」が歴史の最高の段階のもので、それゆえ歴史とは、原始的で低次の段階から高次なものへの「発展」(「あるべき近代」へ向かう、内的な必然性による展開)であるべきだ、という方法論が支配的になった。
ここで、歴史の記述=構成の方法、つまり原始から近代への時系的な経過は、一定の価値観による内的な連関=文脈に沿って編成されなければならない、という視角が台頭した。
マルクス派の「発展史観」もまたこれに属する。
だが、私は「発展」とか「進歩」というように、ある価値観から見て低次な段階から高次な段階への展開=累層という方法論は好まない。歴史進歩や発展の必然性というものも、総体としては信じない。
必然性とか発展という文脈は、局部的、一時的には存在しようが、長期的=総体的には成り立たないと考える。歴史とは、(局部的、微視的には必然性が成り立つが)全体として「偶然の連鎖」である、と考える。
ヘーゲリアンであると自称するくせに、歴史の内的連関とか発展の必然性を認めないとは何事か、と非難されるだろう。私は、便宜的ヘーゲリアンなのだ。
つまり、1つの歴史局面や物語の起承転結をきっちりした組み立てにおいて記述し提示する方法の問題だと割り切っているのだ。その意味では、人間の主観の外に、主観がおよびもつかない「物自体」が存在するとするカント派の立場にも近いかもしれない。
物自体をどのように分析して構成して記述するかは、人間の主観の側の問題である、と。だが、自分の立場をそこまで徹底するほど、私は明晰ではない。
●2009年12月29日(火)●
■映画「のだめ」を観た■
先日、映画版「のだめ カンタービレ!」(最終楽章の前編)を観た。いろいろ事情があって、わざわざ雪深い長岡まで観にいった。重そうな雲が垂れこめた、雨もよいの日に。
私が観た上映の回は、昼少し前からで、満席だった。観客層は、圧倒的に女性が多かった。冬休みが始まった小中学生、高校生(これまた女性が大多数)から、中高年までと、客層は幅広い年齢層にまたがっていた。なかには、「のだめ型」クラシックファンの若い男性(カップルの片割れとかグループ)もいた。
さすが主要なメディアを握っているテレヴィ局が企画した映画作品とあって、幅広い年齢層を動員できたようだ。女性が多いのは、原作マンガが女性向け雑誌に掲載されたからだろう。
さて、映画の物語は、指揮者コンクールで優勝した千秋真一が、あのシュトレーゼマンの音楽事務所の差し金で、すっかり落ち目になったパリのオーケストラ、ルー・マルレの常任指揮者となって、解体消滅の危機に瀕したこの楽団の再建・復活のために奮闘する過程が中心になっている。だから、基本的には原作の筋書きに沿った展開だが、映画ではそれなりに物語や背景、人物ならびに状況設定にリアリティを持たせなければならないので、展開を膨らませたところと端折ったところがある。
そして、ギャグマンガをベイスにしている面白物語なので、「落ち」をつけなけれなばらない。そして、泣かせるところも。
というわけで、笑わせるための起承転結に泣かせる場面を織り交ぜたシークエンスのダイナミズムが、慌ただしく波打つように流れていく。だから、「もう年だ」と思っている私にとっては、ついていくだけで精いっぱい。
はらはらしたり、笑ったり、ジーンと来たりと、まるでジェットコウスターに乗っているような感じだった。
物語の場所はパリなので、街並みや交通機関などの風景は、パリやプラーハでロケイションしたのだが、何やら6月から8月のヴァカンスシーズンに駆け込み的に撮影したように見受けられる。つまり、パリジャンやパリジャンヌたちの姿がまばらな光景が多かったから。
その分、音楽演奏(練習)や会話、人物の性格や生活の描き方がかなり丁寧で、要するに、見栄えのするロケイションよりも演出に金と時間をかけたということがわかる。出来は、かなりいい。
物語の中心がルー・マルレ・オケの危機と再建にあるということから、そのために千秋がコンマスとともに奮闘し、楽団の核づくりを進め、団員の奮起を呼び起こしていく流れを感動的に描き出すことになった。ギャグドラマなりに、厚みや奥行きのある人間ドラマが紡ぎ出されている。
「落ちぶれた楽団の再生」という感動的な物語なのだ。
落ちぶれたがゆえに、団員の生活は困窮していて、音楽の練習よりも、その日の糧を得る仕事に精を出す。そして、輝かしい伝統の復活を熱く求めるコンマスと、別のもっと優秀な楽団への世渡りステップと考えているような団員との衝突。反コンマス派の団員たち(全体の3分の1)が辞めてしまった。残されたのは、頼まれて続けているエクストラが多数派。
楽団と長く付き合ってきたファンたちは、レヴェルダウンした楽団(の音楽)に愛想をつかして離れていく。
だが、楽団のコンサートマスターは、どうやらシュトレーゼマン事務所と結託して、頭抜けた才能を持つ千秋を駆り立てて、楽団の再活性化をもくろんでいるらしい。
というわけで、千秋の苦悩と努力が始まる。のだめは、どちらかというと(キャラクター的には圧倒的な存在感なのだが)千秋の努力を応援し脇で見守る役どころに見えた。
原作にあった「のだめカレー中毒事件」はセンセイショナルに描かれていた。オケのオーディション風景も。
だが、青春譚「ヤキトリオ物語」は描かれていなかった。若者らしい鬱屈と(まだ明確な形をとるようにならない)夢に向けた努力の物語が、私は好きだ。そして、それが、やがて、千秋への共感や応援、オーディションへの応募や楽団改革への動きにつながるのだ。
自分の進むべき道がまだはっきりとは見えないが、とにかく目先の小さな目標に向かってひたむに努力する、そんな姿が好きなのだ。
テレヴィドラマでは、峰龍太郎と真澄ちゃん、そしてのだめが、トリオを結成して、千秋が作曲した作品の復元と完成のために奮闘し、そこにやがて千秋も参加していく(仮に「青春カルテット物語」と名づけておく)、あの物語を入れてほしかったくらいだ。
まあ、この話題は、今回の映画物語の脇筋にすぎないから、メインストリーム・プロットをきっちり描き出すためには、切り取られてしまうことも仕方がなかった。せいぜい、私自身の頭のなかで、この小さな物語を、あの映画の映像を取り入れて再現することにしよう。
それにしても、オケの復活へのステップとして定期公演を成功させるために、千秋やコンマス、黒木君たち楽団員が、ときには反発し合いながら連帯し、結集し、努力してく流れは、感動的だった。
●2010年1月8日(金)●
■「わが文章の師範たち」■
私は以前、不遜にも「ブログライティングのための文章技術コース」という連載講座の記事を書いた。文章を書く行為の本体は、じつは認識活動であって、認識した対象を再構成するための論理を組み立てることが、すなわち文章作成なのだ、という立場で方法論を示した。
日本語(ほかのあらゆる言語についても)の文法が、じつは哲学(認識論と論理学)の基礎から組み立てられているということを出発点にした。ということは、文章を書くという営為は、この世界=対象を批判的に分析し、分解・破壊し、そして構成し直すことなのだ。
こう書くと、何やら小難しい問題を語っているように見えるが、何のことはない、幼児の頃から身につけてきた「言葉を使う」というごく当たり前のおこないを、ちょっと見つめ直すだけのことでしかない。
で、このブログの記事はすべて、この方法論の具体化、実行(少なくとも自分ではそのつもりで努力している)となっている。
さて、そんなこんなの方法論は、一番の土台の(メタフィジカルな)ところには、ヘーゲルの認識論や論理学の方法論(私がそう考える)が横たわっている。だが、実際の文章の書き方としては、過去に読んだ多くの物書きたちの文章や視点、文脈構成の方法を参考素材にしている。
そこで、ここでは、私の「文章の師匠」「文体の師範」について語ろうと思う。
「いつかこんな文章を書いてみたい」と痛切に感じた作家は、島崎藤村で、作品は「夜明け前」だ。私は、この小説が、〈日本のハードボイルド文体の元祖〉だと位置づけている。「骨太な文脈の構成」はいうまでもない。しかも、文章が美しい。そして描き方は、冷徹で対象をとことん突き放している。
この小説の冒頭は、木曽路の地理学的光景、自然と地勢、人の移動を拒むような峻厳な山岳地方の自然と街道の姿だ。震えるほどに見事に構成されている。余計なものがなく、必要なものは出そろっている。
そして、この厳しい自然条件は、この地の人びと、なかんづく主人公、青山半蔵の過酷な人生を予兆しているかのようだ。世界最高のハードボイルドだと思う。
次に物語の構成力、とりわけある時代の歴史的「大構造」をみごとに描き切りながら、同時に、人びとの絡み合いの物語、権力闘争や民衆の苦悩、個人の心情・心理を躍動的に描くという点で、感動したのが、杉本苑子の「穢土荘厳」。
歴史物語の構築性と個人や民衆の描き方を、これほどみごとに統合した作品は、それほどないと思う。
それから、美しい文章、文体だとしみじみ思ったのが、藤沢周平の作品。品格が感じられる。それは、作者自身の端正な人生観や処世観がにじみ出ている。そして、何より好ましいのが、「卑俗な英雄」をつくり上げないところ。
その対極にある、司馬遼太郎の文章は、私はあまり好まない。彼は、英雄を捏造していると感じるから。
ところで、私はヨーロッパやアメリカのハードボイルド作家の作品を何百(千を超えているかも)と読み倒してきた。そのことは、私の映画作品の取り扱い方からも、垣間見えると思う。
なかでも好きなのが、ディック・フランシス。日本語訳でも原文でも、とにかくいい、大好きだ。若い頃は、彼の小説の主人公たちのプロフェッショナル精神にあやかりたい、かく生きたい、と思ったものだ。文章が主人公の自己分析や自己抑制のはたらきを見るようで、厚かましくないのが好ましい。
物事の見方や問題の立て方、説明の論理の組み立て方で、大いに参考にしてきたのは、アイザック・アシモフだ。彼の科学エッセイ集(ハヤカワからシリーズで出ていた)は、すべて読んだ。原文で読んだものもある。
問題提起・設定の方法の巧みさ、意表を突くような、それでいて、きわめて真っ当な問題を明快に分析して見せながら、ウィットとプロットの妙を示してみせる。
フリードリヒ・エンゲルスの文体も好きだ。皮肉を込めながら、既存の価値観や方法論をひっくり返してみせる、あの飄々とした文章と文脈。文章の見せ方が巧みだ。これは、いくつもの国を移住してきたユダヤ人の特徴だろうか(アシモフはユダヤ系ロシア人のアメリカ移民系)。
同じくユダヤ人では、ドイツ出身の政治社会学者、カール・マンハイム。私は彼の「知の社会学」(「イデオロギーとウトピー」)が大好きだ。
まだほかにもたくさん、好きな文章家がいる。今回はここまで。
●20101月12日(火)●
■数値の演算とはアナログ=空間幾何学的なもの?■
アラビア数字は、0と1から9までの記号があって、10以上の数は十進数(10のn乗)の規則で表示する。計算についても、同じ規則で、演算結果を表示する。
もちろん、2進数や3進数…n進数についても、(n-1)の次の数値までいくと桁を繰り上げて表示できる。数の原理というか規則を巧みに表現できる記号で、すばらしい。
ところで、日本には「漢数字」がある。これも、一から九までの文字記号と十、百、千、万…というように、十進数(10のn乗)の表示規則に照応している。
その日本では、かつては、算盤(ソロバン)という計算用具が普及していた。演算そのものは、人間の頭脳がするだが、それを表示・記憶し、かつまた演算を補助し、とくに熟達した人びとにとっては、演算過程を珠の運動として空間図形化して脳の作動を著しく促進する働きをするという。
算盤は、じつによくできていて、最新の型は、上の段に5を表示する珠、下の段には1を表示する珠が4つ付いている。この計算用具は、全体としては十進数の規則で設定されているが、上の段は5進数の約束ごと(5のn乗)を表示し、下の段も5進数の進行を表示するようになっている。
こうして、上の段の5の珠と下の段の4つの珠との合成で十進数を表示するようになっている。
その昔は、上の球は2つ以上、下の珠も5つ以上あった時代もあったとか。
誰が、このようなエレガントな計算補助用具を発明し改良したのか。
算盤の達人を見ていると、彼らの頭脳のなかでは、演算による数の変動過程が、抽象的な数字の動きではなく、算盤珠という空間図形の物理的な動きとして「見える」らしい。抽象的な数の規則を図形的に整理統合しながら、とてつもなく高速の演算を可能にしているのだという。
単純化していえば、5×4=20という数の演算作用が図形の動きとして、見えるわけだ。言ってみれば、抽象的な演算過程を空間幾何学的運動として、思考作用のなかで表示・制御しているわけだ。
あるいは、図形の集合ないし関数として演算をアナログ化していると言ってもいいだろう。
してみれば、演算過程を幾何学化すれば、高速化、効率化できるわけだ。
電子計算機(コンピュータ)もまた、超微視的な回路のなかでの電子の流れる方向の変化の集積によって、演算を高速化、効率化している。つまりは、回路という空間図形のなかを電子という、微視的だが素粒子として存在する空間図形が動くわけだ。
電子の流れは、+と-との変動で混乱が生じないように、直流にしてから、一定方向=「+」に流れる動きを「1」、流れない反応を「0」と設定して、2進数の集積によってあらゆる数値を表現する。
これをたとえば、2の3乗(1,000=8)を1つの集合単位として、組み立てることもできる。
こうして、電子という素粒子集合(電流)の一定方向への動き(あるいは動きの不存在)によって、数値を表現し、演算過程を制御できるとすれば、電流からごく少数の素粒子の運動に置き換えることによって、同じ規則や演算を表現・制御できるだろう。
あらゆる素粒子(それ以下の単位も)は、特定の数量的な値を持つ質点ないし無限に微小な凝集空間に還元して省察する方法が、量子論だから、今の見方を突きつめれば、量子の運動による演算装置も可能だろう。
とはいえ、量子というものは確率論的にしか存在状況を把握できないものだから、情報を運搬し操作する媒体として有効かどうかは、わからない。
いずれにせよ、演算を制御し高速化するための方法は、数値の相互作用と運動を空間幾何学に置き換えるということになる。というのも、そもそも数値とは、実在する数量を表示する記号だから、数値の運動や相互作用とは、この世の中の実在する物体の運動と作用を量的側面から測定したものなのだ。
だから、実在する空間図形に数値と演算を流し込むことは、事物の本来のありように戻すということかもしれない。
だが、人間の頭脳のなかの思考作用としての情報の運動や相互作用も、やはり空間図形的な表示や運動に置き換えることができるのだろうか。
もちろん、思考過程を文字で表すということは、思考作用を記号の運動と相互作用で示すことだから、原理的には可能なのかもしれない。でも、感情や価値判断も、そういえるのだろうか。
■遅れたが、ついに初滑り■
昨日、ようやく今シーズンのスキーの初滑りに行くことができた。長野県内のスキー場はどこでも解禁になったのだが、例年通り、野沢温泉スキー場に行った。
そこでは、今回からティケットに関して新しい管理システムが導入されていた。昨シーズンまでは、滑走=リフト券は電子チップだったが、今シーズンからは、昔風の紙の印刷物になった。
要するに、電子制御システムはハードとソフトの購入・運営管理に金がかかるからだろう。昨シーズンまでのシステムもかなり老朽化していた。これを最新システムに更新すると、何億円以上の単位の出費になる。スキー客がどんどん減っている現状では、リスクとコストがまかないきれないのだろう。
人間の視覚による確認で十分なことだし、昔に戻ってよかったのかもしれない。
さて、スキー場のコンディションだが。
昨日滑走可能になったところは、標高1000m以上のゲレンデ・コース。そして、昼頃から、日影ゲレンデ。急に積雪が増えたので、一気に前部のゲレンデ・コースを稼働させるわけにはいかなかったのだろう。でも、この時期のスキー客数は限られているので、それでも贅沢な空間が用意されていた。
ほとんどゲレンデ・コースでは、私は「貸切り」のようにほとんど人影が見えない雪原を滑ることができた。人が行かないところに行ったのかもしれない。でも、せっかくリフトが動いているのだから、行かないと係員に悪いような気がして、ほとんどの場所を回った。
積雪は、山頂部付近で、だいたい1.5~2.0mくらいか。ピステ圧雪状態で60~100cmというところか。ブナ林の木々の埋もれ具合から、そんなふうに推定した。雪の状態は、この時期としてはまあ良好。軽くて軟らかい雪の状態だった。
で、圧雪していない新雪の斜面を滑ることができた。
本当は、圧雪の上で身体のバランスの基本を確かめたかったが、雪の状態が良すぎた。贅沢な言い分だが。
新雪だと、どうしてもスキーを浮かせて加速させるために、膝から下は前のめりに、腰から上は後傾気味にしなければならない。すると、シーズン初めに身体全体を斜面の下に向かって落としていくイメイジのトレイニングがしにくい。最初のイメイジが浮かし気味で、後ろに逃げ気味で体に刷り込まれてしまうのだ。
その修正には、丸2時間(正味で1日)くらいはかかる。
それにしても、山頂部の雪化粧をしたブナ林は美しかった。
ごく当たり前に、雪が降ることのありがたさよ。
●2009年12月25日(金)●
■「歴史というもの」について■
私は、このブログで、映画作品を人間社会(たまには生物や宇宙などの自然現象)の歴史を物語として描く映像芸術・映像表現だと意味づけている。
では、歴史って何なんだ、と問われると、深くは考えていなかったと答えるしかない。「社会史」という語を使っても、用語事典程度の意味にしか考えていなかった。
その、深く考えていない浅い考えのまま、ここで「歴史」というものを考えてみよう。
日本語では、歴史とは、時間とともに変化する人類社会の経過、営みや仕組みの変移というものとして考えられている。
そのさい、「歴」という漢語は、順序を追った物事の経過を意味する。古代中国での漢字の成り立ちについての、ある事典解説では、もともとは人間の農作業の順序だった動きや流れ、手順を意味する語としてでき上がったと書かれている。つまりは、多少とも秩序だった、前後の順序が整然と並んだ状態を意味するようだ。
ただし、「歴」には多少の波乱や「行きつ戻りつ」の余地が残された語のようで、同じように時間経過を現す「経」が直線的で完全に順次や序列が整った動きだというのとは、少し意味が変わるらしい。経には、ピンと張られた(琴などの)縦糸という源義があるから、直線的な状態を意味するようになったのかもしれない。
「史」は、歴史を含めて、文字に記録された物語という意味らしい。が、古代中国では、「ふびと」、すなわち王宮にあって文書の作成や管理をつかさどる官吏を意味し、そこから王朝の歴史や事件を文字記録・編集する仕事を意味するようになり、「歴史」を意味する語となったという。
さて、ヨーロッパではどうか。
英語の《history》にも、もちろん、時間経過にともなう事象の変移、順序を追った人間社会の経過という意味がある。
ただし、グレコローマン以来の語義の伝承という視点で見ると、《hi+story》という文脈でヒストリーという語が成立したという流れと、《histo》という語から派生した流れとがあるようだ。
「ハイ+ストーリー」の文脈では、当然、「組み立てられた物語」という意味合いが込められる。
「ヒスト」の文脈では、この語がもともと生物の組織や岩石などの組成を意味する語なので、人類社会や事物の変化運動を系統立て、組織だてて記述・編成したものという意味になる。
フランス語では、私見では、「歴史」と「物語」とは同じものの2つの位相であるように解釈されてように思える。とはいえ、ラテン語系の言語なので、英語と基本的に同じような考え方かもしれない。
だが、ヒストリーを、《hi+store》から派生したものと考える立場もある。ここで「ストアー」とは、地層の構造(累層的なもの)とか建築の階層構造を意味する語だ。つまりは、事象の層の積み重なりを意味するようだ。
これはゲルマン語的流れからの派生らしい。というのも、ドイツ語では、歴史は《Geschicht》(物語という意味もある)で、《Schicht》はストアーと同じように層とか階層の累積、階層構造を意味する。で、《Ge》とは、「集合」とか統合された構造・系統を意味する接頭語だから、仕組みや変化の累層構造を意味するようになる。
どうやら、東洋では、経過や流れ=動き、変移を重視するのに対して、ヨーロッパでは、構造論的な見方が強いようだ。つまりは、単なる記録ではなく、記述を編集=構成して提示する方法論や仕組みについて注目するらしい。どちらにしても、因果連関を示したいという意図がうかがえる。
そのさい、東洋では因果関係は、「時系の前後関係そのもの」のなかに含まれていると見るのに対して、ヨーロッパでは時系の順序それ自体は外観的な位相であって、分析し再構成して文脈を描き出さなければならないという課題意識が含まれているようだ。
ところで、ヨーロッパでは、近代啓蒙思想や自然法史観で、理想とすべき「近代社会レジーム」が歴史の最高の段階のもので、それゆえ歴史とは、原始的で低次の段階から高次なものへの「発展」(「あるべき近代」へ向かう、内的な必然性による展開)であるべきだ、という方法論が支配的になった。
ここで、歴史の記述=構成の方法、つまり原始から近代への時系的な経過は、一定の価値観による内的な連関=文脈に沿って編成されなければならない、という視角が台頭した。
マルクス派の「発展史観」もまたこれに属する。
だが、私は「発展」とか「進歩」というように、ある価値観から見て低次な段階から高次な段階への展開=累層という方法論は好まない。歴史進歩や発展の必然性というものも、総体としては信じない。
必然性とか発展という文脈は、局部的、一時的には存在しようが、長期的=総体的には成り立たないと考える。歴史とは、(局部的、微視的には必然性が成り立つが)全体として「偶然の連鎖」である、と考える。
ヘーゲリアンであると自称するくせに、歴史の内的連関とか発展の必然性を認めないとは何事か、と非難されるだろう。私は、便宜的ヘーゲリアンなのだ。
つまり、1つの歴史局面や物語の起承転結をきっちりした組み立てにおいて記述し提示する方法の問題だと割り切っているのだ。その意味では、人間の主観の外に、主観がおよびもつかない「物自体」が存在するとするカント派の立場にも近いかもしれない。
物自体をどのように分析して構成して記述するかは、人間の主観の側の問題である、と。だが、自分の立場をそこまで徹底するほど、私は明晰ではない。
●2009年12月29日(火)●
■映画「のだめ」を観た■
先日、映画版「のだめ カンタービレ!」(最終楽章の前編)を観た。いろいろ事情があって、わざわざ雪深い長岡まで観にいった。重そうな雲が垂れこめた、雨もよいの日に。
私が観た上映の回は、昼少し前からで、満席だった。観客層は、圧倒的に女性が多かった。冬休みが始まった小中学生、高校生(これまた女性が大多数)から、中高年までと、客層は幅広い年齢層にまたがっていた。なかには、「のだめ型」クラシックファンの若い男性(カップルの片割れとかグループ)もいた。
さすが主要なメディアを握っているテレヴィ局が企画した映画作品とあって、幅広い年齢層を動員できたようだ。女性が多いのは、原作マンガが女性向け雑誌に掲載されたからだろう。
さて、映画の物語は、指揮者コンクールで優勝した千秋真一が、あのシュトレーゼマンの音楽事務所の差し金で、すっかり落ち目になったパリのオーケストラ、ルー・マルレの常任指揮者となって、解体消滅の危機に瀕したこの楽団の再建・復活のために奮闘する過程が中心になっている。だから、基本的には原作の筋書きに沿った展開だが、映画ではそれなりに物語や背景、人物ならびに状況設定にリアリティを持たせなければならないので、展開を膨らませたところと端折ったところがある。
そして、ギャグマンガをベイスにしている面白物語なので、「落ち」をつけなけれなばらない。そして、泣かせるところも。
というわけで、笑わせるための起承転結に泣かせる場面を織り交ぜたシークエンスのダイナミズムが、慌ただしく波打つように流れていく。だから、「もう年だ」と思っている私にとっては、ついていくだけで精いっぱい。
はらはらしたり、笑ったり、ジーンと来たりと、まるでジェットコウスターに乗っているような感じだった。
物語の場所はパリなので、街並みや交通機関などの風景は、パリやプラーハでロケイションしたのだが、何やら6月から8月のヴァカンスシーズンに駆け込み的に撮影したように見受けられる。つまり、パリジャンやパリジャンヌたちの姿がまばらな光景が多かったから。
その分、音楽演奏(練習)や会話、人物の性格や生活の描き方がかなり丁寧で、要するに、見栄えのするロケイションよりも演出に金と時間をかけたということがわかる。出来は、かなりいい。
物語の中心がルー・マルレ・オケの危機と再建にあるということから、そのために千秋がコンマスとともに奮闘し、楽団の核づくりを進め、団員の奮起を呼び起こしていく流れを感動的に描き出すことになった。ギャグドラマなりに、厚みや奥行きのある人間ドラマが紡ぎ出されている。
「落ちぶれた楽団の再生」という感動的な物語なのだ。
落ちぶれたがゆえに、団員の生活は困窮していて、音楽の練習よりも、その日の糧を得る仕事に精を出す。そして、輝かしい伝統の復活を熱く求めるコンマスと、別のもっと優秀な楽団への世渡りステップと考えているような団員との衝突。反コンマス派の団員たち(全体の3分の1)が辞めてしまった。残されたのは、頼まれて続けているエクストラが多数派。
楽団と長く付き合ってきたファンたちは、レヴェルダウンした楽団(の音楽)に愛想をつかして離れていく。
だが、楽団のコンサートマスターは、どうやらシュトレーゼマン事務所と結託して、頭抜けた才能を持つ千秋を駆り立てて、楽団の再活性化をもくろんでいるらしい。
というわけで、千秋の苦悩と努力が始まる。のだめは、どちらかというと(キャラクター的には圧倒的な存在感なのだが)千秋の努力を応援し脇で見守る役どころに見えた。
原作にあった「のだめカレー中毒事件」はセンセイショナルに描かれていた。オケのオーディション風景も。
だが、青春譚「ヤキトリオ物語」は描かれていなかった。若者らしい鬱屈と(まだ明確な形をとるようにならない)夢に向けた努力の物語が、私は好きだ。そして、それが、やがて、千秋への共感や応援、オーディションへの応募や楽団改革への動きにつながるのだ。
自分の進むべき道がまだはっきりとは見えないが、とにかく目先の小さな目標に向かってひたむに努力する、そんな姿が好きなのだ。
テレヴィドラマでは、峰龍太郎と真澄ちゃん、そしてのだめが、トリオを結成して、千秋が作曲した作品の復元と完成のために奮闘し、そこにやがて千秋も参加していく(仮に「青春カルテット物語」と名づけておく)、あの物語を入れてほしかったくらいだ。
まあ、この話題は、今回の映画物語の脇筋にすぎないから、メインストリーム・プロットをきっちり描き出すためには、切り取られてしまうことも仕方がなかった。せいぜい、私自身の頭のなかで、この小さな物語を、あの映画の映像を取り入れて再現することにしよう。
それにしても、オケの復活へのステップとして定期公演を成功させるために、千秋やコンマス、黒木君たち楽団員が、ときには反発し合いながら連帯し、結集し、努力してく流れは、感動的だった。
●2010年1月8日(金)●
■「わが文章の師範たち」■
私は以前、不遜にも「ブログライティングのための文章技術コース」という連載講座の記事を書いた。文章を書く行為の本体は、じつは認識活動であって、認識した対象を再構成するための論理を組み立てることが、すなわち文章作成なのだ、という立場で方法論を示した。
日本語(ほかのあらゆる言語についても)の文法が、じつは哲学(認識論と論理学)の基礎から組み立てられているということを出発点にした。ということは、文章を書くという営為は、この世界=対象を批判的に分析し、分解・破壊し、そして構成し直すことなのだ。
こう書くと、何やら小難しい問題を語っているように見えるが、何のことはない、幼児の頃から身につけてきた「言葉を使う」というごく当たり前のおこないを、ちょっと見つめ直すだけのことでしかない。
で、このブログの記事はすべて、この方法論の具体化、実行(少なくとも自分ではそのつもりで努力している)となっている。
さて、そんなこんなの方法論は、一番の土台の(メタフィジカルな)ところには、ヘーゲルの認識論や論理学の方法論(私がそう考える)が横たわっている。だが、実際の文章の書き方としては、過去に読んだ多くの物書きたちの文章や視点、文脈構成の方法を参考素材にしている。
そこで、ここでは、私の「文章の師匠」「文体の師範」について語ろうと思う。
「いつかこんな文章を書いてみたい」と痛切に感じた作家は、島崎藤村で、作品は「夜明け前」だ。私は、この小説が、〈日本のハードボイルド文体の元祖〉だと位置づけている。「骨太な文脈の構成」はいうまでもない。しかも、文章が美しい。そして描き方は、冷徹で対象をとことん突き放している。
この小説の冒頭は、木曽路の地理学的光景、自然と地勢、人の移動を拒むような峻厳な山岳地方の自然と街道の姿だ。震えるほどに見事に構成されている。余計なものがなく、必要なものは出そろっている。
そして、この厳しい自然条件は、この地の人びと、なかんづく主人公、青山半蔵の過酷な人生を予兆しているかのようだ。世界最高のハードボイルドだと思う。
次に物語の構成力、とりわけある時代の歴史的「大構造」をみごとに描き切りながら、同時に、人びとの絡み合いの物語、権力闘争や民衆の苦悩、個人の心情・心理を躍動的に描くという点で、感動したのが、杉本苑子の「穢土荘厳」。
歴史物語の構築性と個人や民衆の描き方を、これほどみごとに統合した作品は、それほどないと思う。
それから、美しい文章、文体だとしみじみ思ったのが、藤沢周平の作品。品格が感じられる。それは、作者自身の端正な人生観や処世観がにじみ出ている。そして、何より好ましいのが、「卑俗な英雄」をつくり上げないところ。
その対極にある、司馬遼太郎の文章は、私はあまり好まない。彼は、英雄を捏造していると感じるから。
ところで、私はヨーロッパやアメリカのハードボイルド作家の作品を何百(千を超えているかも)と読み倒してきた。そのことは、私の映画作品の取り扱い方からも、垣間見えると思う。
なかでも好きなのが、ディック・フランシス。日本語訳でも原文でも、とにかくいい、大好きだ。若い頃は、彼の小説の主人公たちのプロフェッショナル精神にあやかりたい、かく生きたい、と思ったものだ。文章が主人公の自己分析や自己抑制のはたらきを見るようで、厚かましくないのが好ましい。
物事の見方や問題の立て方、説明の論理の組み立て方で、大いに参考にしてきたのは、アイザック・アシモフだ。彼の科学エッセイ集(ハヤカワからシリーズで出ていた)は、すべて読んだ。原文で読んだものもある。
問題提起・設定の方法の巧みさ、意表を突くような、それでいて、きわめて真っ当な問題を明快に分析して見せながら、ウィットとプロットの妙を示してみせる。
フリードリヒ・エンゲルスの文体も好きだ。皮肉を込めながら、既存の価値観や方法論をひっくり返してみせる、あの飄々とした文章と文脈。文章の見せ方が巧みだ。これは、いくつもの国を移住してきたユダヤ人の特徴だろうか(アシモフはユダヤ系ロシア人のアメリカ移民系)。
同じくユダヤ人では、ドイツ出身の政治社会学者、カール・マンハイム。私は彼の「知の社会学」(「イデオロギーとウトピー」)が大好きだ。
まだほかにもたくさん、好きな文章家がいる。今回はここまで。
●20101月12日(火)●
■数値の演算とはアナログ=空間幾何学的なもの?■
アラビア数字は、0と1から9までの記号があって、10以上の数は十進数(10のn乗)の規則で表示する。計算についても、同じ規則で、演算結果を表示する。
もちろん、2進数や3進数…n進数についても、(n-1)の次の数値までいくと桁を繰り上げて表示できる。数の原理というか規則を巧みに表現できる記号で、すばらしい。
ところで、日本には「漢数字」がある。これも、一から九までの文字記号と十、百、千、万…というように、十進数(10のn乗)の表示規則に照応している。
その日本では、かつては、算盤(ソロバン)という計算用具が普及していた。演算そのものは、人間の頭脳がするだが、それを表示・記憶し、かつまた演算を補助し、とくに熟達した人びとにとっては、演算過程を珠の運動として空間図形化して脳の作動を著しく促進する働きをするという。
算盤は、じつによくできていて、最新の型は、上の段に5を表示する珠、下の段には1を表示する珠が4つ付いている。この計算用具は、全体としては十進数の規則で設定されているが、上の段は5進数の約束ごと(5のn乗)を表示し、下の段も5進数の進行を表示するようになっている。
こうして、上の段の5の珠と下の段の4つの珠との合成で十進数を表示するようになっている。
その昔は、上の球は2つ以上、下の珠も5つ以上あった時代もあったとか。
誰が、このようなエレガントな計算補助用具を発明し改良したのか。
算盤の達人を見ていると、彼らの頭脳のなかでは、演算による数の変動過程が、抽象的な数字の動きではなく、算盤珠という空間図形の物理的な動きとして「見える」らしい。抽象的な数の規則を図形的に整理統合しながら、とてつもなく高速の演算を可能にしているのだという。
単純化していえば、5×4=20という数の演算作用が図形の動きとして、見えるわけだ。言ってみれば、抽象的な演算過程を空間幾何学的運動として、思考作用のなかで表示・制御しているわけだ。
あるいは、図形の集合ないし関数として演算をアナログ化していると言ってもいいだろう。
してみれば、演算過程を幾何学化すれば、高速化、効率化できるわけだ。
電子計算機(コンピュータ)もまた、超微視的な回路のなかでの電子の流れる方向の変化の集積によって、演算を高速化、効率化している。つまりは、回路という空間図形のなかを電子という、微視的だが素粒子として存在する空間図形が動くわけだ。
電子の流れは、+と-との変動で混乱が生じないように、直流にしてから、一定方向=「+」に流れる動きを「1」、流れない反応を「0」と設定して、2進数の集積によってあらゆる数値を表現する。
これをたとえば、2の3乗(1,000=8)を1つの集合単位として、組み立てることもできる。
こうして、電子という素粒子集合(電流)の一定方向への動き(あるいは動きの不存在)によって、数値を表現し、演算過程を制御できるとすれば、電流からごく少数の素粒子の運動に置き換えることによって、同じ規則や演算を表現・制御できるだろう。
あらゆる素粒子(それ以下の単位も)は、特定の数量的な値を持つ質点ないし無限に微小な凝集空間に還元して省察する方法が、量子論だから、今の見方を突きつめれば、量子の運動による演算装置も可能だろう。
とはいえ、量子というものは確率論的にしか存在状況を把握できないものだから、情報を運搬し操作する媒体として有効かどうかは、わからない。
いずれにせよ、演算を制御し高速化するための方法は、数値の相互作用と運動を空間幾何学に置き換えるということになる。というのも、そもそも数値とは、実在する数量を表示する記号だから、数値の運動や相互作用とは、この世の中の実在する物体の運動と作用を量的側面から測定したものなのだ。
だから、実在する空間図形に数値と演算を流し込むことは、事物の本来のありように戻すということかもしれない。
だが、人間の頭脳のなかの思考作用としての情報の運動や相互作用も、やはり空間図形的な表示や運動に置き換えることができるのだろうか。
もちろん、思考過程を文字で表すということは、思考作用を記号の運動と相互作用で示すことだから、原理的には可能なのかもしれない。でも、感情や価値判断も、そういえるのだろうか。