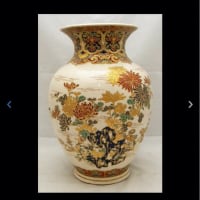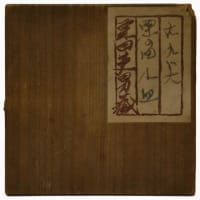2007/1/18(木) 午後 9:24
大学時代、世に中とは何か、人生とは何か、という疑問に、マージャン生活に明け暮れながらも、自分なりに一応の解答を見出すべく考えました。結果、もっとも感銘を受けたのが、デカルトの方法序説、カール・ポパー等につながる論理実証主義と ウィーナーのサイバネティックスでした。
いまの職務も、情報理論がきっかけとなって選んだ気もします。方法序説の、すべてを疑い、疑 いきれない事実のみから思考を組み立てるという立場は、いまでも支持してます。(もっとも、「神はあらゆる性質を有する、ゆえに存在という性質も有する」という結論部分は、神の定義と実在論の混同にすぎないと考えますが。)
残念ながら、小生の世に中の探求は、それで中断し、その後は深遠な思索とは無縁の俗世にまみれた生活をおくってきました。しかし、そのころ出した一応の解答に よって、これまで、各種生活判断をしてきたことも事実です。
正義の判断は、先見的に可能ですが、その根源的理由は、それが、人類の歴史的発展過程において獲得した形質の一つだからではないでしょうか。
生物学者のローレンツは、鳥類の刷り込み現象を発見し、われわれが「愛」と呼ぶものに関しての理解を深めましたが、これと同様なものではないか。これらの資質は、巨視的には利己的な遺伝子の展開過程で形成されたものですが、固体レベルでは直知として認識されるということでしょう。しかし、正義の現実の形相にはバリエーションがあり、現代の諸問題への対処を演繹的に展開するのには限界があるのでないか、と考えます。
もうひとつ、小生の思考習慣となっているのが、方法論的アプローチです。仮に、ある理念があるとして、それはいかなる手続きにより確定されるか。確定手続きが存在しないものは、考えても意味がない。現実の世界で適用可能な形で提起されて初めて意味がある、と思います。
価値自体に関して議論する意義は否定するものではありませんが、方法論と独立した価値論の有意義性は、限定されると考えます。政治においても、まさしく正義の確定過程 と実現過程 こそが主題ではないでしょうか。過程が価値自体を定義することもありうるのでしょう。
世界とはなにか。情報理論は、物質、エネルギー、情報の三要素で構成される、 といいます。物質がなければ世界は存在しない。エネルギーがなければ世界は運動しない。情報がなければ、世界は無秩序となる。
生命とはなにか。遺伝子科学は、自己増殖する統合システムとして捉え、その目的は同一遺伝子を保持する子孫の拡大としてます。この考えによれば、人生とは、主観的には価値追求過程です。しかし、価値を客観的に捉えれば、生命として獲得された潜在形質の、特定の文化、時間、空間環境での発現ということではないか。
ただ、現象にはさまざまのものがあり、個別主体にとって人生が簡単というものではないでしょう。個人にとっての価値確定は、いつも悩み多きもので、新興宗教も哲学も、だからこそ必要とされるのでしょう。
人生(会社、社会も)は、価値実現のための個別の意思決定の連鎖と捉えることができ、そのプロセスを情報理論にも基づき定式化したのが、ハーバート・サイモンというノーベル賞学者でした。
個人的には、人生は、諸先輩の実践と結果から学習するほうが理論に学ぶより有用と考えてます。また、ここまで人生を送ってきて最近感じていることは、世渡りにおいての腰の軽さの重要性です。人の言葉より人の行動を信じよ、という知恵がありますが、自分のものぐさに反省しきりです。
大学時代、世に中とは何か、人生とは何か、という疑問に、マージャン生活に明け暮れながらも、自分なりに一応の解答を見出すべく考えました。結果、もっとも感銘を受けたのが、デカルトの方法序説、カール・ポパー等につながる論理実証主義と ウィーナーのサイバネティックスでした。
いまの職務も、情報理論がきっかけとなって選んだ気もします。方法序説の、すべてを疑い、疑 いきれない事実のみから思考を組み立てるという立場は、いまでも支持してます。(もっとも、「神はあらゆる性質を有する、ゆえに存在という性質も有する」という結論部分は、神の定義と実在論の混同にすぎないと考えますが。)
残念ながら、小生の世に中の探求は、それで中断し、その後は深遠な思索とは無縁の俗世にまみれた生活をおくってきました。しかし、そのころ出した一応の解答に よって、これまで、各種生活判断をしてきたことも事実です。
正義の判断は、先見的に可能ですが、その根源的理由は、それが、人類の歴史的発展過程において獲得した形質の一つだからではないでしょうか。
生物学者のローレンツは、鳥類の刷り込み現象を発見し、われわれが「愛」と呼ぶものに関しての理解を深めましたが、これと同様なものではないか。これらの資質は、巨視的には利己的な遺伝子の展開過程で形成されたものですが、固体レベルでは直知として認識されるということでしょう。しかし、正義の現実の形相にはバリエーションがあり、現代の諸問題への対処を演繹的に展開するのには限界があるのでないか、と考えます。
もうひとつ、小生の思考習慣となっているのが、方法論的アプローチです。仮に、ある理念があるとして、それはいかなる手続きにより確定されるか。確定手続きが存在しないものは、考えても意味がない。現実の世界で適用可能な形で提起されて初めて意味がある、と思います。
価値自体に関して議論する意義は否定するものではありませんが、方法論と独立した価値論の有意義性は、限定されると考えます。政治においても、まさしく正義の確定過程 と実現過程 こそが主題ではないでしょうか。過程が価値自体を定義することもありうるのでしょう。
世界とはなにか。情報理論は、物質、エネルギー、情報の三要素で構成される、 といいます。物質がなければ世界は存在しない。エネルギーがなければ世界は運動しない。情報がなければ、世界は無秩序となる。
生命とはなにか。遺伝子科学は、自己増殖する統合システムとして捉え、その目的は同一遺伝子を保持する子孫の拡大としてます。この考えによれば、人生とは、主観的には価値追求過程です。しかし、価値を客観的に捉えれば、生命として獲得された潜在形質の、特定の文化、時間、空間環境での発現ということではないか。
ただ、現象にはさまざまのものがあり、個別主体にとって人生が簡単というものではないでしょう。個人にとっての価値確定は、いつも悩み多きもので、新興宗教も哲学も、だからこそ必要とされるのでしょう。
人生(会社、社会も)は、価値実現のための個別の意思決定の連鎖と捉えることができ、そのプロセスを情報理論にも基づき定式化したのが、ハーバート・サイモンというノーベル賞学者でした。
個人的には、人生は、諸先輩の実践と結果から学習するほうが理論に学ぶより有用と考えてます。また、ここまで人生を送ってきて最近感じていることは、世渡りにおいての腰の軽さの重要性です。人の言葉より人の行動を信じよ、という知恵がありますが、自分のものぐさに反省しきりです。